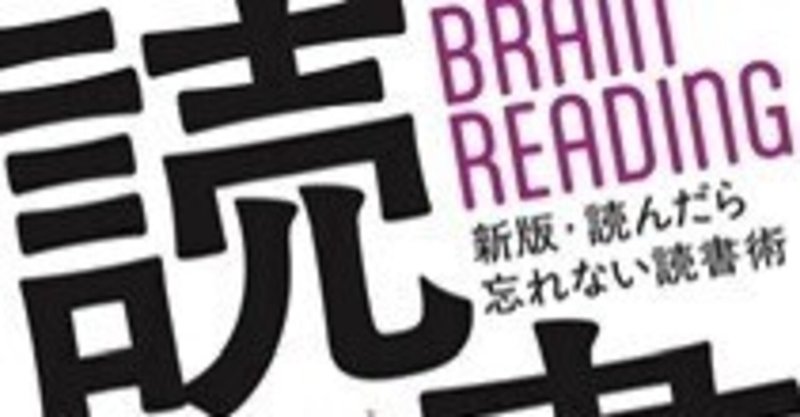
「読書脳」感想文
樺沢紫苑著「読書脳」の感想文です。
私は子どもの頃、作文は苦手だった。
自分の考えを表現することが苦手であった。
原稿用紙を前にして、全く言葉が出ない。何かを生み出さなきゃと思って、何も出てこない。「良いことを書かねば」という思いが強すぎたのだろうと思う。
作文の授業は拷問に感じ、地獄であった。
そんな私が、樺沢先生の本に出会い、こうして文章を書けるようになった。
素直に、感じたことを書いていこうと思う。
社会人になって、人間関係に悩んだり、仕事の分野を深める為、あらゆる本を読むようになった。
しかし、本を読んでもしっくりこない感覚があった。読んでいる時は「なるほど」と思いながら進めるのだが、読み終わって数日経つと、「これは読み終わった本だな」で本の存在が薄くなっていく。
このような調子なので、何冊読んでも身についている感覚が得られなかった。読書をすれば、知識も増えて賢くなれると信じていたが、そんなことないのでは…という疑いを持っていた。
なぜ身につかなかったのか。
それは「読書脳」の中にドンピシャの答えを発見した。
読書の3つの基本原則として、①記憶に残る読書術②スキマ時間読書術③深読読書術が説明されている。(第2章「読んだら忘れない」精神科医の読書術)
一つ目に挙げられている「記憶に残る読書術」では、1週間に3回アウトプットすることが提言されている。私はここにハッとさせられた。今まで、アウトプットをしてこなかったのだ。読んだら終わり。作文でも、「何か良いことを書かなきゃ」と身構えて結局何も書くことはできなかった。アウトプットはそんなにハードルを上げなくても良かったのだ。一言でも、感じたこと、気づいたことを言葉にして、そこから繋げていけばよかったのだ。
本の読み方も、一気に読んでいた。本に熱中する時期とそうでない時期のムラがあった。
「何となく」読書をしてきたことに気づいたのだ。
この基本原則を押さえた上で読書をすれば、読書後に変化することができる。
今は、読書後にSNSで気づき、感じたことを一言でもよいのであげるようにしている。一言つぶやくだけでも、時間が経って振り返るとつぶやきから本の内容がよみがえる。一言でも残そうと思って読むので、読書中の集中力が上がったように思う。また、毎朝15分を読書の時間としてコンスタントに読書ができるようになった。
「第8章 精神科医がお勧めする珠玉の31冊」で読みたい本がたくさんできた。これから読書がますます楽しみである。
樺沢先生によって、読書の取り組みが変わった。
見える世界が変わってきている。
これからも読書をして、生きている限り成長していけるようにしたい。人生を楽しみたい!
以上、読んでくださりありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
