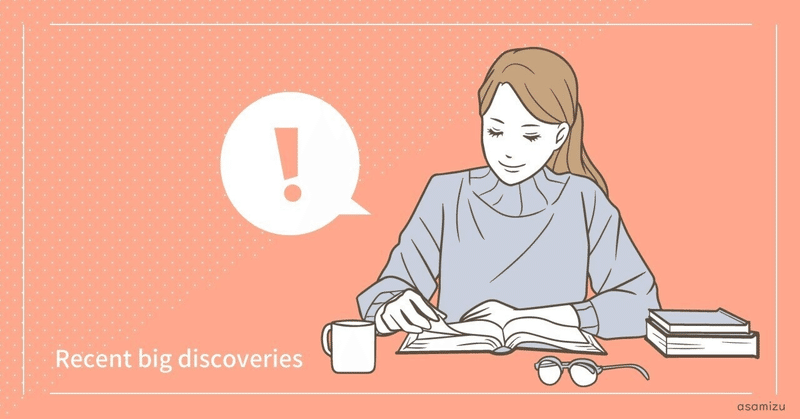
大学3年の秋、とある学問に興味を持つ。|大学生日記10
就活に自己分析、投げ出したいことばかりに向き合う毎日。正直大変。
そんな日常で今までと変わらず続いているのが、週に一回のゼミ活動。人と会う機会が激減した今では、週に一度のゼミ活動が楽しみになっています。
最近になってようやく飲み会についての制限が緩くなり、ゼミでも1年越しにみんなで飲み会をしました。とても楽しかったです。
それがきっかけとなり、ゼミの友人O君と飲みにいく機会も増えました。高校時代からの友人O君です。
今回は、O君との会話の中で登場した「行動経済学」に私はとても興味を持ったので、そのことに関して書いていこうと思います。
O君の話
O君は、私の高校時代の同級生で、同じクラスでした。高校の時は格別仲が良かったわけではなく、たまに話すクラスメイトといった関係性でした。
そこから話す機会が増えたのは、同じ大学を目指していることがわかった時でした。幸いなことに二人とも大学に合格し、そこから濃い関係性が始まります。
授業も一緒に取るものが多く、挙げ句の果てにゼミまで同じになってしまうという、面白い関係です。
そんな彼と私が所属しているゼミは、金融関係のゼミになります。といっても経済学や経営学の知識を使って社会について考えていくという感じなので、あまりお堅い感じではないです。
とりわけ彼は金融に興味を持っていて、同じ経済学部同士、経済の話で盛り上がっていました。
そこで彼の口から出たのは、謎の単語「MMT」でした。
アメリカではMMTがアツいらしい。
今自分の中でMMTがアツいと、面白いと彼は言っていました。
なんだそれ。
そういえばどこかで目にしたことのあるような気がしますが、正直なんのことだかさっぱり分かりません。MMTとはいったいなんなのでしょうか。
気になったので調べてみました。
【現代貨幣理論(MMT)】
貨幣や金融の仕組みを理解し、それを基に経済政策の分析などを行う理論。代表的な主張としては、
①自国通貨を発行できる政府は財政赤字を拡大しても債務不履行になることはない。
②財政赤字でも国はインフレが起きない範囲で支出を行うべき。
③税は財源ではなく通貨を流通させる仕組みである。
の三つ。
https://miraisozo.mizuhobank.co.jp/money/80284.amp
だそうです。この文章だけを見てもいまいちよく分かりませんが、私がこれまで学んできたケインズ主義をはじめとする経済学では聞いたことがありませんでした。というかMMTに関する授業が大学にありません。それほど新しい考え方のようです。
このMMT理論について彼から話を聞いていく中で、私は行動経済学に興味が出てきたのです。さてさて一体どこから…?
理論上は、ってやつでしょ
MMTの基礎的な考えとして、「経済活動が先で、貨幣の増減は後」というものがあるようです。
中央銀行の経済政策などでは市場に流通する貨幣の供給量を増やせば消費活動が増えて市場が活性化し、減らすと加熱しすぎた市場を正常化する効果がある、という前提のもと行われています。そうらしいです。
その一方でMMTではその因果関係が逆になるようで。
社会が好景気となり、お金を借りて事業を発展させたい人が増えた結果として貨幣の量が増加する、という捉え方をするそうです。
お金があるから経済活動をするのではなく、経済活動をしたいからお金を持ってくる、ということですね。
ところでこのお金、どこからくるのでしょう。経済活動をしたいと言っても、お金がなかったらできないじゃないですか。
彼が言っていたのは(酔っていたようで曖昧だけどとあとで言っていた)、国債を大量に発行するということをするらしいです。
そうすると、国民が借金をしやすくなるようです。先ほど書いたように、やりたいことがあるからお金を借りる人が増えるってことですね。その結果経済が回り、企業にお金が入り、企業がナイスな活動をして、社会が良くなって、消費者に帰ってくる。このようなサイクルが生まれるようです。
とても素晴らしい社会がやってきそうですね。
理論通りにことが進めば。
人間ってそんなに単純でしょうか?
消費者心理、それが行動経済学
上で書いたのは、あくまでも理論です。我々人間は、消費者は研究者や学者が思っている通りには行動するとは限りません。
例えば、スーパーやコンビニの例を出しましょう。
今日はお菓子を買わない、そう決めて鋼の意志でお菓子コーナーをすり抜けてきてもレジ前にあるガムや唐揚げを、つい買ってしまう。
はたまた別の例。
性能的には同じスマホなのに、みんな使ってるから、かっこいいからという理由でiPhoneを使う。日本は外国に比べてiPhone率が高いそうですよ。
他にも例を出せばキリがないのですが、ただ「なんとなく」といったことで消費活動の意思決定が成されているということが往々にしてあります。
この人間心理を、学者や研究者は理論に組み込むことができるのでしょうか。この気まぐれな人間心理を、どのように扱うのでしょうか。
現代貨幣理論に関しても、貨幣が多く個人の手元にあったとしても、全員が全員それを社会に還元する、経済活動をするとは限りません。なんとなく将来が不安だから貯金するという人もいるでしょう。
というように、経済学と心理学はなかなか面白い観点で接点があるようです。お分かりでしょうか。
この経済活動における人間心理を研究する分野こそ、行動経済学です。
行動経済学、興味深い
行動経済学(behavioral economics)とは、経済学と心理学が融合した学問で、人間の「人々が直感や感情によってどのような判断をし、その結果、市場や人々の幸福にどのような影響を及ぼすのか」を研究する学問です。行動経済学は経済学の新しい領域として2002年に心理学者のダニエル・カーネマン、エイモス・トベルスキー、そして経済学者のリチャード・セイラーらによって創設されました。
従来の経済学では「人は合理的な行動をする」という前提で研究が進められてきました。つまり、人も企業も政府も、最大限の利益を追求するよう合理的に判断し、一度決めたことは実行することを前提としています。
しかし現実の人間は、必ずしも合理的な判断をするとは限りません。人々は「得られる機能は同じだが、何となく高いほうを買った」「貯蓄や投資をしたほうがよいことは理解しているが、実践できない」など、客観的に見ると不合理と思える行動を取ります。行動経済学では、このように「直感や感情によって合理的ではない判断をする」ことを前提にその理由や理論を研究するのです。
従来の経済学が「常に合理的な行動を取るフィクションの人間」であるなら、行動経済学は「感情によって時に不合理な行動を取る現実の人間」を対象にしたものだといえます。
https://www.sprocket.bz/blog/20220531-behavioral-economics.html
だそうです。
「合理的ではない判断をすることを前提とする」ですって。今までこの発想、私の中にありませんでした。
最近の私は、今まで学んできた経済理論に対して、どこか冷めた目で見ていました。「でもそれって、理論上はでしょ。」なんてね。「情」がある限り全てがうまくいくわけじゃないって思っています。
こんなことも書いたりしてました。
行動経済学は、今の私の疑問にマッチする学問でした。
来年の今頃苦しんでいるであろう卒業論文、そのテーマ候補の一つとして、しばらく勉強してみようと思います。
私が行動経済学を勉強することによって、MMTを勉強するO君との会話が一層楽しくなりそうですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
