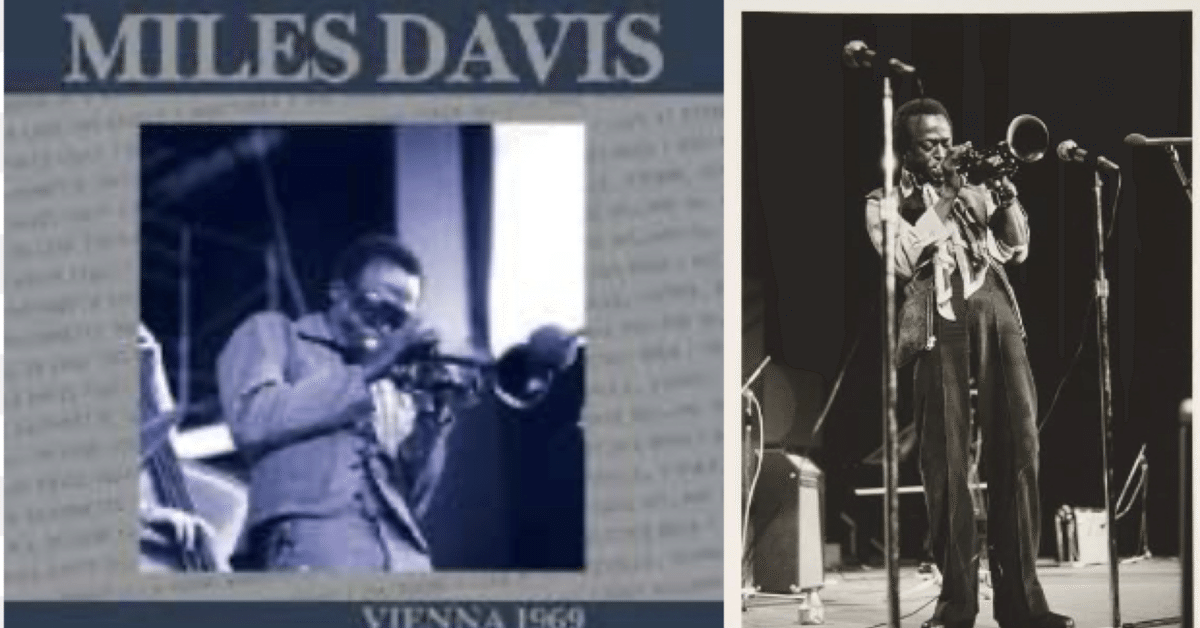
1969年10月31日ウィーンのマイルス・デイヴィスを聴く
personnel
Miles Davis (trumpet)
Wayne Shorter (tenor Saxophone, soprano saxophone)
Chick Corea (electric piano)
Jack DeJohnette (drums)
Dave Holland (bass)
マイルスが1969年に率いた五重奏が”Lost Quintet(失われた五重奏)“と呼称されている事実は、今この記事を読んでいる殆どの人にとっては知れていることであろう。言わずもがな、スタジオはおろか公式録音が一切なされなかったことからこの呼び名が付いている。これもまたどこかで記述したことの繰り返しになるが、このロスト・クインテットが名実ともに「失われた五重奏」であったのは、少なくとも四半世紀以上前。現在では各国のFM音源が多数発掘され、「失われた五重奏」であったのも今は昔…といった観がある。
ロスト・クインテット、あるいはそれに限らず「電化マイルス大発掘時代」の先鞭をつけたのは公式盤『1969 Miles』であったように思う。1993年、マイルスの死後、もっとも早期に登場した「発掘物」は本作であった。というのも、マイルスの生前、1969年~1975年までのライブにおいて、リアルタイムですぐさまに音盤化されたケースというのは凄く珍しい。「レコードに満足して、ライブに客が来なくなるのを危惧した」といったところが理由として大きいだろうが、結果的にこの商業的な手堅さが電化マイルスへの無理解を齎した…というのは考えすぎであろうか。
なにはともあれ、マイルスの死後、事態は(ファンにとっては)好転した。『1969 Miles』には凡そ今までのマイルス者が知り得なかったマイルスの、RTF者が知り得ないチックの、ECM者が知り得ないホランドとジャックの、VSOP者の知り得ないショーターの姿があった。さらにいうと、「オーネットを始めとするフリー派を敵視していたマイルス」なる定説が長年定着していただけあって、ここで聴けるフリー・フォーム・インプロヴィゼーションは一層各界に衝撃を与えた。「まだ誰も知らないマイルスが隠れている」…このロマンが人々を突き動かし、今に続くブート大発掘の時代を迎えることとなる。そんな時代があったからこそ、「今やロスト・クインテットは珍しくない」と言えるのだ。日夜研究に邁進し、幾多の音源を発掘させてきた先人たちには感謝してもしきれない。ありがたやありがたや。
ところで“各国のFM音源が発掘され…“とは具体的にはどの時期のことを指すのであろうか。まず1969年であることは当然として、ここでロスト・クインテットを二つの時期に大別したい。まず発足した2月25日(もしくは3月2日)のロチェスター公演から7月27日ニュー・ブランズウィック公演に至るまでの「アメリカ・フランスのロストクインテット」期。この時期はアメリカを中心に、忙しなくツアーに出ていた時期である。なお音源としては今の所10個ほど見つかっており、7月25日フランス『1969 Miles』もこれに含まれる。記録によると、代表作『Bitches Brew』が録音された8月19〜21日の後も9月9日までアメリカにてツアーに出ていたようだが音源は見つかっていない。今後の発掘が望まれる。
続いてマイルスたちはヨーロッパツアーに出る。10月26日ミラノから最終公演11月9日ロッテルダムまでの時期は「ヨーロッパのロストクインテット」と呼びたいと思う。こちらも数にして10個ほどの音源が存在する。うちオーディエンス録音は26日ミラノと11月1日ハマースミス・オデオンのみであり、その他は全てテレビ・ラジオなど何らかの形で公式録音されている。
なお付け加えておくと、以上の区分は音楽性の違いを示しているわけではない。「それじゃ分けて語る必要なんてないじゃん?」なんて話になってくるだろうが、奇しくも二つの時期で10個づつと綺麗に分けられることから、一応このような説を提唱してみた。今後、現在手付かずな8月の音源が発掘される機会があれば、細かな音楽性の進化について語ることができるようになるかもしれない。いずれにしてもアメリカ・フランス期の暗黒大陸っぷりをみていると「今やロスト・クインテットは珍しくない」なんてことは未だ言えない気がしてくる。
さて、そんなこんなで今回取り扱いたい音源は、ヨーロッパ期より10月31日ウィーン公演である。"So What"レーベルでは『Lost Quintet In Vienna』、"Megadisk"レーベルでは『Vienna 1969』と呼称されている音源である。ちなみに中山氏の『聴け!』においても当然取り上げられているが、その紙面はロスト・クインテットそのものに関する補足で多くが占められている。演奏が地味すぎるあまり、触れようがなかったのだろうか。
いや、むしろ逆だと思う。ロスト・クインテットは確かに激しい。しかし筆者が思うに、この激しさは展開的にかなりパターン化されており、楽理を交えたりしない限り、大抵表現は似たり寄ったりになる。それが演奏例としては晩期に当たるヨーロッパ期ともなれば尚更である。中山氏が演奏にほとんど触れなかったのはこんな理由があったのではないか。
幸いなことに、noteには紙面の限度というものがない。可能な限り仔細に観察して、出来る限り語り尽くしたいと思う所存である。
① Bitches Brew
一曲目は《Bitches Brew》!…とその前に一言いいですか。この音質、ソースはFM音源とのことだが、録音状態があまりよろしくなかったとみる。具体的には「ピーー」というノイズが入っている。「なにをそんな程度で」と仰る方もいるかもしれないが、トータルで48分と少し、このノイズが地味に喧しいのだ。
とはいえ有り触れたオーディエンス物と比べたら美麗に聴ける方。ここはごちゃごちゃ言い立てず素直に楽しむことに集中しよう。
本日一発目のマイルスのフレーズは高らか。ジャックにチックにホランドがその裏で怪しく盛り立てる。混沌の中で静かにジトジトと熱気を増していくこの日の雰囲気はスタジオ版のそれとも非常に近しい。
続くのは本日一発目の登板であるショーター。ヨーロッパツアーでの彼は好不調の波が割と激しいが本日のコンデションはどうだろう。まずは小手先の緩いフレーズから、徐々にきつく締めあげていくのが彼のスタンダード。この日も同じ手段に打って出るが、並走するチックのエレピに迫力で負けている。本日一発目のショーター、点数に直すと65点といったところか(何様?)。
その後のチックのソロでは場が完全にフリー状態と化す。先ほど”この日の雰囲気はスタジオ版のそれとも非常に近しい“と述べたが、当然『Bitches Brew』にはこんな展開は存在しない。フリー嫌いなマイルスのフリージャズ(もちろん当人は吹いてはいないものの)、これこそ秘宝である。
② Agitation
二曲目は第二期クインテットより《Agitation》。マイルスの導入フレーズから疾風のように突き抜ける、突き抜ける。リズム隊がやや激しめの4ビートに逆戻りしてもお構いなし、世間的にはいい歳こいた当時43歳のマイルスを止められるものは誰もいない。考えてみれば電化時代は彼にとって第二の思春期であったのだ。思春期の少年少女が何かと潜在的幼児性暴力癖を患っているように、マイルスの吹くトランペット一つ一つは刃物のように尖っている。
最早入れ替わって出てきたショーターのソロなどどうでもいい。いや、どうでも良いなんてことは無いが。ここでのショーターはソプラノを吹く。オマケにチックの後方支援なのか妨害なのか見分けのつかないバッキングが無いだけに自由に吹きまわり飛び回る。最後にチック・ジャック・ホランドのフリー大暴走が訪れて次の曲へ。
うーん、こう何度もリピートして聴いていると疲れが何倍にも増して蓄積される。やはりロスト・クインテットはサラッと流しで聴くのが一番よいのかもしれない。理性が危うくなる前に程々のところでとどめておこう。
③ Miles Runs Voodoo Down
”マイルスはヴードゥーを走る“とは、改めて考えると電化時代そのものをよく表していたといえないか。“黒”を徹底的に究めつくし、行きついた先は言わずもがな『Agharta』と『Pangaea』。まだ純ジャズの色濃い時代から、この後の未来を既に示唆していた。
それはともあれこの日の《Miles Runs Voodoo Down》はやや異色。特に出だし、ホランドが特徴的なベースラインをいつも以上に丁寧に刻み、ジャックもやや大人しめ。ともすると、スローな曲だと勘違いしてしまいそうだ。しかしながらロスト・クインテットには《Sanctuary》《I Fall in Love Too Easily》といったバラードパートは存在すれど、《Honky Tonk》《Yesternow》といった中だるみする展開はほとんど存在しない。最初爆発すれば、数分数秒の緩みを挿み、その後すぐさま爆発する。爆発→緩みの展開は電化時代のライブに共通した特性であるが、ロスト・クインテットの場合、その「緩み」の場面が極端に短い。トータルとしては爆発している場面の方が圧倒的に多いのである。
ということもあってこの日のテイクもダルな展開とは程遠い。マイルスのソロに対してジャックとチックが入念にツッコミを入れる。マイルスが高らかに吹けば、チックとジャックが一緒に暴れ回り、マイルスが大人しめ吹けばチックとジャックも静謐に後ろ手に回る。そうか、出だしが少しスローであったのは、この展開のためにこそあったのか。
しかしショーターがソロを取るとまたバンドのアトモスフィアが変化する。先ほどとは違い、必要以上にチックとジャックとホランドがアブストラクトに自己主張する。マイルス親分が出ている間は流石に気を遣って主役を譲るが、それ以外の場面であれば全員が全員ライバル同士。ここに1965年Plugged Nickel時のような「マイルス VS それ以外」の構図は再現されない、されようがない。アヴァンギャルド全開で瓦解が目に見えているバンドを、理性とリーダーシップで繋ぎとめているのはマイルスただ一人。これが第二期クインテットとの違いである。
ソロ回しはマイルス→ショーター→チックと来て再びマイルスの手に還る。この辺までになってくると、冒頭で述べた「ピー-」も気にならなくなってきた。それより何よりジャックのドラムである。「なんでやねん!なんでやねん!」とハリセンでツッコミを入れ、ドシンバシンと喧しくてしようがない。この喧しさと比べればノイズの喧しさなんて、てんで大したことがない。
④ I Fall in Love Too Easily
ここからは恒例のバラードパート。取り違えてはならないのが、先ほど述べたように70年以降の《Honky Tonk》ないし《Yesternow》ないし《Ife》などのスローパートとは性格が違うのである。スローパートとはどちらかといえば「ダル」な展開が目立ち、バラードパートはあくまでもマイルスの独唱がメインであるように思う。ともにスローであることに違いはないが、何にせよ文脈と雰囲気が違うのだ。
混沌と混乱のパートは③までで幕を閉じる。長いコンサートであるとこのパートが3、4曲目あたりに持ってこられることが多いが、この日は短めともあってこんな感じの展開に。演奏は静けさに包まれ、ここにきて「ピーー」が再び自己主張してくる。ジャック、ホランドよ、早く出てきて思う存分暴れてくれ!
⑤ Sanctuary ~ The Theme
残る4分間と少しは《Sanctuary》の出番。魔境を乗り越え、華爛漫という表現が似つかわしいのがスタジオ版での《Sanctuary》。10月31日のライブにおいてもその雰囲気が活きてくる。舞台は華やかに、マイルス、ショーターのユニゾンにて綺麗に幕を閉じる。
まだ《Spanish Key》が弾かれていようが、《Funky Tonk》が弾かれていようが、《The Theme》にて強引に〆るのがマイルスの流儀。しかしそれがどうか。この日は実に綺麗に収まっている。てっきり後先考えず勢いで突っ切るのが電化マイルスだと思っていたが、親分は親分でしっかりと頭の中に地図を描いていたのだ。このテイクは、その試みが成功を収めた例だといえよう。
総評
入門度 ★★★☆☆
当然オーディエンスと比べれば良好な音質ではあるものの、『Swedish Devil』や『Second Night』にはパフォーマンス・音質の面で一段劣るのでこの評価。ロスト・クインテット入門には向かない。
テンション ★★★★☆
このバンドの演奏としては平常運転であるテンションの高さが楽しめる。総時間48分と短いが、ロスト・クインテットの熱気をコンパクトに摂取できるので、これはこれでよし。
音質 ★★★☆☆
FMソースとのことだが、若干のノイズと籠り気味な音質が気になる。ヨーロッパツアーのFM音源の中では低ランクに位置する。
パーソネル ★★★★☆
メンバー全員いつも通りの好調ぶり。ただし強いていえばこの日はショーターがちょっとノリ切れていなかったかもしれない。
レア度 ★★★☆☆
FM音源が充実しているヨーロッパ期ともあってレア感はそこまでない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
