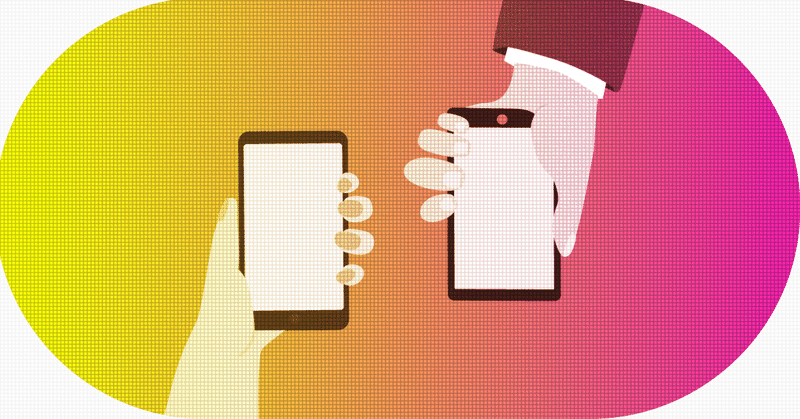
「恋人選びは、AIマリーにお任せください!」 本編
「できたぞ、信也!」
禿げた頭をピカピカさせながら、爺ちゃんが階段を駆けあがってきた。齢六十をとうに過ぎたというのに、足どりが信じられないくらいに軽い。
「聞いてくれ! ついに、完成したんじゃ!」
叫びながら、俺の鼻先にぶつける勢いで、スマートフォンのようなものを突きだしてきた。
「一体、なに?」
のけ反りながらも、かろうじてそれを受けとる。
手にすっぽりと収まる程度の大きさの、黒塗りの四角い板。見れば見るほどに、ただのスマートフォンだ。
「お前、そろそろよい歳なのに、彼女の一人もいないじゃろう? そこで、ワシがお前にピッタリの相手を見つけてやるために、マッチング用人工知能を開発してやったのじゃ!」
「余計なお世話だよ!」
「その名も『AI六号』じゃ! どうだ、すごいじゃろう!」
「俺の話を聞いていないし、命名が雑すぎる……」
まだ高校一年生なのだから、心配されるよう年齢でもないはずだ。
それよりも、目の前で興奮ぎみに話している自称・発明家の爺ちゃんの代表作は、「ミカンの皮むき機」だ。無論、家族の誰も使っていない。
AIなど、本当につくれたのだろうか。それも、六号ということは、前に五台分も作っていたというのか? 胡散臭さすぎる。
「このAIは、すれ違った人物のスマートフォンをスキャンして相手の趣味嗜好を分析し、お前にピッタリな女の子を見つけてくれるんじゃ!」
「それ、ハッキングじゃない……?」
「細かいことを気にしてはいかん! そんなことより、ほれ、使ってみろ!」
爺ちゃんが俺に無理やりボタンを押させると、画面が青く光った。しばらくして、端末から声が聞こえてきた。
『はじめまして、マスター。AI五号と申します。私がマスターの運命の相手を見つけてみせます』
なんで名前が違うのかという疑問はさておき、女性的な合成音が話しだした。しかし、女性だと思うと、なおさら気になって思わず指摘してしまった。
「……五号でも六号でもどっちでもいいけど、その名前はどうにかならない? 呼びづらいよ」
『……では「結婚」という言葉から、マリーとお呼びください』
まさかきちんとした反応が返ってくるとは思っていなかったので、少しばかり驚いた。
爺ちゃんを見ると、どうだといわんばかりの得意そうな顔をしている。
「恋人選びは、マリーにお任せください!」
「わかったよ、マリー」
俺はしぶしぶ、機械に返事をした。
○
爺ちゃんの命令で、そのままマリーを持って近所をぶらつくことになった。気恥ずかしかったので、同行するという申し出は全力で断った。
最初はまともに使うつもりなどなかったが、年の近い女性とすれ違うたびに、マリーが自動的に相性を測定したので、強制的に試すことになった。
占いみたいで、思ったよりは楽しかった。が、結果はどれも芳しくなかった。
最初に出会ったのは、ふわふわとした雰囲気の可愛らしい女の子。ピンクのフリルのついたスカートを目で追っていたら、AIにピシャリといわれた。
『あれはぶりっ子だから、駄目です』
次に会ったのは、清楚系のお姉さん。白いワンピースが眩しい。
『あのタイプは、性格が悪いです』
キレイな女性だと思っていたのに、完全否定された。
「なんか、全部外見で判断してない?」
『そんなことはありません。論理的な分析アルゴリズムで導きだされた結果です。そんなことより、次の女性が来ましたよ』
遠くに女子高校生が見えた。なんと俺と同じ学校の制服だ。近づいてくると、顔にも覚えがある。
学校のマドンナと囁かれている、隣りのクラスの少女だ。確か名前は、相田真里奈といったか。
親の転勤でヨーロッパにいた帰国子女で、透きとおるような白い肌に、サラサラな黒い髪の美人だ。すれ違うと、なんだかいい匂いがした。
彼女はこちらには見向きもせずに、行ってしまった。話したことはなく、面識もほとんどないのだから当然だろう。
彼女が角を曲がって見えなくなった頃、マリーが判定をくだした。
『彼女は素晴らしいです! 最高です! 彼女こそが、マスターの運命の相手です!!』
興奮ぎみにエクスクラメーション・マーク多めに話す様子が、爺ちゃんと重なる。AIも親に似るのかなどと考えながら、答える。
「彼女は無理だよ。学校のマドンナだぞ? さっきだって、目も合わせなかったぞ?」
『それは、恥ずかしかったからです』
爺ちゃんと同じような、こじつけをいってくる。
しかし、彼女は無表情無口なクールビューティー、「氷の女王」だともっぱらの噂だ。恥ずかしがり屋だから、という理由のはずがないだろう。
『とにかく、当たって砕けろ、です。GO! GO! マスター!!』
砕けたら駄目だろう、と思ったが、いい返す気力も失せた。
○
翌朝、いつも通り学校へ行こうとしたら、相田とバッタリ出くわした。ちょうどT字路のところで、相田が角から曲がってきたのだ。
「運命の相手」という言葉を思いだし、ドキリと心臓が跳ねた。
昨日あれから、乙女心の勉強だとかで、女性への気配りの仕方や会話の保たせ方など、さんざんマリーの講義を聴かされた。
マリーはなかなか饒舌なAIだということが、よくわかった。性能も目をみはるものがある。
いっそのこと、マリーのような彼女ができたら、会話が楽しいだろう。断じて、無機物に愛を感じる趣味はないが。
マリーの講義を参考に、相田へ声をかけてみる。
「お、おはよう」
「……おはよう」
緊張のせいで声が上ずったが、なんとか返事はしてもらえた。
「いい天気だね」
「……そうね」
違う、そんなことをいいたいのではない。これではまるで、不審者ではないか。よく無視されなかったものだと思いながら、どうにか次の言葉を探す。
「俺、一年D組の佐藤信也。よろしく」
「……E組の相田です」
会話をもたせようとして唐突に自己紹介をしてしまったが、相手も返してくれたから、よしとしよう。
「ねえ、君ってパンケーキ好き?」
なんの脈絡もなくいってしまったが、これはマリーによるリサーチの成果だ。
相田のスマートフォンをハッキング、もとい分析した結果、ネット検索でよくパンケーキを調べていたらしい。俺にパンケーキの店へ誘うように、力説していた。完全にナンパになってしまったが。
「もしよかったら、今度パンケーキのお店へ一緒に行かない?」
「はぁ……」
なんとも曖昧な返事だ。もしかして、パンケーキが好きではなかったのだろうか。嫌いなあまり、ネットで悪評でも書きまくっていたのだろうか?
「あ、学校に遅れちゃうから……」
彼女はそういって、こちらを見もせずに、足早に去ってしまった。
「なぁ、マリー。話が違うんじゃないか?」
呆然としながら問いかけると、さすがのAIも返事に窮したようだ。
『……マスターの誘い方の問題ですよ』
しばらくしてから、そう短く答えた。
○
放課後。家へ帰る途中、俺はマリーに不満を漏らした。
「分析して、相田さんとは相性ピッタリのはずなんだろう? 俺、彼女と相性が合う自信がないなぁ……。マリーとなら、話が合いそうだけど。いっそのこと、マリーが人間ならつきあったのに」
「本当?」
答えたのは、マリーの合成音ではない、女性の声。
びっくりして横を見ると、遊歩道沿いの木の陰から相田がこちらを見ていた。
なぜ、そんなところに――?
その疑問が口から出せないほどに驚いていると、相田も慌てたのか、顔を真っ赤にしている。
『あ、しまった! 直に声を出しちゃった……』
氷の女王の肩書きはどこへやら、年相応の女の子らしい表情豊かな顔をしている。それが彼女にとても似合っていて、可愛らしい。
だが、今は見惚れている場合ではない。最後の台詞は、端末から合成音として聞こえてきた。
「もしかして、今までマリーとして喋っていたのって……」
少女が顔を赤らめたまま、コクリと頷いた。
「『私です……』」
○
相田を家へ連れていき、じっくり腰を据えて話すことになった。
そして今、目の前で爺ちゃんと相田が並んで正座して、うなだれている。
「これはどういうことだよ、爺ちゃん?」
「どういうことって、いわれてもなぁ……」
精一杯のジト目で睨みつけると、爺ちゃんが禿げた頭を掻きながら、困ったような笑顔を向ける。
「私がお願いしたんです、大おじ様に」
「え? 大おじ様?」
俺に疑問符が貼りついた顔を向けられた爺ちゃんが、なに食わぬ顔で答えた。
「そうじゃ、この子はお前のはとこだ。真里奈ちゃんがどうしてもお前と話したいというから、ワシが一計を案じたんだ」
「なぜ、そこで『一計を案じる』必要が?」
冷えた目を向けると、爺ちゃんが黙った。
「私がお願いしたんです。海外で、見た目の違いから対面でのコミュニケーションが苦手になってしまって。そのせいで、日本に戻ってからも、うまく話せなくて……。でも、日本の友だちとしていた電話でなら、話したいことが話せるんです。だから、信也くんともお電話から始めて、きちんと話せるようになりたいと」
相田が熱の込もった目を向けてきた。しかし、俺は困惑するばかりだ。
「なんで、そこまで? 俺、君と話したこともないのに」
「昔、一度だけ会ったことがあるんです。ずっと小さい頃に。そのときに、その……好きになってしまって」
「え?」
彼女のことを忘れていたことを申し訳なく思って聞いていたら、思いがけない告白をされた。
自分を好いてくれた女の子を忘れるなんて、なおさらひどいではないか。
「それで、大おじ様に、信也くんにアタックする方法はないかと相談したら、今回の『運命の相手』作戦を授けていただきました」
「そうなんだ……。思いだせなくて、ごめん」
作戦名については、全力で聞かなかったことにした。
「いえ、気にしないでください」
そういってはにかむ少女に、失礼を承知で訊いてみた。
「その……俺のなにが好きだったの? 自慢じゃないけど、人に好かれるようなところはないと思うけど……」
相田はえくぼをつくって、ニッコリと笑いながら答えた。
「だって、信也くん、小心もののくせにお調子もので面白いんだもの。昔、『木登り上手だね』って褒めたら、てっぺんまで登って降りられなくなったでしょう?」
その言葉で、ぼんやりとだが、思いだした。
遠い昔、木登りをして遊んでいたら、声をかけてきた少女がいた。すごい、すごいと褒めるものだから、つい調子に乗って降りられない高さまで登ってしまった。
彼女があのときの太鼓もち少女だったらしい。
「それは……思いだしたけど、なんでそれで俺のことが気に入ったのか、全然わからない……」
爺ちゃんが、少し気の毒そうな顔をして、こちらを見ている。
反対に、相田は横でニコニコしている。
AIがニセモノだとわかった今、相性が本当に合うかどうかもわからない。わからないが……。
「まぁいいや。とりあえず友だちから始めよう、マリー」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
