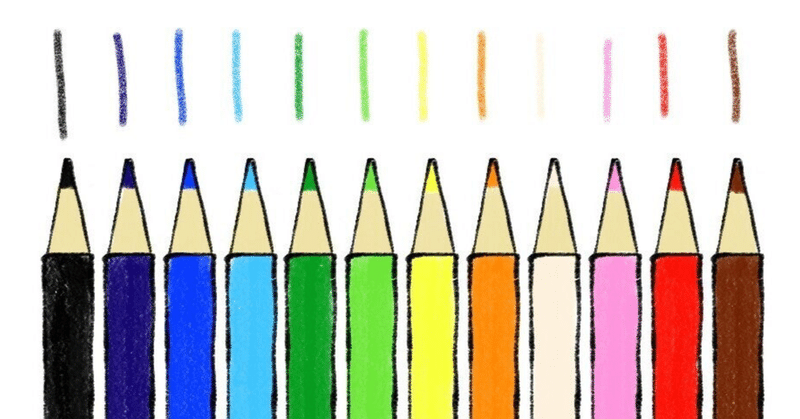
多様性への先行的配慮には限界がある
世の中にはいろいろな人がいる。そしてそのそれぞれが相手に対して何らかの接し方を求めている。しかしその多様性は無数にあり、全てに配慮することは不可能である。
よくTwitterなどで、目に見えない障害や認知度の低い特性を持っていたりする人が、「伝われ〜」や「広まれ〜」という文で知られていない病気・障害を周知するための投稿をすることがある。
それは大切なことだが、そういった少数派の物事は無数にあり、みんなが好きずきにこれ覚えてこれ知ってと言ってもそれは不可能である。投稿された内容のものでも大半の人は次の投稿を見る頃には忘れている。
ではどうすればいいのか。全く人に対して気を遣った話し方をするつもりがない人はどうでもいいと思うだろう。
だが、出来るだけ失礼なことはしたくないと思う人は悩むと思う。
◎持てる知識は持つ
まず出来ることは、可能なだけ知識を持つことだ。全ての知識を得ることは不可能だと言ったが、自分が少しでも興味を持てることや、多様な少数派の中でも多数派の属性なら情報も比較的多いし活用機会も多いので、調べやすいと思う。
◎多様性自体への認識
ただ、先程も言った通り、全ての多様性の知識を持つのは不可能である。では知識の無い多様性に出会った場合どうすれば良いのか。その方法とは、対応の仕方を身につけることだ。
相手がどんな性質を持っていたとしても、相手の言うことを否定したり嫌悪感を出したり勝手に決めつけたりしないように意識しておけば、どんな多様性にも対応出来ると思う。
つまり、話す前から相手が何かの少数派かもしれないと考えて先行的に配慮することには限界があるが、発覚した後に適切な対応をすることはどんなケースでも可能だということだ。
普段から少数派を下に見る意識を持っていなければ、そういう場面に出くわしたときに相手を傷つけない対応は出来ると思う。大切なのは、知識より意識だ。
◎少数派側が気を付けること
少数派側は、相手が明確に悪意があって差別的なことをして来ているのか、そうではないけどちょっと対応しきれていないのかは見れば分かると思う。
そこで、対応しあぐねている人に対して差別だ偏見だなんだと厳しく追及すると相手は萎縮し、そもそも関わろうとしなくなってしまうだろう。
それが息苦しい世の中になったなどと言われてしまう原因になる。過剰に弾圧したり言葉狩りをするのは逆効果でしかない。
自分にとっては当たり前でも相手はそうではない。寛容な精神を持つべきだと思う。
◎多数派側が気を付けること
逆に多数派側の人も、相手が信頼して打ち明けてくれたのだから、無下にしてはいけない。もちろん知識がないのはしょうがないし、勉強しろとも言わない。
ただ、人として出来る対応はあるはずだ。世の中の流れを見ていればどう接すればいいのかも大体分かる気がする。そのくらいはアンテナを張っていてもいいのではないか。
◎配慮したくない人へ
多様性にそんないちいち配慮していられないという考えも、多様性の数的にも知識量の限界的にもよく分かる。
面倒臭いししたくない、する必要を感じない、私の周りにはいないし、と思うのも理解出来る。
でも、やはり出来ることはしてほしいと思う。
しないならしないで構わないが、それなら話した相手が偶然何かの少数派で、無神経な発言をしてしまったときに怒られたりしても反抗せずに運が悪かったと素直に諦めてほしいと思う。
それは配慮をしなかった責任であり、楽をした対価なのだから。
どうせ「少数派」だからそういう人に当たる確率は低いし、当たっていても正直にカミングアウトされることもほぼないから、大半の場合においてしなくてもいい面倒臭い配慮をするよりもしない方がエネルギー的にお得だと思うなら別にそれで良いと私は思う。
こういう皮肉的な言い方はしたが、本当にこういう生き方でも個人の自由なので私は否定などするつもりはないし、自分の中の正義で他人の行動を縛ってはいけないと思うから強制しない。
だがそういう、配慮をしない生き方をするならするでケジメはつけてほしいし、結局傷つけて離れられたり糾弾されたりするリスクはあり、コストはかかっている。
だから、普段から多少面倒くさくても配慮する方をとるか、普段は楽をしてたまにデカいしっぺ返しを受けるか、どっちを取るかになるが、どっちの方が人間的に良い選択であるかは明白だと私は思う。
◎まとめ
配慮する側もされる側も相手を思いやることが大切だ。昔はそんなことしなくても良かったと思うかもしれないが、本来しなければいけなかったのだ。
最近ようやくそれが広く叫ばれるようになったから最近しないといけなくなったように感じるが、人と人が接していくのに、気を遣わなくていいはずがない。今も昔もないのだ。
それなら、持てる知識は持った上で、どんな場合にも対応出来る意識の持ち方を大切にして生きていってほしいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
