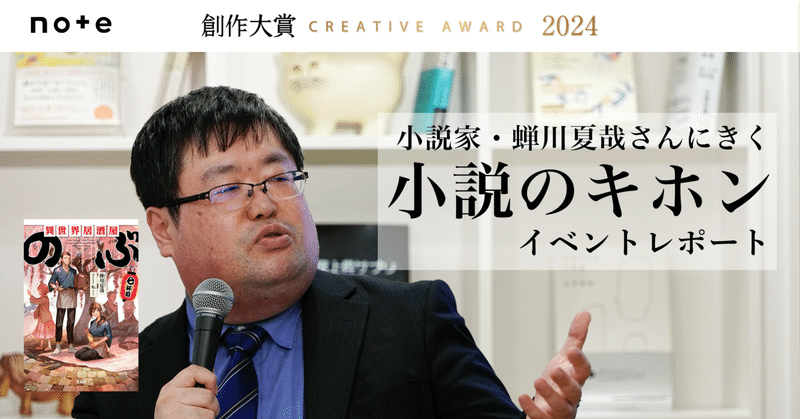
小説の書き方って?『異世界居酒屋「のぶ」』蝉川夏哉さんに学ぶ小説のキホン
イベントレポートはこちら ↓
・・・
創作大賞2024に参加したい。小説を出したいけど、書き方がわからない。そんな方々に向けて、noteでは代表作『異世界居酒屋「のぶ」』の小説家・蝉川夏哉さんに、小説の書き方の基礎的なノウハウを教えていただく講座を開催しました。
蝉川夏哉さんは小説投稿サイトからデビュー。『異世界居酒屋「のぶ」』が第2回「なろうコン大賞」(現・ネット小説大賞)を受賞しました。同作はその後マンガ化、アニメ化、実写ドラマ化など、さまざまなメディアミックスが行われる大ヒット作品となっています。
本記事では蝉川さんが講座でお話しされた内容をもとに、企画やネタの探し方、プロットやキャラクターのつくり方、執筆への向き合い方などをご紹介します。
小説のキホン。まずは書きたいことを書く
——いまはだれでも気軽に小説を読めて、書ける時代になりました。そんななか、改めて「小説を書く」ということについて、蝉川さんはどう感じていますか?
蝉川夏哉さん(以下、蝉川)人類の歴史のなかで、確かに2020年代は最も多くのひとが「書いて発信することができる」時代だと感じます。だれでも文字を連ねていけば小説になりますから。しかし同時に、少子高齢化で小説を読むひとが減っているのも事実。読まれることを目的とすると苦しい時代とも言えるでしょう。この「読まれるのが大変」というのは、noteで文章を書いたことのある方なら、よくご存じなのではないでしょうか。
このような時代であるからこそ、私は逆転の発想で「書きたいことを書く」ことを主眼においてもよいと思います。まずは書きたいことを書く。次に読まれる方法を模索していく。こういった方法もひとつの手段だと感じています。

アイデアは細かい粒子を集めていくイメージ
——小説を書くとき、具体的なアイデアが浮かぶ方と、そうでない方がいると思います。蝉川さんは「書きたいものをどのように見つけているのか」という点について、お聞かせください。
蝉川 欧陽脩という中国の有名な文人は、アイデアが閃くに最適な場所として「三上」を唱えています。具体的には馬に乗っているときの「馬上」、寝る前の枕元を指して「枕上」、そしてトイレのことを示す「厠上」です。現代風に言い換えるなら、「馬上」は乗り物(当時は馬)で移動中ということになるでしょう。
このことから「アイデアが生活のなかに転がっている」のは間違いなく事実で、問題はそれをどれだけ見つけて、憶えて、記録できるかにかかっているということ。なるべくアイデアは、細かい粒子で集めていくことが大切です。
——アイデアが小さければ小さいほど、いろいろな場面でつかいやすくなりますよね。
蝉川 私もそう思います。あとおすすめなのがアウトラインプロセッサなどの、メモソフトです。アウトラインプロセッサは、さまざまな内容をツリーのように階層分けして記録できます。プロットを組んでシーンごとにハコ書きするなど、執筆につかうこともできますが、ジャンルごとにメモを取るのにも向いています。
最大のメリットは、スマホからでもパソコンからでもアクセスできること。出先で見つけたちょっとしたことをスマホでメモして、時間があるときにパソコンで整理できるのです。おもしろいサイトはURLではなく内容をコピー&ペーストして保存しておくこともおすすめですね。Webサイトはよく消えてしまうので……。ただし、コピーするときはどのサイトからいつコピーしたかを必ずメモして、出典を記録しておくことが重要です。写真や音声ファイルも貼り付けられるので、自分だけのネタ帳をどんどん拡充していきましょう。このような記録方法を駆使しながら、「現実を見る解像度を上げる」ことが大切です。
その後は、これがもしも……と、「異化効果」を考えてみてください。たとえば、「ファンタジー世界に居酒屋料理があったらどんな反応があるだろう」といった具合です。
また好きな映画、ドラマ、アニメ、漫画、小説の「何が好きか」をメモすることも重要ですね。意外と自分の「好き」を知らない方は多く、反対に「Not for me」なものも知りません。そして、なぜ好きなのか、好きではないのか、を深掘りすること。すると自分の書きたいものが漠然と見えてきます。
ぜひ「書けるもの(CAN)」、「書きたいもの(WANT)」、「書くことを求められているもの(NEED)」を考えてみてください。商業では「書けるもの」と「書くことを求められているもの」の重なる部分を求められがちですが、好きに書くなら「書けるもの」と「書きたいもの」の重なるところを選びましょう。あとは自分の成長のために書かないといけないものもあります。10年後に書きたい作品がある場合、書くコツを学んでおかないといけない。だからいま書くんだ、というような考え方もありますね。
キャラクターが自分に嘘をつく瞬間にこそ、テーマが宿る
——次にキャラクターを考えるのか、それともプロットを考えるのか。ひとによって異なると思いますが、先にキャラクターについてお話を伺えますか?
蝉川 はい。2020年代において、エンターテイメント小説ではキャラクターの比重がかつてないほど大きくなっていると感じます。いまのエンターテイメント小説の文脈からいうと、ストーリーとはキャラの変化であり、キャラ同士の関係性の変化だと定義付けられるとも考えます。展開に魅力がなくてもキャラが魅力的な物語は作品として成立し得ますが、その逆は現代では限りなく売れにくく、評価されにくいでしょう。そのため、キャラはやはりちゃんと考えたほうがいいよね、と思います。
何か伝えたいことやテーマがあるならば、それはキャラの内面や境遇に仮託するかたちで読者に届ける必要があると思います。キャラの生きざまを通して伝えるのが最善です。よくセリフを通して、伝えようとする方もいますが、実際にはキャラの行動と発言が真逆になった瞬間、つまりキャラが自分に嘘をついているときこそ、テーマは宿ると思うんです。そのようなことを加えられるようになると、作家としても一段上がっていくのではないでしょうか。
ただし、キャラが大切だからと言って、キャラから考えればいいというわけではありません。キャラ・ストーリー構成・テーマ・コンセプトのすべてを考え、そしてまたキャラを考え直す。このように行き来しながら、キャラに深みを与えていくのです。
また一人のキャラからではなく、二人のキャラから考える方法もあります。カップル、夫婦、バディ、親子、兄弟、師弟などの関係性を設定し、このペアがどのような状態から、どのように変化していき、結果的にどうなるかを考えていくと、キャラがより立体的になります。
——よくキャラクターシートをつくるかどうかという議論にもなります。私は企画書を拝見する機会が多いのですが、シートを埋めること自体が目的になっている方がいらっしゃいます。シートはただのスペックを書くもの。そこにキャラの魅力がすべて書かれているわけではないということですよね。

プロットは設計図。自分はどんなタイプの書き手かを見極める
——次はプロット、つまり物語の組み立てについてお話を伺えればと思います。蝉川さんはプロットについてどのようなスタンスをお持ちなのか、お聞かせいただけますか。
蝉川 私の場合、デビューするまではあまりプロットを書いていませんでした。しかしデビュー後、出版社とやり取りをするなかで、やはりプロットはあったほうがいいなと。プロットはいわば設計図です。プロットなしで書ける天才肌な方もいますが、プロットがあればそれを見ながら担当編集と話し合うことができます。
ただ書き手のなかには「プロットを書いて結末がわかったら、たのしみがなくなるからこれ以上書かなくていい」となる方がいます。実際にたのしく書くことは大切で、そういう方の書く作品には宝石のような煌めきが宿ることも事実です。そのため「自分がどのようなタイプの書き手か」を見極めたうえで、プロットを書く・書かないを判断するといいでしょう。
——なるほど。「商業をやっていく上で自分はプロットを書くんだ!」という方はどのようにプロットの書き方を学べばいいですか?
蝉川 物語の構成は、よく「起承転結」や「三幕構成」と言われ、フィルムアート社などから多くの本が出ています。そのなかの一冊を買ってみるのはどうでしょう。けれども、これらの本の多くは映画脚本の書き方の本であって、小説を書くためのものではありません。映像は見せるものですが、小説は読者にイメージを抱いてもらうものです。この違いは、心においてほしいですね。
キャラを中心に考えるなら、「だれがどのような状態から」「どうなった」という最初と最後のオチを決め、その間に「乗り越えるのが困難な障害」を考えるのも、プロットを立てるコツのひとつ。中身については、おもしろいことを思いついたときにどんどん変えていけばいいでしょう。最初のプロットはあくまでも思考の土台です。自分のスタイルに合ったプロットの立て方を見つけ、たのしみながら作品を完成させていってください。

書きながら直すのではなく、書き終えてから推敲
——続いて執筆のコツについてお伺いできればと思います。
蝉川 まず僕がいちばんお伝えしたいこととしては、「文字を書き惜しみしない」ですね。毎日必ず書くことはとても大切で、可能なら毎日1,000字以上、できれば3,000〜5,000字以上書けるとすごいです。この「必ず書く」というのは、風邪を引いていようが二日酔いだろうが、絶対に書ける文字数のこと。それが400字でも構いません。自分が絶対に書ける量を把握しておくことで、自分の定めた締め切りが適切かどうかが分かります。
次に書きながら直すのではなく、一度書き終えてから推敲しましょう。初稿で完璧な原稿を書き上げられるのは天才だけ。現代は何度でも書き直せるのが強みで、どんな駄文でも一度完成すればいくらでも直すことができるんです。何も書かなければ白紙のままですから、あとで直すつもりでどんどん書き進めてください。
——いま「書き惜しみをせず、毎日執筆をしよう!」と思った方も多いのではないでしょうか。実践する上で、何かテクニックなどはありますか?
蝉川 ご存知の方も多いかと思いますが、「ポモドーロ法」をつかうのもおすすめです。ポモドーロ法は、25分作業をしたら5分休憩するという時間管理術。25分でなくてもいいので、たとえば45分書いて15分休憩という執筆サイクルを回すことで、自分のなかにリズムをつくることができます。45分経過するまでは、絶対にスマホを見ないと自分にルールを課せば、自然に執筆文字数もふえるでしょう。
そして1日の終わりは、綺麗に文章を書き終えるのではなく、翌日のために一行中途半端に書いておくのもいい方法ですね。だれでも真っ新な原稿に向かうのは大変です。前日に一つ山を乗り越えておけば、次の日「やっぱり違うな」と思って文章を消したとしても、それを消す作業からはじめられます。作業に入ると、意外と思考を執筆モードに切り替えることができるんです。
——ありがとうございます。最後に本日ご覧になっているみなさんに向けて、メッセージをお願いできますか?
蝉川 "Done is better than perfect." というビジネス界隈でも馴染み深い言葉をご紹介します。「早く実行することは完璧に勝る」という意味だと思ってください。
かつてある編集者から「作家と編集者の違いはピリオドを打つことができるかどうかではないか」と言われたことがあります。小説をつくる上で、編集者は無限の選択を提示できるかもしれませんが、それを選び取り、ピリオドを打つのは作家の役目であり、権利です。
作家のみなさんは一節、一章でもいいので、早く完成させる。その意識を持ちながら、執筆をたのしんでいただければと思います。
質疑応答
当日挙がったなかから、いくつか質問を抜粋しています。全容を知りたい方は以下のアーカイブ動画をご覧ください。
Q1.書いている途中で筆が止まることがあります。何か対策はありませんか?
蝉川 自分のなかでルーティンをつくるのをおすすめします。たとえば、特定の喫茶店に行ったら、必ずポモドーロ法をつかって集中して書くなどを決めておくのです。また、自分の内面が乱れてしまって書けない場合は、「自身の文章を研ぐ作品」を決めておくといいでしょう。その作品を読んで、好きな文体のリズムを自分に取り込むことで、ニュートラルな状態に戻し、執筆に向きやすくするのです。その作品をつねに机の横に置いておけば、筆が止まりそうになった瞬間にいつでも手に取ることができます。
Q2. 蝉川先生が書かれている『異世界居酒屋「のぶ」』には、非常に多くのキャラクターが登場しますよね。それだけ多くのキャラクターを混乱なく書き分け、お話のなかで動かしていくために、整理などされているのでしょうか。
蝉川 実は、編集者と一緒に編集できるGoogleスプレッドシートでキャラクターを整理していました。そのシートには、キャラクターの名前、年齢、特徴、現在の状態などがすべて書かれています。プロットを組んでいる段階で、シートとプロットを見比べながら、各キャラクターがどのような状態になるかを自分で整理しているという書き方なんです。
ただこの方法は、群像劇が好きな人間だからこそできるという面があると思います。そのため、ほかの方は自分の得意な方法を見つけるのがよいのではないでしょうか。
Q3. ボツにしたシナリオやキャラクターがずっと心に残ってしまいます。供養の方法はありますか?
蝉川 そのキャラクターをつかった作品を再び書くのがよいと思います。シナリオも、もう一本書きましょう。先程もお伝えしたように書き惜しみはよくないです。短編でもいいので、たくさん書きましょう。先に短編で書いて、よいと思えばそのあと長編にすればいいので。実は同じキャラクターでも、何度書いてもいいんです。
▼講座のくわしい内容が気になる方は、動画のアーカイブをご覧ください。
プロフィール
ゲスト
蝉川夏哉(小説家)
1983年、大阪府生まれ。大阪市立大学文学部卒業。『異世界居酒屋「のぶ」』にて第二回なろうコン大賞を受賞。他の著書に『邪神に転生したら配下の魔王軍がさっそく滅亡しそうなんだが、どうすればいいんだろうか』(アルファポリス刊)がある。
X : https://twitter.com/osaka_seventeen
note : https://note.com/osaka_seventeen
進行
萩原猛(noteディレクター・編集者)
ファンタジア文庫副編集長、富士見L文庫編集長、カドカワBOOKS編集長、カクヨム編集長を経て、独立。現在は小説のほか、アニメやゲーム、漫画などの企画・原作制作にも関わっている。
Twitter:@yajin
note :https://note.com/takeshihagiwara
日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2024」開催中!
現在noteでは、あらゆるジャンルの創作を募集するコンテスト「創作大賞2024」を開催中です。21のメディアから書籍化や映像化、連載などのチャンス! 小説、エッセイ、マンガ、レシピ、ビジネスなど全12部門で、7月23日(火)まで募集しています。
詳しくは特設ページをご覧ください。
関連イベント
Photo by 玉置敬大 Text by 須賀原優希
