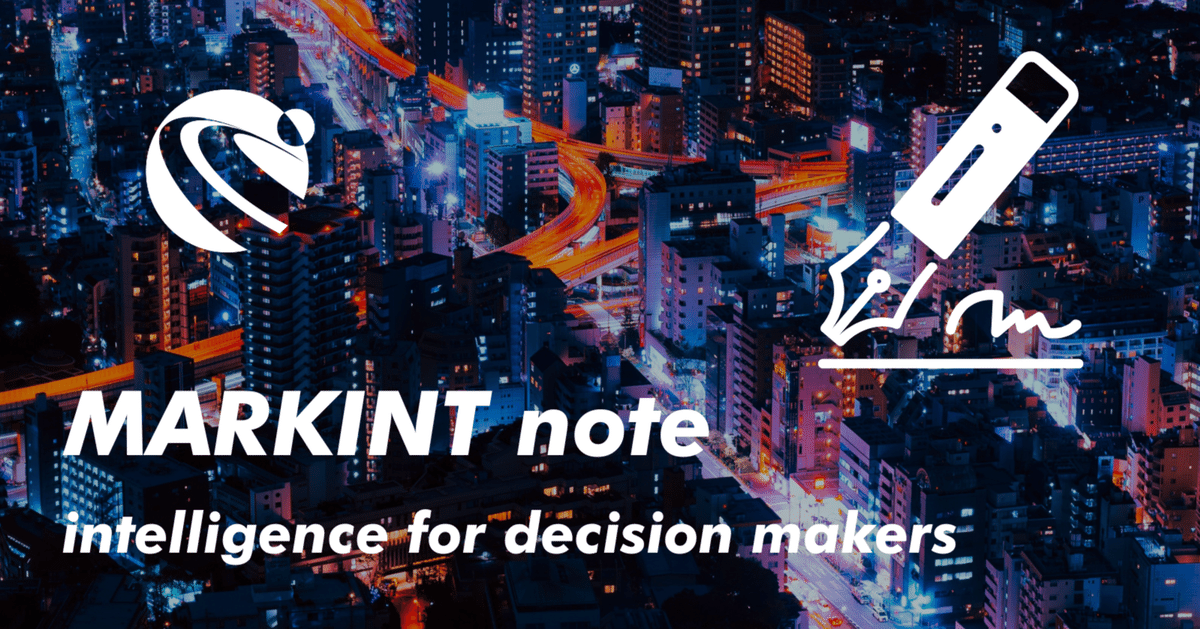
メディアとファシズム・ニヒリズム
昔よく読んでいた思想家に、マックス・ピカートというのがいる。19世紀から戦後まで生きたドイツの思想家で、ということは当然ナチスに関する問題を中心的に扱っていた。私が大学に入った13年前は、まだナチスだとかファシズムだとか、そういうことは興味を持つこと自体がある種のタブーみたいな空気があった。こんな山本七平の『空気の研究』の冒頭みたいなことを自分でも書くようになるとは思わなかったし、ナチズムが未だに蔓延っているということがあからさまになる時代が来るとはそれ以上に思ってもみなかった。山本よりも一歩論を進めるとすれば、「空気」なるものがどうやら日本に特有のものでもなく、全人類がそうなのだということが疫病の期間を通じて分かったことくらいか。日本人の中にも、私のように空気の読めない・読みたくない人もいれば、こちらが大多数を占めるが、群衆の中に埋没して個体識別不可能な状態で社会通念と通俗的概念のなかに融けているのが好きな人もいる。それはどこの国・文化で生まれ育っても、個体差のほうが大きいのだろう。
そういうわけで、大学時代はナチスの話をすること自体を忌避していたが、個人的な興味としてはナチスに関する情報や言説をいろいろ読んでいた。そのほとんどが例のお約束的言説に収束していくのに辟易していたときに、偶々発見したのがマックス・ピカートだったのである。
主著は『沈黙の世界(Die Welt des Schweigens)』で、こちらは日本語訳も絶版でほぼ手に入らない。『われわれ自身のなかのヒトラー』はみすず書房からいまも売られているはずだ。『沈黙の世界』は東大の図書館の書庫にあるのを一度読みに行ったことがある。『われわれ自身のなかのヒトラー』は買って読んだ。どちらも入手困難ないし高価で、そこそこ大部でもあるので読むのは大変だと思うが、そこで展開されている議論はいまでも有効性を失っていないと思う。
彼の主張は「ラジオがファシズムを生んだ」というものだ(だから『沈黙の世界』というタイトルになっている)。だがそれは何もナチスがラジオや演説によって大衆の心理を煽動したからだ、というような通念的な話ではない。ラジオが崩壊させたのは、社会におけるそれぞれの場面の境界である。つまり、ラジオ以前には職場は仕事の、教会は宗教の、自宅は家庭の、商店では買い物の、政治的集会では政治の、それぞれの物理的空間にそれぞれの場があった。人々はそれぞれの場にふさわしい振る舞い、そこでの人間関係、用いられる言葉、服装などを峻別し、各々の空間における力学に沿って生きていた。
それをラジオは崩壊させ、たとえば神父の説教のあとに政治的な演説、そのあとに天気の話、それから娯楽、ニュース・・・というように、個々の文脈から解体された状態で乱雑に情報が人々に投げ込まれるようになった。娯楽にしても、高尚とされているようなものから低俗なものまで、ニュースにしても政治ニュースや経済ニュースや社会ニュース、なんでもかんでもが無造作に、乱雑に放送される。
こうして特定の文脈を失って乱雑に提供される情報の中では、人間は批判的な思考や体系的な思考を失っていく。そこからニヒリズムが生じ、人々は抵抗する力を失っていき、その結果としてヒトラーのようなものでも台頭してきたのだ、というのがピカートの主張の概略だ。
ピカートの考え方は現代でも通用すると言ったことの意味はこれで、ナチスの時代を経て戦後はテレビ、それからインターネット、スマートフォンにSNSと、ラジオのように「既存の文脈から解体された情報の奔流」というものに日々の生活が浸食される割合は一貫して増えてきている。その最たるものがSNSだろう、というのが10年くらい前にツイッターを見て私が考えていたことで、疫病を経てそれはさらに酷くなった。テレワークでは職場と自宅の境界を消滅させ、同じパソコンの画面上にいずれもが展開されることが当然となった。物理的空間の制約や場の違いといったものがデジタル上では皆無になる。究極がメタバースということになるのだろう。
それがなぜファシズムにつながるのか。メディアを通じて得るすべての情報に対して、人間は等距離のところに置かれる。たとえばテレワークのパソコンで、会社のシステムにログインして仕事をするのも、娯楽としてYouTubeを見るのも、株取引をするのも、すべて等価で交換可能な行為である。これはコミュニティや人間関係の中でもそうで、あらゆるコミュニケーションが等価でフラットになることによって、人間は本来所属していた共同体から切り離されることになる。既存の共同体を解体し、国家や大資本に隷属させるのがファシズムの進め方であり、精神的にそれを進めていくのが昔はラジオ、今はインターネットというわけである。
ものすごく俗っぽく結婚を例にとって説明すると、昔は限られたコミュニティ、例えば学校や職場、行きつけの飲食店やサークルなどの物理的な空間の中で出会った人間の中から結婚相手を選ばねばならなかったから、その選択肢の中から選んでいたものが、いまやネットを通じて無限に「もっとよい理想の相手」を探し続けることができる。職業もそうだ。インターネット・デジタル上では、すべての選択肢がフラットに等価に見え、そこからいくらでも選択ができるような錯覚が生まれる。このような錯覚が強ければ強いほど、コミュニティはその構成員のコミットメントを欠いて弱体化していくに決まっているだろう。デジタル化の進展に伴って、企業の帝国化や日常の精神的負担が増加していることの真の背景はここにある。
むろんこのような流れに個人で抗うことはできない。ネットなしで生活するのだって到底無理だろう。だが上のようなインターネットの特性をよく理解して、その上で自分にとって良い使い方を模索していくことは不可欠だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
