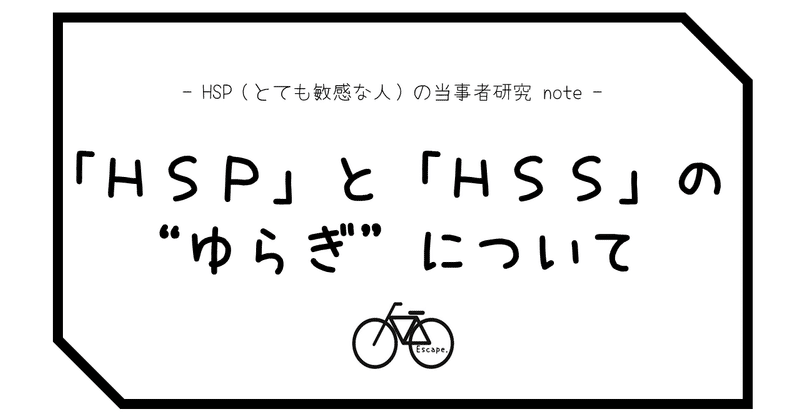
「HSP」と「HSS」の“ゆらぎ”について
「えすけーぷ。」の、HSP(とても敏感な人)の当事者研究ノート。
今回はHSPと、HSS(刺激追求型)の研究です。
4/19に開催された、
“HSP(とても敏感な人)の当事者研究会 9かいめ【オンライン開催(Zoom)】”
でも、「HSS」についてのお話になりました。
・当事者は「HSS」という概念をどのように捉え、受け入れているか?
・「HSS」ならではの困り事とは?
・「HSP」と「HSS」はどのように関係しているか?
などなど…
非常に興味深いお話が沢山出ました。
このお話を僕らだけが独占しているのはもったいないので、この場をお借りして、今回の研究成果を共有しておこうと思います^^
そもそもHSSって?
HSS(High Sensation Seeking = 刺激追求型)は、HSPとはまた独立した概念で、「強い刺激」を好む性質のことを指します。
この概念を提唱したマービン・ズッカーマンさんは、HSSを「変化に富み、新奇で複雑かつ激しい感覚刺激や感覚を求め」、また「こういった経験を得るために肉体的、社会的、法的、経済的なリスクを負うことを好む」性質だと説明しています。
ここで言う「刺激」とは、例えば「ジェットコースターに乗ること」であったり、「激しい恋愛に落ちること」であったり、あるいは「外に出て人と遊ぶのが好き」ということかもしれません。
刺激の少ない、落ち着いた状況よりも、刺激の多い、気持ちが興奮し、昂るような状況を好む性質のことですね。
「HSP」と「HSS」というフレームを使って、人類を分類するなら、
①HSPでHSSの人(繊細なのに、刺激を求めちゃう)
②HSPで非HSSの人(繊細で、刺激は欲しくない)
③非HSPで、HSSの人(繊細でなくて、刺激を求める)
④非HSPで、非HSSの人(繊細でなくて、刺激を求めない)
という四種類の人が、この世の中には存在することになりますね。
「HSPで非HSS」は意外と少ない?
ウチの研究会では、最初にまず参加者さんが今興味を持っていることを聴いてから、みんなで研究テーマとしてお話しすることを決めます。
今回の研究会では、「HSS」についてお話してみたいという方が多くいたので、このテーマで話を掘り下げることに決定しました。
参加者は10数名。
ファシリテーターをしている僕が、まず参加者に質問してみます。
「この中で、自分がHSSだと思う人ってどれくらいいますか?」
すると、多くの人が手を挙げてくれました。
そこで今度は、
「では逆に、自分はあまりHSSってぴんと来ないという人はどれくらいいますかね?」
と質問してみると、意外なことに、今度は誰も手が挙がりませんでした。
今回参加してくれた人は、たまたまHSS型HSPの人ばかり集まったということでしょうか?
話を掘り下げていくと、どうもそういうわけではないようです。
HSS型の境界はどこか?
上に書いた分類の仕方では、全てのHSPは「HSS型HSP」と、「非HSS型HSP」のどちらかに分かれることになると思うのですが…
今回の研究会では、「どうもそこまで、その2つに明確に線を引くことは出来ないんじゃないか?」という仮説を発見することが出来ました。
これはつまり、どういうことでしょう?
詳しく見てみましょう。
「HSP」と「HSS」の“ゆらぎ”
参加者さんの、ご自身に対して感じる「HSS性」についてのお話を掘り下げていくと、「HSS型HSP」という固定的な自分が居るわけではなくて、自分が今置かれている時と場合によって、HSS型っぽい行動を取ったり、非HSS型っぽい行動を取ったりしていて、自分の中にその両面があるようだという意見が多かったです。
「職場では非HSS的で、常に周囲の様子を伺い、あまり刺激を求める行動をすることはない。でも、プライベートでは、自分のHSSな側面がよく出てくる」という参加者さんの意見に、共感する声が多かったですね。
まわりの様子に合わせて、無意識のうちに、HSSな自分が出てきたり、非HSSな自分が出てきたりと使い分けられているようです。
「特性」というものの単純には語れなさというか、多面性が表現されていて、とても興味深いです。
「HSS」的な困り事
HSPという概念を提唱したエレイン・N・アーロンさんは、HSS型HSPのことを「アクセルとブレーキを同時に踏み込んでいるようなもの」と表現していますが、HSS型HSP当事者はしばし、自身の中の「刺激を求めて行動したい」という性質と、「落ち着いてゆっくりしたい」という性質の“矛盾”に困らされているようです。
例えば、
・語学が好きで、外国にもよく行っちゃうのだけど、自身の繊細さによって結局行ってからいつも疲れてしまう…。
・知らない人のイベントに、急に顔を出してみるんだけど、行ってみると一言もしゃべれなくて、結局後悔する…。
などなどの声がありました。
どうやら二つの矛盾した性質が、自分の中で綱引きをしてしまうようですね…(^^;
この「綱引き」が、HSS型HSP当事者に混乱をもたらし、困り事を生み出す構造があるようです。
動いて後悔するか? 動く前に止められるか?
HSSの衝動性にまつわる困り事も、二種類あるのではないかというお話がでました。
ある人は自分のHSSな困り事は、
「HSSな自分が衝動的に動いてしまうんだけど、HSPな自分は刺激の多さに疲れてしまって、結局あとで後悔する…」
とお話してくれましたが、また別の参加者さんは、
「HSSの自分は色々と衝動的に動きたいと思うんだけど、HSPの自分がリスクを予測して、その衝動性を止めて、動けなくさせてしまう…」
と表現してくれました。
動いてしまってから、後で後悔するのか?
それとも動く前に止められて、身動きが取れなくなってしまうか?
HSS型HSPの困り事にも、どうやら多様性がありそうですね。
「HSPさん」と「HSSさん」はどうしたら仲良くなれる?
ここまでのお話をまとめると、HSS型HSP当事者の中には「HSP」な自分と、「HSS」な自分とが、それぞれ居るようです。
仮にそれらを「HSPさん」「HSSさん」と名付けておきましょう。
「HSPさん」は落ち着いた刺激の少ない状況を求めていますが、「HSSさん」は自分を興奮させてくれる、刺激的な状況を求めています。
というわけで、この二人は求めているものがまるで真逆なんですけど、二人を中に飼っている自分は一人しかいないので、二人の言い分を全部聴こうとすると、自分が引き裂かれてしまいますね…(^^;
また、HSSさんの衝動性がもたらす結果を、HSPさんは事前に予測して教えてくれるんだけど、その予想を聴いているのにも関わらず、結局アクセルを踏み込みしてしまって、後で後悔してしまうことが多いという意見も。
HSSさんとHSPさん、両方の声を尊重するということに、なかなか難しさがあるようです。
今回お話してくれた参加者さんは、自分の中のHSPさんと、HSSさんの仲が悪いという人が多いようでした…(^^;
この二人の仲の悪さが、HSS型HSPの様々な「生きづらさ」を作る一因となっているようです。
では、どうすればこの二人を仲良しにすることができるのでしょうか?
今回の研究会では、そこまではまだお話を掘り下げることが出来ませんでしたが…今後とも当会では、引き続き研究していきたいテーマですね。
(書き手:足達龍彦)
【研究者求ム!】
現在、「えすけーぷ。」のHSP当事者研究会は、
オンライン通話を使い継続して活動しています。
次回の開催は、
4月26日(日) 14:00〜16:00【テーマ:フリー】
4月27日(月) 18:30~20:30【テーマ:HSPと「コロナ疲れ」】
参加費は無料。
今、不安を感じていたり、困りごとのあるHSP当事者さんの
力に少しでもなれたらと思っています。
お気軽に遊びに来てくださいね^^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
