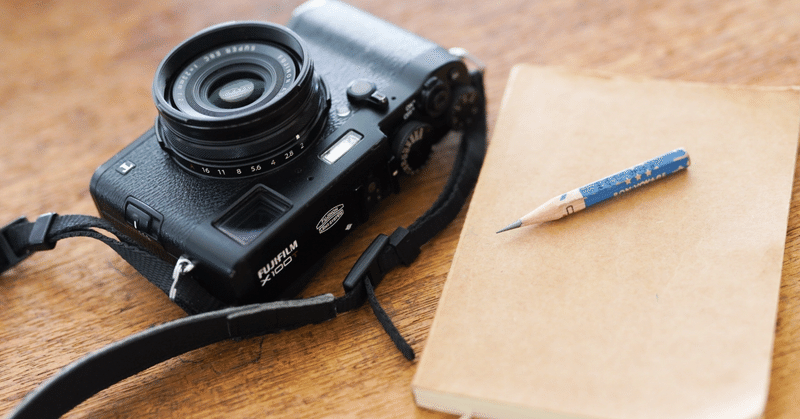
【広報担当者向け】"伝わる"インタビュー記事ってどう書くの?~①取材編
2年半ほどビジネス系WEBメディアの担当をしていたので、ざっと数えても150人以上にインタビューを行い、インタビュー記事を執筆してきました。インタビュー対象は、主にインターン生や新卒1~2年目の若手ビジネスパーソンたちです。そのため、キャリアについて話を聞くことが多かったのですが、時には仕事のこと以外にも、学生時代の話やプライベートの話までしてくれる人も。すでに世に名前が出ている所謂「成功者」「著名人」へのインタビューとは異なり、これから世に名前が出ていくであろう可能性あふれる若者へのインタビューは、私自身にもたくさん勇気をくれました。
数々とインタビュー記事を公開していくうちに、「こうしたらうまく話が引き出せるかもしれない」「こういう姿勢でインタビューに臨むことが大事なのかもしれない」と自分なりに気付くことが多く、それをSNSで発信してみると、インタビュー初心者の方や広報ご担当者などから好反応をいただくようになりました。中には「あなたに取材してほしい」「インタビューのノウハウについてセミナーで話してほしい」と言ってくださる人もいました。正解はないと言えど、私の経験が少しでも役に立つなら…。そう思い今回は、若手社員インタビューを行う機会が多いであろう広報ご担当者に向けて「"伝わる"インタビュー記事ってどう書くの?」と題し、「取材編」「執筆編」の2本に分けてnoteを書いてみることにしました。
①事前に設定すべきは「取材の目的」
インタビュー対象者が著名人や、これまである程度実績を積み重ねてきたビジネスパーソンであれば、ネット上にもその人の情報がたくさん溢れているでしょうから、事前調査はしやすいと思いますが、まだそういった事前情報のない若手をインタビューしてきた私は、ほぼ事前準備ができませんでした。
しかし、担当メディアの方針で「何のためにインタビューをするのか」「このインタビュー記事で読者に何を伝えたいのか」は明確でしたので、そういった"インタビューの目的"から逆算して、事前に想定質問事項を作成していました。また、インタビュー対象者の中にはSNSで日々の仕事について発信している人も多かったので、そういったご本人の発信も事前にチェックしていました。(インタビュー時に「Twitter覗かせていただきました~!」と伝えると恥ずかしながらも喜んでくれた人が多かったです)
社員インタビューを行う広報担当者も「なぜこの社員にインタビューをするのか」「インタビュー記事を通じて、誰に何を伝えたいのか」を予め明確化しておくと、"伝わる"インタビュー記事の土台が出来るかと思います。また、ここで定めた目的は、取材前にインタビュー対象者にしっかり共有しておくことをおすすめします。(意識のすり合わせ、大事)
②話を引き出すために意識したい3つのこと
・インタビューは「会話」脱線も恐れないで
いざインタビュー開始!となると、どうしても「準備してきた質問についてちゃんと聞かなきゃ」「時間内に終わらせなきゃ」といった気持ちになってしまい、「入社した経緯は?」「では、一番難しかった仕事は?」「最後に、一緒に働きたい人はどんな人?」などと淡々とした質疑応答になってしまいがち。ですが、これでは相手は準備してきた回答以上の答えは得られません。
せっかくインタビューを行うなら、インタビュー対象者が準備してきた回答以外の話も引き出したいし、何なら本人すら気が付いていない「何か」に気付き、本人すら予想できていなかった実りあるインタビューにしたいですよね。
そのためには、脱線を恐れず、会話を意識すること。これが一番大事だと思っています。想定質問事項はあくまでベース。受け取った回答の中で「えっ」「おぉ!」と思った箇所についてはちゃんとリアクションして、掘り下げて聞いてみるべきなのです。実は「あまり取材に関係ないことかもしれませんが…」といってインタビュー対象者が話してくれたことが、取材の軸になったという経験は少なくありませんでした。
もちろん"取材の目的"は忘れてはいけないのですが、少しぐらい脱線したほうが、相手も話すことが楽しくなり、面白い話もどんどん出てくる可能性が高まる気がしています。インタビュー対象者に「これはインタビューというより、楽しい会話だなぁ」と思ってもらえたら勝ち!と思っています。
・「これって、こういうことかな?」と思ったら仮説を立てて聞いてみる
いくつか質問を重ねていくと、「さっき話してくれた内容と、今話してくれている内容には、こういう共通点がありそう」と感じることがあるかもしれません。そう感じたなら、「的外れかもしれないから、取材後にちょっと自分で考えてみよう」ではなく、取材中の今、インタビュー対象者に聞いてみるべきです。
例えば「先ほど話してくれた上長との会話で得られた気付きが、今の話の原点になっているのように感じるのですが、どう思われますか?」と聞いてみると、以下①②のパターンが想像できます。
①仮説が合っている時
インタビュー対象者に「よく気付いてくれたなぁ」「ちゃんと自分の話を聞いてくれているんだ」と思ってもらえるかも。そして、ここから「ほかに、同じようにしてこの気付きがもとになって起こした行動はありますか?」とさらなる別のエピソードを引き出すことができるかも。
②仮説が間違っている時
仮説が合っていない時こそ、大チャンス。「いえ、実は今の話は、別の時の経験が原点になっていて…」と、また新たなエピソードが引き出せるかもしれません。
インタビューでは、インタビュー対象者から一つでも多く具体的なエピソードを引き出して、その中で核となる「共通点」を探していくことになりますが、仮説立てて聞いてみることは、①のパターンでも②のパターンでも、収穫が大きい可能性大です。人って、単に「具体的なエピソード教えてください!」と聞かれても、なかなか思い出せないし、思いつかないもの。だから、こちらから「引き出す」術を身につけておくべきなのです。
・「思考の転換」をしてみるのも効果的
特に若手ビジネスパーソンは、取材の時点でまだ本人の中でも考えがまとまっていなかったり、自分の強みや弱みに気付いていなかったりすることもあるかと思います。
インタビューはカウンセリングではありませんが、せっかく話を聞くのなら、積極的に話を聞いて、「これってこうなんじゃないかな」と感じたことはどんどん伝えていきたい。私はそう思っています。
例えばインタビュー冒頭に「自分はプライドが高くこだわりが強いタイプ」「いつも一人でなんとかしなきゃと思ってしまう」と話していた人が、質問を重ねていく中で「成果を上げられるようになったのは、苦手分野について先輩からアドバイスをたくさんもらったから。自分の力じゃないんです」と話してくれたとします。本人は「自分の力で成果を上げたいのに、それが叶わずもどかしい」と思っているのかもしれませんが、もしかしたら「先輩からアドバイスをもらい、それをもとに行動を改善する」という「高きプライド」とは結び付かない自分の行動の変化に気が付いていない可能性があります。その点について、こちらで思考の転換をしてみて「でも、人に頼れるようになったということですよね」と話してみると、案外「そうかもしれませんね、確かに!」と素直に受け取ってくれることも多いんです。
この時に気を付けたいのは、自分の意見を押し付けないこと。あくまで自分の意見として投げかけてみる姿勢で接することが大切かなと思っています。
こうして聞き手と話し手が「新しい発見ですね~!」と盛り上がると、そのポイントが取材の軸となり、"伝わる"記事にぐっと近づく気がします。
③全体を通して持っていたいのは「応援の気持ち」
特に若手へのインタビューでは、「この記事を通して求職者にこんなことを伝えたい」等といった広報担当者の思いもあるかもしれませんが、「本人のモチベーション向上にも繋げたい」といったインタビュー対象者への応援の気持ちもあるのではないでしょうか。
そういった本人へのエールの精神を持っていると、とても質の良いインタビューになると思います。というのも、「この人を応援したい」という気持ちは「この人をもっと知りたい」「この人がどう成長しているのかを知りたい」「この人が今後どう活躍していくのか知りたい」という"好奇心"につながっていくからです。
私はメディアの担当者だったので日ごろのインタビュー対象者の様子がわからない状態ではありましたが、常にエールの精神は持っていましたし、取材後も、記事公開後も、今でもずっと応援しています。広報担当者であれば、普段のその人を知っているので、もっと大きな愛情、もっと大きなエールの精神を持っているはず。心揺さぶられる社員インタビュー記事には、取材のスキルとか、書くスキルとか、そういったものだけでなく、こういった精神がきっと宿っているのだと思います。
続く②執筆編では、取材を終えて記事を書く時、どんなことを意識すればいいの?タイトルってどう決めるの?ちょうどいい文字数は?といった内容について書いていきたいと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
