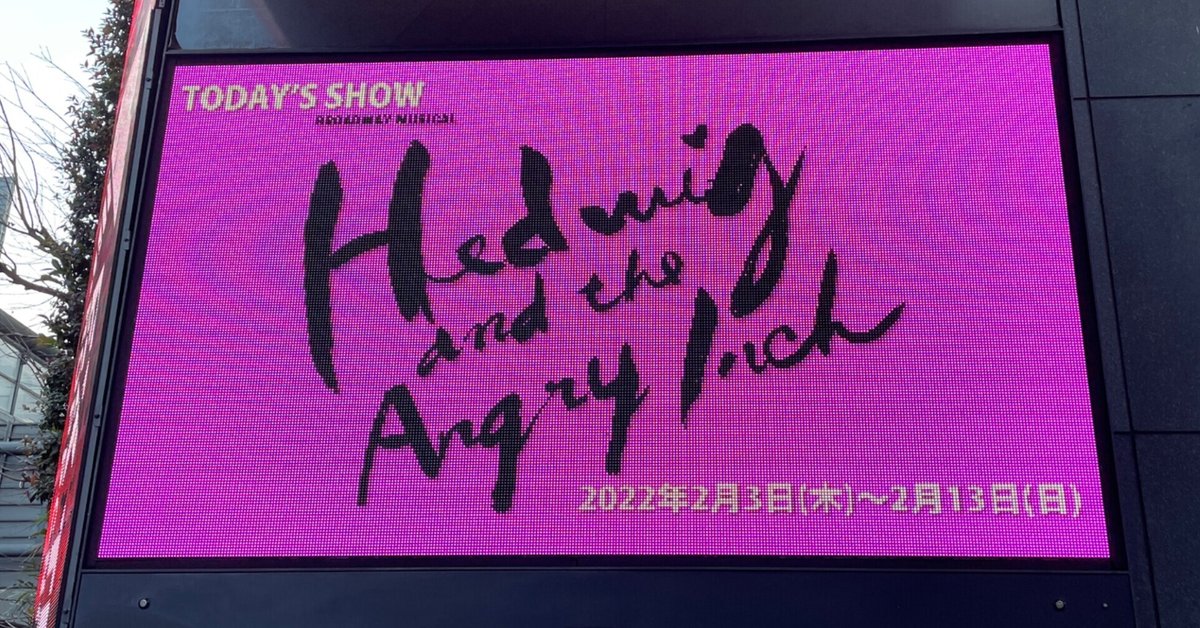
エンタメ専攻の大学生がヘドウィグ・アンド・アングリーインチを観た話
⚠️前提として、私はプロの批評家でも演劇や音楽の専門家でもありません。主に映像作品を中心としたエンタメ作品の研究をしていた一介の大学生です。観劇時の記憶をもとに、完全に個人の感想・解釈としてこの記事を書いています。それだけご了承いただけると嬉しいです。
と、前置き(というかほぼ言い訳)はこれくらいにして本題へ。
2022年版『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』(以下、ヘドウィグ)、全公演無事終了!お疲れ様でした!
↑↑ココで言及する『ヘドウィグ』はこちら↑↑
不安定な状況が続く中で大千穐楽まで完走できたことは、1ファンに過ぎない私ですら言葉にし難い感慨があった。
ありがたいことに初日、地方(名古屋)公演、千秋楽と何度か観劇できたので、素人なりに『ヘドウィグ』と共に歩んだ日々について記しておく。できれば手短に書きたい。サクッと読める分量にしたい。しかし、バチバチに長くなる予感がしている(震え)。お時間のある方は是非お付き合いいただければと思う。
※案の定、本文だけで1万字近くなってしまったのであらすじや作品概要等は割愛しました。
私と『ヘドウィグ』の出会いから観劇まで
かれこれ2〜3年前だろうか。2019年に何かの舞台を観に行った時に浦井さん版のフライヤーをもらったのが、私が『ヘドウィグ』を知るきっかけとなった。
↑こちらが浦井さん版のHP。女王蜂のアヴちゃんの出演もかなり話題になっていた。
フライヤーのデザインとあらすじに興味を惹かれたものの観劇には至らず。しかし後々行かなかったことを後悔する羽目になり………「次再演したら絶対観に行く!」と密かに心に決めていた。
そして2021年。ついに『ヘドウィグ』の再演が決定。しかも、かねてから応援していた丸山さんが主演!初めて情報を目にした時の、心臓を素手で掴まれて100メートル先までぶん投げられたかのような衝撃(どんな衝撃?)は忘れられない。ずっと観たかったヘドウィグを、大好きな丸山さんで観られるなんて!!
胸が高鳴ると同時に、チケット取れるんか?作品自体のファンの方々はどう思ってるのかな?丸山さん自身も相当プレッシャーを感じているのでは?と色んな想いが脳内を駆け巡った。
それからというもの、チケ取りとスケジュール調整に奔走する毎日(他にすることないんか)。初日に向けて着々と準備を進めていった。
エンジンを温めていった東京公演@ EX THEATER ROPPONGI
なんとか行きたい公演日のチケットが手に入り、ついに迎えた2022年2月3日。丸山版『ヘドウィグ』公演初日!
フラットな気持ちで見たかったので映画版は観ず、とはいえ予習ゼロは怖かったので大体のあらすじのみ確認。『ヘドウィグ』のサントラを聴いてテンションを上げつつ、いざ劇場へ!
舞台セットは想像していたよりもずっとシンプル。中央には「HEDWIG’S BRAIN INSIDE」と書かれた、大きなピンクの箱(?)が置かれている。多分、この中からヘドウィグが出てくるんだろう。その他にはバンドメンバーの楽器や、小道具と思われるウィッグが点在しているのみ。客待ちの音楽などもなく、街の雑踏の音だけが聞こえてくる。まさに「嵐の前の静けさ」といったところ。
開演時間になると、黒い服に身を包んだスタッフらしき人が登場。ピンクの箱の側面を2人がかりでゆっくりと片付けていく。何が始まるんだ?と客席もソワソワ。
スタッフが捌けると、自然な流れでバンドメンバーが登場。彼らと一緒にさとうほなみさん演じるイツハクも、マイクとスタンドを持って姿を現した。勿体ぶる様子もなくあっさりと登場したことに少々驚きつつ、いよいよ幕が開くのだと思うとこちらも背筋が伸びる。
正直、初日の空気はとてつもなく張り詰めていて、尋常ではない緊張感が漂っていた。そんな重い空気を切り裂くように、イツハクの雄叫びがEX THEATERに響き渡ると、バンドの重低音が全身を突き抜けていく。
そして、「HEDWIG’S BRAIN INSIDE」の後ろからヘドウィグが登場。客席に背中を向け小さくうずくまるヘドウィグを、イツハクが奮い立たせる。大きなマントを広げ、スポットライトを全身で浴びながら振り返るヘドウィグ_____。
何度観劇してもこのシーンでは毎回テンションブチ上げだったのだが、とりわけ初日の湧き上がるような興奮は忘れられない。そこにいるのは丸山さんではなく、丸山さんがヘドウィグになりきっている姿でもなく、紛れもない「ヘドウィグ」そのものだったから。身体中を血液がドゥワーーーーーっと駆け巡っていくような感覚。今これを書いてる間にもあの瞬間を思い出してちょっとゾワゾワしているくらいだ。
1曲目の「Tear Me Down」が始まると、これまた色んな意味で衝撃。
まずシンプルに、丸山さんの歌唱力の高さに驚いた。関ジャニ∞として歌う丸山さんを見ていてもここ数年のレベルの上がり方には舌を巻いていたので、歌に関してはかなり期待をしていた。が…………こちらの想像なんぞ軽々と超えてくるのがプロ。丸山さんってまだまだこんな表現ができたのか。くるくる変わる声と表情に毎秒腰を抜かしそうになった。椅子があって本当によかった(?)
そしてもう一つ。全編英語で歌っていたこと。これも超腰抜かし案件。
台詞以外はオール英詞、しかも字幕なし。丸山さんが英語を話すイメージがなかったし、海外ミュージカルを日本人キャストで上演する時には訳詞で歌うものだという先入観があったから、最初の2〜3曲はちょっと狼狽えたのはここだけの話(笑)。
予習せずに観に来る人や1度しか観劇の機会がない人にはあまり優しくない演出だな〜と感じたのが正直なところ。とはいえ、わかりやすければ良いかと言われると全くそんなことはなくて。丸山さんの声質や歌い方に英詞がバチっとハマっていて心地よかったし、言語としての意味を理解できなくてもそれはそれで想像力を掻き立てられたので、物足りなさは全く感じなかった。
初日は全体的にアドリブも少なめで、台本と元々の演出に忠実に演じられていたよ気がする。先述したように客席の空気も若干重ためで、私自身も堅くなっていた気がする。もっと予習していれば盛り上がれたかな?とも思ったが、初日特有の緊張感や初めてヘドウィグと対面した衝撃をじっくり味わえたので結果的に良かった。
その後、EX THEATERでの公演に何度か足を運んだ。10日間に渡る東京公演は、「繰り返すことで磨かれていった」という印象が強い。
回を重ねるごとに演者側もお客さんもブーストがかかっていくのが手にとるようにわかった。初日の冷静さと緊張感のあるステージも素敵だったが、東京公演後半にはエンジンをガンガンにふかして突き進むヘドウィグたちにどんどん心を奪われていった。
初日と良し悪しを比較しているのではないことだけご理解いただきたいのだが、繰り返し上演する中で『ヘドウィグ』が次から次へと形を変えていったのは確かだ。初日は「演劇」「芝居」としての色が濃く、徐々に客席とのコミュニケーションが増えて「ライブステージ」としての濃度が高まっていった。
毒霧のシーン(*1)やデスマスクのくだり(*2)など、演じている丸山さん自身がどんどんヒートアップしていく様子を見ていると「次は何をしてくれるんだろう?」と期待も高まった。客席から滲み出る「面白いことやって!!」というプレッシャーも日に日に強まっていった気がする(笑)。
お客さんの表情やリアクションに対して愛あるイジリをかましたり、眠そうなお客さんを見つけて大声で起こしたり。やりたい放題になっていくヘドウィグの魅力に吸い込まれていくような感覚を味わった。
また、この東京公演の間にかなり重要な演出の変更があった(変更前後の公演に行った友人からの情報)。これについては地方公演の項目で触れるとして、私はこの変わることを厭わないカンパニーの姿勢にも感銘を受けた。
演劇やライブという生のエンタメにおいて、「変化を大切にする」ことは当たり前のことかもしれない。しかし、一度客前で上演している演出はそれなりの覚悟を持って決定しているものであり、それを覆すことは決定時以上の覚悟や意図が必要なはずだ。より良いものにしていくために形を変えていく『ヘドウィグ』を観て、「演劇は生き物である」ということを再認識した。
(*1)ヘドウィグがステージドリンクを口に含み、客席に向けて吹き出すフリをするシーン。「このご時世だからこれもできないのよね〜」と残念がるまでがワンセット。
(*2)ヘドウィグの顔(メイク)がついたタオル=デスマスクを客席に向かって投げるフリをするシーン。こちらもご時世的にNGなので残念。
換骨奪胎の地方公演@Zepp Nagoya
東京公演から日があくこと約2週間。会えない時間が愛を強くするとはよく言ったもので(?)、ヘドウィグのことをぐるぐると考えれば考えるほど彼女に早く会いたくて仕方なくなっていた。会いたくて会いたくて震えはしなかったものの、東京公演の頃とはまた違った心持ちで当日を迎えた。
名古屋公演の感想を一言で言うとしたら、「換骨奪胎してる!」
(最近では悪い意味で使われることが増えているらしいが、良い意味で使うのが正しいとのことなのでここではポジティブな言葉として使う)
つまり、「完全に自分のものにしたな」ということ。
「ちょ、おま、オリジナル版も映画版も過去の日本版を観てないクセに何を根拠に!?」と思われるかもしれないが、「あ、丸山さんこれ完全に掴んだわ」と感じる瞬間が格段に増えたのだ。
東京公演から「丸山さんらしさ」は備わっていたと思うが「ジョンキャメ(*3)に似てる」「ジョンキャメリスペクトを感じる」という感想も散見され、(もちろんこれらの言葉もかなりの褒め言葉だが)まだまだオリジナリティを追求する余地があったとも捉えられるだろう。
そこから大阪・福岡公演を経て「丸山さんにしかできないヘドウィグ像」を確立させていったことが、名古屋公演のステージから感じ取ることができた。
中でも、陽と陰のメリハリと緩急は「丸山さんらしさ」を語る上で外せないポイントだと考える。
「関ジャニ∞の丸山隆平」「アイドル丸山隆平」は、ぱっと見わかりやすい元気キャラ・お笑いキャラである一方で、その背後に孤独さや闇深さが見え隠れする「危うさ」が魅力だ(と私が勝手に分析しているだけで異論は全然認める。異論ウェルカム)。
この「危うさ」がヘドウィグというキャラクターに色濃く反映されるようになったのが、丸山ヘドウィグに「換骨奪胎」を感じた根拠かもしれない。
ヘドウィグは、客前でジョークを飛ばし、毒を吐き、イツハクには威張り散らかし、ステージに立つ自分に確固とした誇りを持ちながら、パワフルに歌い踊る。怒りも、悲しみも、エネルギッシュに音楽に乗せて伝えていく彼女は、紛れもないロックスターだ。
しかしその裏で彼女は、自身のアイデンティティや愛についてひたすらに悩み、苦しみ、終わりの見えない暗いトンネルを彷徨い続ける。時にそれは音楽をもってしても乗り越えられないほど大きな闇となり、歌うことすらできなくなる(The Long Griftでは、マイクをイツハクに押し付けて退場してしまう)。
一見相容れないように見えるものが共存し、頑丈に見えて実は脆くもあるヘドウィグを、「アイドル」という輝かしい職業を全うしながらも仄暗さと人間臭さをはらんでいる丸山さんが演じる。その意味が存分に発揮されるようになっていった。
また、東京公演の章で触れた「演出の変更」についてもここで掘り下げておきたい。
具体的にどのような変更があったか簡単に説明する。今更ではあるが、ここで初めてガッツリとラストシーンのネタバレをするので読みたくない方はすっ飛ばしてGO⚠️
まず、初日から上演されていた演出は以下のようなものだった。
トミーが「Wicked Little Town」を歌う
↓
歌い終わったトミー(ヘドウィグと同化した状態?ここではヘドウィグでもありトミーでもあると捉える)にイツハクが近づいていき、ウィッグを被せようとする
↓
ウィッグを手で拒むと、不思議そうにイツハクを見つめるトミー
↓
ウィッグを手に茫然とし、ステージを後にするイツハク
そして、変更後の演出は次の通り。
トミーが「Wicked Little Town」を歌う
↓
歌い終わったトミーにイツハクが近づいていき、ウィッグを被せようとする
↓
ウィッグを手で拒むトミー。少し間があった後、トミーはイツハクの手からウィッグを取り、イツハクの頭に被せる
↓
トミーはイツハクの顔をじっと見つめた後、イツハクを舞台袖に向き直らせて背中を押す。ステージをゆっくりと、しかししっかりとした足取りで後にするイツハク
違いは、イツハクがウィッグを被せようとした後のトミーの行動。ただウィッグを拒むだけの前者と、拒んだ後にイツハクの頭に被せる後者とでは全くもって意味が変わってくる。では、具体的にどう意味合いが変わるのか。私なりの考察をお話ししたい。
変更前の演出を初めて見たとき、私は「ヘドウィグがトミーの中に消えていってしまったのかな?」と感じた。幼い頃から「カタワレ」を探し、一つになる事を望んでいたヘドウィグは、トミーが自身の「カタワレ」であることに気づき、トミーという一人の人間の中に取り込まれることで「一つになる」事を叶えたのではないか、と。
ファンタジーすぎるというか、ご都合主義的な解釈であることは承知の上だが、そもそもワクチンやPCR検査の話をしながらヘドウィグが生きてきた時代設定などは変わっていない(*4)時点でファンタジーだし、舞台上では説明のつかない事象だって起きて当然だし!?と勝手に腑に落ちていた。
イツハクが「Midnight Radio」で再登場するときの表情からも、ヘドウィグという拠り所を失った戸惑いや絶望感が滲み出ている。ドラァグクイーン時代のドレスに身を包み、ヘドウィグと結婚するために「二度とと被らない」と誓ったはずのウィッグを頭に乗せ、不安げな表情で現れるイツハクを見ていると、「もうそこにヘドウィグはいない」と思わされた。言葉を選ばず言えば、イツハクが「置いていかれた」「取り残された」ように見えた。
一方で、変更後の演出については「ヘドウィグはトミーの元に自分の居場所を見出し、トミーと共に生きることを選んだ」という解釈をしている。
ヘドウィグにとってのカタワレはトミーである、という見方は前者の演出と共通するが、「トミーの中に取り込まれる」のではなく「トミーと共に生きる」という形で「一つになる」事を叶えたのではないか、と感じた。トミー(ヘドウィグ)がイツハクにウィッグを被せて背中を押す時、彼(彼女)はイツハクを慈しむような優しい表情をしていた。それは、紛れもなくヘドウィグの顔だった。
私たち観客からはトミーの姿しか見えない。しかし、そこにはヘドウィグも存在しており、最後にイツハクと向き合って微笑んでいたのは確実にヘドウィグだったのである。
この後の「Midnight Radio」でイツハクは、両手を広げて天を仰ぎ、清々しさすら感じられる表情をしていた。その姿からは、不安や絶望、後悔は感じられなかった。イツハク自身も、ヘドウィグやトミーと同様に自らが本来生きていくべき場所を見つけることができたから、そのようなポジティブな表情になったのではないだろうか。
………書いてる方もだんだん混乱してきた(笑)
要するに!
変更後の演出では一人の役者の身体を通して「ヘドウィグ」と「トミー」という二人の存在を見る(感じる)ことができた。そして、イツハクの未来にも希望を見出すことができた。
この点が、演出の変更に伴って大きく変わったところだろう。変更前の演出も絶妙にあとを引く感じで好きだったが、ストーリーを的確に伝えているのは後者の方だと思う。
説明が長くなったが、変更された演出を名古屋公演で初めて観て、まるで東京公演と全く違う作品を見ているのではないかと思うほどの新鮮さを感じたのである。
(*3)ジョン・キャメロン・ミッチェル。本公演の演出家であり、オリジナル版と映画版でヘドウィグを演じた。
(*4)今回の『ヘドウィグ』では、冒頭の語りや要所要所で「このご時世」について言及されている。つまり、ヘドウィグがライブを行っているのは今現在・2022年であるはずだが、ヘドウィグが生きた時代は1970年代〜1990年代とオリジナルの設定と変わらない。以上のことから、今回の公演においては時間軸の整合性は重要視されていないと考えられる。
「特別」じゃないけど「貴重」だった凱旋公演@Zepp Divercity
名古屋公演からさらに1週間。いよいよツアーラストの地であるZepp Divercityにヘドウィグが降り立った。
もう最初に言っちゃう。本当に本当に素晴らしい最後だった。「有終の美」とはこういう時のためにある言葉なんだ。そう感じた公演だった。
大千秋楽の日のカーテンコールで、丸山さんはこう言っていた。
「今日だけが特別じゃないんでね。1公演1公演の積み重ねなので」
私はこの言葉に全てが集約されていたと思ったし、凱旋公演の魅力を語る上でもこの丸山さんの言葉が欠かすことができないと思った。
決して大千秋楽だけが「特別」なわけじゃない。初日も、中日も、同等に尊いものであって、全てに違った意味がある。
凱旋公演だけが「特別」じゃない。それでも、私の人生経験において何にも変え難い「貴重」な時間であったことは確かだ。
何度も観劇した中で、なぜ凱旋公演を「貴重」と感じたのか。それは、舞台上の世界と自分の生きる世界がリンクし、繋がっている感覚を味わったからだ。自分が生きている日常と、ヘドウィグが生きる作中の世界、そしてヘドウィグを演じる丸山さんが生きる世界が、全て地続きに繋がっている事を強く感じられた。
それは正直なところ、凱旋公演を迎えるまではあまり感じられなかった感覚だ。東京〜名古屋公演を通して、ヘドウィグの境遇を憐れんだり、彼女をどう捉えるべきか悩んだり、はたまた彼女のように強く優しくなりたいと思ったりした。かと思えば、あれだけの台詞量と曲を自分のものにして進化を続ける丸山さん自身に尊敬の眼差しを向けることもあった。それだけ考えを巡らせていても、彼らの人生と私の人生とは決して交わらない平行線上にある気がして、一歩引いて見つめていたのである。
観劇した時の私自身の精神状態も影響しているだろうし、演者側の微細な変化によるところもあるだろう。現時点ではっきりと「これが理由だ」と言い切ることはできない。抽象的すぎる感想になるが、凱旋公演では確実に、私とヘドウィグとトミーと丸山さんの人生が一点で交わる感覚を味わったのだ。
特に印象的だったのは、最後に歌う「Midnight Radio」。地方公演の章で先述した通り、この曲を歌っているのはヘドウィグでもあるしトミーでもあると解釈している。しかし、凱旋公演で初めて「ヘドウィグでもありトミーでもあり丸山さんでもある」と感じたのだ。これまた根拠は曖昧なのだが、歌っている中でふと見せるリラックスした微笑みや客席を見つめる柔らかい眼差しに、これまでの公演では見せることのなかった表情がチラチラと見え隠れしていたのである。私にはそれが、「アイドル丸山隆平」としてステージに立つ時に見せる表情であるように見えた。
これは決して、「演じることを忘れて素に戻っていた」と言いたいのではない。ヘドウィグを1ヶ月間演じ続けたことによって、ヘドウィグと、トミーと、丸山隆平という3人の人間の魂が一つになった。一つの肉体に、3人の魂が宿った。私はそんな風に感じたのである。
いよいよオカルト的な事を言い出したなコイツと思った方もいらっしゃるだろう。書いている自分でも熱くなりすぎている自覚はあるし、若干自分で自分に引いている(おい)。ただ、私があの時感じた感覚を表現するとしたら「3人の魂が一つの肉体に宿っている」と言う他ないのだ。
そして、カーテンコールの最後に丸山さんが言った言葉。
「皆さん、お互い良い人生を送りましょう」
この言葉を聞いたときに、私は舞台上にいる丸山さん、さとうさん、バンドの皆さん、そして会場を埋め尽くすお客さんたちの人生と自分の人生が、ぶっとくてでっかい一つの点で交わっている感覚を味わった。何故か涙が止まらなくなった。もうここまでくると理由なんてない。
まだ20年とちょっとしか生きていないが、生まれてから今までさまざまなフィクションに触れてきた。演劇やミュージカルもそれなりに見てきたつもりだ。それでも、作品の世界と、演者と、周りのお客さんとこれほどまでに一つになる感覚を味わったことはなかった。丸山さんがインタビューで幾度となく口にしていた「僕のカタワレはファンの皆さんです(*5)」という言葉の真意が少しだけわかったような気がしている。
(*5)初日公演の前に行われた囲み取材にて、自身にとっての「カタワレ」を問われると「全国のファンの皆さんです」と回答。公演パンフレットのインタビューでも「僕は今、ファンのことをカタワレと言っていますが」と発言している。
↑囲み取材については上記より引用。
「ヘドウィグは壁だ」とはどういうことか
ここまでつらつらと『ヘドウィグ』への想いを語ってきたが、ここで一つ問いを立ててみようと思う。
「Tear Me Down」の曲間で、イツハクが叫ぶ言葉がある。
「ヘドウィグは壁だ!」
観劇するたびに、私はこの言葉について考えを巡らせていた。
「ヘドウィグは壁」ってどういうことなんだろう?
この文章の総括として、現時点での私なりの答えを出したいと思う。尚、以下の章については公演パンフレット掲載の「『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』とLGBTQ+」(よしひろまさみち著)を参考とし、考察の手がかりにさせてもらった。
「アタシがいなければアンタたちは何者でもないのよ」
「ヘドウィグは壁だ」について考えるにあたって、ヘドウィグ自身が言った上記の言葉を避けては通れないだろう。
ヘドウィグがいなければ、私たちは何者でもない。言い換えれば、ヘドウィグがいることで私たちは何者かになることができるということだ。
ヘドウィグは、自分自身のアイデンティティに悩み続けた人間である。東ドイツでハンセルという名の男性として生まれ、故郷で性別を(半ば強引に)変え(られ)るが、股の間には「怒りの1インチ」が残り「完全な女性の体」になることはできなかった。それでもヘドウィグという名の女性として結婚をして、アメリカへと渡るが、離婚。さらに、異国の地のテレビで故郷が変わっていくさま(ベルリンの壁崩壊)を目の当たりにする。
男なのか女なのか。どちらかに決めなければいけなかったのか。果たして「5インチ」を手放す必要はあったのか。いつまでもそこにあるはずの生まれ故郷すら曖昧になっていく中、帰る場所はどこにあるのか。
物語の序盤で叫ばれる「ヘドウィグって誰?」という台詞は、ヘドウィグ自身が自分に問い続けた命題そのものである。
そんなヘドウィグが言う「壁」とはなんだろう。
ベルリンの壁のように視界を遮って分断を生む「悲しい壁」が存在する一方で、真っ暗な闇の中を手探りで進まなければならない時に、手で伝うことによって今いる場所と道筋を示してくれる「頼もしい壁」も存在すると、私は考える。
ヘドウィグは前者の「悲しい壁」の存在と、後者の「頼もしい壁」の不在に苦しめられたのではないだろうか。性別や国籍という「壁」を越えようともがき、自らを良き人生へと導いてくれる「壁」を探し続けた。誰よりも「壁」に振り回された彼女だからこそ、もう「悲しい壁」で分断が生まれることのないように、そして「頼もしい壁」のない暗闇で彷徨い続ける人がいなくて済むように、自らが揺るぎようのない「頼もしい壁」となることを選んだのではないかと私は考える。「壁」であるヘドウィグと向き合うことで、私たちが自分の存在を認め、自らの居場所を確認できるように。
アタシが真ん中にいなきゃ ベイブ アナタは何者でもないわ
壊せるもんならかかって来なさい
出典:公演公式パンフレットの訳詞掲載ページより
ヘドウィグは、いつも強気に歌う。本当は脆く傷ついているはずなのに。それでも決して壊れない「壁」であり続けようとする姿は彼女の強さと優しさ、そして孤独さを象徴している。
つまり、「ヘドウィグは壁だ」とは、私たちがヘドウィグという揺るがぬ存在と対峙することによって、偏見や差別にとらわれることなく自分自身のアイデンティティを見つめ直し、捉え直すことができるということを表しているのではないだろうか。
多様性の時代に『ヘドウィグ』が上演されるということ
丸山さんは、2022年に『ヘドウィグ』を上演する意味について次のように語っている。
自分との距離感もあると思うんですよね。自分と向き合うことの大切さと、認めることの大切さと、いろんな要素があるので、それをこの舞台でどんな風にお客さんが感じて持って帰ってくれるのかっていうのを、今の時代にはピッタリな作品なんじゃないかなと
出典:上記のインタビュー動画。引用したのは3分56秒あたりから。
あらゆる物事を分断する「悲しい壁」が少しずつ壊され、風通しが良くなり、偏見も差別も減りつつある現代。もちろんまだまだ課題だらけだし、本当の意味で多様性が認められているかは甚だ疑問だ。それでも、昔に比べたらはるかに選択肢が多く、自由に人生選択ができる世の中になってきていると思う。
自分らしく生きられる時代。なんて良い時代なんだろう、と思う反面、なんて生きづらい時代なんだろう、とも思う。
「悲しい壁」が無くなったからといって、暗闇を彷徨う私たちを導いてくれる「頼もしい壁」が現れてくれるわけではないのだ。
自分の生き方を誰も決めてなんてくれない。幸せになれる正解もない。全て自分が決めることだから、良し悪しだって自分にしかわからない。全ての責任が自分にのしかかる。そんなの今に始まったことじゃないかもしれないけど、時代が進むにつれて「自分らしさ」という言葉のもつ力はどんどん強くなり、まるで脅迫されているかのように私たちの脳内に刷り込まれていく。「自分と向き合うこと」から逃げることが許されない社会。
そんな私たちに、ヘドウィグは言う。
「アンタたちなんて、アタシがいなければ何者でもないのよ」
「壊せるもんならかかって来なさい」
自分の内側ばかり見つめ、答えが見つからず彷徨う私たちの目を、ヘドウィグは彼女自身に向けさせてくれる。
やり方は荒っぽくて、ちょっとお下品。でも、根っこの部分はあたたかくて愛に満ち溢れている。それがヘドウィグ。
私は、今この時代にヘドウィグに出会えたおかげで、自分自身の将来の解像度が少しだけ上がった気がしている。
まだまだ長いこれからの人生、自分を見失うことなんて数え切れないほどあるだろう。そんな時にはもう一度、ヘドウィグに会いに行こうと思う。
そうすればきっと、「アンタ、そんなことでウジウジ悩んでバカね!」なんて言いながら、また私の前に「壁」として立ちはだかってくれるはずだから。
終わりに
ここまで読んでいただきありがとうございました。
長文の観劇記録を書くのは初めてだったので稚拙な点も多々あったかと思いますが、ちょっとでもイイなと思ってくれた方はいいね&シェアしていただけると幸いです。
最後に、一緒に観劇に行って意見を共有してくれた友人、知人にも、この場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
