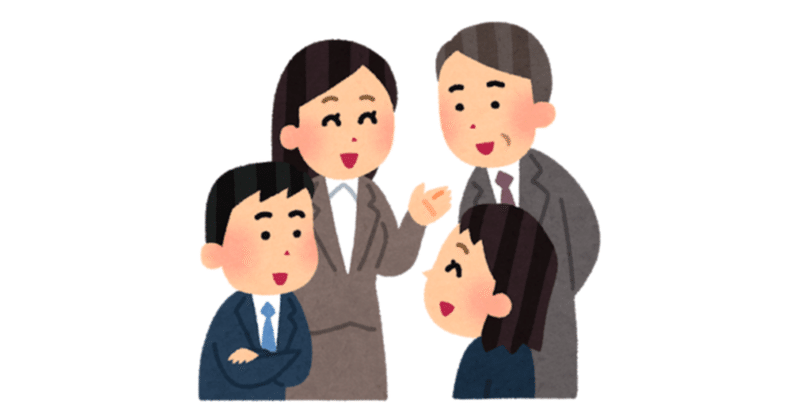
社内教育としての言語教育
明治大学大学院国際日本語研究科主催の「やさしい日本語とやさしい英語」に参加しました。株式会社メルカリの社内研修についてです。以下覚えのメモ。
日本語教育の中身/自社の課題にマッチした日本語テストを独自で展開
メルカリでは以前、日本語教育を日本語学校に外注していたそうです。しかし、なかなか成果が上がらなかった。そこで、研修部門のLET(Language Education Team)は考えた・・・職場で必要な力は言語の知識ではなくコミュニケーション力(会話力)。この力は知識を問う従来型のテストでは測れない!そこでメルカリ独自の日本語テストを開発したそうです。「何ができる」がわかる(SEFR準拠)を明確に打ち出した内容にした、とのこと。
その成果があって、従来A2レベルを獲得する社員は20%だったのが、今では100%を達成したそうです。
歩み寄りのコミュニケーションで課題克服
研修成果が表れ、CEFRのB2の言語力レベル(無理なく自然な会話ができる)に達したとしても、実際の仕事場面でコミュニケーションは完璧ではない。とすれば、それは聞き手の問題ではなく「話し手」の問題だ、という考え方から、メルカリの「やさしいコミュニケーション(日本語・英語)」は発しているとのことです。つまり
・日本語母語話者はやさしい日本語を使い
・英語話者はやさしい英語を使う
→相互が歩み寄る努力でコミュニケーションの課題を克服する
というわけです。
ベストプラクティスはチーム員が自ら構築
やさしい日本語・英語は、「短く言う・スラングを使わない・複雑な用語や高レベルな用語を簡単な言葉に置き換える・文化的な背景がわからないような内容で話さない・インクルーシブな表現を使う」といった配慮がいります。メルカリでは、これらノウハウを伝えるだけではなく、英語学習者と日本語学習者、上級母語話者が混在の研修ワークショップを実施しているとのこと。例えば、「ぴかぴか」しか言ってはいけないクッキングワークショップを実施するなどしているそうです。単に言語の習得を目指しているのではない、多国籍・多文化の同僚が自らチームで起こり得る課題を越えることこそが大事、という考え方があります。
根底にある考え方=ダイバーシティ
これらのメルカリのプログラムが目標としているのはダイバーシティな組織。インクルーシブなコミュニケーションは、言語の壁を取り払って意思決定に参加できたり、業務遂行の過程で心理的安全性が確保されるのに寄与しているとのことでした。
【感想】多国籍企業だけではない!組織の風通しのよさの必要性
今回、日本語の社内教育に興味があってこの講義に参加しましたが、射程はもっと広かったのでとても参考になりました。組織がイノベーションや改善を推進するためには、場が心理的に安全(言いたい意見が言える、受け入れられる)でなければなりません。それは多国籍企業ではなくても同じこと。言語の壁があってもなくても、お互いの考えを出し合って向上できるようにする事こそが「場」には必要なんじゃないかなと思いました。
ご希望の方に論文の練習相手をします。あなたが作成した文章にコメントを付けてお返しします。画面最下部にある「クリエイターへのお問い合せ」からご連絡ください。
