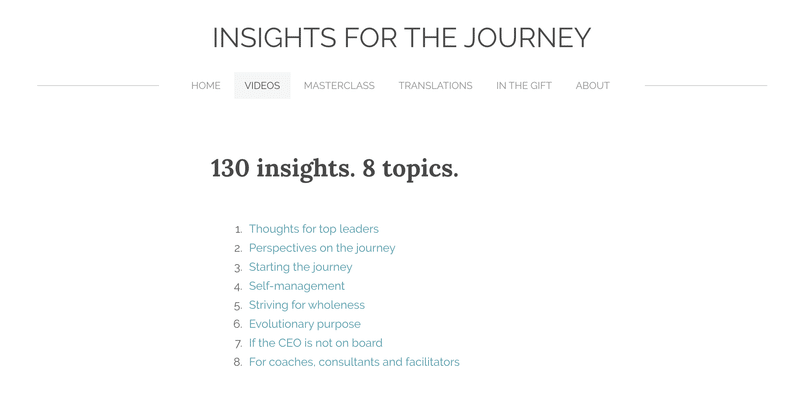- 運営しているクリエイター
2018年11月の記事一覧

【2.14】新しいコミュニケーションの方法(Communicating in new ways)
※ティール組織の著者Frederic Laloux によるINSIGHTS FOR THE JOURNEYの日本語訳の個人的なメモを公開しています。 ————————————————————— ■元のURL https://thejourney.reinventingorganizations.com/214.html ■翻訳メモ * 無味乾燥な文章の並んだwordや、言葉の多いpowerpointの資料はもう止めてほしい * 新しい組織に移ろうとしているのに、なぜ古いやり方でコミュニケーションもとろうとするのか * 少なくとも、私はもうそういうものは読みたくない * もう一方の端には、カラフルな洗練されていて、どこか権威的(autehntic)なドキュメントもある。社内コミュニケーションの部署が作ったような、ある意味で広告のようにも見えるもの * それには、時間もお金も掛かる * 新しい組織ではどうやってコミュニケーションをとるのがいいか? * ときにはwordやPPTを使うこともあるかもしれないが、色んなことを試してみればいい * たとえばビデオを撮るかもしれない。きれいなものではなく、スマホでミーティングで話したことをそのまま説明する * それは早いし、簡単に始められるし、そしてそれでも十分に機能する * 他には、イラストレーションの効果はすごく感じる * 長いドキュメントを作るのではなく、イラストを書いてもらってもいいかもしれない。 * それも、外に目を向けるのではなく、社内で、誰か喜んでやってくれる人が居ないかを探してみる。 * あとは手書きの大きなポスターがあって、アドバイスプロセスです、ぜひ好きにコメントして、というほうが、wordやpower pointよりも機能するかもしれない * 表現するメッセージのうち、どれくらいの割合が頭から来ているか?どれくらいが心から?腹の底から? * 私達は100%頭にするようにトレーニングされているが,それはドライで冷たく感じる * もっと個人的になって、「私達」として話せないか。また、もっと感情について話せないか、ニュートラルにするのではなく。 * たとえば、誰かが「透明性を高めるために、すべてのミーティングの議事録はサーバー上に公開されるべきだ」と提案したとする。かなり急進的な提案。 * それは冷たい印象がするし、業務連絡のようだし、それを読んでもワクワク出来ない * 私達はこういった書き方をするようにトレーニングされている。 * もし私だったら、これをどう書くか? * 「私達は、本当は知っているべきだったことを噂話として聞くと、とてもフラストレーションを感じる。それを防ぐために、すべてのミーティングの議事録をサーバーに上げるようにしよう」 * ほんの少しの違いだが、「私達」として話すし、どんあフラストレーションがあるのかも書いている。 * もちろんもっと個人的な書き方にすることもできるが、あくまでサンプルとして、どういう表現の仕方があるのかを考えてみてほしかった * これまでの例として上げたビデオやイラストレーションは、全て1wayなコミュニケーション。 * 従来の組織では、多くが1wayによって成り立っている * 新しい組織にシフトすると、非常に多くの2wayのコミュニケーションが起きるようになる * 以前のような「私のオフィスはいつも空いている」というのは、もはや機能しない * 多くの組織では、スペースを用意して、アジェンダもなく、すきなことを話せるようにしている * たとえば、小さな組織ならweeklyの朝食会でもいい * 好きな人が集まって、そこで好きなようにそこで話せばいい * ある非常に大きな組織では、一箇所では出来ないので、ビデオストリーミング、CEOの名前をとって「Ask Michel」というのをやっていた。そこに誰でも参加して好きに質問できる * これを何度も続けることに意味があった。やってみればいいじゃないか、と色んなことに言い続けた * あとはブログポスト。ビュートゾルフでもやっている。これは最初は1wayだが、そこにコメントが帰ってくると2wayになっていく * 私からの提案は、あなたのコミュニケーションを全く新しい見方で見てほしい * 伝統的なコミュニケーションは、冷たい、頭から、短く、業務的、1way。新しい世界ではそれはフィットしない。 * 新しいやり方にむけて、ぜひ色んな実験をしてみてほしい ■お願い 動画の最後にもあるとおり、この取り組みはすべてギフトエコノミーによって成り立っています。 この取り組みを支援されたい方は、以下のリンクからLalouxへのご支援をお願い致します。 https://thejourney.reinventingorganizations.com/in-the-gift.html ■翻訳メモの全体の目次 https://note.mu/enflow/n/n51b86f9d3e39?magazine_key=m3eeb37d63ed1

【2.13】ユーモアと気軽さ(Humor & Lightness)
※ティール組織の著者Frederic Laloux によるINSIGHTS FOR THE JOURNEYの日本語訳の個人的なメモを公開しています。 ————————————————————— ■元のURL https://thejourney.reinventingorganizations.com/213.html ■翻訳メモ * 多くの組織の中では、私達はとても真剣に考えて振る舞っている * 組織には目的があって、それは尊く、意義深いものだと思う。また仕事はお金のためにも家族のためにもしているし、それは一定のリスペクトを受けるべきものでもある * ただ、家族や友達、そういったものは私達にとって同じかそれ以上に大切だが、そこではよく笑うし、ユーモアや気軽さが存在している * とても深いところでは、私達が「プロフェッショナルとして振る舞う」というマスクと、この真剣さは結びついているように思う * ユーモア、気軽さ、好奇心は、そういった真剣さを壊してくれて、私たちの人間性を取り戻してくれる役に立つ * ある組織では、どんなミーティングをするときも、1分間の静けさかジョークのどっちかから必ず始める。 * それによって、気になってることや、自分自身のエゴから、気を紛らわしてくれることにもなる * SoundsTrueという組織では、パジャマで過ごすという日をイベントとして楽しむ日がある。思いきり楽しんで、社内には犬もいるので、犬のためのパジャマを用意する人もいる。 * 面白いのは、ここには伝統的なヒエラルキーはあるが、マネージャーがパジャマを着ているのをも居ると、それが関係性を変えてくれる * あなたへの面白い提案としては、大小様々な形で、ユーモアや気軽さ、好奇心を、組織の中に取り入れられないか * たとえば、CEOのための駐車スペースをなくすのではなくて、それを面白おかしくした表現に変えることはできないか?など * 個人的な経験として、あるスタートアップで仕事をしていたときに、少し変わった動物のおもちゃがあった。なぜそれが始まったのかわからないが、新しく入った人は、どれかを選んで机の上に置くようにしていた。 * これはとても変わった取り組みだが、自分たちの違った面を引き出す役に立っていた * こういった取り組みで、真剣さを壊すことに意味がある。マスクを取って自分たちらしく居ることができる * これは個人的な提案として、リーダーであるあなたの人生の中で、ユーモアや気軽さはどれくらい意味があるか? * もしくは、この組織の変容の中では? * ひょっとしたら、人生の中でも、気軽さやユーモアにももっと役割があるかもしれない * あなたの周りの人にも、それを一緒にもっと取り入れたい、ということを相談して頼んでもいい * パラドックスがある。もっと気軽さやユーモアがあると、同じくらい、もっと深いこと、たとえば目的に関する深いことを話せるようになる。 * 一方に進むと、もう片方にも、もっと深く進めるようになる ■お願い 動画の最後にもあるとおり、この取り組みはすべてギフトエコノミーによって成り立っています。 この取り組みを支援されたい方は、以下のリンクからLalouxへのご支援をお願い致します。 https://thejourney.reinventingorganizations.com/in-the-gift.html ■翻訳メモの全体の目次 https://note.mu/enflow/n/n51b86f9d3e39?magazine_key=m3eeb37d63ed1

【2.12】変容の現実とシャドー(Reality and shadows of the transformation)
※ティール組織の著者Frederic Laloux によるINSIGHTS FOR THE JOURNEYの日本語訳の個人的なメモを公開しています。 ————————————————————— ■元のURL https://thejourney.reinventingorganizations.com/212.html ■翻訳メモ * このビデオのトピックは哲学的に聞こえるかもしれないが、とても示唆があります * この変容の旅の中で、私達自身が求められる変化のうちの一つは、メンタルモデルの中で生きるのではなく、現実(reality)の中で生きること * 多くの場合、私達は現実ではなくメンタルモデルの投影を見ている * 例えば、存在するのに見えないものもあれば、逆に、存在しないのに見えるものもある * 2つの例を紹介できます * あるCEOが戦略立案をしたがっていた。それはなぜか?どんなテンションを感じているのか?と聞いてみた * その質問に対して、彼はきちんとした答えを持っていなかった。戦略立案をするのが当たり前だと思っていたから、やりたいと思っていた。 * そこにテンションはなかったが、彼は何かやらなければならないと考えていた * もう一つの例。私達は、問題が存在しないのに、それを回避するためのポリシーやプロセスを作っていないか? * たしかに、ときには作る必要があるが、多くの場合、それが発生したら考えればいい。 * しかし私達は、あらゆるリスクは備えられるべきだ、というメンタルモデルの中で生きている。95%のリスクは、起きてから対応しても問題ない * 反対の見方もできる。現実には存在するのに、私達が見たくないと思っているせいで、見えていないものもある。 * 先日、ある興味深いセッションがあった。それはこの変容の旅で起こるシャドーについて扱うもの * そこで、多くの人がシャドーと呼んでいるものは、私達が見たくないもの、光を当てて明るみに出したくないもの。 * なぜ見たくないかと言うと、私達のメンタルモデルにフィットしないから。 * 多くの人が紹介していた事例は、ティールではこう言われている、セルフマネジメントではこうあるべき、といった内容だった。 * 例えば、ある組織では、結果が良くなかったが、それを認めたくなかった。新しい世界では厳しい数字について話すべきではなく、人について話すべきだ。そうやって、結果について話すことをシャドーの世界に押しやってしまった。 * もちろん、結果は大事なこと。以前は結果だけにフォーカスしていたが、いまはそれだけではなくなっているが。 * 別の例では、新しい組織になって、サボっている人が居た。そのときに、私達は互いに優しく接するべきだ、と思っていたので、そのことを扱わなかった * もちろんそれも違う。実現したいことの妨げになることが起きるなら、それに対して自分たちを守ることも必要になる。現実には向き合う必要がある * もう一つの典型的なものでは、トップは意思決定をするべきではない、というもの。トップにいた人は、もちろん多くの貢献ができる。 * じゃあ現実に向き合って、どうすればトップに居た人がイニシアチブを発揮して、意思決定もして、一方でそれがヒエラルキー型にならないようにできるか。そのやり方を探してみる。 * もしかしたらそれはアドバイスプロセスと呼ばれるかもしれないが。 * 次の事例。お互いに競争しているのに、それを見ようとしない。私達は協力の世界に行くのではないか、と思うと、それを見ないようにする。そのときも、その現実を受け止めればいい。 * 大事なのは、私達の頭の中、メンタルモデルの中で生きるのではなく、なるべく現実をそのまま受け止めるようにすること * ホラクラシーはテンションということでそれを扱おうとしている。 * 私たちはテンションを頭で感じるのではなく、必ず体の何処かで感じている。それはすぐに頭での理解につながるのだが。 * ここからのinvitationは、メンタルモデルで生きるのではなく、もっと上手にセンシングすること。身体で感じること。なにがうまくいっていないのか、自分がそれをどう感じるのか。 * 可能な限り、現実をそのままに感じて、受け止めてほしい。 * シャドーと言って押しのけるのではなく、きちんと向き合ってほしい * テンションを感じたら、それは本当か、昔からそうだと思っているだけではないか。 * これが重要なのは、メンタルモデルでいきているとき、シャドーを押しのけるときは、たくさんのエネルギーを使っている * 現実をそのままで受け止めると、エネルギーも、movementも、人間性も戻ってくる。 * これは組織としても実践することでもあり、個人がこの変容の旅の中で取り組むべき素晴らしい実践にもなる。 ■お願い 動画の最後にもあるとおり、この取り組みはすべてギフトエコノミーによって成り立っています。 この取り組みを支援されたい方は、以下のリンクからLalouxへのご支援をお願い致します。 https://thejourney.reinventingorganizations.com/in-the-gift.html

【2.11】抵抗する人とどう向き合うか?(How to work with people who resist)
※ティール組織の著者Frederic Laloux によるINSIGHTS FOR THE JOURNEYの日本語訳の個人的なメモを公開しています。 ————————————————————— ■元のURL https://thejourney.reinventingorganizations.com/211.html ■翻訳メモ * よく議論している質問だと気づいたものがある。それは「変容のジャーニーの初期に抵抗する人とどう関わっていくのか」というもの。 * 新しい組織への変容を始めると、必ず抵抗する人は出てくる * 変容を経験した多くのリーダーから聞いたアドバイスは、抵抗する人に焦点を当てず、熱意のある人に焦点を当てること * それには3つの理由がある * 1つ目は、エネルギーを正しい方向に向けたい。熱量のある人にエネルギーを注ぐと、結果的に抵抗する人に注目しないことになる * 2つ目は、自分自身のエネルギーを取られてしまうから。抵抗する人と向き合うにはエネルギーを使う * 3つ目は、あなたが熱意のある人に注目すると、その人達が、抵抗する人と向き合うことができる。 * それは強力なこと。抵抗する人にとって、リーダーから言われるよりも、同僚から言われる方が効果がある * ただ、このときに、人のことを「決めつける」ことがないように気をつける必要がある * 先程、私は「熱意のある人」と「抵抗する人」という分け方をしたが、安易なラベル付けはリスクがある。 * この場合は特に、ラベルが一時的なものであることも多い * 私は、最も強固な反対勢力だった人々が、結果的には最も熱烈な推進者になったケースをたくさん聞いたことがある * それは、過去に何度も取り組んでうまく行かなかった経験があり、すっかりシニカルになってしまっていることもある * ラベルを貼って、そのラベルに合わせて対応してしまうようになると、抵抗する人を冷たく扱ってしまったり、無視してしまったりする * この変容の尊厳(dignity)は、こういった抵抗する人にどう対応するかに現れる * リーダーたちのアドバイスが、熱意のある人に注目すべき、と言っていることはとても筋が通っている。 * 全員にinvitationを出し続けて、それに熱意を傾ける人にだけ、自分のエネルギーも傾けていけばいい。 * 私達は抵抗する人も尊重しなければいけない。批判的になっているのは、過去に挑戦したものの、今のシステムがそれを阻んで失敗してしまったからなのかもしれない。 * もしくは、被害者意識に強く苛まれている人もいるかもしれない。それは変化するには深い個人的な変容が必要になる * そして、今度はまったく違う答えも提示したい * 抵抗する人ときちんと向き合ってもいいかもしれない * 他のビデオでも話したが、表面的なレベルで話すのではなく、好奇心を持って、深く相手の話を聞いてほしい * 何に本当に抵抗しているのか?本心にある理由は何か? * NVCでいうように、満たされていないニーズそのものは議論や否定をするものではない * 典型的なものは、セルフマネジメントに抵抗するのは、どうやって組織が運営されているか理解できなくなるから。 * 私は何を期待されているのか、何が起こるのか * それは明確さ(clarity)がほしいといっている。 * そういう人は、変容において必要なものを教えてくれる存在になる。抵抗する人は、熱意のある人が見逃していることを教えてくれる * ある組織で抵抗していた人は、変化に抵抗するのではなく、みんながストーリーを語るときに、過去のことを尊重しないことを指摘していた * 彼女が進むためには、過去の良かったことを認めることが必要だった * 今お伝えした2つのアドバイスは一緒にできる * 熱量のある人に、リーダーであるあなたのエネルギーを沢山注げばいい * そして少しは、抵抗する人とも向き合う * ただ表面で向き合うのではなく、深いところにあるニーズに耳を傾ける * 場合によっては、抵抗する人が一線を超えて、変容に加わることを止めてしまうことがあるかもしれない。そのときは踏み込んでいく必要がある * そのときは、すばやく、強制的に介入する。 * それは矛盾して聞こえるかもしれないし、抵抗を感じるかもしれない。これから目指したい方向性とは逆に聞こえる。 * あるフランスの組織では、CFOが抵抗を示していたので、CEOが介入して役割から外した。その後しばらくしてから、CFOはCEOに感謝して、あのときに介入してくれてありがとうと涙ながらに語ったらしい。 * 介入する際には非常に慎重になる。CEOが自ら介入しなくても、他の人が関わらないのか。もし関わらないならば、何が彼らの動きを止めているのか。 * そういうときは、きちんと話す機会を持ってもいい。何が機能していて、何が機能していないのか。 * CEOが自ら介入しなくても、そういう話される場を設けてもいい。 * 最後に、少し違った形として、抵抗ではなく「無関心」という場合もある * チリであるリーダーと話したことがある * 抵抗ではないが、関心がない人が多かった。教育水準が高くない人が多かった。そういう人は新しい可能性に惹かれなかった。 * 彼には、同じように好奇心を持って向き合ってみたらいいと話してみた。きっと無関心に見える人達は、そうやって扱われることに慣れているが、深く耳を傾けたら聞こえることもあるはず。中には、怒りを感じている人もいるかも知れない。 * 結果的に彼は、無関心に見える人が、どういう人生を歩んできたか、無関心になることで自分を守っているのか、ということを知っていくことになった * 彼に対して提案したのは、その話自体をみんなに伝えてはどうか。 * 無関心な人たちと向き合って感じたことを、そのまま伝えていけば、なぜ組織の変容を進めたいのかがもっと伝わっていくに違いない ■お願い 動画の最後にもあるとおり、この取り組みはすべてギフトエコノミーによって成り立っています。 この取り組みを支援されたい方は、以下のリンクからLalouxへのご支援をお願い致します。 https://thejourney.reinventingorganizations.com/in-the-gift.html