
【キャリアコンサルタントとして仕事したい人に読んでほしい】新米カウンセラーが陥りがちな4つのタイプの話
先月末、ミートキャリア(株式会社fruor)主催、「未経験キャリアコンサルタントがプロとして仕事するための実践講座(キャリアサポーター・アカデミー)」が、1年ちょっとの幕を閉じた。
私は講師として、通算5期に渡り、計40名の模擬カウンセリング講座を担当させてもらったのだけれど、受講生の半数以上(23名)が「国家資格キャリアコンサルタント」で、民間カウンセラー資格や、コーチング資格、産業カウンセラー、キャリアコンサルティング技能士や公認心理師など、そうそうたる資格保有者が集まっていたのが、なんとも印象的だった。
つまりそれだけ、
「資格を取得しても実践の場がない」→「実践の場がないから自信が持てない」→「自信がないからプロとして一歩踏み出せない」という人が多い、ということなんだと思う。
講座は終わってしまったけど、きっとこれからも、実践の場や、リアルなフィードバックを求める声はきっと一定あるんだろう。
そんな声のために、何か伝えられること、シェアできることはないかしら…
というわけで、このnoteを書くことにした。
たくさんの気づきと学びと出逢いをくれた講座への感謝も込めて。
まだきっと、たくさんいるであろう、「自信がないせいで行動できない」カウンセラーたちに向けて。
私自身が、講師として見てきたこと、感じてきたこと、受講生たちに伝えてきたことを、思いを込めて綴ってみようと思う。
このnoteは、
■ 講座卒業生たちが「原点」に立ち返れる場所として
■ 「キャリア支援に関わりたいけど、スキルに不安があって踏み出せない」
という方のチェックポイントとして
■「仕事にしてはいるけど、これでいいのかとイマイチ自信が持てない」
という方の振り返りメニューとして
活用してもらえたら、ものすごく嬉しい。
これぞ、というところから自由に読み進めてもらって、なんならぜひ、感想やコメントや、「もっとこんな話をしてほしい」というリクエストなど、いただけたら感激です。
1. まずはじめに。私が目指す「カウンセリング」とは
カウンセリングに「正解」はないし、カウンセラーの価値観やスタンス、人間性の分だけ、手段も手法もあると思う。
このnoteはあくまでも、「私自身が考えるカンセリング像」をベースにしているので、まずは、それがどんなものなのかをお伝えしたい。
(その像が、自分自身の目指すものとはちょっと違うな、という場合には、遠慮ぜず、「この人みたいになりたい」という人を探すことから始めてほしい。きっといるはずだから。)
私がカウンセリングをする上で意識していることは、次の3つ。
1. 「支払った金額以上の価値」を感じられる時間にすること
2. 「今」を聴き、「未来」を共有した上で、「今できる行動」に繋げること
3. 「安心感」と「納得感」、そしてちょっとの「勇気」を引き出すこと
私が個人でやっているキャリアカウンセリング料金は、新規の場合、60分8,800円。無料カウンセリングをしている方や機関があることを考えたら、決して安い金額ではないと思う。
そもそも日本には、「カウンセリングにお金を払う」というカルチャーが根付いていない。
相談者(クライアント)にとって、その投資は、大きな期待と、「変わりたい」「変えたい」という意志の強さの現れなんじゃないかと、私はいつも思っている。
では、どんなとき、「投資して良かった」と思えるか?
それは、「新たな気づき」があり、「変化の兆し」が見えたとき。ではないだろうか。(もちろん、カウンセリング後に、じわじわと感じる自分自身と身の回りの変化も、満足度を上げる要素として超重要なのだけれど)
「気づき」があるから「行動」が生まれる。
「行動」するから毎日が「変化」する。
これこそが、私が一番大事にしていること。
そのために、
「今」のモヤモヤをじっくり聴くことが大切で、
「本当はどうしたいの?」と、ちょっと先の未来を見てみることが大切で、
「今できることって何だろう?」って、一歩踏み出す勇気を引き出すことが大切なんだと思うのだ。
以上が私のベースにある「カンセリング像」。
私はこれをもとに、受講生40名のカウンセリングを受け、フィードバックをしてきた。
では、ここからが本題。
講師録を振り返る中、フィードバックの傾向から、4つタイプが見えた。
これからそのタイプ別に、傾向と対策を紹介します。
2. ここが本題。新米カウンセラーが陥りがちな4つのタイプ
①最も多い「カウンセラー主体」タイプ
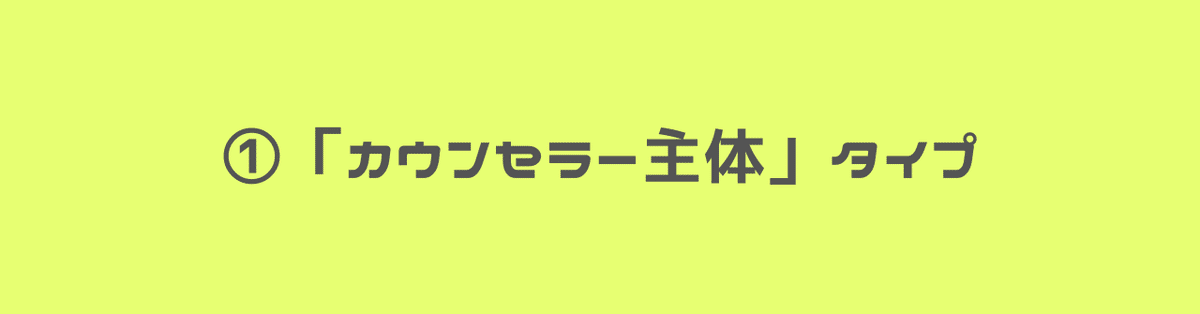
一生懸命「見立て」をし、事前準備を徹底するからこそ陥りやすいのがこのタイプ。(他のタイプに当てはまる方も、この要素は混じっていることが多い。「新米だからゆえの」とも言えるタイプだから、ここは必ず読んで欲しい。)
「これを聞こう」「あれを聞こう」と考えるうち、いつの間にか、「これを伝えよう」「こうやって着地させよう」と、カウンセラー側が会話の流れをコントロールしてしまう。
このタイプは、
カウンセラーが聞く → 相談者が答える → カウンセラーが受け止めて「解釈」する → カウンセラーが次の質問を投げる
という流れで会話が進むことが多く、「いま一歩、会話が深まらない」のが特徴だ。
以下に当てはまる場合には、「カウンセラー主体」になっている可能性があるかも。ぜひ見直してみてほしい。
☑「カウンセラーが聞きたいことを聞く時間」になっている
☑ 相談者が考えている間に、合いの手を入れてしまう(待てない)
☑ カウンセラー自身が「解」を探りながら質問を重ねている
☑ カウンセラー自身の「意見」や「ジャッジ」が入ってしまう
このタイプのカウンセラーに伝えたいのは、次の3つ。
「相談者が話したい事を話す時間」に徹底的にコミットすること
少なくとも開始30分は「提案」を避け、ただただ聴く(Listen)姿勢を保つこと
自身の価値観より、「相談者がどう思っているか」を大事にすること
カウンセラーとして、やりたいこと、叶えたいことがあるからこそ陥るタイプだとも思うので、「自分にはそれだけ情熱があるんだ」と、まずは受け止めるだけで、必ず変わっていけると思う。
はじめのうちは、会話の流れが思わぬ方向に進むことが怖いかもしれない。
でもきっと、大丈夫。
相談者を置いてけぼりにせず、できるだけ自分をまっさらにして。話の流れそのものを、相談者に委ねてみる。
考えて答えを出すのは、相談者自身。
流れに身を任せて、相談者から出てくるものにのっかってみる。きっと、相談者が話す量が増えていき、自然と会話が深まっていくのを感じられるはず。
②"理解したい"あまりに陥りがちな「情報収集」タイプ

「相談者のことを理解したい」と思うがあまりに陥りやすいのがこのタイプ。①との共通点がとっても多いのだけれど、「今」より「過去」に焦点を当てがち、という点に特徴がある。
例えばオープニングのあと、「ではまず、これまでのお仕事について聞かせてください」など、突然経験や経歴の確認に入ってしまう。
この場合、相談者は「聞かれたことにただ答える」ことがメインの体験になってしまうため、会話は常に一方通行。
本質に触れたり、新たな気づきを得たりするには、「気持ち」の理解が足りないことが多い。
チェックリストはこちら。
☑ 経歴(経験)確認や、今後の希望条件ヒアリングに時間をかけている
☑ 質問の回答を受けて、
「ありがとうございます」「なるほど」「わかりました」という言葉が出る
☑ カウンセラー自身の「納得感」に重きが置かれている
このタイプのカウンセラーに伝えたいのは、次の3つ。
「今」の状況と「気持ち」を知ることからスタートすること
「目の前の相談者の言葉から」相談者を理解するように心がけること
過去に遡るときには、相談者の了承を得ること
模擬カウンセリング後、このタイプのカウンセラーには、私は必ず次の質問を投げた。
「相談者が悩んでいるのは、"いつ"のことですか?」
すると決まって、気まずそうに、こう答える。
「”今”ですね。」
続いて、「今日のカウンセリングで重きを置いたのは、いつのことですか?」と聞くと、
「"過去"ですね」と必ず答える。
つまり、頭ではちゃんと分かってるのだ。
ただ、
相談者のことを理解したい、
勇気づけに繋がるトピックを拾いたい、
そんな相手を思う気持ちから、知らぬうちに、情報収集に走ってしまうのだと思う。
相談者が悩んでいるのは「今」だということを忘れちゃいけない。
「今の気持ち」をスルーして過去に遡ってしまうと、相談者の気持ちは置いてけぼりになり、消化不良感がのこってしまう。
カウンセリングの中で、過去を知る必要があることももちろんある。
そういうときは、「〇〇について、もう少し理解を深めたいので、過去のことを少し聴いてもいいですか?」と相談者に確認を取るといい。
そうすれば、相談者も安心して一緒に過去へ遡れるし、そこで何か気づきを持って帰ってこられるかもしれない。
大事なのは、「目の前の相談者の”気持ち”から離れない」ということ。
このタイプは誠実で、責任感の強いタイプが多いから、そんな自分を受け止めた上で、もっと肩の力を抜いて、頭より、心を動かして、相談者の話を聴いてみるといいと思う。
③管理職経験者に多い「解決に焦る」タイプ

このタイプは、比較的聴き上手でまとめ上手な方が多く、「一部を切り取れば有料カウンセリング級」というレベルの方もたくさんいた。
「自分がなんとかしなくては」という気持ちの強さゆえに陥るタイプで、後半に連れ、徐々にカウンセラーのコントロールが強くなってしまう。
「ここまでの話から、やはり転職するという選択肢の方が濃厚のように見えたので、後半は転職の方法について具体的に話しましょう」など、カウンセラー自身がテーマを決めてしまったり、結論を急いで提示してしまったりするところに特徴がある。
チェックリストはこちら。
☑ 「解決すること」に焦点が当たっている
☑ 後半に近づくに連れ、カウンセラー自身が、
持っていきたいゴールに向けて、質問を重ねてしまう
☑ カウンセラー自身に消化不良感が残る
(上手くできたかな、これでよかったのかな)
私も現在、一つの会社で管理職をしているので、課題が目の前に現れたら、「解決思考」が全面に出る気持ちはとてもよく分かる。
ただ、前述の通り、カウンセリングにおいては、「考えて答えを出すのは相談者自身」だということを忘れちゃいけない。
目の前の相談者の「気持ち」から最後までそれないこと。
解決しようとしなくて大丈夫。
「気づき」を与えるだけで十分なのだ。
カウンセラー自身が、完璧を求めなくていい。
上手くやろうとしなくていい。
カウンセリング後、「上手くいったかな」と考えてしまうのは、「カウンセラー自身の成果」に焦点が当たっている証拠。
限られた時間を精一杯、相談者と共にして、スッキリ終われるようになれたとき、きっと見える景色が変わるはず。
④"リードすること"を恐れる「フィードバック不足」タイプ

このタイプは、受容と共感が上手で、丁寧に話を聴くことができる。
カウンセラー自身が、「受け止めたことや感じたこと」をフィードバックしたり、会話をリードしたりすることを躊躇するために陥るタイプで、全体として、カウンセリング自体がぼんやりしてしまう点に特徴がある。
話の方向性が一向にはっきりせず、複数ある選択肢に迷っている相談者は、結局その選択肢をどれも潰しきれずにエンディングを迎えてしまう。
チェックリストはこちら。
☑ カウンセラー自身が感じたことや捉えたことを、伝えずに飲み込んでしてしまう(間違っていたらどうしよう)
☑ 自信がなくて、一歩踏み込めない
☑ 相談者に「決断」を促すことに抵抗がある
「カウンセラーがフィードバックなんてご法度」という考えもあるから、これはあくまで私のスタイルの話にはなるけれど、「ただ話を聴いている」だけでは、なかなかカウンセリング後の「行動」までには繋がらない。(相談者は「即効性」を求めている)
前述の通り、私は、カウンセリングによる「気づき」と「変化」を大切にしているから、「気づき」を与えるためには、しっかりと「相談者を映す鏡」になって、言葉を打ち返してあげる必要があると思うのだ。
「お話を聴いていると、私にはこんな風に見えます(感じます)が、どうですか?」
そんな風に、「Iメッセージ」でただ素直に伝えるだけでいい。
すると、「確かに・・・」と勝手に内省が進んでいくのがよく分かると思う。
そんなやり取りを繰り返しながら、話の本質が見えてきたら、「今の〇〇さんにとって、AとB、魅力に感じるのはどちらですか?」など、比較させたり、優先順位を確認させたりしながら、相談者自身が、自分で「決断」できるようにリードしていく。
そうすることで、次第に相談者の視界がクリアになる。モヤがかかっていたトンネルも、出口さえ見えれば、あとは駆け抜けるだけだ。
このタイプは優しく、謙虚な人が多いから、「自信がなくて」と口にする人も多い。でも私は、カウンセラーに自信は必要ないと思っている。
大切なのは、「正しさ」より「素直さ」。素直に関わるその姿勢が、相談者を救うのだ。
3.知識と経験だけじゃない。受講生に教わった「カウンセリング」に欠かせない3つの要素
ここまで、私が講座の中で感じたこと、伝えたことを述べてきたわけだけれど、40名のカウンセリングを受ける中で気づいた大切なことがある。
それは、相談者が「カウンセリングを受けた(話をちゃんと聴いてもらえた)」という気持ちになるに当たって、最も大切なのは、カウンセラーの知識量でもスキルでも経験でもなく、カウンセラー自身のスタンス(人間性と関わり方)だということ。
「この人はちゃんと話を聴いてくれている」
「目の前の自分自身を理解しようとしてくれている」
そう思えたときの模擬カウンセリングは、私自身も、設定なのか自分のことなのか、境界があいまいになることが多かった。そして何より、リラックスして、「話す」ことに集中できた。
また、受講生自身も、「できたかどうかは別として、自分自身はリラックスして楽しめました」と、決まってイキイキと良い表情をしていた。
1.カウンセラー自身が自然体であること
2.カウンセラー自身がその場を楽しめていること
3.目の前の相談者に集中していること
相談者にとって、この3つが、何よりも大切であるということを、ぜひ覚えていてほしい。
4.最後に一言。キャリアコンサルタントとして仕事をしたい方へ。
つたない文章、人生初のnote。
偉そうに綴ってしまって、公開するのも勇気がいる。でも、このまま「過去の経験」として記憶の中にとっておくだけではもったいないくらい、人間力に溢れた受講生たちと出逢ってきた。
だから、同じように、「よし!やってみよう」って、1人でも、前に進める人がいたらいいなと思うのだ。
時間もお金もかけて勉強して、資格も取った。もう基礎知識は十分なはず。
今、思うように動けていないとすれば、それは知識不足のせいじゃなく、自信不足のせい。
私も、ちょっと前まではそうだった。「自信がない」を言い訳に、いろんな決断を後ろ倒しにしてきたタチだ。
でも、「自信なんてなくていい」と思うようになっただけで、コトがどんどん進んでいくことに気づいた。
経験をひとつひとつ積み重ねて、一定の量と期間を積み上げたときに見える景色。そこでようやく、手応えのようなものを感じる。それが、自信になっていくのだと思う。
だから、まずは、「今」できることからやってみよう。
試しにやってみて、ダメなら、また別の方法を探せばいいだけなんだから。
500円スタートでもいい。報酬を手にすることで、「仕事」にしていく意識は必ず強化されていく。
人生は一度きり。
好奇心と柔軟性と「なんとかなる」の精神で、あらゆる挑戦を続けていこう。
きっと、言葉の重みも、相談者にかけられる言葉も、変わっていくから。
ここまでお読みいただき、本当にありがとうございました!
感謝を込めて。
えんどう みずほ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
