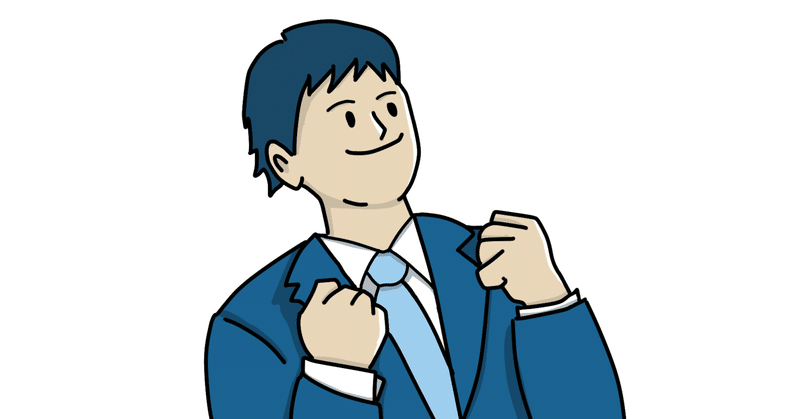
子どもたちが職員会議でプレゼンをする時…の教職員側の準備
どのタイミングを見られても、見せられる自分でいれるか。
100点満点ではないプレゼンを受けても、見る側は、そのプロセスを見て、
いかに、次につながるフィードバックをするか。それが指導者の観点。
さて前回は、こちら↓の話をしました。
いよいよ、
「高校生活の想い出になる、全員参加できるイベント」
を目的としたイベントを、子どもたち主体で企画書を作り上げ、そして「職員会議」にて、プレゼンをするに至るまでの軌跡についてです。
職員に必要なスキル、聞く側に求められる姿勢
その日は午後15:00から会議を開始。
会議を行う場合は、基本的には生徒は完全下校、居残り禁止としています。
朝礼時に全職員に対し、以下内容を強く伝達しました。
・15:00~職員会議開始で、冒頭30分程度に生徒からのプレゼンがある。
・15:00開始:時間厳守。そのため生徒完全下校のため、対象以外の生徒については、必ず14:50までには下校させること。
・15:00ちょうどから開始するので、職員は準備の徹底を。
・プレゼンについては、流れとしては10~15分程度発表、残り時間は質疑応答となる。
・会議内での提案事項として、基本的に”一社会人”として接し、質疑応答に臨むこと。
私の意図としては、今回のプレゼンの中で、職員への意識・行動変化も出来れば引き起こしたいということで、特に上述内容を伝えました。
当時の職場では「時間に対する意識」が少し欠けているように思えました。
教職員が率先垂範をする風土を改めて作り出すチャンスでもあるので、改めて意識を高めてもらうためにこの伝達を行いました。
職場にもよるとは思いますが、会議やイベントが立て続いたり、面談・授業が連続すると、時間に対する意識が欠如し始め、会議に遅れたり、授業時間に少し遅れたり、面談時間が伸びたり…が発生し始めます。
これはファシリテーションを実践していく中でも非常に大事な視点で、その時間帯に遅れるということ自体が、深層心理内に
”優先度が低い”という状態
であることは間違いないのです。
本当に大事な会議であれば、かなり時間に余裕をもって集合時間や開始時間に間に合うようにしているでしょうし、また事前の準備もしっかりしているはずです。
例えば本当に自分が見たい映画や劇、ライブなど…開演前に座席についてることが普通ではないかと思います。
これは裏を返すと、部下や生徒もその視点を深層心理的に持っているものです。会議に社長や部長がちょっと遅れてくると「あ、この会議はさほど重要ではないのかな?」と思わせてしまうということです。
※例えばですが、株主総会などで、金屏風の前に座る人たちが遅れることってあまりないですよね?重要度は知らず知らずのうちに行動に表れているものです。
今回は生徒の見本とならなければならない”職員”
やはり率先垂範してもらわないと、見本にはなりません。いかにタイムマネジメントをしなければならないかを考えてもらう機会にしました。
目の前の生徒がいれば、対応したくなるのが職員の性ではあるとは思いますが、どれだけ時間を意識した行動が出来るかをもう一度改めて考えてもらいます。
”突発的案件”や、”この登校してくれた機会を逃さないために!”というのは往々にしてあるのですが、それが『免罪符』のようになるのも実は多いのです。だからこそ、時間を意識した行動をどれだけできるかを、職員側にもう一度見つめなおしてもらうことが必要と感じていたのです。
・それ、本当に今対応しなければならない案件でしょうか?
・もう少し前から計画的に行うことはできなかったのでしょうか?
・準備することにどれだけ”全力”を出せていたでしょうか?
個人的には、出来る人ほど”時間に強い”イメージがあります。
時間通りに始まり、早く終わらせる。
時間通りに始まるということの”凡事徹底”は常に必要なのでしょう。
フィードバックの姿勢をどう整えるか
もう一つここで大事なのが”フィードバック力”です。子どもたちの発表に対して、フィードバックを行うことは当然必要になるのですが、今回の件でのポイントは、
「どのタイミングで”教師の仮面を脱ぐ”か」です。
上段でも述べたように、
・会議内での提案事項として、基本的に”一社会人”として接し、質疑応答に臨むこと。
これが大事なのです。どうしても”教職員”という立場から、発表についての準備から、発表方法、資料の準備具合なども含めて、そちら側に対するフィードバックを行ってしまいがち。
ただ今回は職場の同僚・後輩が、新たな企画を提案してきたとする場合、そうしたフィードバックは別のタイミングで行い、本旨である具体的な内容に関する質疑応答や実行に向けての改善案など、”企画会議”としてのスタンスになるはずです。これを大人たちに交じって、どれだけできるか?ということを体験させてあげたいので、上述のように”一社会人”として対応することを意図しました。
指導ではなく、同じ土俵に立つことで、改めて一緒に作り上げていくことの重要性を知ってもらいたいということからです。
つまり”教師の仮面”をとって、同じ共同体の一員として、企画に向き合うことで議論が活発になることを目標としたというわけです。
新たな視点、新たな気づき
今回のこの目標設定は、結果から言うと「◎」でした。
やはり新たな刺激、新たな気づきは、教職員だけでなく、子どもたちにも良い影響を与えてくれました。
教職員は、新鮮な感覚で…
・自分が新人の頃の緊張感を思い出しました。
・一生懸命に答えようとする生徒たちの姿勢を見て、会議で議論をすることの重要性を再認識しました。
・子どもたちでも十分には発表もファシリテーションもできることの気づき。そしてこれは伝播していくことができる可能性を感じました。
子どもたちからは…
・やはり先生たちの見ている視点は、我々生徒をどう動かすかというところに重きを置いてくれていて、勉強になった。
・細かい部分に関しての意見も参考になったし、見てる視点の違いが凄いと感じて、先生たちは沢山考えているんだなと改めて感じた。
・先生たちが手を挙げて、そして本当に興味を持って質問をしてくれる姿が嬉しかった。本気で考える場って緊張するけど、面白い!
これだけでも十分な気づきや学びではないですか?
常に我々、大人は”学ぶ”姿勢を見せていく必要があると改めて感じます。
さて、いよいよ次回は子どもたちの発表の方法や、その発表が終了した後のフィードバック・感想会について、お話をしていきたいと思います。
ご覧いただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
