瀬戸内寂聴という生き方
今月の始め、「瀬戸内寂聴さんがお亡くなりになられた」というニュースが飛び込んできた。享年99歳。
一報の翌朝、新聞の特集記事を読みながら、私は寂聴さんの生涯に思いを寄せた。
◇
私が寂聴さんのプロフィールで知っているのは、幼い娘と夫を残して若い男性と駆け落ちしたこと、「花芯」という小説を書いて文壇からバッシングを受け長く不遇の時を過ごしていたこと、妻子持ちの小説家と不倫を重ねていたこと、出家して僧侶になったこと、「源氏物語」を全訳されたこと…以上の五点である。
それ以外では、出先に置いてあれば手に取ってみる女性週刊誌に「青空説法」のコーナーがあって、そこに記載されている寂聴さんの参拝者への返答を「うんうん、なるほどなぁ」とうなずきながら読んだくらいだろうか。
あと、私の蔵書の中に、寂聴さんが独自の視点で「源氏物語」について解説した本が一冊ある。
90歳を超えて体調を崩されていたとはいえ、いつも笑顔がチャーミングで若々しく、時にはピシャッと叱る潔さもあり、今や「高齢者の見本」のような立ち位置でいらっしゃった。
そんな寂聴さんが100歳を目前にお亡くなりになられたと知り、私は彼女に関する小説や著書をちょっと読んでみたくなった。
『あちらにいる鬼』井上荒野
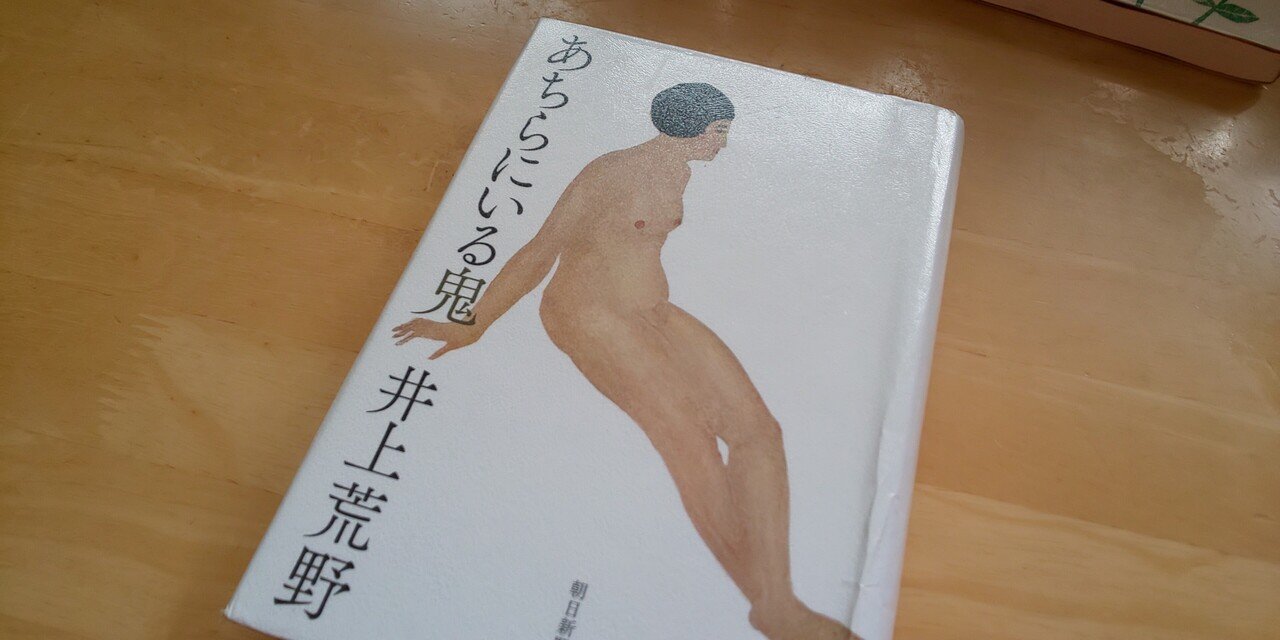
こちらは、小説家・井上光晴の娘さん、井上荒野さんの小説。
先述の新聞記事から、寂聴さんがモデルになった小説があると知り、図書館で探して借りてきた。
主な登場人物は、妻子持ちの小説家・白木真二、女流小説家・長内みはる、白木の妻・白木笙子である。
白木真二と長内みはるの出会いから小説は始まり、二人は不倫関係へと落ちていく。白木の妻の笙子は二人の関係に気づきつつも、白木との家庭を大切に守り続け、いつしか笙子とみはるは、白木を挟んだ形で不思議な友情を育んでいく。
実は、この小説のモデルは、荒野さんのご両親と瀬戸内寂聴さんだった。
白木真二のモデルは(父親の)井上光晴さん。白木笙子は(母親の)井上郁子さん。そして、長内みはる(小説上でも出家して寂光となる)のモデルは、小説家の瀬戸内寂聴さんである。
つまり、荒野さんは、お父様の不倫とご両親の夫婦仲を、小説の題材にされて書かれた…ということである。
この小説を書くにあたって、荒野さんは寂聴さんにその決意を報告したそうだ。すると、寂聴さんはたいそう喜び「どんどん書きなさい。何でも話します。」と賛成したそうな。もともと、寂聴さんと井上家は、家族ぐるみで親しくお付き合いをされていらっしゃったそうで、同じ小説家として、寂聴さんは、荒野さんの才能を高く評価されていたとのこと。そんな荒野さんに「いつか自分のことを書いてほしい」と願っていたそうだ。
こうして出版された荒野さんの本の帯に、寂聴さんはこう書いている。
モデルに書かれた私が読み 傑作だと、感動した名作!
作者の父井上光晴と、私の不倫が始まった時、作者は五歳だった。五歳の娘が将来小説家になることを信じて疑わなかった亡き父の魂は、この小説の誕生を誰よりも深い喜びをもって迎えたことだろう。作者の母も父に劣らない文学的才能の持ち主だった。作者の未来は、いっそうの輝きにみちている。百も千もおめでとう。瀬戸内寂聴 (帯より抜粋)
多分、一般人の感覚だと「親の不倫を子供が小説にする」なんて、とても信じられないことだろう。しかし、ここに出てくる父も母も娘も、そして寂聴さんも、みんな小説を書く人である。小説家の視点で見ると、こうした特殊で特別な関係は、小説のネタとしてはいかようにも調理できる。
現に、この小説でも、父(真二)が他で引っ掛けた女が、白木家に飛び込んできて「一緒に暮らす」と大騒ぎする場面があるのだけど、おろおろする父とは対照的に、その場に居合わせた母(笙子)は「これは小説に書けそう」と冷静に観察し、(成人して小説家になった)娘もこの様子を小説にするかもしれないと思うシーンが登場する。
この場面だけで、白木に関わる女性たちのなかでも、白木の妻が一番腹が座っていて達観していることがわかる。白木の妻になるということは、単に好きだ惚れただけでは務まらない。また、白木の愛人であるみはるも、生きる覚悟ができている。みはるの出家によって白木との愛人関係は終わったけど、その後も二人の縁は切れることなく続き、今度は家族ぐるみの温かい交流へと発展していく。こうして二人の女人の関係が発展していく様子は、『源氏物語』の紫の上の明石の上のようでもある。正妻と愛人、この二人が友情を分かち合えたのは、妻の笙子も愛人のみはるも、人として深くゆるぎないものを心の芯に持っていたからだと思う。
嘘と現実が混ざり合い何が真実なのかサッパリ分からない白木の話を、時には面白がって聞く笙子。白木の嘘の奥にある淋しさをじっと感じ取るみはる。互いに、愛する男を静かを観察し、相手への思いと同じくらいの深さで自分の心情をもじっくり見つめて感じ取り、自分で自分に折り合いをつけながら、自らの人生を静かに生きていく。
ここで描かれているのは「三人三様の生き方」だけど、不倫の恋を介して、最初はバラバラで別々の存在だった三人が、時間の経過と共にそれぞれが「掛け替えのない存在」として繋がっていく。まさに「因縁」だなぁと感じた。
ちなみに、この小説の主人公は「みはる(寂光)」と「笙子」であり、主人公が交代しながら話が進んでいく。
読んでいると、「みはる」の章では、寂聴さんそのものが真実を語っているように感じられ、また、「笙子」の章になると、荒野さんのお母さんが本心を語っているように感じられ、どんどん物語の世界に引きずり込まれていく。そして、この二人の女性の視点から、白木真二(井上光晴)という男性の姿がリアルに彫り起こされていく。
◇
今度、この小説は映画化されるそうだ。
実写ではどんな風にこの世界が描かれるのか。非常に楽しみである。
【単行本】
【kindle版】
『笑って生ききる』 瀬戸内寂聴
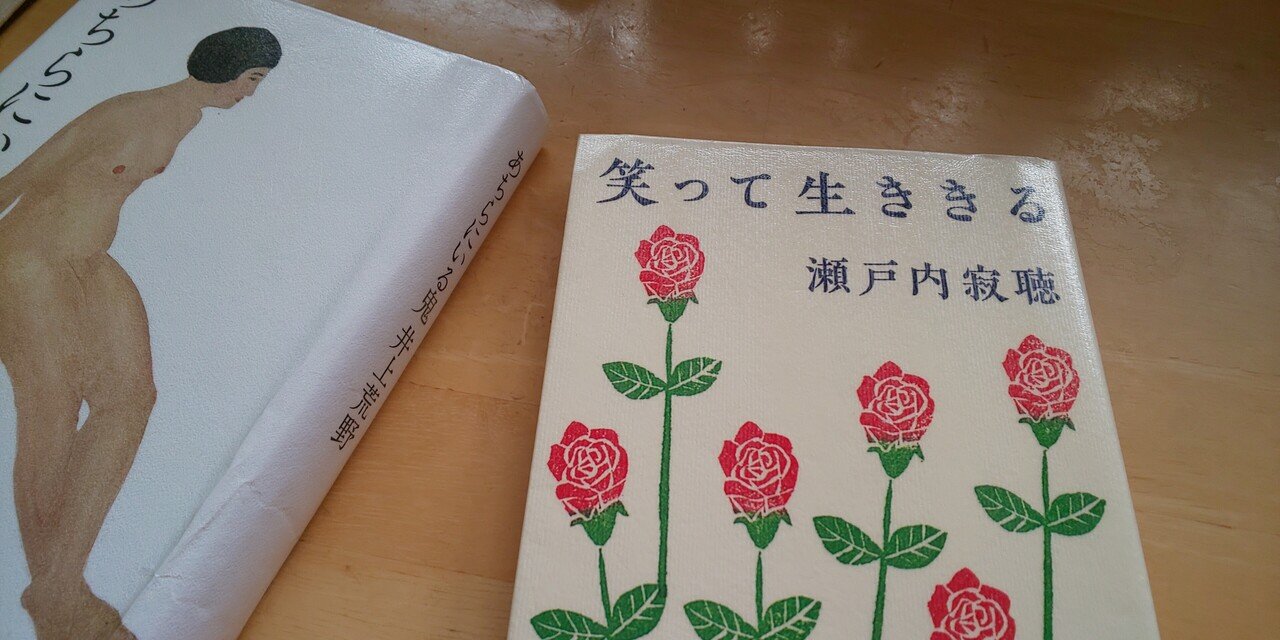
打って変わって、こちらは「婦人公論」に掲載された寂聴さんのエッセイ・対談・インタビューを厳選して集めた一冊。
この中に、なんと井上荒野さんとの対談も収録されている。
『あちらにいる鬼』を読んだ後に、寂聴さんと荒野さんの対談を読むと、上記でご紹介した寂聴さんの帯の言葉通り、お父様の井上光晴さんは、あちらの世界で娘が書いたこの小説を喜んでいらっしゃるのではないか…と思えてならない。
◇
この『笑って生ききる』は、今は書店に平積みされて大々的に売られているので、皆さんも目にしたことがあると思う。この本の帯の写真がユーモラスなので、「ケラケラと陽気に笑える楽しい本なのかな?」と思いきや、いやいや、心の奥深くにずっしりと響く良いお話ばかりで、人生について深く考えさせられる内容だった。
エッセイの合間に対談が挟み込まれていて、非常に読みやすい。忙しいときでも、ぱっと開いていつでも寂聴さんに触れることができる。
きっと若い人も、この本を読んで胸がスッキリするんじゃないかなと思った。
◇
この本のなかで、私の印象に強く残ったのが、第4章だ。
ここでは、寂聴さんがご自身の半生について書いた手記が2つ載っている。その中でも、1962年に公開されたという『「妻の座なき妻」との決別』という手記。妻子ある小説家Jとの決別や自らの半生について赤裸々に語っている。
ここで寂聴さんは、幼い娘を残して駆け落ちしたことにも言及していて、相手の男性のことを「初めての恋だった」と記している。そう、あれは初恋だったのだ。
恋多き女と言われていたけど、まだ少女だった彼女は女学校時代を優等生で過ごし、(当時の若い女性が皆そうしたように)親に言われるまま、普通にお見合いをして、何も考えずそのまま結婚して、子供を産んだ。
つまり、当時の寂聴さんは、恋を知らないまま結婚して、妻になり母になったのだ。ごく普通の、いやどちらかと言えば模範的で真面目な妻であり母であった。
しかし、子供が4歳の時、彼女は恋を体験してしまったのだ。夫ではなく、夫の教え子に…。
彼女が駆け落ちしたのは25歳のとき。相手の男性は21歳だった。
この年齢を改めて目にしたとき、私の息子の今の年齢よりも年下であることに驚いた。若い…と。
現代なら、20代前半といえば、まだまだ子供みたいな年頃で、恋愛や友情に忙しい時である。年齢的にも親や社会から半人前扱いされることも多いし、一方で、面倒見がいい大人たちから可愛がれる年代でもある。
しかし、この時の彼女…いや当時の女性たち、更には若い男性たちは、恋を知らずして、あるいは恋を実らせることもなく、親が探してきた相手と、相手がどんな人かよく分からないまま結婚し、そのまま模範的な家庭人になることを求められてきたのだ。
そんな規範に厳しかった時代に、女人の煩悩に焼き尽くされながらも、女性らしく逞しく生き抜いた寂聴さん。
世間の人々は、そんな寂聴さんのことを「ふしだらだ」とか「不道徳だ」と責めてきたけど、当時の社会背景を想うと、これは仕方がなかったことなんじゃないか…と思えてならない。
晩年は、生き別れていた娘さんとの交流が復活し、海外に住むお孫さん達ともお会いになったとか。血を分けた肉親が許しているのだから、いつまでも彼女の過去を責め立ててバッシングするのは間違っているのではないか。みんな幸せになったのだ。だから、世間も彼女の生き方を裁くべきではない…と思う。
◇
駆け落ちの後、恋人と別れ、全てを失った彼女は生きるために書いて書いて書き続けた。小説家として大成しつつも、また新しい恋をして、いくつかの別れも体験し、やりたいことをやり尽くし、51歳で落飾して僧形となる。出家後は人々のために身を捧げる生き方にシフトし、いつも弱者の心に寄り添ってきた。常にエネルギッシュで「書く」ことに最後まで情熱を燃やし続けてきた。
こんなにも太く強くしなやかに大きく振り切った生き方は、今の若い世代でもなかなか難しいと思う。
娑婆の酸いも甘いも全てを味わい尽くし、人間の弱さも醜さも愛も涙も全てを絡め取ってその腕に抱いたまま、彼岸へと旅立たれた寂聴さん。
彼女の生き様から、私は大きな力をもらった。
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは旅の資金にさせていただきます✨
