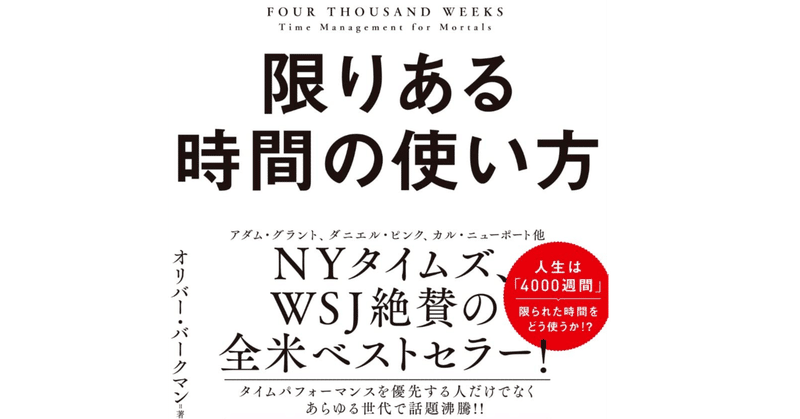
ちっぽけな自分を受け入れる――「限りある時間の使い方」を読んだ
ベストセラー書として紹介されて、気になって読んでみました。
原著は2021年8月に出版され、和訳が2022年6月に出版されました。
著者はニューヨーク在住イギリス人記者のオリバー・バークマン、
訳者の高橋さんの訳書には「エッセンシャル思考」「エフォートレス思考」などがあり、それらの流れを受けている本です。
邦題の印象はライフハック系のビジネス書のようですが、中身は自己啓発書です。日々忙しく過ごすビジネスマンに読んでほしくて、手に取りそうな邦題にしたのだと思います。
自分にとっての理解と備忘のために、印象に残った部分を共有します。
Pert1: 現実を直視する
「私達は有限なのだ」という現実を直視することが重要だというのが前半部の主張です。
まず、私達の生産性が上がったとしても、また別の忙しさが私達の時間を埋めてしまうものだという点から始まります。
(パーキンソンの第一法則と言われるものですね。)
したがって、時間を効率的に使うだけでは堂々巡りです。より俯瞰した見方から時間に関して理解を深めるべきだと展開していきます。
「時間がある」という前提を疑う
3章では、哲学者のハイデガーの主張を踏まえ、そもそも時間とは何なのかということを考察していきます。
「私達が時間を持っている」(has-a関係)というよりは、「私達は時間の一部である」(is-a関係)のではないかという仮説から考察していきます。
人間が存在するとは、そのまま時間的に存在することを意味する。時間抜きで存在を考えることは不可能だ。生まれてから死ぬまでの時間。いつか終わりが来ることは確かで、でもいつ来るかはわからない、その間の時間。「自分の時間は有限だ」と僕たちは考えるけれど、ハイデガーの奇妙な視点から見れば、「自分は限られた時間である」という方が正しい。限られた時間こそが、僕たちの存在の本質なのだ。
その視点を踏まえると、「歴史の全体の中で私達が存在できる時間は限られている」。したがって必然的に私達は有限なのであり、その有限性を楽しむことが重要なのだと主張しています。
メニューから何か一つしか選べないことは、決して敗北なんかじゃない。決められた時間のなかで「あれ」ではなく「これ」をする、という前向きなコミットメントだ。自分にとって大事なことを、主体的に選び取る行為だ。
「ほかにも価値のある何かを選べたかもしれない」という事実こそが、目の前の選択に意味を与えるものだ。これは人生のあらゆる場面に当てはまる。例えば結婚に意味があるのは、その他の(ひょっとすると同じくらい魅力的な)相手をすべて断念して、目の前の相手にコミットするからだ。
この真実を理解したとき、人は不思議な爽快さを感じる。
「失う不安」のかわりに「捨てる喜び」を手に入れることができる。
この考え方は、「あれもこれも」という終わりのない欲望に囚われないようにする方法としてしっくりきました。
私達が時間なのだ、というのは面白い表現ですね。
P95では具体的な実践方法が書かれています。
「優先度「中」を捨てる」というもので、
人生でやりたいことを25個挙げる
上位5個を残して、残りの20個をすべて捨てる
それくらいに1つのことに集中しないと何かを満喫することはできないのでしょう。1/5しかやらない、という集中具合に、はっとさせられました。
本当の敵は自分の内側にいる
6章では、仏僧の事例から、有限性との向き合い方を述べています。
「不思議なのは、やらなければならないことのほとんどを、やる気になれないことだ。別にトイレ掃除や確定申告だけではない。心からやり遂げたいと思っていることでも、やらなければと思うと、なぜかやりたくなくなっているのだ」
(中略)
この不可解な現象の答えは、何を隠そう、僕たちの有限性にある。
僕たちが気晴らしに屈するのは、自分の有限性に直面するのを避けるためだ。つまり、時間が限られているという現実や、限られた時間をコントロールできないという不安を、できるだけ見ないようにしているのだ。
(中略)
だから、全てをコントロールしたいという欲求を捨てて、とにかく進んでみるしかない。
何かしないといけないことを前に、部屋の掃除が進んでしまったことは僕も一度や二度ではないです。それは完璧主義から生じていて、自己の有限性からの逃避である、という説明はとてもしっくりきました。完璧主義にとらわれない事が必要ということですね。
巻末の付録部分に、日々気をつける10の実践があるのですが、その中の1つに「失敗すべきことを決める」というものがありました。
人の時間とエネルギーには限りがある。だから、思うようにできないことがあるのは当然だ。失敗は避けられないと思ったほうがいい。
大事なのは、戦略的に失敗することだ。
人生のどの側面で失敗を許容するかを、あらかじめ決めておく。そうすれば時間とエネルギーを効果的に使えるし、うまくいかなくても必要以上に落ち込まなくてすむ。
(中略)
失敗していいことリストに「芝生の手入れ」や「キッチンの整理整頓」を入れておけば、芝生が伸び放題でも、キッチンがぐちゃぐちゃでも、自分を責めなくていい。
(中略)
これは完璧なワークライフバランスを追い求めるよりも、バランスを崩すことをあえて受け入れる生き方だ。今はうまくできなくても問題ない。そのうち力を入れるべき時がやってくるのだから。
普段から「力を入れる・入れない」のメリハリはつけているつもりだったのですが、「失敗すべき」という表現は、より力を抜くことを可能にしてくれると思うので覚えておこうと思いました。
Pert2: 幻想を手放す
後半部では、それではどうすれば有限性を受け入れられるのだろうという実践方法に焦点が当たります。
ちっぽけな自分を受け入れる
13章では「宇宙的無意味療法」という考え方が紹介されます。
日々の不安や悩み事は、宇宙の規模に比べれば無意味である
(P242より要約)
宇宙的無意味療法は、この壮大な世界におけるじぶんのちっぽけさを直視し、受け入れるための招待状だ(考えてみたら、自分の行動で宇宙を左右できるという考えのほうが、ずっとおかしな話に思えてこないだろうか)。
4000週間という素晴らしい贈り物を堪能することは、偉業を成しとげることを意味しない。
むしろその逆だ。
並外れたことをやろうという抽象的で過剰な期待は、きっぱりと捨てよう。そんなものにとらわれず、自分に与えられた時間をそのまま味わったほうがいい。
宇宙を動かすという神のような幻想から地面に降り立ち、具体的で有限な――そして案外すばらしいこともある――人生を、ありのままに体験しよう。
「無意味」というと仏教の空観のようですが、主張としては中観だと思っています。
(仮観、空観、中観に関しては次の記事が分かりやすかったです。)
完璧主義に囚われず、自己の有限性を埋め入れるための思考として、要所要所で取り入れていきたいです。
暗闇の中で一歩を踏み出す
最後の14章では、「それでは、何ををしたらいいんだろう」を考えるために、「それしかできないこと」というキーワードに着目します。
いくつか問いかけの質問があるのですが、私は下記が気になりました。
もしも行動の結果を気にしなくてよかったら、どんなふうに日々を過ごしたいか?
世界は複雑で、厳密な因果関係の立証が難しいことも多いです(ヒュームの呪い)。また、結果が現れるまで時間がかかるような長いプロジェクトもあります(教育や研究など)。
「結果を知りようがない」という事実を受け入れた上で、だとしても、これがやりたい、というものは何なのかを考えてみるための問いとして、大切にしてみようと思いました。
本章の最後では心理学者のユングの言葉を引用し、自分にとっての「それしかできないこと」が何なのかを考えてみることを促されます。
「前もって知ることはできません。あなたが一歩を踏み出したとき、そこに道ができるのです。……ただ静かに、目の前のやるべきことをやりなさい。やるべきことがわからないなら、きっと余計なことを考えすぎるほどにお金がありあまっているせいでしょう。しかし次にすべきこと、もっとも必要なことを確信を持って実行すれば、それはいつでも意味のあることであり、運命に意図された行動なのです」
自分にとっての確信、という部分がポイントなのだと思います。
「止められてもやる」「どうしようもなく好き」「確信がある」「運命づけられた」など、表現としては様々なニュアンスがありますが、要するに意味を感じることをやる、ということなんだと思います。
(理解した内容をどこかにまとめておく、というのは私にとって確信を持ってできることのひとつだと思っています。)
本書の締めの言葉です。
時間をうまく使ったといえる唯一の基準は、自分に与えられた時間をしっかりと生き、限られた時間と能力のなかで、やれることをやったかどうかだ。
表現としてはシンプルになっていますが、全体の流れの中から重みが感じられるので、気になったら本書をお手に取ってみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
