
interview Makaya McCraven:時を経て形を何度も変えた楽曲の断片を繋ぎ合わせて作る”時間を超えた”作曲法
マカヤ・マクレイヴンの『In These Time』は新たな金字塔だ。
これまで「生演奏」と「ポストプロダクション」を巧みに共存させてきたマカヤが、そこに更に「作曲」「編曲」を加え、その四つのプロセスの境界がわからなくなるほどに溶かしてしまった『In These Time』には誰もが驚いた。どこからどこまでが作編曲された楽曲を生演奏したものなのか、どこからどこまでが解体再構築されたものなのか、ちょっと聴き込んでもさっぱりわからない。すべては滑らかに混ざり合っているが、ところどころでさりげなく違和感が聴こえてくる。マカヤはとんでもないものを作ってしまったと思う。
このアルバムについては以下のRolling Stone Japanのインタビューでマカヤに話を聞いている。
またアルバムの制作の中のマスタリングを担当したデイヴ・クーリーにも話を聞いている。
ただ、プロセスの話は掲載されていなかった。ここでは『In These Time』の制作プロセスのディテールについて少し踏み込んだ話をした部分を掲載する。マカヤがアルバムに込めた意図がかなり見えてくるようなヒントが埋まっていると思う。
そしてその延長でマカヤは自身の音楽家としてのアイデンティティや音楽観みたいなものも語っている。そこも併せて、読んでもらいたいと思う。
生演奏とプロダクションがせめぎ合うサウンドはこの先、どんどん進化していく予感がある。現時点でのそのコンテクストの最高傑作とも言えるこのアルバムを深く理解することはこの先のジャズの動向を見据えるために役立つに違いないと僕は思っている。
取材・編集:柳樂光隆 通訳:青木絵美
◉『In These Time』におけるポストプロダクション
――『In These Time』ではどのようなやり方で曲を共有して、演奏して、録音したのでしょうか?
このアルバムは様々なセッションを通して、さまざまな形へと変化して進化していったんだ。だから曲はあらゆる方法で存在していたよ。コンサートのための譜面もあったし、その録音した音源を俺がさらに編集した音源もあった。俺は自分の活動に対して、あらかじめ具体的なことを決めないようにして、むしろ過程やステージなどをセッティングするだけにしている。そこに自分が良いと思う人を引き込んで、十分な関係性が育まれる時間さえ与えれば、直線的でなく、蛇行しながら進むかもしれないけれど、何らかのものが出来上がる。そして、今というこの時点に辿り着くことができた。
――ポストプロダクションの部分について聞かせてもらえますか?
「In These Times」にはさまざまな瞬間が引用されているから、たくさんのレイヤーで構成されている。Symphony Centerでのライヴから、スタジオでのセッション、さらにはWalker Arts Centerで演奏されたサックスのソロや、他のライヴからの録音、オーバーダブ、ストリングスのアレンジメントなど数多くのレイヤーが入っている。曲全体にわたって、ライヴの音源とスタジオの音源を行き来しているから、全てのタイミングを合わせるのに細かい微調整が必要だった。あの曲ではポストプロダクションにものすごく手間と時間をかけたね。
ーー様々な時期に様々な場所で演奏された録音状態もテンポもフィーリングも異なる「In These Time」の断片を組み合わせてアルバムに収録されたヴァージョンが出来ていると。途方もない作業ですね…
「The Knew Untitled」も手間と時間をかけているんだ。ここにはバンドの初期のセッションが取り込まれている。「曲」という形ができてからは最も長い間、手をかけて、アレンジしていた曲かもしれない。何年間も色々な形でバンドと一緒に演奏していた曲を、このアルバムに向けて新たな形にして、Chicago Symphony Centerでライヴ演奏したんだ。でも、そのベース・トラックはそのライブよりも以前にやったセッションからのものを使っている。このアルバムの多くの曲は時を経て形を何度も変えていき、色々なヴァージョンとして存在しているんだ。再度録音されたものや再度アレンジされたもの、様々なヴァージョンや様々なセッションの音がアルバムに収録されている。だから、アルバムをまとめる段階では、色々な音源を聴き直して振り返りながら、このアルバムにふさわしい物語や流れを作ろうとしたんだ。
――「In These Times」「This Place That Place」など、 “live at Le Guess Who? 2019”で既に演奏されていた曲に関しては、少なくとも3年前にはかなり完成されていたと思います。このライブでのヴァージョンが、どんな変更やポストプロダクションを経て、アルバムに収録されていたヴァージョンになったのでしょうか?
例えば、「The Knew Untitled」のアルバム・ヴァージョンは俺たちがライヴでやるヴァージョンと音楽の形式が違う。今後のツアーでもこの曲はアルバムとは異なるスタイルで演奏されると思うし、もしかしたら逆に昔、演奏していたような形に戻して演奏するかもしれない。俺にとってさまざまなヴァージョンが存在するのは自然なこと。ヴァージョンが古いものはボツにされるわけじゃないんだ。
――なるほど。
ジャズの曲の良いところは、曲が決まっていれば、それを新しい解釈や新しいフィーリングにして表現することが許されること。別のアルバムや別のバンドで、その曲の新たな解釈をすることができるし、再構築をすることもできる。だから、作曲をする時には、今後その曲が新たに解釈されたり、自分たちのその時のフィーリングやライヴセットでのハマり具合によっては異なるフィーリングで演奏される可能性も考慮して書くようにしている。その曲のヴァージョンはどんどん変わるかもしれないけれど、また元のヴァージョンに戻ることだってあるってことだね。
――必ずしもどんどん変えて前に進むだけじゃなくて、敢えて元のヴァージョンに戻すこともあり得ると。時間の進行は一方向じゃないわけですね。面白い。
そういうことだね。「The Knew Untitled」に関してはアルバム・ヴァージョンではライブとはアレンジが変わっているんだけど、ギターソロに関してはライヴで録音したものをそのまま使っている。でも、別の箇所ではスタジオで録音した音源を切り刻んだものも入っている。ライヴ中は演奏を録音して、それをその場で切り刻んで入れ替えたりできないよね?俺はどうせアルバムをつくるなら録音された音源だからこそ存在することができる要素を入れたいんだよ。そういったライヴ演奏との大きな違いがいろんなところに存在している。
◉ライヴにおける『In These Time』
――同じ曲の中のギターに関してもスタジオで録ったものとライブで録ったものが混じっていると。アルバムではライブではできない要素を入れるようにしているんですね。
そうだね。でも、逆にライヴでしかできないこともある。もちろんレコーディング音源を操作して(ライヴのように聴かせることは)可能かもしれないけれど、ライヴのような効果は得られない。そもそもライヴだったら、演奏する直前に新しいアレンジを思い付いて、その場で変えちゃうかもしれないしね。例えば、バンドのみんなに「最初はスローなテンポで始めて、だんだんビルドアップして」とライブ前に指示を出すことができる。「決まっている楽式を交互に演奏するのはやめよう」と指示をして、「Aセクションだけを演奏して、Bセクションは合図待ちにしよう」ってこともできる。「前回は楽曲形式通りにA、B、C、A、B、Cと演奏していたけれど、今回は違った感じにしたいからCセクションは俺が合図を出すまで演奏するな」って指示も出せる。そういった変化を入れて演奏すると、別のフィーリングの曲になるんだ。
ーーライブでも事前に浮かんだ編曲のアイデアによっていくらでも新たなヴァージョンを生み出すことができると。
だから、アルバムのヴァージョンはあくまでも「とりあえずアルバムに収めたひとつのヴァージョン」ってこと。つまり、幾つもあるヴァージョンを切り刻んだり、組み替えたりして、アルバム用にまとめたヴァージョンのひとつに過ぎないんだ。でも、その曲をライヴで演奏することになったら、バンドがいつも演奏している方法だけじゃなくて、過去の演奏方法で演奏するかもしれない。もしかしたら、アルバムのアレンジに忠実に演奏したい時もあるかもしれない。ライブでは「その場にいる演奏者が誰なのか」「その場の雰囲気がどうなのか」など、全ての要素を考慮した上で変幻自在に演奏する曲の形を変えるんだ。
◉ドラマーではなく、ミュージシャン、プロデューサー、作曲家
――楽曲は変化し続けると。ところであなたはドラマーなわけですが、『In These Times』ではあなたはドラマーとしてどんな演奏をしようとしたのでしょうか?
この質問にはいくつかの解答方法があるかもしれないけれど、俺がアルバムを作っているときは自分をドラマーとして見せたいわけではないってことは言っておきたい。自分をミュージシャン、プロデューサー、作曲家として表現している。つまり、いち演奏者ではなく、音楽を作っている人としてね。
ドラマーは昔からバンドリーダーになりにくいとされてきたし、人々もドラマーがバンドリーダーになることを期待していなかったと思う。だから今、自分がバンドリーダーでもありドラマーであることに対してはありがたい状況だと思っている。
そもそも俺は昔から自分をドラマーとして見せたいとは思っていなかったんだ。だから、「どうやったらこのアルバムで最高のドラマーになれるだろう?」とか「ドラマーとしての自分を目立たせるために、どんなテクニックを披露すればいいんだろ?」とか考えたことがない。
俺が考えていたのは、「どうやったら自分が聴きたい音楽や、自分と自分の仲間たちがライヴで楽しんで演奏できる音楽を表現できるか」「自分たちが感じている感情を観客に伝えることができるか」ということ。俺のライヴを観にきた人だけじゃなくて、母親からも「ライヴはすごく良かったけれど、なぜもっとドラムのソロをやらなかったの?」とか言われたことがあるよ(笑)。でも、「お袋、俺はバンドリーダーだから、ライブ中のバンドの状況を常に把握しなきゃいけないんだよ」って答えたよ。バンドは常に俺を見て、俺の合図を待っている。それが俺の役目。ドラムで目立って注目を集めたいわけじゃないってことだね。
――ドラマーである前にバンドリーダーだと。とはいえ、変拍子も含めたリズムのアプローチはこのアルバムの重要なポイントだと思います。
もちろん。このアルバムの音楽の核心には「リズム」がある。もちろんハーモニーやメロディもあるし、リッチなサウンドや要素が入っているけれど、このプロジェクトの起動を担ったのはリズムだし、それがこのプロジェクトのスタート地点となっているのは間違いない。
でも、作曲に関しては、これまで学んできたピアノやベースの奏法や、譜面の書き方などを駆使して曲を書いた。それらは「ドラマー」としてではなく、優れた「作曲家/プロデューサー」になるために学んできたスキル。そのような作曲のスキルを、基盤としてもともとあったリズムの上に載せていったんだ。ドラマーの自分にとってリズムはこのアルバムの焦点になっていたと言える。だからリズミカルなドラミングが入っている。でも、それは自分が本当に追求したかったものではないんだ。アルバムでやりたいこと、伝えたいことはそういうことじゃない。
最終的に俺が伝えたいのは「良い音楽」と感じられるもの。それを他のプレイヤーたちと一緒に演奏して、彼らに楽しんでもらうこと。正直、演奏が難しい音楽であると思うけど、それでも演奏を楽しんでもらいたいと思ってる。そして自分たちが面白いと感じる音楽が、リスナーにとっても面白いものになっていたら嬉しい。俺の音楽のリズムの複雑性を楽しみながらも、そこに心地よさや喜びも感じてもらいたいんだ。
――つまり、あなたは作曲家やプロデューサーの側面にアイデンティティがあるし、ライブだとバンド・リーダーとしての側面が強いんですね。僕はこれまでに何度かインタビューしましたけど、言われてみるとあなたは自分のドラミングの話をしてこなかった。
そうだね。俺はドラマーとしての自分に焦点は当てていないだけじゃなくて、「あなたはドラマーなんですね」と言われると少し気に触るくらいなんだ。別にドラマーであることが嫌な訳ではないよ。そうじゃなくて、俺は特定の楽器の演奏者ではなく「ミュージシャン」でありたいし、そこを聴いてほしいってことだね。これは「あなたはジャズを演奏するんですね」と言われるのと似てる。確かにそうなんだけれど、俺の音楽は「ジャズ」という括りには入り切らないとも思っている。俺はもっと大きな領域で音楽をやっているから。
ーーそうだと思います。
そもそも「括り」や「領域」についての区切り方や定義は人によって違うからね。だから、このトピックについては、また新たな扉が開いて延々と議論ができてしまうんだけど、言葉には表現の限度がある気がするんだ。音楽、特にインストゥルメンタルの音楽を演奏するとき、俺たちミュージシャンは抽象的な伝達手段で伝えたいことを表現することができる。それは文字や言葉を使った「言語」では困難とされている表現。音楽について「今、どんな音が聴こえているのか」「それに対してどう感じるか」を言葉を使って表現するためにはかなり高度な知能や知識を必要とする。でも、ミュージシャンはそれをサウンドで表現することができるし、感情を伝えることができる。それは特別なことだと思うよ。音楽は、言語にはできないことが可能だってことだから。音楽も言語もある種の伝達手段ではあるんだけれど、その次元や領域が異なっていると僕は思うんだ。
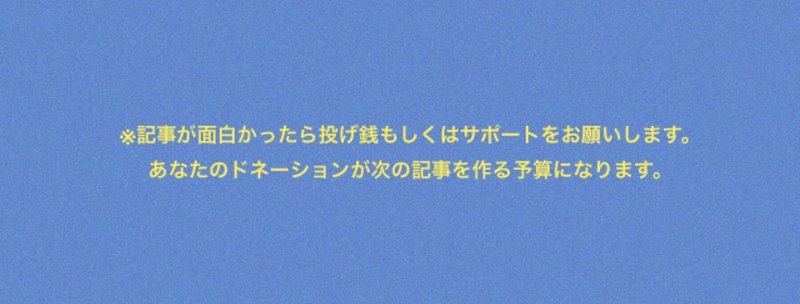
ここから先は
面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。
