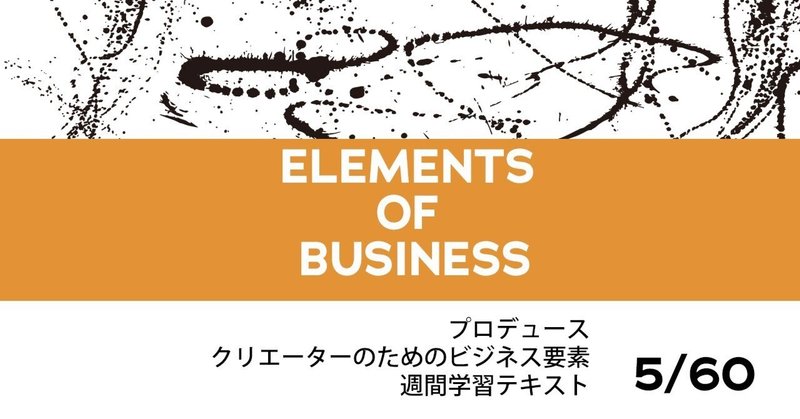
no.5 着想 - コネクト(理解する)
テーマにコネクトする
テーマが決まったら、次は? 典型的なクリエーターであるアーティストは、これについてどう言っているだろうか?
「コネクト」の意味をつかむ、アーティストのさまざまな事例を紹介する。
近代日本画を代表する画家・東山魁夷は、奈良・唐招提寺御影堂の障壁画を依頼された。御影堂と呼ばれる庵は、中国から渡来し、仏教の発展に多大な功績を残した高僧である鑑真への感謝を込めて建てられた庵だ。鑑真は船の難破で失明した後、奈良にたどりつき、唐招提寺を建立した。御影堂は彼への鎮魂の意を捧げているのだ。
魁夷はこの作品の依頼を受け、まず鑑真の生涯を徹底的に研究し、この偉人の全人格と経歴にコネクトしようとした。
著書の中で、彼はこの依頼を受けての心境とその後の取り組みについて語っている。 (⑥)
鑑真の像が今も生前そのままの姿で永遠に生き続けているような庵に、この主題の障壁画を描くことは、鑑真の意志に合致するのではないかと思った。
わたしにできるかもしれないと思いました。
奈良と大和を訪れるたびに、唐招提寺に行き、御影堂に座っていました。 5回の失敗でほとんど挫折し、12年の歳月を経てようやく実現した鑑真の来日を思いました。鑑真の不屈の精神力、律宗の根本道場として創建された唐招提寺の性格を想起し、次第に白い襖に描く作品のイメージが浮かび上がってきました。
「コネクトする」イメージは小説家が文章を作るプロセスからもつかむことができる。 池波正太郎 は著書『男のリズム』の中で次のように書いている。 (⑦)
今日の夜更けから翌日の未明にかけての仕事のことを朝目覚めた時から胸の内に「思いつめていること・・・」が私にとっては大切なことだ。ストーリーをああしようとか、こんなふうに書いてやろうとか、そうしたことではなく、絶えず思いつめている。小説は一日一日が勝負で、例えば今夜小説の中で仕掛け人・藤枝梅安が強敵をどのような手法で仕留めるかというのは、その場面まで書き進んでみないとわからぬことなのだ。始めからそれを考えていたのでは、不自然になってしまう。そのためにうまく辻褄をあわせて書き進めるようなことになりかねない。敵を仕留めるのは私ではない。藤枝梅安が仕留めるのであるから、梅安の思慮と行動に任せなくてはならない。そうした時には、自分でもいったいどうなるのか?うまく書き終えることができるのだろうか?と不安でならない。ただもう、思いつめて自分がその時の梅安になりきることができれば、自ずと的を仕留める手法も浮かび出てくるのだ。
コネクトは統合だ。テーマに「コネクトする」というイメージを感じてもらえただろうか。
ビジネスの場合、テーマが決まった後、例えば、
シャネルの場合 モードの創造
スターバックスの場合 ヨーロッパスタイルのカフェ
イケアの場合 大衆向け家具の製造・販売
といったテーマ。
これらのテーマにコネクトするためには、ターゲットとなる顧客や消費者を深く知ることが不可欠である。
テーマに沿って顧客を理解し、顧客との一体感(統合)絆を築く必要がある。これは、どんなビジネスであれ、長く成功し続けるための本質的な鍵である。たとえば、イケアを見てみよう。
カンプラード氏は世界有数の億万長者に数えられる大富豪の1人だったが、飛行機での移動にはエコノ
ミー クラスを利用し、駅ではポーターを使わず、旅行鞄は自分で運んだ。庶民やマスコミにも愛される数少ない経営者であった。
従業員は、カンプラードがコペンハーゲンからフムレベークまでの鉄道駅でスーツケースを引きずっているのを見て唖然としました。彼らはカンプラードを助けるべきでしょうか? しかし、カンプラードは一切の助けを拒否します。カンプラードは特別な人間ではありません。彼は普通の人々の生活がどのようなものか知りたいのです。 歩き回るための、自分の運転手、執事、または宮殿は必要ありません。
彼は群衆の中に溶け込みます。 (⑧)
カンプラードは、彼自身イケアのターゲット顧客の1人であり続けようとしていた。それでイケアのレストランでホットドッグを5クローネで販売するといったアイデアが生まれたのだ。
この段階でのプロデューサーの主な仕事は、「テーマとコネクトする」ことだ。子ども向けのサービスであれば、子どもの目線からテーマを考えるということ。高齢者向けのサービスであれば、高齢者の立場からテーマを考え、体験するということだ。米国オハイオ州シンシナティにある世界最大の総合日用品メーカー、プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)のイノベーション・センターには、マーケティング担当者がターゲット消費者の日常を実体験するため、実験設備と施設が完備されている。 P&G は、このような消費者の理解、調査、実験、分析に年間 4 億ドルもの巨費を投じている。年齢も立場も違う人の気持ちを知るのは難しいが、まずは「コネクトする」ことだ。
もう一つのポイントは、これは起業家として新しいビジネスを始める人にとってというより、既存のビジネスのリーダーや経営者に必要な日常生活の態度についてである。
それは単に夢見る…というのではなく、実際の現実とコネクトする、ということだ。
あなたが組織の中で上位の地位に就くと、周りの人はあなたのような上級管理職に都合のよいニュースを優先して伝えてくる。しかし、プロデューサー自身が常に事実を把握し、真実にコネクトしようとする姿勢を持ち続けることができれば、現実世界の荒波の中で企業目的を達成するための戦略を立てることができ、また、チームメンバーをまとめることができるのだ。目的を達成することにフォーカスした組織を作ることができる。
スターバックスの業績が一時的に悪化したとき、シュルツ氏は次のように感じた。
スターバックスには、ネット上の論争に効果的に参加するためのツールがないのは明らかだった。美しくデザインされたスターバックスのウェブサイトには、コーヒーの紹介とニュースや財務データが掲載されているが、基本的には一方通行で、デジタル時代には十分に対応していなかった。スターバックスは、ネット上における対話型の手法を備えていなかったのだ。
私たちの声をお客様や投資家やパートナーに直接伝え、相手からも意見を言ってもらうことができなかった。私たちが何を大切にしているかを伝えることができなかった。つまり、店舗においても外の世界においても、私たちの物語を語ることができなくなっていたのである。
二度目の挑戦の時が来たのを感じた。(⑨)
現実を無視するのではなく、自ら探そうとしてほしい。広い心で現場の声に耳を傾け、コネクトすることが大切なのだ。
改めて「コネクトする」ことについて、ビジネスでプロデュースする場合をまとめてみよう。
ここまでの説明で、「コネクトする」には2つのステップがあることを理解していただけたと思う。
最初にテーマを見つけるために、自分や会社の現状にコネクトする、次に選んだテーマにコネクトするというステップがある。
ビジネス環境の分析からテーマを決めること。
そして次のステップの「コネクト」は、この決められたテーマに沿って、ターゲットや市場、そのニーズやウォンツを理解することだ。
つまり、自社、競合他社、消費者、流通業者、等の状況の現在の傾向を分析して、次の課題をどこに置くべきかを決定する。 (ビジネスをどうするか。) そして、分析の結果として、ターゲット市場と、会社の製品とサービスを通じて、それを利用する顧客 (および/または消費者) に提供すべき便益を決定する。 P&Gでは、このステップをWhere to Playを決定するプロセスと呼んでいる。
この枠組みが確立されておらず不明確な場合、つまり、誰が、どのようなビジネスディール(取り引き)を必要とし望んでいるかを1、2分以内に簡潔に説明できない場合は、ビジネスを始めるべきではない。
なぜならそれがビジネスの土台だからだ。
ビジネスの動機は、何か良いものを生み出すことでなければならない。目に見える良いもの、明確な良いサービスを顧客に届けるというところから事業を始めなければならないということだ。
参考文献:
⑥ 「唐招提寺への道」 東山魁夷著((株)新潮社)
⑦ 「男のリズム」 池波正太郎著((株)KADOKAWA)
⑧ 「イケアの挑戦 イングヴァル・カンプラード 創業者は語る」バッティル・トーレクル著(ノルディック
出版)
⑨ 「スターバックス再生物語」 ハワード・シュルツ、ジョアンヌ・ゴードン著(徳間書店)
