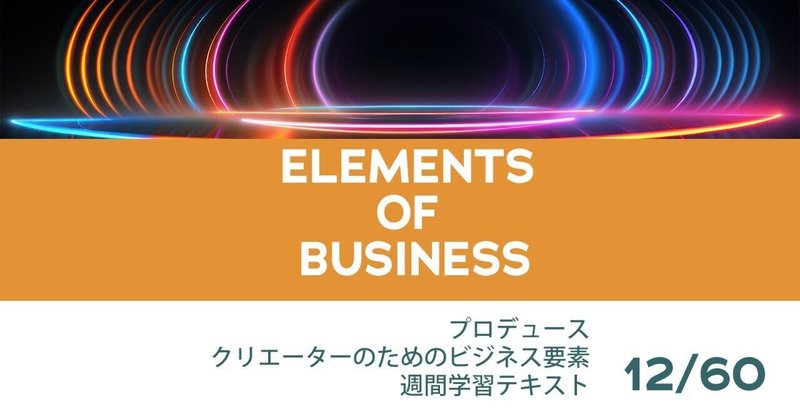
no.12 着想 ― コントリビュート(貢献)
演繹法、帰納法、デザイン法
適切なモノやサービスを生み出す方法には、「演繹法」、「帰納法」、「デザイン法」といったオーソドックスな考え方もある。それらについて簡単に説明したいと思う。
演繹法とは、前提から論理的に結論を導き出す方法である。この演繹法は数学や自然科学で活用され、ビジネスにおいては、この考え方を、既存の商品やサービスの現在の強みをさらに強化したり、弱点や不足を克服したりするために使える。
ビジネスでは、既存の顧客がその商品やサービスの強みゆえにブランドを支えている。よって、もしそれをさらに強化する方法がある場合は、それを検討すべきだ。また弱点は顧客にとっては望ましくないものであり、この不足を何らかの方法で修正し、 新しいやり方を提案できれば、顧客は、このビジネスが改善の努力を惜しまないことを知って、そのブランドをより支援するだろう。
この演繹法では、既存の顧客の声に耳を傾け、なぜ彼らがそのビジネスのファンなのか、あるいはどこに不満・不便を感じているのかを突き止める必要がある。顧客の意見に誠実に耳を傾けることが演繹法の鍵なのだ。
帰納法では、演繹法とは対照的に、事実とデータが出発点となる。既存の論理からは少し離れて、実際の具体的ケースに目を向け、これらのケースを研究することで、その下にある一般的な原理を導き出す。
データに基づく思考が導入部である。まず、データの収集から始めなければならない。
では、どのようなデータを収集する必要があるのか?
我々はプロデュースしてテーマを達成したいのだから、そのテーマに関連する類似分野の(過去に達成、成功したプロデュースの)データを収集する。国内だけでなく、海外や異業種の事例も調査。具体的な事例を見つけて、その「成功の秘訣」をみつけよう。
それらから自分のテーマに何を適用できるかを考えよう。この過去の成功事例や異業種の成功事例を応用する手法は「サーチ&リアプライ」と呼ばれ、大手企業のマーケティング部門でも常に試みられている。
次に、演繹と帰納を組み合わせた方法について説明する。これはデザイン法と言えるだろう。
このデザイン法は、ターゲットのニーズやウォンツを理解することから始める。対象者の現在のライフスタイル、さまざまなシーンでの行動、購入シーン、利用シーンなどをチェック。
ニーズとウォンツを特定することから始める。ターゲット顧客と徹底的にコネクトするために、理想的な顧客になる可能性が最も高い人々のグループを特定する。ターゲット層の中でも、特にその欲求、要求が顕著で、それを満たすことができれば、大きな需要が短期間で見込まれそうなグループだ。これらのグループを最上の見込み客(プライムプロスペクト)と呼び、その中で選ばれた、ひとりの人物の具体的な個性や感性を調査・分析する。この個人: 最上の見込み客のグループから選ばれたペルソナは、プロデューサーがコネクトすべき人物である。このペルソナが現在利用している、テーマに関連した商品やサービスから、彼/彼女が評価していると認められないものをそぎ落とす。また、求めている価値が明確で、現在それが提供されていない場合は、既存の商品やサービスと組み合わせ提供することができないかを検討する。
その後、探し出された知見からプロトタイプの作成を開始する。このプロトタイプがどのように理想を具現化できるかは、プロデューサーがペルソナとどれだけ深く包括的にコネクトするかにかかっている。
デザイン法では、ターゲット顧客グループにこのプロトタイプに対する意見や反応を尋ねないといけない。次に.これらの意見や反応を慎重に検討し、最終的プロデュースにつなげる。
その他の貢献段階のツールとしては「KJメソッド」や「マインドマップ」がある。地理学者・川喜多二郎氏が提唱する「KJ法」 。これも演繹法と帰納法の組み合わせの一種である。
また「マインドマップ」は、教育コンサルタントのトニー・ブザン氏によって提唱されている。これも潜在意識を利用した演繹法である。
これらも様々な場面で有効に活用できる。
テーマを解決または実現するためには、時間をかけて固有の状況に適した方法を見つける必要がある。そして、あなたが取るアプローチが、貢献のための発想の内容を決めるのだ。
