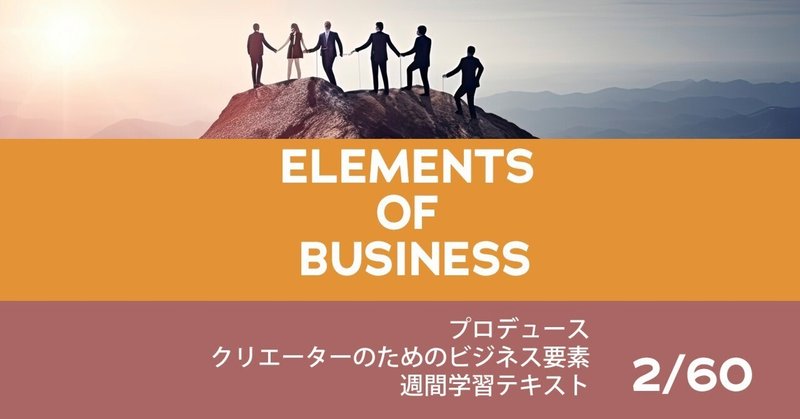
no.2 序章
約50年前、ハーバード大学のケネス・アンドリュース教授が記した重要なビジネス書(正確な名前は失念した)を読んだ。
その中で私は経営者の3つの役割について学んだが、それらは、
1. 組織の目的を構築するアーキテクト
2. 組織のリーダー
3. 組織戦略の実行者
これら3つの役割だった。それぞれの役割は、ビジネスだけでなく、政府や軍隊など特定の目的を達成するために作られた機能体組織にとって不可欠であるという。
言い換えると、これらの役割は、第一がプロデュースすること。 第二は、リードすること。そして第三は管理することである。
かつて社会の変化のスピードが遅く、競争環境が比較的地域的、国内的であり、消費者や顧客の欲求もあまり多様化していなかった時代には、これら3つの役割は1人の優秀な人によって担当された。
しかし、ITが世界をグローバル化し、情報・金と人が圧倒的なスピードで絡み合う現代の複雑な時代において、1人で3つの役割を同時にこなすことは非常に困難になってきている。
こういった背景から、多くのエグゼクティブを目指す人達は、MBAの資格をとり、管理スキルを磨くことに集中している。マネジメントを通じて利益を確保し、企業価値の最大化を常に目指すことは非常に重要だが、この流れの中でプロデューサーシップやリーダーシップなどの要素は、あまり深く考慮されたり議論されたりしない傾向にある。
また、一般的に保守的な日本人は、現在の既存のルートで利益を上げることに安心感を持っている。多くのビジネスパーソンには、革新的な物やコトをゼロから生み出したり、チームメンバーに新しい挑戦的なタスクを引き受けるように促したりする<プロデュース>や<リード>という役割は、危険で困難に思えるのだ。
その結果、事業の新たな価値を生み出す手段<プロデューサーシップ>がおろそかになってしまった。
そして、イノベーションに挑むべき組織や人材も、その多くが足踏み状態だ。
また、組織で働く人々は、上司をリーダーとして認識しなくなってきている。リーダーシップとは、結局のところ、人々が期待する未来を描き、それを組織のメンバーに共有させることである。例えば、日本にとって20世紀は生活水準で欧米諸国に追いつくことが基本目的の時代であった。しかし、そのような推進力は時代遅れになっている。
人々をやる気にさせるための金銭的な報酬も、明確な貧富の格差、その拡大により、今日一部の白けた人々にとっては、小さな影響力しかない。
リーダーはまず、従業員を個人として受け入れ、個人として尊重する必要がある。
心を開いたリーダーが必要だ。そして、リーダーは組織の目的を率直にチームメンバーに伝える必要があるのだ。
また、消費者や顧客は各々の生活を個人的にとらえている。消費は、必要性(ニーズ)がベースではなく、欲望(ウォンツ)がベース。そして、彼らの欲求はそれぞれの心の中で完全に明確ではないにしても、常に興味深いオファーというものを探している。
消費者は、個人の生活や価値観を満たすために、楽しいこと、面白いこと、良いサービスを求めているのだ。
このような時代では、企業はまずその目的を明確に定義し、消費者や顧客が、企業が提供するものを認識できるようにする必要がある。
つまり、当該企業が提供できる価値を定義しながら、組織の目的を再構築するということが重要なのだ。
プロデューサーシップが不可欠だ。企業の目的を定義してはじめて、それを達成するための実際の製品またはサービスを開発できる。そしてこのためにはクリエーターが適材だ。プロデュースに必要な能力や意欲はクリエーターに潜在的に備わっているからだ。
時系列で言えば、まずゼロから目的を作るプロデューサーシップがあり、次にその実現に向けて人々を団結させるリーダーシップがあるはずだ。最後に、プロセス途中で発生するさまざまな問題を解決し、プロセスそのものを合理化し、監督するためにマネジメント(管理)が必要になる。経営者は、これまで述べてきたこの3つの役割を担う必要があるが、これらを1人で完璧にこなすことは難しいため、まずそれぞれの本質を理解し、必要に応じてその機能の一部を誰かに任せる必要がある。
たとえば、プロデュースが得意なクリエーターは、自分に代わって組織を率いたり管理したりできる人々の助けを必要としている。逆に、強いリーダーシップとスキルを持っている人なら、そのスキルを活かして、他の人の助けを借りてプロデュースと管理を実現するのが現実的だと思われる。また、優れたマネージャーは、社内起業家と、その起業をサポートするために適切な指導力を持つリーダーを見つける必要がある。
この3つの役割、すなわちプロデュース、リード、マネージ、を理解するために、これら3つの基本的な考え方をこのテキストで明確にしていこう。
プロデュースにおいては、まずプロデューサー自身が目的を確固たるものにすること、再確認することが重要であり、そのためには知性と感性の両方が求められる。
単なる思いつきだけでプロデュースを始めることは可能かもしれないが、プロデュースをさまざまな角度から探求する必要なステップ無しでは、失敗する可能性が高くなる。成功の確率を限りなく高めるために、このテキストにあるプロデュースの3つのステージ、8つのステップを学んでほしい。
ここでプロデュースという言葉をしっかり定義づけ、共通の認識を確立しておこう。
プロデュースという言葉は、日本語と英語の本来の意味が少し違う言葉である。三省堂の国語辞典によれば、プロデュースは
映画、演劇、音楽、テレビ番組などのイベントや作品の企画・実施
など、エンタテインメント分野の用語と見なされている。ただし、英語での本来の意味は、
新しいものを創造する。
革新的なアイデアを実現する。
というように、この言葉はビジネスやテクノロジーの分野、またはより広く政治や科学などの分野でも使用されている。これがプロデュースの正しい用法である。
このテキストでは、本来の英語の意味でプロデュースを捉えてゆくことにする。
プロデューサーがいない世界はどうなるか? 保守的で変わりたくない人だけ。彼らは自分たちの生活がこのまま続くことを望んでおり、未知への挑戦はしない。
ルーティンで働き、似たような人とコミュニケーションをとり、人生を楽しむことに貪欲で、財産や地位にこだわる。彼らは他人の挑戦の足を引っ張るわけではないが、新しいものを創造したり、ユニークなものを実現したりすることには関心がなく、ましてや人々が試みたことのないことを達成する、といったことには興味がない。
そんな人ばかりの社会はどうなる?
人材以外の資源が乏しく、長期的には人材も減少していく日本は、ますます世界から取り残されることになるだろう。プロデューサーシップを持った元気な人がいなければ、日本の未来は明るいとは言えない。
15年以上前の2007年2月13日、東京新聞夕刊に日本の小説家・高村薫の次のような記事が掲載された。
“振り返れば、受験のための詰め込み教育では個性が育たないという理由でゆとり教育の発想が生まれたのは、約30年前だった。当時も長大な装置産業から情報通信産業への大きな構造転換のときで、大人たちは欧米との競争に勝つためには、想像力や発想力が必要だと考えた結果、全体の底上げよりも個性重視へと方針を転換したのだった。”
想像力と創造力がプロデュース能力の基礎とされ、日本の教育界もこの必要性を認識していた。社会は新しい価値を創造できる者を必要としていたのだ。
しかし、この必要な想像力と創造力(革新能力)は、ゆとり教育の結果として開発されただろうか。私はそうは思わない。想像力と創造力が必要なら、もともとこれらに富んだクリエーターにもっと活躍の場を与える一方、プロデュースの方法論をクリエーターが短時間に学べる機会を与えるべきなのだ。
近年、メディアには大量の情報が発信され、その領域は無限に広がっており、個人はそのような情報世界に自らの想像力や創造力の断片を種蒔いている。しかし、彼らの多くは、この種を育てて花を咲かせ、実を結ばせる忍耐力を持っていない。若者の多くは、プロデュースに必要なステージとステップを慎重に踏んでいくための規律を身に着ける機会を持っていないのだ。また、その創造につながる基本的な人間力は、個人にゆとりと自由を与えるだけでは生まれない。このスキルが自然に身につく、ということもないのだ。
では何が欠けているのか? 必要なプロデュース技術の体系的な開発に真剣に取り組まなかったのは、社会の怠慢だったのかもしれない。そのような能力を開発し促進するための方法の習得と、環境づくりはなされなかった。
新たな価値を見出し、十分な成果を生み出すためには、それを実行する能力と手法、そして挑戦する意欲が必要だ。
必要な能力や方法の明確な説明がなければ、自分の何かを世に出したい、または新しいことに挑戦したいと思う者だけがプロデュースに挑戦し、多くの場合、最初の障害でそれらの試みをあきらめてしまうだろう。このテキストでは、ビジネスをプロデュースするための考え方を紐解いていく。
アメリカのスタンフォード大学付属のデザイン研究機関であるIdeoがまとめたレポートによると、プロデュースは3つのステージで達成されるという。 ( ① )
それらは着想 (通常は1 人による)、発案(複数の人に向けて)、実現(組織を活用)の3つである。
序文で説明したように、この 3つのステージ、特に実現プロセスでは管理能力が必要であり、発案ステージではリーダーシップ能力が必要だが、着想ステージはほとんどの場合、プロデューサーひとりが行うプロセスである。そして、この着想プロセスは、今まで明確には探求されていない。これに必要なスキルは非常に個人的で神聖なものだからだ。
学習の最初の数週間は、この「着想」を扱い、あえてこの神聖なプロセスを調べてみる。
後ほど、発案、実現についても順を追って説明するが、ここでこのテキスト全体で使用される図を 1つ紹介しよう。

トータルプロデュースシップに必要な手法や考え方を視覚的に表現した図である。この図では、着想ステージを3つに分けている。発案ステージには 2つのステップがあり、実現ステージは着想と逆の形をしており、この実現も3つに分けられる。
ここで注意しなければならないのは、着想・発案・実現の中の各ステップは階段のように明確に分かれているわけではなく、重なり合う部分があるということである。例えば、一年のうちの春、夏、秋、冬の四季のように。便宜上、暦には彼岸、夏至、冬至など季節の節目があるが、実際の気候では肌寒い日と暖かい日が重なり、冬から春へと徐々に移行していく。
これは、着想、発案、実現の 3つのステージにも当てはまる。発案のステージにおいても、着想の検証や実現の方法の検討など、いくつかの重複があるかもしれない。あるいは、プロデューサーは、自分自身で実現の最初のステップに取り組みながら、発案ステージを精査しているかもしれない。
また、着想と実現の図の、らせん(円)の大きさは、それぞれのステップに費やされる時間とエネルギーの量を表している。 2つの三角形が重なるマークについては、発案のプロセスで詳しく話すことにしよう。
また、このテキストでは、政治、科学、ビジネス、テクノロジーなど、さまざまな分野に適用できるプロデュースのプロセスについて説明するが、便宜上、特にビジネスに焦点を当てることにする。
また、プロデュースの大きな流れは、一人のプロデューサーがすべての段階を担当する場合もあれば、プロデュースチームが担当する場合もあり、現在ではウェブ上でネットワークを形成して、連携したさまざまな個人がプロデュースする場合もあり、様々である。
それぞれの場合で方法や注意点に多少の違いはあるが、一人で行う場合も複数人で行う場合も、基本的な考え方は同じである。
したがって、このテキストでは、1 人の個人が 3つの役割をすべて果たすという単純な前提で進める。
参考文献:
① 「デザイン思考が世界を変える イノベーションを導く新しい考え方」 ティム・ブラウン著((株)早川書房)
