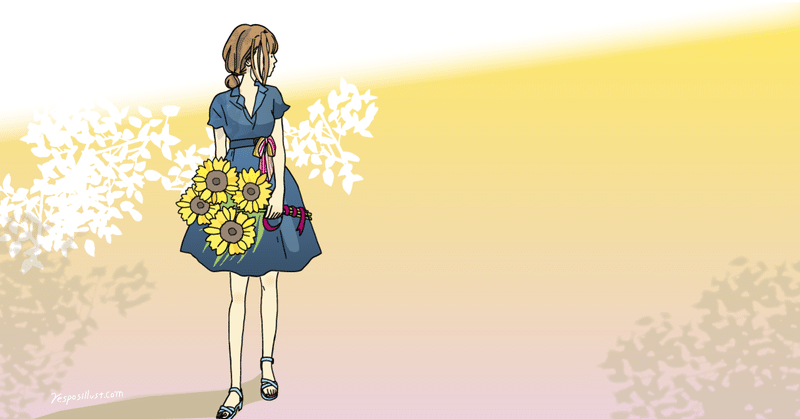
Re: 夏と不思議な彼女の事情。
ある夏の出来事。今もバッタを見つけると、そっと微笑む私がいる。
・・・・・・
ちょっとした用事を済ませて、銀行の駐車場に停めてあった私の車に乗り込もうとしたときだった。
向こうから、30代のOL風のきれいな女性が、長い髪を揺らしながら、なんと、小走りで私のほうへと向かって来ていた。
こういう思いがけないシーンに出会うと、一瞬、人は本当に、何も考えられなくなるものらしい。私は呆然とその場に立ち尽くしてしまい、身動きが取れなくなってしまった。
それでも走馬灯のように何事かを思い出してみた。でも、まったく思い当たらないのだ。その女性が誰かも知らないし、銀行の人でもなさそうだし、私のほかには誰もいないし、走ってくる彼女はまさしく、この私に向って来ているのだった。
やがて彼女は、私の目の前でピタリと止まった。まだ日差しの強い、真夏の午後2時の太陽は、彼女の額に、いくつかの汗を作っていた。少しだけ呼吸を整えながらも、やがて彼女は私にこう言った。
「あのう…すみませんが、カマキリは、大丈夫ですか?」
まったく意味がわからない。
いや、それは当然だろう。
”カマキリ”という単語からして、あまりにも唐突過ぎる。これが「あのう…熱中症は、大丈夫ですか?」ならまだ、幾分、許される質問だろう。でも、彼女の質問は「カマキリは大丈夫ですか?」というものだった。
何が大丈夫なのだろうか?カマキリについての知識?またはカマキリの料理を食べること?それとも私が知らないうちにカマキリに何かをしてしまった?いやいや、どれにしても、まったくわけがわからなかった。
それでも、きれいな女性の理解できない意味不明な言葉は、何かドラマのはじまりにも似て、不思議にとても心地よい感覚を覚えた。
いやいや、何を考えているのだ。
今はそれどころじゃない。とりあえず今の私としては彼女の質問に答えなければならないのだ。なにせ彼女は息を切らしながらも私に、その質問をするために、走ってきたのだから。
「えぇ、たぶん、大丈夫だと思います」
こんなとき、男は随分といい加減なものになる。”たぶん”という言葉で曖昧さを残しつつも、私はそれでも大丈夫と答えてしまった。
答えてしまった後でやはり、後悔をした。
「いや、ちょっと…」とごまかせばよかったんだ。
大丈夫と言ってしまった以上、私はきっと彼女に対して何らかの行動を起こさなければならないのだろう。その「カマキリは大丈夫ですか?」の問いに対して何らかの成果を。
そんな私の迷いを吹き飛ばすように、彼女はありったけの笑顔を浮かべながら、私にこう言ったのだ。
「よかったー!どうしたらいいのか、迷っていたんです。駐車場に誰もいないし、だからといって、このままじゃどうしようもないし…そうしたら、あなたの姿が見えたんです。早く私の車に一緒に来て下さい!」
そう彼女は私に言うと、私を彼女の停めてある車の前まで連れて行った。どこかに連れて行かれるのだろうか?私はこれからまだ仕事があるし、次に立ち寄らなければならない用事もあるし。
これは一体なんなんだ?
(1)新手の何かの勧誘?それとも、(2)何らかの事件に巻き込まれる?それとも(3)新たな恋の予感… どうせなら、(3番)であって欲しいのだけど、今はそんな冗談を言ってる場合じゃない。
赤い小さなかわいいワンボックスカーを前に、彼女はその車のドアを開けるとこう、私に言った。
「ほら、こっちに来て!」
やれやれ、どう言うつもりか知らないけれど、やはり、そうなってしまうのか?私は彼女の車に乗ることになるのか…そう思いつつ、身構えしながらも彼女の運転席を見ると…
そこにはカマキリがいた。
いや、よく見ると、正確にはそれは大きなバッタだった。彼女の車のハンドルに、そのバッタはいたのだった。それですべての謎が解けてしまった。
私は何かふっきれた気持ちになると、そのまま何も言わないで、静かにそのバッタをつまむと、外へと逃がしてやった。
「あ、ありがとうございます!本当に助かりましたっ!私、どうしても昆虫が苦手で…でも、このままじゃ、運転も出来ないし、ずっと迷っていたんです!」
そうして彼女は、かわいい笑顔と軽快なカーステレオの音楽と共に、ぶるんと小さく車体を震わすと駐車場を後にした。私の手のひらに乗せたバッタも、ひらりとどこか夏の空へと飛んで行った。
知らないうちに、私一人だけ
駐車場にぽつんと残った。
「あのう、カマキリは、大丈夫ですか?」
何の始まりもなく、
終わってしまった夏の出来事。
入道雲が、ひとり残った私のことを
なんだか笑っているみたいだ。
とても、くすぐったいようなおかしな気分。
そんな不思議な、夏の想い出。
最後まで読んで下さってありがとうございます。大切なあなたの時間を使って共有できたこのひとときを、心から感謝いたします。 青木詠一
