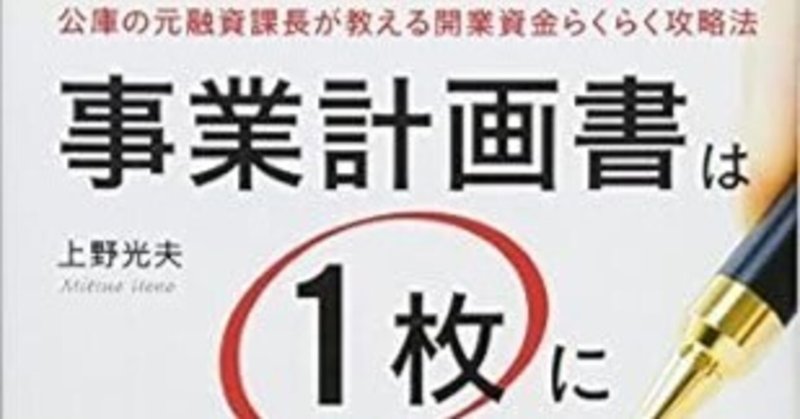
#03 行政書士開業前に読むべき本「創業編」
「事業計画書は1枚にまとめなさい」上野光夫著(ダイヤモンド社)を読みました。
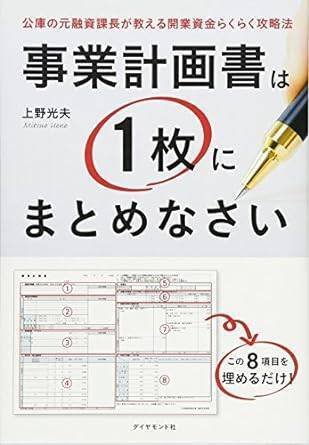
内容としては、創業融資を受けるための事業計画書の作成方法が書かれています。
第1章 発想やアイデアは不要!
起業の事業計画書は最低限でいい
第2章 起業前に知っておきたいお金の知識
第3章 融資はどこに申し込みすればいいか
第4章 融資を受ける際のハードル
「審査」について知っておこう
第5章 審査でチェックされる
ポイントを教えます
第6章 創業融資の事業計画書は
用紙1枚でいい
第7章 「創業計画書」左側の記入方法
第8章 「創業計画書」右側の記入方法
第9章 融資面談は大切なプレゼンの場
第10章 創業融資ノウハウ集
7つのポイント
第1章では、創業融資を受けるための事業計画書について書かれています。
ここでは、起業のための資金調達には、
「エクイティファイナンス」
「デッドファイナンス」
「創業補助金」
これら3つがあるとしています。
中でも、
「エクイティファイナンス」
「創業補助金」の2つは、
事業計画書のボリュームが
多くなるのに対し、
「デッドファイナンス」では、
一目瞭然で理解できるシンプルな
事業計画書の方が断然いい、としています。
そして、ポイントを押さえれば
融資担当者をうならせる事業計画書を
書くことが出来る、として
7つのポイントが挙げられています。
どんな事業をやろうとしているのか
この事業に関連する経験はあるか
セールスポイントはあるか
取引先は固めているか
他の借り入れはどれくらいあるか
投資計画と資金調達の内訳は妥当か
収支見込みは大丈夫か
この後に書き方についても
掲載されていますので、
本書を参考にして頂ければと思います。
8割以上が存続
第2章では、起業形態別の資金調達先などの
お金の話が出てきます。
起業後の存続率についての正確なデータは
ないという前提はついているのですが、
著者の主観として、
起業後3年以内に3~4割は廃業していると
述べられています。
これだけ聞くと、とても怖い数字では
あるのですが、そのあとの文章には
救いのデータも掲載されています。
日本政策金融公庫から
創業融資を受けた起業家は、
5年経過しても8割以上の企業が
残っていると書かれています。
是非とも、
公庫からの融資を受けたくなります。
無担保・無保証人
第3章では、各融資先の説明が載っています。
「日本政策金融公庫」
〈メリット〉
1.無担保・無保証人で利用できる
2.利率が比較的低く固定である
3.返済は長期分割で可能
4.申し込みをしてから
融資金が出るまでの期間が比較的短い
5.民間金融機関からの融資を受けやすくなる「呼び水効果」がある
「制度融資」
〈メリット〉
1.日本政策金融公庫よりも
利率が低い制度が多い
2.自治体によっては優遇措置がある
3.信用保証協会の信用が得られる
〈デメリット〉
1.自己資金の条件が厳しい
2.審査の関門が多い
3.申し込みをしてから
融資実行までに時間がかかる
審査
第4章では日本政策金融公庫の審査について
書かれています。
審査をパスする確率について、
著者の主観の数字が書かれているのですが、
50~60%くらいだそうです。
また、創業融資の審査には明確な基準は
ないので、審査に携わる人たちの経験や
勘に基づいた「総合的な判断」によって
決まっていると書かれています。
この「総合的な判断」の中身に切り込んだ
コツが、本書には書かれているので、
是非参考にして頂きたいと思います。
自己資金の重要性
第5章では、創業融資の審査の
チェックポイントが書かれています。
「経営者としての資質」
「財政状態」
「収支見通し」
の3つです。
この3つについてページを割き、
解説されているのですが、中でも、
起業前にできるだけ多くの自己資金を貯めるべき
という考え方は、審査において
重要なポイントであると書かれています。
数年前に制度が改正され、
自己資金は「10分の1以上」と
なってはいますが、それでも自己資金の
「3分の1以上」あった方が良い
という考え方です。
事業計画書は1枚
第6章では事業計画書が1枚でいい理由が
書かれています。
現役の融資担当者3名のコメントが
掲載されていますが、
なるほど、というものばかりでした。
また3つのチェックポイントを意識して
創業計画書をつくることも書かれていますので参考にしたいところです。
創業計画書の左側
第7章では、
「創業の動機」
「経営者の略歴」
「過去の事業経験」
「取得資格」
「取扱商品・サービス」
「セールスポイント」
「取引先・取引関係等」
「販売先」「仕入先」「外注先」
等について書かれています。
飲食店、製造業、学習塾など、
具体例を挙げて書かれているので
とても分かりやすいです。
創業計画書の右側
第8章では、
「従業員」
「お借入れの状況」
「必要な資金の調達方法」
「設備資金」「運転資金」
「調達の方法」
「事業の見通し」
「創業当初」「軌道に乗った後」
「売上高の予測方法」
「売上原価の予測方法」
「経費と利益の予測方法」
等について書かれています。
創業計画書を書く真の目的も書かれていて、
しっかりしたものを作りたい、
という意欲が湧いてきます。
大切なプレゼンの場
第9章では、融資面談の際に求められる
資料について書かれています。
担当者との面談をうまく乗り切るための
ポイントや面談当日の服装、質問の受け答えの方法についても細かく書かれています。
「非現実的な夢を見ている人」に
ならないようにするポイントについても
書かれているので
注意していきたいところです。
ノウハウ集
第10章では、融資を受けやすくする
裏技やコツが紹介されています。
店舗や事務所を借りるときの留意点
資格・許認可・届け出を必要とする
業種の留意点個人情報にネガティブな情報がある
場合
どれも細かいなと思う所ですが、
担当者にとっては重要なポイントなので
見ておきたいポイントです。
まとめ
開業に向けて、起業に関する本を見つけては
読んでいますが、融資に絞った事業計画書の
ノウハウ本は意外と少ないのが現状です。
行政書士の開業をする場合、
自治体ごとに登録費用がまちまちなのですが、登録費用30万円、年会費7万円あたりは
どうしても必要になります。
プラスして、
事務所の机、イス(ソファ)
スキャナ付きのプリンター
事務所の実印
ゴム印などの事務用品
スーツ(新調するかどうか)、ネクタイ
靴(意外と重要)
表札(必置)
ホームページ作成費用
など節約していいところ、
お金をかけるべきところの判断が
難しい所を加味しても、
さらに数万円~十数万円(何十万円?)は
必要になります。
自己資金だけで事業を始め、
黒字経営なのに資金がショートしてから
借り入れを行おうとしてもすぐに
融資が下りるわけではないそうです。
なおかつ、起業前、あるいは起業して
すぐの状態が最も融資が通りやすい
状況である、とも書かれています。
「日本政策金融公庫から
創業融資を受けた起業家は、
5年経過しても8割以上の企業が残っている」という現実もあるので、
公庫からの融資を考えてみようと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
