
良い学びを実現するために必要な体制・環境とは?
良い学びを実現するにはどのような体制・環境が必要でしょうか?
私自身、常にこの問いを考えながら事業展開をしています。
この問いにおける、良い学びの定義は、それぞれの学校やクラスにおいて"良い学びであると自分達が認識する"、としています。学年や特性、嗜好性によって異なると思います。それぞれのシチュエーションにおいて理想的な学びになっていることが良い学びを享受できる状況にあると言えるのではないでしょうか。
また、上にある問いでは"どのような体制・環境"が必要かとしています。
良く議論として上がるのは、良い学びを実現するための授業や教材はどういうものか?のような形で学びに直接つながる部分を考える、勉強会やイベントは多く存在しています。
一方で、体制・環境と表現しているのは、授業や教材のみならず、様々な仕組みや環境も包含された意味合いになっています。
なぜそうしているかというのかというと、今、目の前の授業でそのような教育を展開していることは、その裏にある様々な要素が複合的に重なり合って、そうなっているからです。
例えば、
先生の授業が一斉授業で、学校としては個別最適な形で変化させていきたいが、うまくできていない。
といったケースに関しては、よくあるのは、先生の意識変革を促すような教員向け研修をするべきだ、などの意見が必要だったりします。
確かにその側面は間違いなくあるのですが、直接的でなくても間接的に関係している何かが影響を及ぼしていたりするのです。
例えば、先生の労働時間。日々迫り来るタスクに忙殺され新しいことに対する時間的余裕がないからかもしれない。
例えば、先生間のコミュニケーション。学校という組織として、統一認識がなく、属人的な活動をよしとしてしまっているかもしれない。
例えば、保護者の理解。保護者自身が10年後、20年後、また今必要な学びの形式について理解がないため、保護者が学びの変化に気づかないが故にむしろ変化しない方が穏便に済ませられるからかもしれない。


こんな感じで、今目の前で起こっている教育課題のあれこれは、さまざまなファクターが複雑に絡み合って、あるべくしてそのような現状になっているわけです。
そして、教育事業に従事する我々のような存在は、一側面のアプローチだけでは、教育を抜本的には変えることができないのです。
今回は教育に関わるセクターを整理したいと思います。
そして、今後は一つずつの要素を教育課題として顕在化していくような投稿を増やしていきます。
良い学び=そこまでのプロセスが良好であること
良い学びが実現するのは、その前の過程が適切である必要があります。
良い品質の車を製造することを想像すれば容易かもしれません。
良い車を作りたければ、製造ラインの適切な品質管理や製造プロセスがなければなりません。

これを教育に当てはめると、良い教育を実現するには適切なプロセスで学びの環境構築が必要なわけです。
では、良い学びを実現するうえでどのような観点について考えなければならないのか。
登場人物としては以下が考えられます。
教員
児童生徒
保護者
教育委員会、行政
そして、それぞれのセクターにおいて、細分化された課題があります。
例えば、教員であれば以下のような要素があります。
労働時間
待遇・評価制度
研修等のトレーニング
教材やICTの取り扱い
あくまでこれは要素でしかないのですが、もう少しイメージをつけるために、〇〇を実現したい。というWillベースで考えると想像しやすいかもしれ亜ません。
これからICTを活用して主体的・対話的・深い学びを実現したい、というミッションがあったとします。それに対して、それぞれの要素からの障壁を見てみます。
労働時間:
1. 日々の業務に追われているので、新しい学びのデザインやICTについての理解を深める時間がない
待遇・評価制度:
1. 学びのあり方が変化しても、昇進するわけでもないし、給与が上がるわけではない。むしろ学びのあり方を変化させるとサービス残業が増える可能性を孕んでいる
研修等のトレーニング:
1. コストの関係で外部講師を招いたりすることができない
2. 労働時間同様に、十分なトレーニング確保のための時間が取れない
教材やICTの取り扱い:
1. 新しい教材を選ぶ以前に背景を理解できていない (時間がない等で)
2. 十分なトレーニングを受けていないのでICTを使うのが怖いと思ってしまう
3. これまでの教材の扱いに慣れているので、新しい教材の扱いに不安が残る
ざっと洗い出しましたがこんな感じでしょうか。
何か一つを変えよう、新しいものを導入しよう、とすると教員だけでもこれらのハードルがあるわけです。
そのほかにも、保護者、教育委員会・行政にもそれぞれの障壁があります。学校現場において、これらの障壁要素が複数絡み合って、"変化することができない"という状況に陥っています。
この現状を打破するためには、それぞれのセクターにある"ツボ"を押さえて、良い学びがアウトカムとして出力されるような環境整備が必要になるということです。

国際エデュテイメント協会は今の現状を受けて、何をしているのか
弊社は、現在主に3つのセクターへのアプローチをしています。
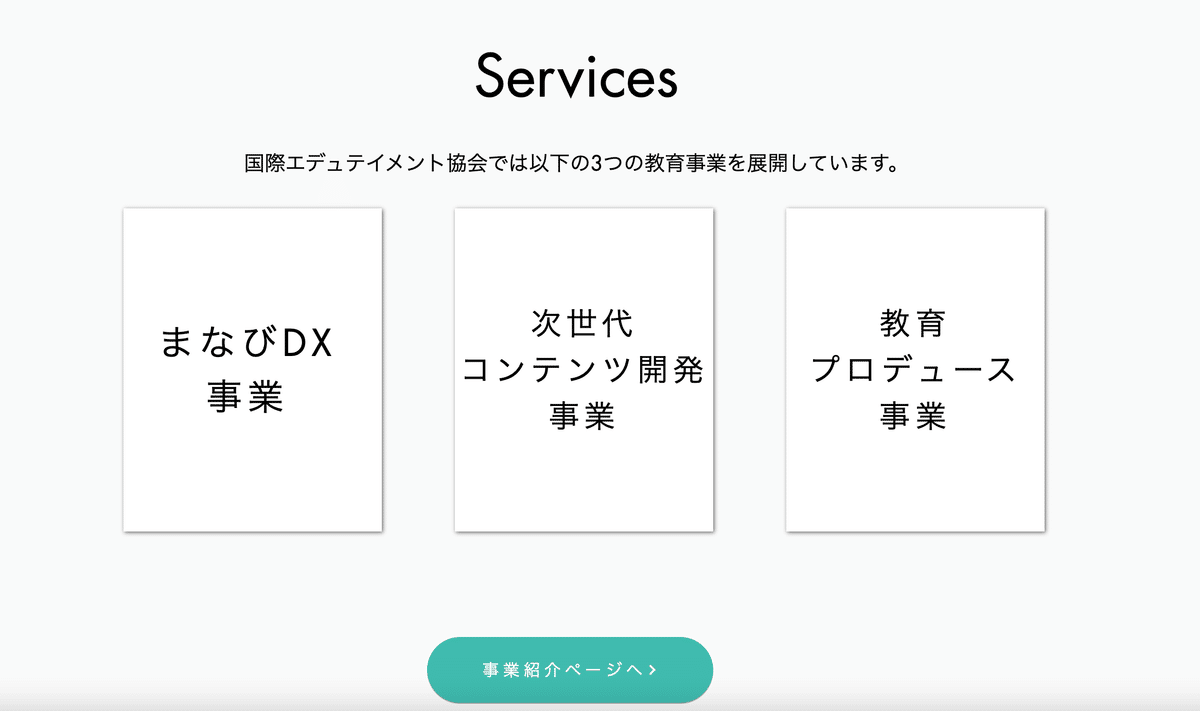
教員へのアプローチ
生徒へのアプローチ
組織へのアプローチ
1.の教員へのアプローチに関しては、現在ICT研修を中心の軸に据え、いかにこれから必要な学びをデザインできるような教育実践の手助けができるか、ということを日々考えながら全国の教育委員会及び学校に向けて研修を行っています。
2つ目の生徒へのアプローチについては、これまで何度もブログにて紹介しているSDGs英語教材の提供です。これからを生きる上で必要な能力である"クリティカル・シンキング"スキルを特定の社会課題について真剣に取り組みながら養う教材です。
3つ目の組織へのアプローチとしては、学校法人向けに広報・PRの領域でお手伝いをしています。主にプレスリリースのリリースネタ企画戦略や実際のプレスリリースの書き方、またWEB、新聞、テレビなどのメディアとのメディアリレーション構築支援をしています。一見、良い学びについて繋がっているイメージがないと思われがちですが、実は一番大事なポイントであると個人的には考えています。
世界的なECサイトで有名なアマゾンは、何か新規事業を行うときに、まずプレスリリースを考えると言います。なぜなら、端的にどのような背景で、どのような課題に対して、新規事業をやるのか、その新規事業は共感を得られるのか、という観点がプレスリリースには凝縮されています。
学校もそれぞれの組織において、これから目指すべき教育方針を明確にした上で、一貫性のある学びのデザインをする必要があります。
ICTやEdTechサービスの台頭により、学校や教員はたくさんの選択肢の中から学びをデザインできるようになりました。
しかしながら、学校、組織として、最終的な目指すべき方向性の認識が組織内に共有されていないと、どんなにその教科で魅力的な授業を展開していても、機会損失をしている部分もたくさん含んでいるのです。
ある先生はPBL授業を推奨している反面、ある先生は知識習得の部分を重要視しているなんてことが起これば、生徒はどちらの領域にフォーカスすれば良いのか分からず、戸惑ってしまいます。
今後は、学校という一つの共同体が自らどのような教育を目指したいのかを明確にした上で、教育活動を行う必要があると考えています。その過程においてプレスリリースや学校のコアの領域に対して対話ができるのは3つ目の事業になります。
ぜひ弊社の取り組みに興味がある方がいらっしゃればお気軽にご連絡ください。対話をしましょう。
我々は明日から何をすれば良いのか
さて、ここまで良い学びを実現するには、様々なセクターにおける課題を一つ一つクリアにしていかなければならない、という内容を記載してきました。

非常に難解な課題ですよね。到底一人ではできないなと思ってしまったかもしれません。
では、私たちは明日から何をすれば良いのか。
以下のようなステップが重要です。
1. その現象にフォーカスするのではなく、その背景にある様々なセクターが絡み合っていることを知る
2. セクターごとの課題を洗い出す
3. 顕在化した課題に取り組んでいる業者と連携する
これをするだけで多くのことが変わっていくのではないかと考えています。
最終的にはこれまでのブログでも繰り返し書いてきましたが、その領域のスペシャリストと手を組んで一緒に課題解決に向けてアクションをしていく、です。
アフリカのことわざでは、"早くいきたければ一人でいけ、遠くへいきたければみんなで行け"という表現があります。
結局、良い学びの実現には、大きなエネルギーが必要です。かなり遠くまで行かなければ小手先の応急措置止まりで、抜本的な課題の解決にはつながりません。
ですので、みんなで手を取り合い、補い合い、一緒にリソースやコストを出し合いながら、教育を良くしていければ良いのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
