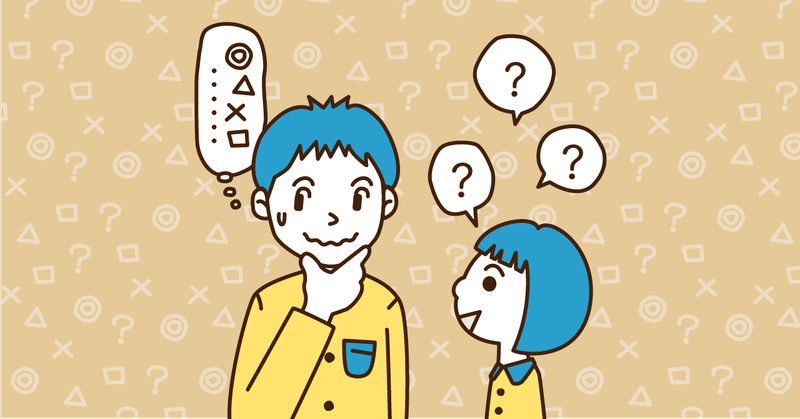
困ったあの人との接し方
打てば響くように仕事をしてくれる同僚が時々いる。それと同じぐらい、全然噛み合わない同僚もいる。
こういう人が嫌だからと遠ざけてしまったら、いつまで経っても会社は回らない。
ここでは私が心がけていることについてまとめておこう。
第三者に客観的な意見を求める
なかなか噛み合わない同僚のことを、ある日信頼のおける先輩に相談したら、うーんと少し考えて
「それ、どっちも悪いよ」
とスパンと言われた。
凄くざっくり言うと、私の指示出しが曖昧だったりスケジュールに無理があって、そのことの怒りを同僚がかなり強い言葉でストレートにぶつけてきたのだ。
頭に血が上りそうになった私はなんとか堪えて、結論を曖昧なままにして話し合いの場を中断した。
スケジュールに無理があるなら後輩からリスケの提案をするべきとも言えるし、私が途中で無理なスケジュールに気づいて軌道修正すべきともいえる。
人はついつい自分目線で考えがちだけど、やっぱり第三者にジャッジしてもらうって大事だなぁ、と思った。
そう思ってからは同僚の発言の背景まで思いを巡らせられるようになった。
先手を打って自分から反省の弁を述べる
よほどのことがない限り、相手の言ってることにも一面の真理はある。
その場ではカチンときたとしても、冷静に捉え直すと確かに怒るような行動をとってしまったらかもな、と思える。
で、先回りして「あなたの発言をもとに振り返ったけど、自分にも〇〇という悪いところがあった」と言ってしまう。
これをやると良識のある相手であれば「もしかしたら私も悪かったかも」と思ってくれて、お互いにここを直してゆこう、という流れになる。
これなら建設的な会話になる。
ストレス耐性の活かし方
ここで重要なのは「ほどほどに傷つけあう」ことへの耐性だ。
ストレス耐性はいきなりレベル100にはならない。
レベル10を耐えて、次に15を耐えて・・・と徐々に上げていくことでストレス耐性は高まってゆく。
曲がりなりにも30代まで社会人をやってきたが、最大の成果はこの「耳に痛いことを受け入れられるストレス耐性」かもしれない。
これがあると軌道修正をすぐできるようになるし、ビジネス相手ともただの喧嘩別れを避けられるようになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
