
母の喪失 #磨け感情解像度
母はいつも「お父さんとは話ができない」と言った。
会話が成立しない、食事を作っても「おいしい」ひとつ言わない、戸の建付けが悪いと何度も言っているのに、いつまで経っても直してくれない。
父は「まずかったら食べない」と、眉ひとつ動かさずに言う。これもいつものことだ。
父は無口で何を考えているか分からない上、私達の小さい頃よく暴力を振るった。牛乳のグラスが倒されて食卓に白い川ができた。攻撃を受ける母にも怖くて近づけなくて、私は妹と自分達の体を抱き締めあった。父が力任せにドアを開け、パチンコかどこかに行ってしまった後の、開け放たれたままの玄関。実家の居間の引き戸には一箇所、鋭く凹んだ場所がある。その下に丸まって身を縮めていた母に、父がライターを投げた跡だ。
◇ ◇ ◇
就業時間がそろそろ終わる頃、妹から電話があった。会社が入っているビルのクリーム色の廊下は、西日でギラギラと光っていた。妹の低い声はあえぐようにうわずっていた。
お母さんが倒れた。意識はあるけど起き上がれない。
早めに仕事を切り上げて実家に寄った。母は首から下が動かなくなっていた。今からでも大きな病院に行った方がいいのではと思ったけれど、家を出た私が口を出すことではないような気がした。母の症状は二十数年前に罹った病気の再発であろうことは明らかで、両親は当時の思い出から大病院に強い不信感を抱いていた。
母はしばらく自宅療養をすることになった。お世話になっている東洋医学の先生に頼み込み、毎日往診してもらった。実家に寄ると大抵先生がいて、懐かしい薄茶色の瞳で挨拶をしてくれた。黒かった天然パーマの髪は全て白髪になり、一回りも二回りも小さく、丸くなっていた。
私が一人暮らしの部屋を畳んで戻ってくるという選択肢ははじめからなかった。夜討ち朝駆けのような仕事の仕方をしていた私は戦力にならない。その上引っ越しで一時的にせよ実家をごたつかせるなんて。「まあお姉ちゃんはそのままで」という話になった。
たまに様子を聞いても妹の口は重かった。母は自分で下の処理も出来なくなっているので、その点だけでも母と父と妹の間には様々な失敗や恥辱、尻ぬぐい(文字通りの!)があり、母は当然それを広められるのを望まなかった。私はそこに入り込めなかった。
話は飛ぶが、小学生の頃から飼い始めた柴犬系の雑種の犬が死んだときも、私は実家から遠く離れた地で勉学していた。あんなに愛していた犬の死に目に私は会えなかった。犬の死を発見し、垂れ流された汚物などを処理したり体を清拭したりしたのは妹だったと母から聞いた。妹は偉くて、私は冷たいという訳だった。そう、今回も。
二十数年前は母を救った東洋医学も、今回は力不足だった。再度発作が起き、今度こそ救急車で運ばれて大きな病院に入院することになった。
「あの頃とは違い、ある程度の治療方法が確立しています。発症時に来てくれれば、すぐに手術できたかもしれないのに」病院からはそういった趣旨のことを言われた。
親族を巻き込んだ大騒ぎになった。父の兄は知人の知人にいる病院関係者に働きかけてなんとか早く手術ができないか、せめて医師の中で腕のいい人が担当にならないかと掛け合った。母の田舎の人達は代わる代わるやってきては、「病院に良くしてもらうにはやっぱりこれよ」と箱買いした缶コーヒーや菓子折り、白封筒を押し付けようとする。伯母の一人は父と妹を気遣って、定期的に何種類かのおかずをタッパーに入れてきてくれた。そういうことが私には雲をつかむような話として伝わってくるが、それは父と妹には眼前にある生活なのだった。
一番の当事者であるはずなのに、母はベッドの上で取り残された形になった。母は体を動かせない自分の境遇を嘆き、じりじりとしか進まない時計を恨み、自分を一事例として扱う冷徹な主治医を呪い、馴れ馴れしく話しかけてくる隣の患者を厭った。せっかく娘たちから手が離れて、これからだったのに。そして何もかも覆い隠すのっぺらぼうのカーテンの中に閉じこもるようにして暮らした。
……とまで書いておきながら、母が実際どういう思いでいたか、私は理解していないことに気付く。私が病室に見舞いに行けたのは頑張っても週に一、二度だったし、それは洗濯物を交換しにいったりお茶を交換したり備品を持っていく必要があるような、父や妹の見舞いとは全然別の濃度の見舞いだったに違いない。あの頃の私は家族の中で自分が鬼っ子のようだと強く感じていた。一応血を分けた家族であるのに、自分だけ求められていない。何とか周りの人を元気づけようと、道化のようなことを演じても白けさせてしまう。そのうち、もう自分はこのままでいいんだと、自らに与えられた余所余所しさを受け入れるというような。
手術は年末の長い休みに入る少し前で、最初の発症から三か月以上経っていた。私は数日繰り上げて有給休暇を取ったはずだ。当日は父方の親族も母方の親族も入れ替わり立ち替わりやってきて、早朝から母の個室は暖房と人いきれでもわっとしていた。
親子水入らずでと親族に送り出され、ストレッチャーに乗った母と一緒に出発した。目的地は幾つか病棟をまたいだ先で、恐ろしく長く感じた。サブエレベーターしか空いていなくて、そこは暗くて狭かった。途中で患者が点滴台を引いて乗ってきた。しんみりしてるところなのに空気の読めないおじさんだなとか、立って歩けるなんてズルいなどと思った。自分でも理不尽なのは良くわかっていた。……100%手術が成功する保証はなかった。
手術室、正確には手術前処置室の扉が閉まった時、父がぽつりと言った。
「行っちゃったな」
それは私が初めて聞いた父の声だった。こんな声をこの人は出せたのか。父は母のことを実はとても愛していた。多分ずっと。そのことが、私の前にものすごい確からしさで迫ってきた。
母は父の愛にまるで気付いていなかった。そして気付かないまま、手術室に行ってしまった。届くべき人に届かない思いは、病院の廊下に漂っている。
私は母を悪者にしたいわけではない。そんなに母のことを大事に思っているなら、もっとやりようがあったはずだ。特に暴力は、母の心を殺すのに十分だっただろう。しかし暴力を振るう前、母は父のやることなすことにダメ出ししていなかっただろうか。でもそのもっと前、父は祖母にいびられながら、小さい私たちを育てる母をきちんとケアしただろうか。
問題の端緒はもはや分からない。
元気なころ母は良く「私が離婚しないでいるのが不思議だ」と言った。でも、今や父が母と離婚しないでいるのが不思議だった。父は母が入院するまで慣れない料理を作り、掃除をし、自分が言うと母は聞き入れないからと、伯父を通じて母を励ました。表向きは言葉少ななまま。
手術を終えた翌日だっただろうか。父と妹と三人で実家で昼食を食べた。母がいないと家はぐっと静かだった。父は私が思っていたのと同じことを言った。
「一人いないだけで静かだな」
それを聞いた妹が茶化して、父に言う。
「淋しかったら素直にいいなしゃい」
父は泣いた。
母の病気の再発以来初めてのことだった。いや、そもそも父の涙なんてこれまで見たことがあっただろうか? 茶化した妹も私もつられて泣いた。母のいない家はあまりに静かで、あまりに広かった。
三人で泣いているのがおかしくて、誰からともなく笑い声が漏れはじめ、バカ笑いになった。私は炒飯が鼻に入って大きくむせ、鼻水まみれになった。「汚いねえ」と妹が笑い泣きしたままティッシュをくれて、私はやっぱり道化だった。
◇ ◇ ◇
あのとき以来、私は強い母を喪失した。
思えば入院中の母は「弱くなった」訳ではなく、元々弱い人だったのだ。母自身が自分を弱い人間に見せないようにしていたので、気付かなかっただけだ。
結婚し、子供を設けた今、そのことを強く再認識する。強くて全き母親はいない。どの母親も、母親である前に、弱くて不完全な一人の女なのだ。そう、私の母も。
それに気付いた時、私は母の毒を100%憎めなくなった。「でもあの時母がこうしてくれていたら今頃」と、やっぱり思ってしまうけれど。
私は子供がいる前でも泣くし、怒る。そしてそのことを正当化しない。なるべく限界まで頑張るけれど、「ここまでは無理」と言うようにもしている。
私は強くない。子供よりほんの少し生きている時間が長いだけだ。
Twitterで知り合ったお母さんたちの中には、子供の絶対的な安全基地になろうと、子供の前ではしゃんとした大人でいようとしている人が多い。その姿は潔く凛々しくて尊敬するけれど、私はその道に進むのをやめたのだ。出来ないから開き直っているだけではと、毎日自問自答するけれど。
子供たち、ごめん。あなたたちは、強い母を最初から喪失している。
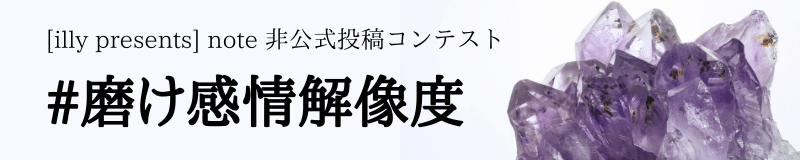
サポートいただけたら飛んで喜びます。本を買ったり講習に参加したりするのに使わせて頂きます。
