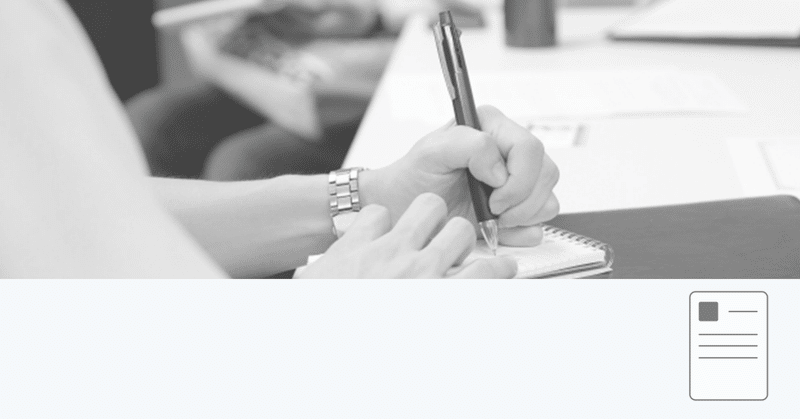
中学生|「総合的な学習の時間」を使った俳句指導5
この記事は、日本俳句教育研究会のJUGEMブログ(2018.12.13 Thursday)に掲載された内容を転載しています。
参照元:http://info.e-nhkk.net/
nhkk事務局スタッフ:
山口県の中学校にお勤めの紺野久典(俳号・クラウド坂の上)先生から、お寄せ頂きました「俳句創作指導」資料のご紹介、第5回目です。
第5回目は【文化祭「俳句相撲シナリオ」&垂れ幕フォーマット】資料です。
「俳句相撲」とは
夏休みに宿題として、秋の雑詠を三句詠ませ、それをクラス内の選句会で代表五句を決め、俳句甲子園のように5対5の団体戦形式で文化祭当日に戦わせました 。

中学生であり、初めての俳句作りなので、ディベートはありません。「相撲」と名がついているのは、チームがそれぞれ東西に分かれることと、行司が中央で軍配を持って進行していくことによります。

審査は会場の上級生と教員赤か青のうちわを上げ、その数を行司が判断して勝敗を決します。

作者は最後に発表で、あの子があんな句を!?と驚きの声があがりました。
俳句を作り発表した生徒、観客兼審査の生徒、保護者、他学年の教員に、「とてもおもしろい!!」、「中学生でもあんなに上手にできるんだね!」と大好評でした。

「俳句相撲」シナリオ
詳細のシナリオです。行事の「はっけよ~い、のこった!」でうちわをあげるというのもユニークです。(nhkk事務局、補足)

垂れ幕フォーマット

nhkk事務局スタッフ:
紺野先生、2学期間にわたる俳句指導の貴重な資料をご公開頂きまして本当にありがとうございました。
すでに俳句指導をされている先生にはもちろん、これから始めようという先生方にとりましても、大変有意義な資料となりました。
「次は、冬休みの宿題で『冬、新年』の季語での句作をさせ、またクラスで句会を開きたいと思っています。」とのこと。
またぜひ句会のご様子などもお知らせ下さい。楽しみにしております。
紺野先生のご実践を拝見して、年間を通じて四季の俳句作りを続けていくならば、学年末にクラスでの句集作りを取り入れるのも盛り上がるのでは! と思いました。
■日本俳句教育研究会(nhkk)
「俳句」を教材とした様々な教育の可能性を研究する日本俳句教育研究会は、「俳句」を教材に教育活動を展開しようとする教師や俳句愛好家の情報交換の場になりたいと活動する任意団体です。
ご連絡は、HPの「お便り・お問い合わせ」からお願いいたします。
