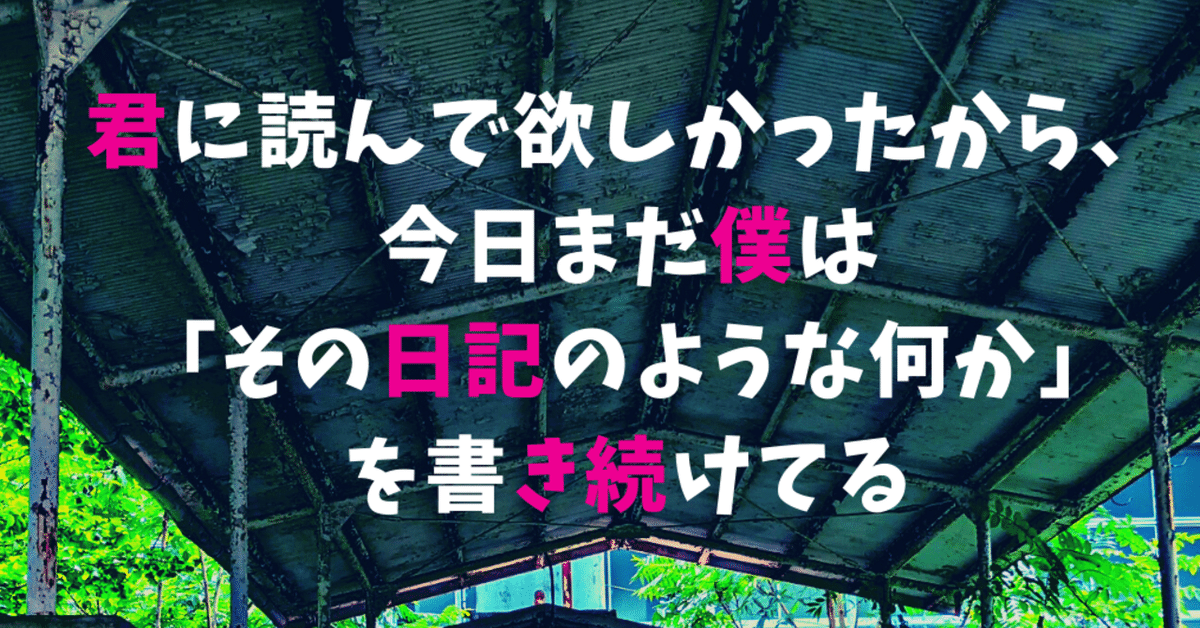
君に読んで欲しかったから、今日まだ僕は「その日記のような何か」を書き続けてる

はじめに。
僕、ダイナマイト・キッドこと佐野和哉は今年35歳になる、愛知県豊橋市在住で肥満体の会社員です。
趣味は文章を書くこと。小説や作詞のほかに、思いついたことや好きな映画、漫画、プロレスやプロレスラーのことなどを、あちこちの投稿サイトで場所をお借りしては書き続けています。
基本的に頼まれもしないのに、好きなので時間を作っちゃ書いています。なので勝手に書いて、自分のTwitterやFacebook、インスタグラムにLINEなどのアカウントでセッセと宣伝したり、コメントを頂いたときには殆ど必ずお返事をさせて頂いたりしています。
殆ど必ずってのは、返事のしようがないコメント(絵文字だけとか、ワンフレーズだけとか、なんかそういう……)も時々あるので……。
相手のある話だと(誰それ主演の映画が、とか、プロレスラーの誰々が、とか)時々、その話のご本人がコメントやいいねを下さったりして、とてもうれしいですし、同じ趣味の方や自分の知らないことを知っている人からコメントを寄せて頂くことも毎回の楽しみのひとつです。
そんな風に自分の作品を通じてコミュニケーションをはかるために、自分で書いた文章を読んで欲しくて、それをアピールして……なんでそんなことをするようになったのか。
実はハッキリと、今でも覚えている「#あの会話をきっかけに」そうなったのだという瞬間があります。それを、今回つまびらかにして見たいと思います。
色々と思い出して補足したり省略したりしていますが殆ど実話です。
今もこうして、ココにそんな作品を載せている、その端緒となった物語を是非ご覧くださいませ。
以下本文
中学一年の三学期、それも春先のこと。それまで読んで来て好きだった椎名誠さんのあやしい探検隊シリーズや、当時新日本プロレスのリングアナウンサーだった田中ケロさんの旅日記シリーズを真似して、自分でも何か日々の事を書き留めてみるようになった。
小学校の頃から読書感想文や遠足、運動会といった学校行事の後に出す作文を書くのは得意だったけど、自分で内容を考えつつ自由に何かを書きまくるというのはコレが初めてだった。
近所の文房具屋さんでルーズリーフのノートを何冊も買ってきてひたすら机に向かってノートを書いている僕を見て、母子家庭でありながら一生懸命に私を育ててくれていた母にしてみれば、カズヤ君は勉強熱心なことだとさぞかし感心してくれただろうけれど……実際は勉学などテキサス州より遠いところへ追いやってしまっていたのだった。
内容には日常の様子だけでなく、自分の好きなものや思い出に残っている出来事など色んなことを盛り込んでいった。好きな映画、漫画、プロレスやプロレスラーのことなど……ホントに今と大して変わらないことを書いていたと思う。
学校の宿題なんかちっともやらないくせにコッチはセッセと書き続け、その日記のような何かは一週間足らずで早くも二冊目に突入した。一冊目は全部黒のボールペンで書いてたせいで読みづらかったので、またしても近所の文房具屋さんでカラーペンをアレコレ買ってきて登場人物のセリフをそれぞれ別の色で書くなど細かい工夫も入れてみた。
そして案の定ただ書くだけじゃ物足りなくなった僕は、その日記のような何か、こと力作の詰まったノートを学校に持って行って教室や部活前の柔道場(僕は柔道部だった)で友達に見てもらうようになった。みんなからお世辞半分ネタ半分でも面白いと言われたら嬉しくって。それで図に乗ってまた書いて。その繰り返しがひたすら楽しかった頃。
その日記のような何かはクラスや部活で一緒だった数人の友達にだけ見せていたから、あの時分に僕が嫌いだった同級生Nのこととか、顧問の先生の顔がコワイとか、結構なんでも言いたい放題好き勝手に書いていた。だから自分の文章がどうとかより、身内のノリで面白がってくれてたのも多分にあったと思う。
でも自分ではシーナさんやケロちゃんになった気分で、得意満面のご満悦だった。
結局、その日記のような何かは全部合わせるとルーズリーフのノート六冊分になった。後にも先にも、ノート一冊アタマから最後まで使い切ったことなんて、この時ぐらいのもんだ。それも短期間で、買ったそばから書いて埋まっていくなんて。
近所の文房具屋のオジサンも、佐野君は勉強熱心だと褒めてくれたっけ。
実際は勉学などM78星雲ウルトラの星より遥か遠くに追いやってしまっていたのだけれど……。
それから少し経って、中学二年になってすぐのこと。
春の大型連休最終日にしてゴールデンウイーク中で唯一の部活のない日曜日に、部活の仲間たちと自転車で遊びに行くことになった。行先は豊橋市郊外にある嵩山の蛇穴(すせのじゃあな)という洞窟で、仲間のうちケンちゃんやコンちゃん、オーノは小学校の遠足で行ったことがあるけど、彼らとは校区の違う佐野君こと僕やダイちゃん、ダンディ山田(何故か入学当時からそう呼ばれていたので僕らもダンディと呼んでいた)は、まだ行ったことがなかった。
蛇穴は我らが豊橋市内にありながら県境の深い山の中に存在するため、未開の秘境を案内してもらうみたいな気分だった。そこにイッコ下で柔道部に入って来た細田君も加わって、みんなでちょっとした自転車旅行をする春の一大イベントだ。
ところで、僕は当時すでにモーレツなプロレスマニアで、地元の体育館で試合があるたびにおじいちゃんから譲り受けたお古のカメラを抱えて特別リングサイト席に陣取り、暴れるレスラーたちを激写していた。だから中学生にしては立派なミノルタのカメラもあったし、撮影にも慣れていた。
1998年頃の話なので、勿論フィルムカメラ。
小遣いの乏しい中学生の僕にとってカメラのフィルムは血の出るような貴重品で、一枚、一枚をそれは大事に撮っていたのを思い出す。
今回の旅ではカメラと一緒にフィルムを三本も持っていったから、僕にとっては大変ゼータクな話でもあった。その日の道中でもパシャパシャ撮って、おじいちゃんの行きつけの小さなカメラ屋さんで現像してもらった写真には色んな風景が収められていた。
急な上り坂で必死な形相をして自転車を漕ぐケンちゃんとダンディ、途中で立ち寄った貯水池の芝生で一休みする細田君、自販機でジュースを選ぶコンちゃん、そのジュースをひとくち貰っているダイちゃん。
五月晴れの青空に映える漆黒の瓦屋根と大きな鯉のぼり、新緑の萌える山道、遂に辿り着いた洞窟。そして、よりによってそのすぐ手前で自転車がパンクして今にも死にそうな顔をしているオーノ。
蛇穴を目指した旅は(約一名の自転車を除いて)無事に終了し、帰宅した僕は予めこの時のために用意しておいた新品の、いつもよりちょっといいルーズリーフのノートを取り出すと早速ペンを走らせた。いつもよりちょっといいだけあって、茶色くて厚めの表紙のざらりとした手触りが心地よい。
そして当日の朝みんなが集合するところから解散するまでの様子を子細にわたって書き連ね、現像した写真も厳選して一枚ずつ貼り付けていった。
自分なりに誌面のレイアウトも考えたし、見出しや写真のキャプションを付け、時には写真そのものにもペンでコメントを書き込んだ。毎週、プロレス週刊誌を穴が開くほど読んでいたのがここで活かされた。
さらにオマケとして近況やコレを書くにあたっての前書き、あとがきなども一丁前に記し、いつもよりちょっといいノートきっかり一冊分を書き上げた。
そうして、この世にたったひとつしかない、入魂の一冊が出来上がった。とはいえコレは身内の遊びでしかない、ということぐらい……当時の僕だって薄々わかっていた。
ではなぜ、こんな手の込んだ真似をしたのか。
ハナシは蛇穴自転車旅行の少し前に遡る。
春先の二年一組の片隅にて。
その当時、僕は二年三組のMさんのことが1986年生まれの人類の中で一番大好きだった。Mさんは学校でもトップクラスの成績を誇るカシコイ女の子で、雪のような素肌と長い黒髪をポニーテールにしているのがとてもステキだった。が、それ以上に僕が彼女のドコに惚れ込んだかと言えば、明るく屈託のない、誰に対しても分け隔てなく話してくれる優しいところだった。
僕とは幼稚園以来の友達だったテッチャンがMさんと同じ部活で仲良しだったことから、彼女は休み時間になるとよく一組の教室に遊びに来て色んな話をしていた。
その話題もテストや教科の真面目な話から、バカなことやくだらないこと、果てはちょっとエッチなコトまで幅広くて。彼女にぞっこん一目惚れしていた私は、いつしかテッチャンと二人でバカな話をしてはMさんに笑ってもらうことが毎日の楽しみであり喜びになっていた。そのために学校に行っていたと言ってもいい。
ある日の休み時間。僕はテッチャンに、例の日記のような何かを読んでもらっていた。テッチャンは仲間内でも利発で理論派だったから、彼に面白いと言われることは普段とはまた違った意味で自信になった。身内ネタやテッチャン向けのフレーズなんかもあったから、そういうのを拾いつつ、ココやココが面白くて、ココはちょっと長ったらしい、とか、コレはよくわからないとか……今にして思えば担当編集者に添削してもらっているようなものだったのかも知れない。
と、そこへMさんがやって来た。
(ヤバイ!)
僕は反射的に、そう思った。
一見何の変哲もないルーズリーフのノートだが、中身はバカな事ばかり書いてるし、下ネタも多いし、ロクなもんじゃないんだ。
(こんなものを読まれたら絶対に嫌われる……!)
顔面蒼白の僕をよそに、Mさんはまんまとテッチャンの持っているルーズリーフのノートを目に留めて、それなあに? と手に取った。
「佐野が書いてる日記。結構おもしろいよ!」
そしてあろうことかテッチャンは、それを何気なくMさんに手渡した挙句、面白いよ! とのお墨付きまで下さりやがったのである。
(こんの野郎ヨケーなことするんじゃねえよ!!)
と古い付き合いのお友達にスタン・ハンセンばりのウエスタンラリアットをお見舞いしたいのをグッと堪えていると、Mさんは僕のノートをパラパラめくりながら
「へえー、佐野君てこんなの書けるんだ。すごいね!」
と言ってくれて、さらに笑顔のまま、続けざまにこう言った。
「ねえ、これ、借りてもいい?」
「へ?」
「家で読むね! ありがとね」
あ、ああいい……よ、と答えた筈が上の空。そのまま始業のチャイムが鳴ったので、Mさんは見慣れたルーズリーフのノートを小脇に抱えたまま三組へ戻って行ってしまった。
終わった。
もうダメだ。絶対に嫌われた。おのれテッチャン……僕はスリーカウントピンフォール負け寸前の気分で窓の外を見ては長い付き合いの友達を逆恨みしたり、ため息をついたり、夜は自己嫌悪に忙しかったりしていた。
しかし──
Mさんは翌日の二時間目と三時間目の間の長い休み時間に一組の教室へ入って来るなり僕に駆け寄り
「ねえ! これすっごい面白かった!!」
と満面の笑顔を見せてくれたのだ。はい、ありがとね、と手渡されたルーズリーフのノートからは、ちょっといい匂いがした。
作り話じゃねえよ、ホントだよ。あとでコッソリ嗅いだんだから。
カウント2.99で立ち上がった小橋建太のような気分で茫然としている僕を尻目に、テッチャンが
「なんか連休中に蛇穴行くらしいよ?」
とMさんに僕の予定を告げた。するとMさんが
「そうなんだ? 誰と?」
「部活の友達と」
「ふーん、で……それも書くよね?」
「えっ」
「日記。書くよね?」
「あ、ああ。まあ多分……」
「書け、いいから! 佐野カズヤ、日記を書け!!」
「え? あ、う、うん! わかった、絶対書くよ!」
僕が生まれて初めて、ヒトサマから文章を書けと言われた瞬間がコレだった。
それも、大好きなMさんから目の前でハッキリ言われた。
うれしかった。
そんなこともあって、蛇穴に行く前からもう「これは書こう!!」と心に決め、そのためにいつもよりちょっといいルーズリーフのノートまで買いこんで、フィルムも潤沢に用意してあったというわけ。
やがて連休最終日から数日。当時の僕の最高傑作が完成した。
いつもよりちょっといいルーズリーフのノートに記された、いつもよりちょっと違う熱のこもった、その日記のような何かを、遂に僕はMさんに手渡した。
Mさんは喜んで受け取ってくれた。良かった。
真に受けるなよ、とか言われたらどうしよう、忘れられてたらどうしよう、って、実はずっと、書きながら心の何処かで不安だった。でもそれは杞憂だった。君に読んで欲しくて僕は、その日記のような何かを書き上げたんだ。
Mさんは例によって家で読むからと言って、いつもよりちょっといいルーズリーフのノートを抱えて三組の教室に帰って行った。
だけど、そのままそのノートは返って来なかった。月日が経つうちにMさんが忘れてしまったのもあるだろう。でも、それ以上に返しづらい状況になってしまったのも大きな原因だったと思う。
それからすぐ後。中二の夏前。僕は思い切ってMさんに、生まれて初めてのアイノコクハクというやつを挙行したのだ。そしてそれはもう、モノの見事に玉砕した。
失恋という超弩級のウエスタンラリアットを喰らった僕は今度こそ完璧なスリーカウントを聞いたうえ、Mさんともそのまま疎遠になり、中学を卒業するころには殆ど話すことすらなくなっていた。
あのノート、せめて捨てないでおいてくれたらいいなと思っていた。今となっては流石に残っていないだろうし、出て来たって恥ずかしいからそれでいいけど。
2021年。早いもので、あれから二十年以上が経った。Mさんは中学卒業後、県内でも有数の進学校から東京の大学へ行ったらしい。その時々で流行ったSNSで、たまにMさんのアカウントを見ることはあったけど……フォローしたり声を掛けたりは今もって出来ないでいる。
彼女は僕が手渡したノートいっぱいに書かれた、あの日記のような何かを……まだ覚えてくれているだろうか。
僕は間違いなく、#あの会話をきっかけに して今日まだ文章を書き続けている。バンドを組んだ時には作詞も始めたし、2018年には自作のホラー小説が、少しだけど某社の文庫本に載せてもらるということもあった。
そして今でも僕は自分のアカウントを作って、こうしてあの時と同じく、その日記のような何かを書き続けている。
もっともっと書いて書いて読まれて読まれて……いつかMさんの目に留まって、また手に取ってもらえたらいいな、と。ほんの少しだけ思っている。
貴女に読んでもらって、またあの屈託のない笑顔で「面白いね!」って言われたいから。
六冊あったノートはひとつも残らなかったけど、今日このnoteに、あの日の記憶を思い出して書き留めてみました。
Mさんありがとう。
小銭をぶつけて下さる方はこちらから…励みになります また頂いたお金で面白いことを見つけて、記事や小説、作品に活かして参りますのでよろしくお願いいたします。
