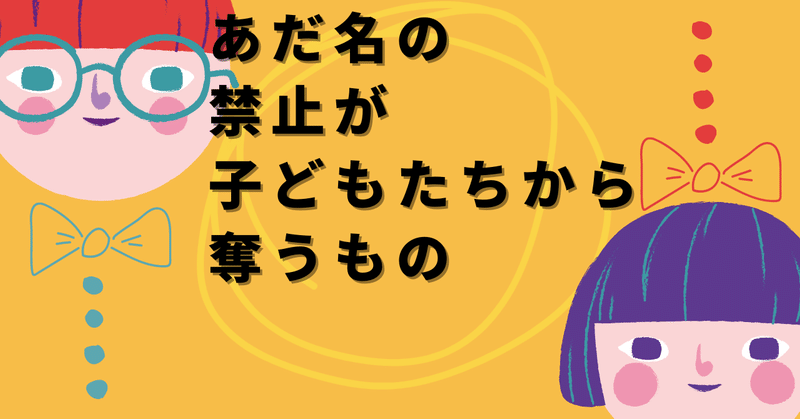
あだ名の禁止が子どもたちから奪うもの
あんたはガキンチョの頃にあだ名を付けられていたかい?
あだ名ってのは実に創造性が求められるものだよな。
泳ぎが上手いやつには「かっぱ」。
鰹節がスキなやつには「ぶし」。
なんとも、自由な発想だ。
ところが、今の小学校ではあだ名で呼び合うのはダメってことになっているんだそうだ。
今回は子どもたちがあだ名を使っていた意味を考えてみる回だ。
ちっと人間関係の基礎を作り出す時期のあだ名について考えてみようぜ。
ブタゴリラのスゴさ
松井さんのマンガ、すげぇスキなんだよな。
女性の格闘技を扱ったマンガであるハナカクなんて、グイグイ惹き込まれる感じがするんだよね。
読んでみ?
で、松井さんの奥様がキテレツ大百科に出てくる「ブタゴリラ」ってあだ名がひどいねって言うのから夫婦であだ名を付け合うっていう、なんつーか心温まるエッセイマンガがさっきのnoteだ。
たしかにブタゴリラはすげえあだ名だ。
なにがすげぇって、ブタゴリラというあだ名を受け止めているブタゴリラの胆力というか器のデカさみたいなものを感じる。
それもこれも、友人同士の信頼関係ってのを子どもたちが経験しているから成立することだと思うんだ。
最初は悪口だったかもしれない。
それでもお互いの人間性を子どもたちが理解し合って行くってプロセスを経験することって、メチャクチャ大切なことジャンか。
あだ名が禁じられた理由
それでも今の小学校はあだ名を禁じている。
どうも調べてみると、この動きは1990年代後半から始まっているらしい。
上記サイトによれば、あだ名どころか「くん」で呼ぶのもダメなんだそうだ。
理由はLGBTQ。
セクシャリティの多様性からくんづけで呼ばれたくない子どもへのいじめを抑制するって意味からなんだそうだ。
なので、一律で「さん」で呼び合うようにしているってことらしい。
……おかしくね?
それってセクシャリティどころかパーソナリティの均一化であって、多様性を認め合うってのとは真逆の活動に思えるじゃんよ。
子どもたちが多様性を認めるために出来ること
でも、たしかにLGBTQのような大人ですら扱いが困難な課題に対して、子どもたちに受け入れさせるってのは実に難しいと思う。
現実問題として、実際のクラスを担任してくれている先生は子どもたちに教育を施すのが仕事で、当然その教育の中には多様性を受け入れるってことも含まれているけれども、そもそも世の中でどうやって多様性を受け入れるべきかっていう方法論が確立していない以上は、どうやっても先生たちの個人の裁量に任せざるを得ない部分が出てくる。
その上で文部科学省や教育委員会からは一定基準のいわゆる「勉強」を子どもたちにさせることが求められている。
ある程度、子どもたちを均一化させないとコントロールもままならないってのが実態だろう。
でもセクシャリティだけじゃなくて、あだ名を禁ずることでパーソナリティまで奪っちまっている現状は決して健全じゃない。
じゃあ、どうするのか?
思うに多様性を子どもたちが理解するためには経験するしか方法が無いと思うんだ。
どうやって?
おそらく実例をしめしながら子ども同士でディスカッションを重ねる場ってのを増やしていくことなんじゃないかって思う。
当然そういうディスカッションの場を取り仕切るファシリテーターにはある程度の専門性が必要になるだろうから、そう言う人材を学校別に用意するための補助金を国から出すようにすれば良いんじゃないだろうか?
多様性という課題に、俺たちヒトが立ち向かうためには「考える」しか方法がないはずだ。
子どもたちがその「考える」を経験することは何よりも大切なことだと思うんだよな。
なあ、あんたはどう思う?
あだ名の禁止が子どもたちが多様性を考える機会を奪っている気がしないかい?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
