
ブルックリンから持ち帰った“衝撃”が、日本のヒップホップの“未来”をつくった~『スカイ・イズ・ザ・リミット ラッパーでもDJでもダンサーでもない僕の生きたヒップホップ』ためし読み公開
ZeebraやOZROSAURUS、SOUL SCREAMらを擁した国内初のヒップホップ専門メジャーレーベル「フューチャー・ショック」のオーナーによる自伝的小説『スカイ・イズ・ザ・リミット ラッパーでもDJでもダンサーでもない僕の生きたヒップホップ』が本日発売になりました。

90年代の“ヒップホップ黄金時代”をブルックリンで体験した著者・市村康朗 a.k.a ブルックリン・ヤス氏だからこそ書ける、リアルなエピソードが満載の本書から、「Buy one, Get one free」の冒頭部分をためし読み公開いたします。
時は1990年、アメリカの高校に留学した「僕」をさまざまな“衝撃”が待ち構えていた。日米における文化のちがい。のちにラッパーとして大成する盟友、タリーブとの出会い。反戦デモに参加して知る、アメリカの光と影――。ぜひご一読ください。
* * *
Buy one, Get one Free
ヒップホップを心から愛してやまない人間なら、かの有名な演説は知っているはず。“I have a dream.”と叫んでいる、アフリカ系アメリカ人公民権運動の指導者、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの演説のことだ。彼が生誕した日は、アメリカ合衆国の国民の休日として定められている。
あれはたしか1990年のことだった。マーティン・ルーサー・キング・デーに、僕が通っていたチェシア・アカデミーの学生は、平和的な座り込み抗議活動を行なった。
僕たちはキング牧師の誕生日を特別な日ととらえていた。なぜならキング牧師がいなかったら黒人解放運動は別のところにたどり着いていたかもしれないし、そうなってくるとヒップホップが誕生しなかった可能性すらあるからだ。
抗議は公民権についての議論へと発展していった。それ以来、毎年学校側は、マーティン・ルーサー・キング・デーに、学生を教育するためのプログラムを開催するようになった。
当時のニュースは、全校生徒が授業をボイコットしている様子を世の中に伝えた。学校で行われた抗議活動の発起人は、フューチャー・ショックのコンピレーション・アルバムにも参加しているラッパーのタリーブだった。当時、コネティカット州においてキング牧師の生誕日が祝日として定められていないことに対して憤りを感じたタリーブは、全校生徒に呼びかけて学校側に抗議した。
彼がフューチャー・ショックの作品に参加した経緯は、いうまでもなく、僕たちが高校時代に同じ学生寮で暮らし、その後のブルックリンでの日々があったからだ。
僕が通っていた学校は、全米はもちろんのこと、ヨーロッパや南米、そしてカリブやアジアなど、世界中のさまざまなところからやってきた、やんちゃな連中がいるところだった。
生徒たちはそれぞれの部屋の壁に、好きなポスターを貼っていた。ティーンネイジャーが自分の部屋の壁にポスターを貼る文化は世界共通のものだ。大概が音楽関係のポスターであり、それは個性を主張する手立てのひとつだったともいえる。インターネットが発達していない時代、音楽はとても身近な存在だった。なかには、カセットテープのコレクションや、ターンテーブルとレコードを持ち込んでいる強者までいた。
寮で暮らしている生徒たちは、各自がさまざまなジャンルの音楽に精通しながら個性を発揮していた。僕はその時になって初めて、音楽は流行り廃りではないということを知ることとなった。ロックを聴くやつは何がなんでもずっとロックを聴き、ポップスを聴くやつはどんなことがあってもポップスを聴く。日本で生まれ育った僕にとって、そんな様子を目の当たりにしたことは、それまでになかった。
僕が通っていた日本の中学校時代の同級生は、みんなが流行を追っていた。テレビに出ている流行りの歌手だったりバンドを、みんなで一緒に聴いている感じ。右へならえ。回れ右。足踏み始め。前へ進め。全体止まれ。みんなとちがう動きをしたら、ほーら言うことを聞いていないからだと罵られ、眉をひそめられてしまう。揚げ足を取られたあげく、ペテン師扱いされ、あっちいけしっしっという具合に。
だから留学したアメリカの高校で、各自がそれぞれの趣味趣向で音楽を選り分けながら聴いている様子が、すごく新鮮に感じられた。毎日朝の7時になると、上の部屋から爆音のレゲエが聞こえてくる。隣の部屋からはラップ。ルームメイトはパンクロック。向かいの部屋はダンスポップで、斜め前からはヘビーメタル。そんな環境で僕が聴いていたのは、初めのうちは日本から持って行ったブルーハーツだった。
けれども寮生活というのは、放課後だったりに少しでも時間があったら誰かの部屋に遊びにいくのが当たり前だった。したがって僕は遊びに行く先々で、いろいろなジャンルの音楽に触れていくことになった。
ほかの生徒たちの部屋で耳にするのは、僕がそれまでに聴いたことのなかった音楽ばかりだった。そんな時には自然と、これは誰のなんていう曲なの? と訊くこととなった。するとみんなは得意になりながら、自分の好きなジャンルについてひと通りの説明をした後、お気に入りの曲を見繕ったミックステープまで作ってくれた。
日本にいた頃は、レンタルレコード屋でたくさんのジャケットを見比べたうえでジャケ借りをして、聴いてみてハズレだったり当たりだったりを繰り返していた僕からすると、それぞれのマニアやエキスパートがジャンルごとにおすすめしてくれる、これほど効率の良いシステムはなかった。
エリック・クラプトンがソロになる前はクリームというバンドにいたなんていう小話から、ビートルズやオジー・オズボーン、ジューダス・プリーストにパブリック・エネミー、はたまたN.W.Aのような過激な楽曲までいっぺんに吸収できた。それぞれのアーティストの楽曲をウンチクを交えながら聴くことができる彼らとの時間は、学校の勉強より遥かにためになった。
なかでも僕がひときわ心を奪われたのは、スティングとボブ・マーリーだった。音楽に思想やメッセージを込めるだなんて、目から鱗だった。英語を覚え始めていた僕は、スティングとボブ・マーリーが、教科書から学ぶことよりも断然濃い内容を歌っていることに感動し、昼夜を分かたずひたすら聴きまくった。
そうやって音楽を通じて仲良くなった同級生たちは、休みになると僕のことを実家に泊まりに来るよう誘ってくれた。
白人の同級生の家に泊まりに行くと、夕食の際に相手の親から、黒人の友だちじゃなくてアジア人の友だちが遊びにきてくれて嬉しいと言われた。逆に黒人の友だちの家に泊まりに行くと、白人の友だちのあいだで自分の子どもが虐められていないかと心配している親が多いことに驚かされた。日本人の君は良い子だろうし、信頼しているからと言われるたびに、僕はいつも複雑な思いを抱いた。
タリーブとの出会いは、午後の授業を終えて学校の敷地内にある寮に帰った時だった。
建物の1階にある、校庭に面した大きなドアの入り口を開けると、すぐのところに公衆電話があった。そこで僕は、新入生と思われる見慣れない黒人の姿を目にした。
髪型はショートドレッドで、いかにもニューヨーク出身という感じの容姿をしていた。受話器を握る男は独特のアクセントでまくしたてていて、僕が通りかかった時、丁度会話を切り上げるところだった。ガチャンと音を立てながら勢いよく受話器を置いた彼は、向かいから近づいてくる僕にじろじろと視線を這わせながら言った。
「ヨー。お前はどこの国のやつだい? 日本人か? 韓国人か? この学校には中国人があまりいないってことは聞いてるぜ」
タリーブの話を耳にした僕はすかさず答えた。
「日本人さ」
すると、彼は特徴のあるイントネーションで続けた。
「オー! まーじかよ、お前は日本人か! 日本ていったらアメリカに原爆を落とされてるよな。原爆って、ガチにヤベエよな。でもな、お前らはアメリカに落とされた原爆でたくさんの人が殺されたけど、国土も残っているし、さかのぼっていける歴史があるのも救いだ。ご先祖様をたどっていったら、サムライだニンジャだっていう歴史が残っている。だけど俺たち黒人は、奴隷としてこの国に連れてこられたから歴史なんてものは存在しないんだよ。奴隷の子孫は、たとえマイケル・ジャクソンやマイケル・ジョーダンといった有名人だとしても、先祖をたどっていくと奴隷としてどこどこの港に連れてこられたってところでおしまいなんだ。その前の血筋をひもとこうとしても、アフリカのどの辺りの、どういう部族の出身とか、一切わからないんだ」
その時僕は、タリーブの早口の英語をあんぐりと口を開けながら聞いているしかなかった。それくらい、圧倒された。同級生のなかにはバスケットが上手で奨学金をもらっている黒人の生徒もいたけれども、タリーブはそんな連中ともちがう感じがした。
「お前、おもしろいこと言うやつだな」
僕がそう言うと、タリーブは満足そうな笑みを浮かべながら、寮の1階にあった彼の部屋まで招いてくれた。

高校時代の友人の部屋にて
部屋に入ると、正面の窓ガラスの脇の壁には、メガネをかけた黒人のポスターが貼ってあった。
「この人はマルコムXっていうんだ。日本人のお前だったら、キング牧師くらいの名前は聞いたことあるかもしれないけど、マルコムXもタイトな革命家なんだぜ。キング牧師の発言はマイルドだけど、この人は過激な言動で、新しい世代のアイコンとして受け入れられたんだ」
僕はタリーブの話に引き込まれていった。
「ボブ・マーリーはわかるだろ? ジャマイカで起きたレゲエ・ムーブメントが、ニューヨークで発展したものがヒップホップなんだ」
そう言ってタリーブは、まだ荷ほどきの終わっていない鞄のなかから、次々とカセットテープを取り出して説明し始めた。鞄から取り出された、X・クラン、ブランド・ヌビアン、ア・トライブ・コールド・クエストといったヒップホップグループのアルバムは、高校のダンスパーティーでDJがかけるパーティーチューンとは別の種類のサウンドで、僕に新しい刺激を与えてくれた。
タリーブとデモに参加したのは、パパ・ブッシュが中東で戦争を始めた頃だった。ブラウン管から流されていた「ナイラの涙」と重油まみれのウミネコの映像は、今でも僕の脳裏に明瞭に焼き付いている。まさかその映像が偽物だったなんてことは、初めのうちは全然気がつかなかった。アメリカ政府が戦争の口実を作るためにメディアを操っていたことを知ったのは、もっと後になってからだ。
僕が日本で暮らしていた頃に通っていた私立の小学校では、高学年になると社会科の時間の大半が、平和の尊さについて費やされていた。わら半紙とインクの匂いがする「太平洋戦争と反戦」に関するプリント用紙の端を、指先でくるくると丸めながら黒板の前に立つ先生の話に耳を傾けていた。修学旅行で広島の原爆ドームの向かいにあるホテルに泊まった時には、被爆者に会うために近くの老人ホームに行った記憶がある。そうやって日教組の執拗な洗脳を浴びせられながら育った僕にとって、タリーブとデモに参加したあの日は、忘れられない一日になっている。
私立の小学校と公立の中学校に通っていた僕がアメリカの高校に留学して驚いたのは、歴史の時間だった。日本の歴史の授業といえば、縄文とか弥生時代までさかのぼったところから始まる。一方、アメリカは建国してから日が浅いこともあって、アメリカ史は200年ちょっとしかない。
授業中に時系列を追いながら淡々と語られるのは、歴史的英雄の退屈な武勇伝。そいつがどこからやってきて、戦争によってどこの領土を獲得、みたいな感じ。ついでにその英雄の名前を冠した地名まで答案用紙に書かなければ、A評価はもらえない。そういうアメリカが国家として成り立つまでのあらましは、舞台の脚本を棒読みさせられているような空疎な印象だった。
日本との戦争に関しては、アメリカの歴史の教科書のなかでたった半ページしか扱われていなかった。原爆のキノコ雲を添えた簡易的なイラストが1枚きり。
「アメリカは、盗人が奪いとった土地の上に築いた国家。そんなやつらの主張することに、正義なんてあるわけがない」
当時ギャングスタラッパーとして若者の心を掴んでいたアイス・キューブの言葉は、メディアや白人の大人に煙たがられていた。メディアが一介のギャングスタラッパーのリリックに目くじらを立てたのは、それが正鵠を射ていたからだろう。

タリーブ。ボストン近郊の「Obey」アートピース前にて。90年代初頭
戦争が始まって1週間ぐらいしてからだと思う。水曜日の放課後に、州都の街で反戦デモがあるから、興味のある生徒はサインアップしろと先生が言った。
デモに参加したのはデイビッド・シャーマンとマイク、それから僕とタリーブの4人だった。
デイビッド・シャーマンと僕はすごく仲が良かった。彼の名前の響きを初めて耳にする日本人なら、誰しもがブルックス・ブラザーズのパリッとしたピンク色のボタンダウンにプレスの効いたチノを穿いているような七三分けの白人を想像するかもしれない。しかし彼は裕福な家庭出身だったことは間違いないのだが、四六時中マリファナの匂いを漂わせているようなヒッピーだった。休憩時間に、舌の上にLSDを染み込ませた紙切れを乗せたまま野球をやって笑い転げているくらいの不届きものだ。
スケーターのマイクは白人だったが、家庭環境は決して良くなかった。一年中、色落ちしたリーバイスのブルージーンズに、首まわりの伸びたヘインズのTシャツを着ていた。もしかしたらほかにもデモに参加した生徒はいたかもしれないけど、今の僕に思い出せるのはこの4人だけだ。
デモ会場に向かう道中は、まるでスティーブン・キングの『スタンド・バイ・ミー』みたいだった。全然中身のない話を、雨上がりの優しい午後の日差しが降り注ぐなかで語り合っていた。
僕の想像では、デモというのはジョン・レノンの「イマジン」なんかをラジカセで流しながら、ピースマークのプラカードを掲げて大声で戦争の愚かさについて叫ぶというイメージだった。しかし実際に会場に到着してみると、自分の認識がどれだけお花畑だったかを知ることとなった。
街はデモの参加者であふれていた。だがデモの雰囲気はイメージからかけ離れていた。さまざまな団体が参加していて、なかにはタスキをかけていたり、同じ手袋をしたり、Tシャツを揃えている人たちまでいた。
それぞれの団体が、それぞれの主張を掲げていた。「ふざけるな、戦争に使う金があるんだったら自分たちに予算をまわしやがれ」とホームレス撲滅を掲げる団体もいれば、癌患者に対するサポートを叫んだり、家庭内暴力に悩む子どもたちを救えなんていうプラカードまで散見することができた。
確かに彼らの主張はまったく間違っていなかった。けれどもそこにいる全員が自分の主張を伝えるのに必死で、他人の話に耳を貸す余裕や協調性を挟む余地はなかった。
がらんどうで、何もない、見せかけだけの正義のもと、国民それぞれが異なるバックグランドを持つアメリカ。この国で自分の主張を通すということは、他者を押しのけなければならないということなのかもしれないと、僕はこの時、初めて痛感した。
そこにはアメリカの光と影が混在していた。光が強ければ強いほど影も濃くなる。愛情が強ければ強いほど、憎しみが強くなるように。
“Buy one, Get one free”に代表される、アメリカの商業施設で頻繁に目にするこの手のポップは、一体誰が初めに考え出したのだろう。「1個買ったら、1個無料」なんていうエコノミックな商業広告は、アメリカ的な資本主義の象徴以外の何物でもない。
社会に出ると、本音と建前をまざまざと見せつけられる機会が増えてくる。子どもの頃の僕は、ポップに書かれた文字を字面通り真に受けてしまい、その裏に何が潜んでいるのかを想像することができなかった。投げつけられたファクトをそのまま受け止めるしかなかった僕は、アメリカはすごいところで、アメリカこそ人類の未来であると信じて疑わず、そして思春期を迎えた頃にアメリカの高校に進学することになった。
デモに参加した僕は、それまでアメリカに対して抱いていた幻想を一気にひっくり返されることになった。子どもの頃から憧れ続けていたアメリカ。けれども実際にはその背中だけを見て追いかけていただけだった。正面から間近にその顔を覗き込んでみたら、そこには鬼のような形相をした、醜く、利己的で、なおかつ傍若無人に振る舞うアメリカの本性があった。
あの日を境に、自分で勝手に恋い焦がれていたアメリカに対する幻想が崩れていった。そしてそれまでは他人事のように、タリーブみたいな考え方もあるのか、と思っていた黒人文化が、リアリティをともなって自分のなかに入ってくるようになった。
(この続きは好評発売中の『スカイ・イズ・ザ・リミット』にて)
* * *
《書誌情報》

『スカイ・イズ・ザ・リミット
ラッパーでもDJでもダンサーでもない僕の生きたヒップホップ』
市村康朗+公文貴廣 著
四六版・並製・336ページ
定価(本体2,200円+税)
ISBN: 978-4-86647-130-3
2020年10月30日(金)発売
https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK282
1997年に設立され、ZeebraやOZROSAURUS、SOUL SCREAMらを擁した国内初のヒップホップ専門メジャーレーベル「フューチャー・ショック」のオーナーによる自伝的小説。
●90年代の“ヒップホップ黄金時代”をブルックリンで体験した著者だからこそ書ける、リアルなエピソードを多数披露。
・ニューヨークの辛口ラップリスナーも舌を巻いた、ナズの衝撃のデビュー作『イルマティック』
・KRS・ワンの手から直接託された秘伝の書「ラップの化学」
・地元ブルックリンの英雄、ザ・ノトーリアス・B.I.G.との遭遇と、“キング”の粋な振る舞い ほか
●レーベル設立の経緯から、人気ラッパーたちの知られざる一面、レーベル運営で直面した困難まで、日本のヒップホップ史にその名を刻む「フューチャー・ショック」のすべてを赤裸々に告白。
・雷、キングギドラ(現KGDR)、ブッダ・ブランドほか、超豪華メンバーが出演した伝説のイベント「鬼だまり」の熱狂
・SNSもメールもない時代に、電話と郵便とVHSテープだけで作り上げた日米コラボアルバム『Synchronicity』
・マイアミ空港でテロリスト扱いされ、まさかの逮捕!?
・日本語ラップのクラシック『ROLLIN’045』制作秘話と、MACCHOとの横浜ドライブ
・年商1億円を誇ったレーベルが消滅してしまった理由 ほか
〈あらすじ〉
90年代、アメリカに留学していた「僕」はニューヨーク・ブルックリンに移り住み、ヒップホップカルチャーの洗礼を受ける。ザ・ノトーリアス・B.I.G.やKRS・ワンなどと出会うなかで、自らもヒップホップを生業にしようと決心するが、ラップするわけでもDJでもない自身のアイデンティティに苦悩する。
所変わり、現代の東京。懲役から帰ってきた「おれ」は十数年ぶりに“ブルックリン・ヤス”のもとを訪れ、フューチャー・ショックの仕事をしていた当時を振り返る。MACCHOが飼っていたBBという名前のアメリカン・ピットブル、幾度となく語られたヒップホップレーベルの存在意義と未来――。

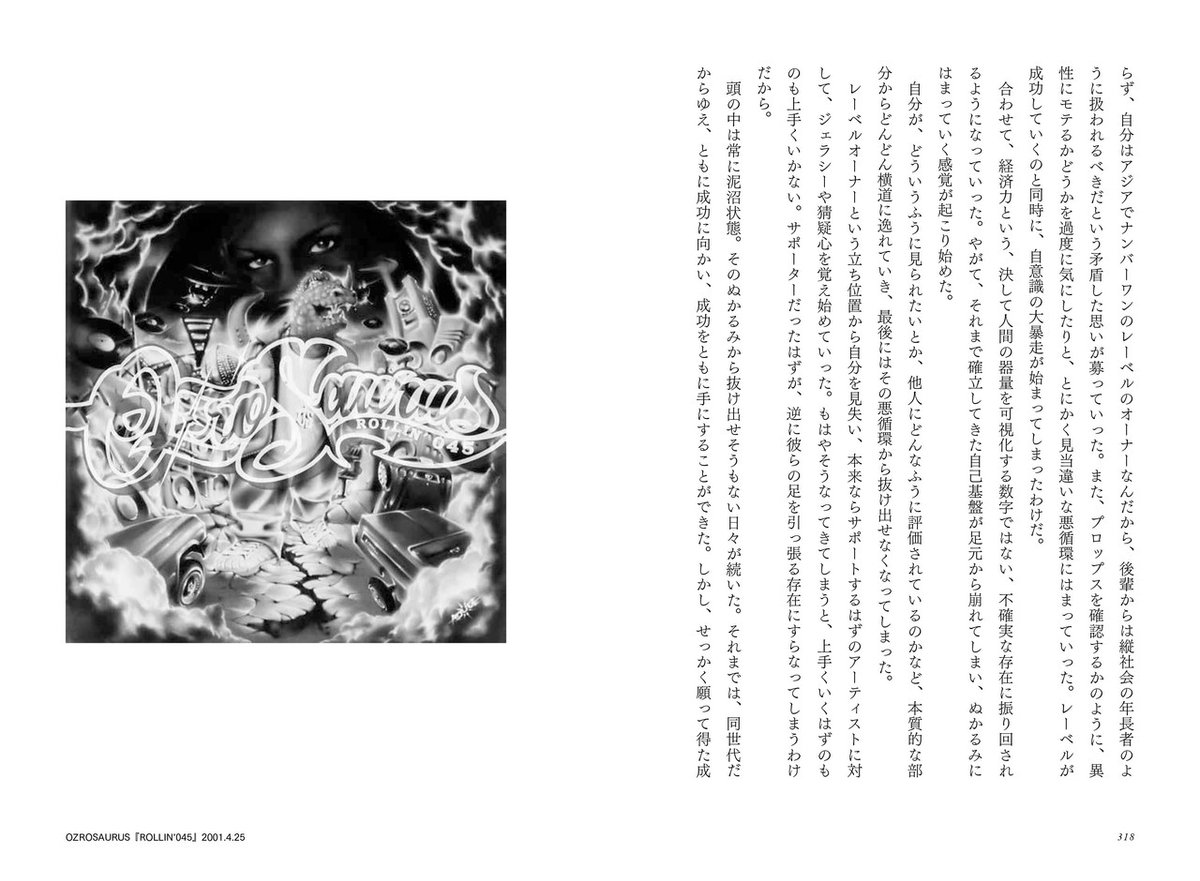
〈著者略歴〉
市村康朗(Yasuaki Ichimura)
1973年生まれ。幼少期を横浜と東京で過ごし、カリフォルニアの小学校に編入。中学を日本で卒業後、アメリカ東海岸の高校・大学に進学する。90年代の“ヒップホップ黄金時代”をブルックリンで体験し、帰国後イベント興行やラジオ番組のプロデュース、アーティストのマネージメントを経て、Zeebraなどを擁する日本初のメジャー・ヒップホップレーベル「Future Shock」を立ち上げる。
現在は、ベトナムでストリートアーティストや多岐に渡るクリエイターを擁するクリエイティブエージェンシー「MAU」を立ち上げ、アジア各国のトップアーティストのコラボ作品制作をはじめ、アジアのストリートカルチャーシーンをつなぐ活動を展開中。
公文貴廣(Takahiro Kumon)
ブックデザイン 森田一洋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
