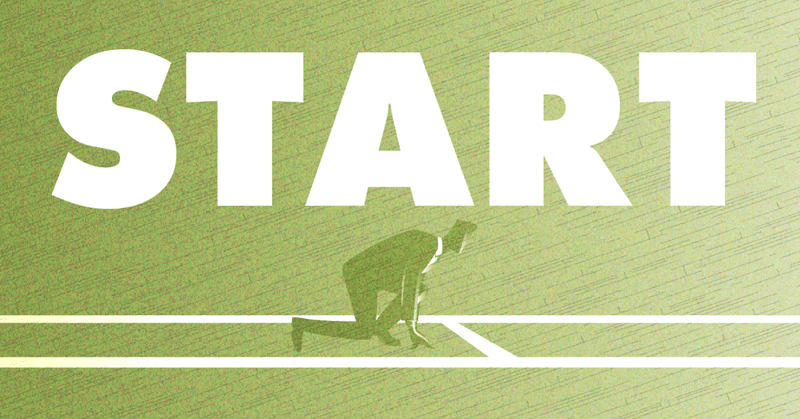
今すぐ実施できるインハウスのやり方
こんにちは。高瀬です。株式会社ハートラスの取締役CSMOとして経営、戦略策定、事業全体を管掌しています。主に手掛けているのは「インハウス支援」です。
前回のエントリーに引き続き、今回は、タイトルの通り「今すぐ実施できる」という視点で書いてみます。
何度か書いていますが、インハウス=完全内製することではないと思っています。とはいえ、どうやって取り組めば良いのか、は私の知る限りオープンにされている情報はほぼありません。
これまでの様々な経験をしてきたので、その経験を踏まえた一つの最適解として受け止めていただけると嬉しいです。
取り組むステップ
いきなりですが、以下内容を整理すれば、インハウスは実行できると思います。
-----------
・インハウスしたい領域を決める
・その領域の業務内容を全て洗い出す
・並行して投下リソースと効率化/削減(されるであろう)できる業務、コストを整理する
・内製化する「範囲」を決定する
・業務設計を行い、実行する
-----------
これで終了です。

もちろん、上記全てを実行するには、社内の承認や各種予算取り、採用など、再現性をもって実行するためにやらなければないことも発生しますが、基本的に上記が網羅されていれば「あとはやるだけ」状態にもっていけます。
これで一件落着と言いたいところですが、やはり抑えるべきポイントが必要となります。具体的な内容は以下をご参考ください。
そもそも、何を目的とするのか
いわずもがな、です。
「何のためにやるのか」が無ければ、よくいう「目的と手段が、、、」という話になってしまいますし、場合によっては「で、どうする?」という最悪の状態になってしまいます。
何事も、まずは目的を明確化すること。これは、インハウスを取り組むことに関しても同様です。
これまで実際にご相談いただいたものや、良く耳にする目的は以下です。
-----------
1.ノウハウや経験を社内に蓄積する
2.よりイニシアティブをもって外部パートナーと物事を進められる状態をつくる
3.PLを改善する(コストコントロールをより可能とする)
-----------
(勿論、こちら以外にも各社の状況に応じた適切な目的はあります)
また、上記目的を達成した先にある「あるべき姿」をしっかりと描いていることも前提となっています。
そして、こういった目的の背景として、考えらえる問題意識はこちら。
-----------
・自社内に知見/ノウハウが溜まっていない
・特にデジタル領域での取り組みに関しては専門性が乏しく、良くも悪くも丸投げになってしまっている
・広告宣伝、販売促進の費用は相当掛けている一方で、販管費とのバランスがとり切れていない
・結果的に、顧客に向き合い、考える時間が割けていない
-----------
私が知る限り、インハウス支援のご相談をいただく際、各社ともに現状のパートナー会社に対し値引きを求めたいわけでは無いですし、大きな不満があって取引を停止したいわけでもありません。むしろ、パートナーシップを組んだうえでしっかりと対価を払いたい、というコメントの方が圧倒的に多いと感じます。
よりスピーディに、よりスムーズに物事を進めるために。教育や採用の強化やPL視点での販管費最適化等を実現するために。
そのためにインハウスを検討し、目的を設定されている会社ばかりです。
対象領域と業務内容を可視化してみよう
目的を明確にしたうえで、まずは「どこの領域をインハウスするのか」を決めていきます。
冒頭にお伝えした「内製化する範囲を決める」という部分にあたります。
一例として、
・広告の「運用」や「オペレーション」
・「制作」や「分析」など、外部パートナーが関わる(であろう)領域のいずれか
・はたまた、そもそもインハウス化をするための土壌づくりとしての「組織の再構築」、「あるべき人材の再定義」、「社内向けの業務整理」など
※こちらのエントリーで、インハウスの「幅」について書いてありますので、お時間のあるときにご参照ください
目的を達成するために、その先にある「理想像」に向かうために、今何が問題となっているのか。いきなり着手するのではなく、まずは問題点を洗い出し、課題を設定してみましょう。
結果的にインハウスすべき対象の領域が見えてくるはずです。
※実際には、複数見出すことになるケースがほとんどです。その場合は、各領域を段階的に着手するスケジュールを引くことが望ましい
そして、対象の領域を選定できたら、次にやるべきは「業務内容を可視化」することです。弊社もそうですが、可視化できているようで、実はしきれていないということは多々あります。
具体的には「業務を細分化」してみることをお勧めます。どのような業務にも、基本的に業務フローが存在します。業務フロー図に落としていてもいなくても、ほぼ必ずと言って良いほどありますね。
例えば結果的に15個の業務が流れて一つの業務が完了するとします。その15個のうち、「どこまでを内製化するのか」を検討/決定するイメージです。
そこまで整理したうえで、「じゃあ、具体的に内製化するためのタスクの洗い出しとスケジュールを決めていこう」となります。

つらつらと書いてしまいましたが、改めてポイントは「対象領域」と「その領域の業務内容を可視化してみる」です。
ここまでくれば、インハウス化(内製化)の再現性が一段引きあがると考えてよいと思います。
業務効率化、削減コストとのバランス
いざ実行する、となるとそれなりに社内の人員、リソースを割くことになります。ここで外部に丸投げしたら内製化の意味がありませんので、むしろ「かけるべき人員、リソース=投資をどこまでとするか」がポイントとなります。
一つの基準として「想定される、削減できそうなコスト」があります。一例として以下が考えられます。
-----------
・既存お取引先との契約内容の見直し
・既存お取引先とのコミュニケーション時間
・社内実行に伴う業務効率化
-----------
インハウス化→多くのリソース確保→コストアップ、というイメージもあるかと思いますが、上記「削減、効率化」部分を加味すると、判断がしやすくなると思います。
これは、1か月、2か月という短期間で完結するものではなく、通期のPLを鑑みて設計することが望ましいと思います。
※注意点として、上記以外にも多数の観点がありますし、コスト削減が目的ではないケースも多々あります。あくまで一例としてとらえていただければと思います。
最後に
今回はインハウスに取り組むステップや考え方を書いてみました。いかがでしたでしょうか?まとめると、こんな感じになるかと思います。

今後も、実際のインハウス化における取組事例含めて、書いていければと思います。
ご意見、ご興味等ありましたら、いつでもご連絡ください。
