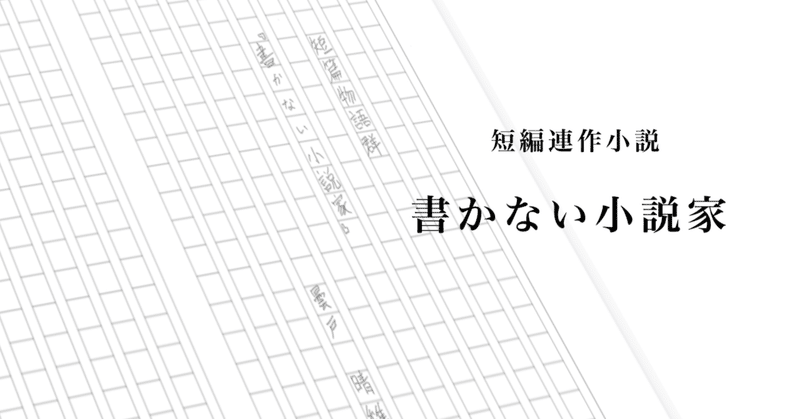
【小説】書かない小説家 三月四日その3【完結】
「妻へのプレゼントでいつも悩むんです。
私はサプライズのようなものが下手で……いつも欲しいと言われたものを一緒に買いに行く始末で」
彼は続けて言うが、私の頭にあるのは忘れていた結婚記念日のこと。
まずい。
非常にまずい。
どうしたものか。
彼の相談にも乗ってやりたいことは確かであるが、最早これは私の問題でもある。
考えろ。
頭を回すのだ。
小説のことなど一旦忘れろ。
さすがに礼替わりに、と言っておいて、この状況を説明するのは恥が多すぎる。
というわけで、私は勤めて冷静に言う。
「無難だが、花束というのはどうだね」
「花束ですか」
「ああ、オーソドックスだがそれ故の効果と理由はある」
自分で言っていてなんだが、うまく的を射ているのではないか。
こういうときは無難なものがいいのだ。
奇をてらうよりも、王道を征く。
王道は王道たる所以があるものだ。
苦手であれば尚のこと。
料理なんかと同じだ。
基本ができないのにアレンジをすれば痛い目を見る。
目の前のこの男。
気風はよく、爽やかで頭も回る。
清潔感に溢れ快活で、見てくれも悪くない。
正直な物言いは人によっては格好つけに見えるだろうが、だいたいの人間の目には誠実に映る。
であれば、余計に王道が映えるというもの。
しかし、この男、考え込んでしまって、いまいち納得していないのではないだろうか。
顎に手をやり、何を考えていることやら。
こういうやつはあれだ。
理論では納得しているけれど、一抹の不安が残っているやつだ。
私もよくなる。
ならば、と、私はひとつ、咳払いをする。
「男はいつまで経っても子どもだが、女は生まれたときから女だよ。
美しいものが嫌いな女性などいない。
まして、それが惚れた男から贈られたものならな。
こんなこと、今どき言うと差別だなんだと怒られるかな……」
紡いだのは、小説の台詞。
小っ恥ずかしいが、こういう時はこういうのが効くんだ。
少しくらい格好つけてて、理屈じゃなくて、なんとなく、そうか、と納得してしまうような。
自分の小説からの引用というのが、最高に恥ずかしい。
成り切るのだ。
絶対に表情を崩すな。
そして不意にかかる声。
「お待たせしました」
妻だ。
どきり、と高鳴る胸。
緊張、焦り、羞恥、そういったものが一気に押し寄せる。
ずいぶんとまあ、タイミングが良いものだ!
だがしかし、ここで曝け出してしまえば、全て水の泡。
耐えろ、耐えるのだ。
「ああ、すまん。入ってきたのに気付かなかった」
「わかってますよ。ちっとも目を合わせないんですから……そちらの方は?」
……『わかっている』に存外の意味が込められている気がする。
こいつ、さてはさっきまでの会話を聞いていて、見計らって声をかけたな!!!
恥ずかしさで表情が崩れる。
ああ、記念日、どうしよう。
そんな焦りもあって、脳内はてんやわんやだ。
しかし、ここは私の格好のため、妻にも付き合ってもらおうか。
なに、この妻だ。
うまく察して、うまくやるだろう。
「ああ、少しばかり話を聞いてもらっていたんだ」
そういうと、僕の方こそ、と言ってくれる彼の言葉を遮って、妻は、偏屈爺だから大変だったでしょう、と続ける。
しどろもどろになる私と彼。
いうにことかいて偏屈爺とな。
間違っちゃあいないと納得してしまう自分が情けない。
「まったく。どうせ何か面倒臭いことでも言ってたんでしょう。
若い人をあまり困らせるものじゃあ、ありませんよ」
おまけにこれだ。
表情は柔らかなのに、目がしっかりと笑っとる。
やっぱり、こいつ、わかっててやっとるな。
ならば、とばかりに少し語気を強めて言ってやる。
「ええい、うるさいな。この通りなんだ、まったく」
「あら、話っていうのは私への文句かしら」
売り言葉に買い言葉。
しっかりと反撃してくる妻に、舌を巻く。
「口の減らん奴だ。もう行くぞ」
こういうときは逃げの一手だ。
彼には悪いが、ボロがでないうちに退散しよう。
コートに手をかけると、妻は、はいはい、と勝ち誇ったような笑みを浮かべ、私と彼の伝票を取る。
スマートに支払いを申し出る妻に、彼もたじたじ。
そうなんだ。こういう女なんだ。
わかってくれ。
問答の末、しっかりと彼にも勝った妻はレジへと向かった。
撤退は、私の都合。
彼への借りは返せたとは思えない。
何より、私は彼が気に入った。
だから……
「まったく。すまないな、恥ずかしいところを見せた」
「いえ、そんなことは」
「ああ、そうだ。君への礼だが、あの程度で返せると思っていない」
本当に、不思議な男だ。
すらすらと心から言葉が漏れる。
「私で力になれることがあれば、連絡を。
忙しいときは出ないが、それも月に十日程度だ。
雑談でも何でもいい。愚痴でも。
それだけのことを君はしてくれたと思って欲しい」
そういって、連絡先を渡す。
年甲斐のない、どうにも偏屈な爺ですまない。
だけど、
「こういう縁は、大切にしたい」
そう伝えると、彼は今日一番の笑顔で、必ず連絡します、と言ってくれた。
そうして、喫茶店を出ると、妻が待っている。
「おまえ、わかっていたんだろう」
「なんのことかしら」
顎に人差し指をあて、はて、とばかりに顔を傾ける。
いい歳だというのに様になるのが憎々しい。
「私の面目というものがなあ」
「いいじゃないですか。私だって少しくらい格好つけたって」
それはそうだが、と口ごもってしまう。
それに、と彼女は続けて、少し遠い目をしている。
ああ、そうだな。
わかるよ。
「息子がいれば、あんな感じだったかもしれないな」
「ふふふ」
「なんだ」
「あなたもそう思ってくれていたのが、嬉しくて」
柔らかく微笑む彼女に敵うわけがなかった。
横に並ぶと、腕を取ってくれる。
そうして、二人で歩きだす。
帰宅後、一息ついた私たち。
よし、と覚悟を決めて、妻に向き合う私。
あら、と背筋を伸ばす妻。
「すまなかった!!」
「へえ、なにがです?」
「結婚記念日……を忘れてました」
敬語になってしまった。
ふぅん、とお茶を啜りながら言われ、冷や汗が止まらない。
こういう時は、王道でいいのだ。
悪いことをしたのだから、謝る。
それが王道……なんとも情けない王道もあったもんだ。
だがしかし、これでいいはず。
きっと。
たぶん。
「若い人を引っ掛けて、格好つけて相談に乗っておいて、その子の話で自分が結婚記念日を忘れていたことに気付いて。
花を贈れ、なんて、わざわざ御自分の小説の台詞まで引用して教えて、その本人は記念日にお花のひとつもなし」
耳が、痛い。
あと、なんだか息も苦しい気がする。
なあ、妻よ。
やめよう。
ちょっと限界みたいだから。
「……なんて、あなたにそんなことを期待しててもしょうがないから、とっくの昔に諦めましたけど」
だいたい、昨日の時点で、この人は絶対に思い出さないってわかってたんです、とか、何年一緒にいると思っているんだ、とか矢継ぎ早に詰め寄られ、どんどん小さくなる私。
「いや、あの、ごめん」
もう出てくる言葉はこれしかなかった。
妻は、はあ、と溜息を吐くと、言った。
「許します。溜飲は下がりましたから」
そして、あっ、と何かに気付いたように続ける。
「ひとつ、無茶なお願いいってもいいですか?」
汚名返上のチャンスをくれるというのなら、願ってもない。
だが、そこは私である。
「できるだけ、叶えられるものだと助かる」
嗚呼、我ながら、本当に情けない。
そして出された、妻の願いは、今までにない願いだった。
しかし、それは確実に私が叶えられるもので、――きっと妻はわかっていたんだろう。
私が今、話したいことだった。
「次の小説、どんなのを書くのか教えて」
そう言って、差し出される灰皿。
ポケットから煙草の箱を出して、一本取り出す。
口に咥え、ライターをつける。
カチッ、と乾いた音がして、火がちりちりと煙草の先を焦がす。
深呼吸するように、すう、と吸い込み、ゆっくりと吐き出す。
目の前には、にこにこと笑う妻。
その笑顔は、プレゼントにもらった絵本を読んでもらう子どもの様。
王道を書きたい。
王道以上に王道なものを。
人の幸せを。
それも、どんどん幸せになるやつを。
読んでいるだけで、人っていいもんだな、こういうのが幸せだよな、って思えるようなやつを。
抗うでも、争うでもなく、ただ自分たちがどう生きるか、向き合うような物語。
挫折や、壁なんて、そんなのはみんな、現実の生活で飽き飽きしているだろう。
だから、こういうこともあるよな、って、ほっ、とするような。
わかるわかる、って自然と思えるような。
精一杯とか、一生懸命とか、命懸けとかでなくてもいいんだ。
みんな、どうにかこうにかやっているんだ、って日常でいい。
今、持っている幸せを、ひとつひとつ拾い集めるような物語。
感動とか、なくていい。
ドラマチックでも、ロマンチックでもなくていい。
私たち、人の営みから見える幸福を噛み締めるような、そんな物語が書きたい。
――いいですね。主人公はどうします?
そうだな。
と、いっても私にそんな深い描写が書けるとも思わない。
誰か。
そう、誰かをモデルにして、書ければいいのだけれど。
今日会った、彼。
あの子は、いい子だったな。
いつか、ああいう男が主人公の気持ちのいいものが書ければいいのだけれど。
――いい子でしたね。今はまだ、書けませんか?
ああ、あの子のような気持ちのいい男は、まだ書けないなあ。
どうしたものか。
私の小説の登場人物はみんな、偏屈になる。
私がそうなのだから、仕方ないのかもしれないが、書きたいテーマに沿っていない。
――ふふふ、あなたは今幸せですか?
幸せに決まっている!
毎日好き勝手にものをして。
書きたいものを書いて、うまいものを食って、呑んで、寝る。
季節の移り変わり、時代の流れ、自分の時間を肌で感じて、ゆっくりと生きている。
かと思えば、時を忘れ、恥も外聞も忘れて没頭できる何かがある。
こうして、私の語りを楽しそうに聞いてくれる、お前がいる。
愛する人が、自分を愛していると実感できる。
それが幸せでなくて、なんだというのだ。
――なら、『あなた』を書けばいいんですよ。
わたしを?
――ええ。偏屈で、変わり者で、それでも大切なものを忘れない。少年のように身を焦がす。そう、小説家を。
そうか。
そうなのか。
お前は、そういうものが読みたいのか。
小説家が、小説家を書く、か。
面白い。
なにより、お前がそういうものを読みたいなら、書くしかない。
私以外の誰が書くんだ。
誰にも書かせてなるものか。
――あなたったら、若い頃と変わっていませんね。
ああ、尽きないとも。
そうだ。
モデルは私でいい。
偏屈な変わった爺。
呑んだくれて、拗ねて、ヘソを曲げて、大人気ない。
そんな男だけれど、私は毎日が幸せだ。
そうだ、幸せなんだよ。
私のことは私がよく知っている。
私が幸せなことは、私がよく知っている。
袖振り合うも他生の縁。
お互い様の心を忘れず。
生きるだけで丸儲け。
そんな精神で生きている。
大事なものは全部ある。
幸せってのは大きいものじゃない。
小さいものの寄せ集めが大きな幸せになるって、常々思っている。
そんな偏屈男の日常なんて、誰が見たがるだろう。
しかし、他でもないお前が見たがってくれるのだろう。
それに、担当のあいつだってきっと喜んで見たがる。
そうして、誰かが読んで、「この人、くだらねえなあ」なんて呆れて、ひと笑いでもしてくれればいい。
――そうね。きっとそれがいい、それでいい。それにあなたは自分が思っているより素敵ですよ。
君といい、今日の彼といい、担当のあいつといい、私の周りには素直なやつばかりだ。
それが、どれだけ素晴らしいことか。
素直でいれることは素晴らしい。
そして、周りがそうでいてくれることがありがたい。
そういう日常が書きたいんだ。
――ええ、私もそういうのが読みたいです。はらはらどきどき、なんてしなくていい。
そうだ。
そういうのは他の作家に任せてしまえばいいんだ。
日々の出来事で、じゅうぶん事件なのだ。
それでいいではないか。
そうだ。それでいい。
ああ、書きたい。
書きたいな。
無性に、書きたい。
――あなたの部屋、そのままですよ。パソコンも、型は古いけど使えるんじゃないかしら。
なに、使えなくても、紙とペンがあればいいさ。
紙もなけりゃあ、頭の中でじゅうぶん。
言葉が溢れてくる。
止まらない。
ああ、書かねば。
なあ、いつもありがとう。
こんな『俺』についてきてくれて。
いつも支えてくれて。
――お互い様でしょう。
愛しているよ。
――ええ、私も。
ちょっと、書いてくるよ。
――ええ。あ、あなた、ちょっと待って。
なんだい
――タイトルは、なににするの?
そうだな。
『書かない小説家』なんて、どうだろう。
――いいじゃないですか。楽しみにしてますよ、先生。
任せとけ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
