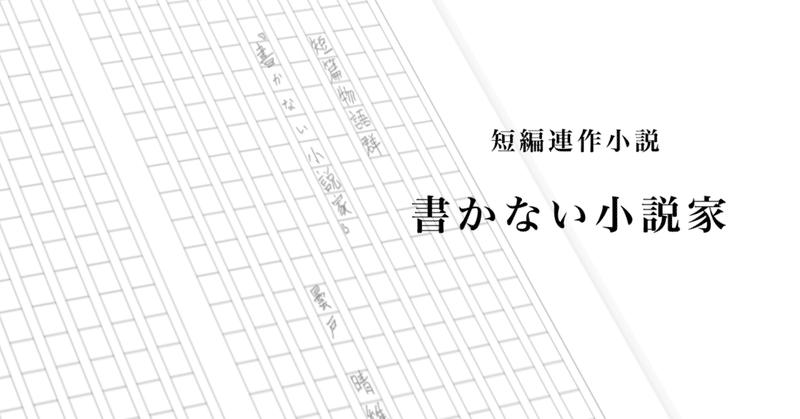
【短編】書かない小説家 三月一日【小説】
2023/03/01
すっきりと目が覚めた。
どれ、とひとつ伸びをしてみる。
パキパキッ、と、小気味いい音をあげる身体。
指、手首、腕、肩、足首、膝、腰、最後に首。
順番に、隅から隅まで、しっかりとストレッチして解していく。
うむ、すっきり。
スマートフォンで時刻を確認すると、なんとまだ午前十時ではないか。
いつもは眠くなったら寝て、目が覚めたときに起きるという生活をしている。
その上、呑みたくなったら呑み、食いたくなったら食うのだ。
こんな時間に起きることは滅多にない。
ふむ、どうしたものか。
そういえば、今日は水曜日である。
そして、水曜日といえば思い出すのが他ならぬ妻のことだ。
生活習慣や性格の違いなどを考慮して互いを尊重した結果、といえば聞こえはいいが我々は現在、別居中。
とはいえ、仲が悪いわけでもないので、本当に言葉通り、お互いを尊重した結果なのだ。
そんな妻が毎週、水曜日に様子を見にくる。
たまに何かを察して突然やってくることがあるが、そういう時は大概、私は執筆に夢中か、風邪でも引いて寝込んでいるので記憶にない。
本宅から、何か食べるものを拵えてきて、邪魔にならぬよう、そっと帰るのは我が妻ながら、なんともできた人だな、と思う。
自分の妻に母親紛いのことをさせているのは気が引けるが、なんだかんだでうまくやっている、はず。
いや、あの気の強く、行動力のある妻のことだ。
嫌であれば、もうすでに紙切れ一枚くらい役所から持ってくるだろう。
そういうことがないくらいには、うまくやっているわけだが、こう考えると心なし、不安になってくる。
そうだ。
たまには本宅に顔を出すのもいい。
そういえば、最後に帰ったのは年末年始。
もう丸二ヶ月も前だ。
このままではこちらが本宅になってしまう。
言葉の意味上、すでにこちらが本宅だが。
などと、若干言い訳がましいことを考えながら、正直になれない自分を正当化した。
そうと決まれば……
いや、どうするか。
用事もないのに顔を出すのも不思議なものだ。
よもや、思いもしれぬことになっているかもしれん。
万が一、あの妻に限ってありえないことだが、男でも連れ込んでいたらどうする。
あれで、妻は器量良し、性格良しで若い時分から、言い寄られていた。
持ち前の気の強さと面倒見の良さから、寄ってくる男は歳下の甘えん坊と、妻の好みには嵌まらなかったようだが。
あいつも、歳をとった。
何かの気の迷いから若い男との火遊び、なんてこともなくはないと思うが、私がこの体たらくなのだ。
愛想を尽かされていても、不思議はない。
ふむ、何か、何かいい言い訳はないだろうか。
と、そこで腹の虫が鳴る。
そういえば、すっきりと起きたはいいが何も口にしていない。
今日に限っては煙草ですら。
一本吸えば、何かいい案でも浮かぶだろう。
そう考えた私は、しゃきっと立ち上がると、台所へ向かう。
箱から取り出し、咥え、火をつける。
すーっ、と、吸い込み、ゆっくりと吐き出す。
目が冴えるような何かを感じるが、これは私がニコチン中毒というだけだ。
それにしても、腹が減った。
とりあえず、腹ごしらえでもするか、と冷蔵庫を開ける
……何もない。
こりゃあ、買い物も行かないとだな。
今日は、何を食うか。
昼、昼……
ううむ。
そういえば、子どものときは、よく母親が昼御飯に焼きそばを作ってくれた。
肉はソーセージやハムで代用した、かつぶしも青海苔もかかっていない、家庭の焼きそば。
待てよ、本宅にはホットプレートがあったな。
と、ここで閃いた。
よし、と、煙草を押し消すと、早速着替え始める。
財布、スマートフォン、近所のスーパーのポイントカード、そしてエコバッグを忘れずに。
そうして準備を終え、意気揚々と外へ出た。
普段、こんな時間に歩くことのない商店街。
こんなにも活気付いていたか、と自分の記憶を探る。
探っても探っても、思い出せるのは夕方ばかり。
どうにも数年単位で午前中にここを通ることがなかったらしい。
手前の魚屋でイカを、次の八百屋でキャベツ、そして肉屋で豚バラを買う。
商店街の端にあるスーパーでキムチやチーズなど、数点を購入。
よし、完璧だ。
商店街から小路地を抜け、住宅街へ。
元から家々が立ち並ぶエリアだったが、しばらく見ないうちに建築ラッシュがあったようで、新築の家が目立つ。
年末に帰ったときには、執筆明けでふらふらだったから、覚えていない。
年明けに別宅に戻ったときも、酔っ払っていてふらふらだったから、これもまた覚えていない。
そうこうしているうちに、本宅へと辿り着いた。
表札は力強い字体で、私の苗字を記している。
知り合いの書道家に頼んで書いてもらい、表札家に頼んで作ってもらった立派なものだ。
拘った門は、重々しく、それでいて気品が感じられる。
プランターに咲く草花は、妻の趣味の園芸だ。
確かに私の家なのだが、なぜか門の前で立ちすくんでしまった。
「一報、入れておくべきだったよなあ」
ひとりごちる。
すると、そこに天から声が聞こえてきた。
「何しているんですか。自分の家の前で」
そう言われて上を見やると、妻がベランダから覗いていた。
洗濯物でも干していたのだろう。
その顔は、笑いを堪えたのが丸わかりで、こちらとしても立つ瀬がなくなる。
「いや、なに、たまにはと思ってな」
「あら、珍しい。早くお入りになってください」
そう言うと、ふふふ、と笑いながらさっさと引っ込んでいった。
この調子なら、迷惑ではなさそうだ。
よし、と、久々に門を開け、玄関に入る。
つっかけを脱いでいると、パタパタと妻がやってきた。
「ただいま、でしょ?」
「ああ、ただいま」
「はい、おかえりなさいませ」
気恥ずかしい。
これでは、久々に実家に帰ってきた子どもと親である。
そんな私をよそに、妻は、あら、こんなに買って、とエコバッグを覗いていた。
ああ、ダイニングテーブルにでも持って行ってくれ、と言うと、よっこいせ、と担ぎ上げていく。
私が持つべきだったなあ。
別宅とは違い、明るい家。
陽がよくとりこめるようにと、デザイナーが頑張ってくれた我が家。
どうにも落ち着かなくて、どうしようもなかったが、こうやって来る分にはやはり、落ち着く。
洗面所で手洗いうがいを済ませ、キッチンへと向かう。
「なあ、ホットプレートって使えるかな」
「ええ、棚の横にありますよ。ちょっと待ってください。埃被ってますから」
いそいそと雑巾を取りに行ってくれる妻に申し訳なくなる。
やはり、一報入れるべきであった。
箱の埃を拭き取り、ホットプレートを取り出す。
こいつもしばらく使ってなかった。
「何か食べたいものがあるのでしょう。言ってくれれば作るのに」
「なに、たまにはな」
そう言って、私は台所に立つ。
勝手知ったるなんとやら。
小麦粉と粒状出汁、それにお玉やボウルを取り出す。
イカと豚肉は先に切って、火を通す。
キャベツは微塵切りにしてボウルへ。
別のボウルに、水と小麦粉を五対一くらいで入れ、しっかりと溶く。
「冷蔵庫、開けてもいいか」
「ご自分の家で何を遠慮しているんですか。いいに決まっているでしょう」
テレビを見ていた妻が、やれやれ、と言った様子でぴしゃりと言う。
そんなに強く言わなくてもいいじゃないか。
と、思いながら冷蔵庫からウスターソースを取り出すと、先ほど作った生地に入れる。
そして、ホットプレートの電源を入れ、鉄板に熱が伝わるのを待つ。
そうだ、あれを出さなければ。
確か、この辺に。
「なに探しているんです?」
「ヘラ、あったろ」
「ああ、それなら……」
ゴソゴソと奥の方から取り出したのは、耐熱プラスチック性の小さなヘラ。
そう、私が作っているのは、もんじゃ焼きだ。
「あなたがこれを作るの、久しぶりね」
「まあ、なんだ、たまにはな」
熱の入った鉄板で、イカとキャベツを混ぜながら焼く。
適当に火が入ったところで、土手を作って、生地を流し入れる。
土手が決壊しないように混ぜながら生地に火を通して、いい具合になったら全部ぐちゃぐちゃに混ぜ合わせてしまう。
「よし」
「ああ、いい匂い」
いただきます、と二人で言って、食べ始める。
「美味しい」
こんな、料理とも言えないもので、これでもかと笑顔になってくれる妻。
それが嬉しくて、気恥ずかしい。
「今日は、どうしたんですか。御握り持っていこうと思っていたのに」
「邪魔だったか」
「そんなわけ。嬉しいんですよ」
そうか。
そうか……
「あ、そうだ。あなた、キムチ、買ってましたよね?」
「ん、あるぞ」
「じゃあ、試してみようかしら」
台所へと向かう妻。
それにしても、嬉しい、か。
思えば、最近、ろくに妻をかまってやったこともなかった気がする。
旅行に行ったり、買い物を一緒に行ったり、そういうことをしていたのは何年前だったか。
もしかしたら、妻も妻で不安だったのかもしれない。
こんな広い家で、たった一人で。
そう思うと、なんだか涙が溢れそうになってきた。
「あなた、これ、入れてみましょう?」
そう言って妻が持ってきたのは、チーズ、キムチ、餅。
は?
それを入れるのか?
もんじゃに?
はてなマークが出て止まらない私を見て、くすくすと妻が笑う。
「結構、巷じゃ定番らしいですよ」
ほ、ホントかあ〜?
不安になる私をよそに、さっさと二つ目を作り始める妻。
ほどなくして出来上がったそれを見つめる私。
まあ、キムチもチーズも発酵食品だ。
餅だって、最近はグラタンにしたり、洋風にしても美味いっていうじゃないか。
「ほら、どうぞ」
ううむ。
意を決して、食べる。
ほほう。
なかなか。
これは。
「美味いな」
「でしょう?」
あ、この顔、こいつどっかで食べたことあるな。
そんな私の心中を察してか、妻が言う。
「園芸サークルの仲間と一緒に行った居酒屋ですよ。あなたの思うようなことなんてなんにもありません」
ぴしゃり、と言う妻に、呆気に取られてしまう。
「そんなことより、たまにでいいから、こうして帰ってきてください」
素直に言う、その顔は、出会った頃と変わらず、気の強そうな、自信満々の綺麗な妻だった。
「ここは、あなたの家なんですから。いつでも」
そう続けたときの顔は、少し憂いを帯びて、寂しそうだった。
「うん。なるべくそうする」
「期待しないで待ってます。さ、食べましょう」
そうして、ゆっくりとした時間を過ごす。
うむ、やはり、こういう時間は大切だし、良いものだ。
だから、今日は絶対に書かない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
