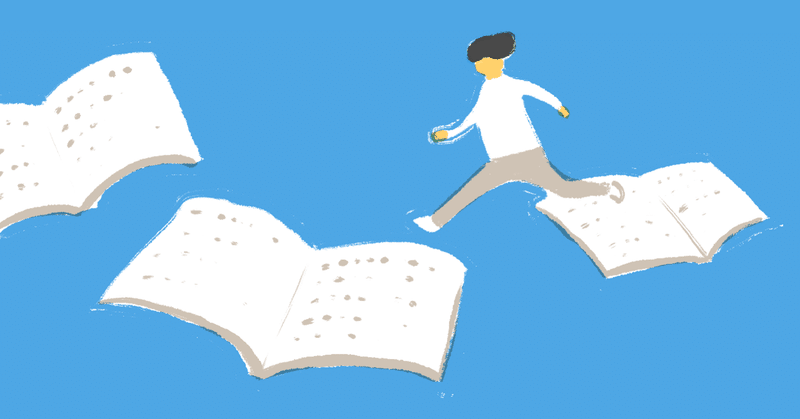
2つの図書館を持つー読書感想#31「読んでいない本について堂々と語る方法」
ピエール・バイヤールさん「読んでいない本について堂々と語る本」は読書を豊かにする本でした。読んでいない本を語るには「2つの図書館」を意識する。第一の「共有図書館」を持っていれば、「見晴らしよく」本を語り、教養人として振る舞える。一方で「内なる図書館」。誰かと共有できない「内なる書物」が詰まっている。二つの図書館を持ったとき、もっと率直に、読書に向き合えるようになる。
中身を知るより「位置づける」
「読んでいない本について堂々と語る本」は、千葉雅也さんの「勉強の哲学」を読んで初めて知った。千葉さんは「読書の完璧主義の主義を治療する」本として紹介して、その要諦をこう伝える。
バイヤールによれば、読書において本質的なのは、本の位置づけを把握することです。
たとえば、ハイデガーの『存在と時間』は、二〇世紀の哲学において決定的に巨大な業績である。『存在と時間』は、フッサール現象学を背景に、ハイデガーが独自の方向を提示したものである。いまの説明では、大まかに哲学史における重要性を言い、そして、他の哲学者との関係でどういう位置にあるかを言ったわけです。(「勉強の哲学」p172)
読書において本質的なのは、本の位置づけを把握する。千葉さんの言うようにこれこそが、バイヤールさん流「読んでいない本について堂々と語る」方法です。
例にあるように、「存在と時間」という本は、哲学史における位置や、ハイデガーとフッサールの関係を把握すれば、その中身について語れる。極論すれば、この位置さえ知っていれば、実際に中身を読むことさえ必要ない。
この考え方は「図書館」という施設の特徴でもある。図書館は、無数にある本を分類し、配置することでその本の意味を明確化する。司書さんは全ての本を読んだことはないだろうけれど、それぞれの本がどんな本かは的確に答えることができるだろう。
さらにバイヤールさんは、一冊の本を読む上でも「位置づけ」が重要だと語る。
「全体の見晴らし」という概念は、なにも図書館の蔵書だけに適用されうる概念ではない。それは一冊の本をひとつの全体として考えた場合にも有効である。図書館のなかで自分を見失わない教養人の能力は、一冊の本の内部でも同じように発揮される。教養があるとは、一冊の本の内部にあって、自分がどこにいるかをすばやく知ることができるということでもあるのだ。(「読んでいない本について堂々と語る本」p39)
もしもその本で語られている中身をうまく「位置づけられる」なら、その本を理解したということ。だから、本を読み切るとか、一語一句覚えることは重要ではない。たとえ流し読みでも、断片的に読んでも、その中身のポイントが見通せるなら、それは「読んだ」ということだ。
「位置づけ」さえ明確なら、本について語れる。つまり、人と本を語るということは「共有図書館」について語るということである。
内なる書物
本書はここからさらに面白くなる。バイヤールさんは「共有図書館」とは別に「内なる図書館」も存在することを語り始める。
例にとられるのが、人類学者ローラ・ボハナン氏とアフリカのティブ族との対話(p125~)。ボハナン氏はティブ族の前で「ハムレット」の中身をレクチャーする。しかし、人々はいちいち突っ込み、物語はなかなか進まない。
たとえばハムレットが父親の亡霊に会ったシーンで、ティヴ族の人々は「亡霊とはなんだ?」と立ち止まる。「死んでいるが話せる存在。でも触れられない」と説明しても「ゾンビは触れる」と反論する。「ゾンビじゃない。魔術師に使役させられてるのではなく自ら動いている」と言えば「死人は歩けない」。「亡霊とは死者の影だ」と言い換えても「死者に影はない」と終わりがない。
バイヤールさんはこの現象をこう解説する。
ただ、彼らはたしかにこの戯曲の内容に関して自分たちの考えを表明するが、かといってその考えは、戯曲を知ると同時にできあがったものでも、それよりあとに生まれたものでもない。それは極端にいえば戯曲を必要とすらしていない。彼らの考えはむしろ戯曲を知る前からでき上がっていたのである。つまりそれは、ひとつの体系として組織された、ある世界観の総体を形づくっているのであって、そのなかにシェイクスピアの作品は迎え入れられ、場を得たのである。
(中略)私はこの神話的、集団的、ないしは個人的な表象の総体を〈内なる書物〉と呼びたい。(p135)
ティヴの人たちは自分たちの世界観にハムレットを迎え入れる形で、読む。「内なる図書館」にある「内なる書物」は、その人にとって大切な世界において独自に編まれるものであり、ここでもやはり、本そのものとは必ずしも一致しない。
「共有図書館」が知的世界の「位置づけ」ならば、「内なる図書館」は個人的世界の位置づけと言える。だから、ハムレットを西洋社会で当たり前のようにティヴの人たちに読んでもらうことは難しい。
かといって、ティヴの人たちはハムレットを理解していないわけではない。むしろ、彼らなりの世界観で受容しようとしている。だから自分たちの世界には存在しない亡霊とは何かに、あそこまでこだわる。
本を語ることは「位置づけ」さえ分かればある意味簡単だ。一方で本当の意味で読む、「内なる書物」に付け加える試みは、格闘とも言えるものかもしれない。
読書のパラドックス
人と語り合うときは「共有図書館」を使い、じっくり本と対話するためには「内なる図書館」に招き入れる。これだけでも読書はずいぶん豊かになるはずだけど、最後にもう一つ、「読書のパラドックス」という概念を紹介したい。
読書のパラドックスは、自分自身に至るためには書物を経由しなければならないが、書物はあくまで通過点でなければならないという点にある。良い読者が実践するのは、さまざまな書物を横断することなのである。良い読者は、書物の各々が自分自身の一部をかかえもっており、もし書物そのものに足を止めてしまわない賢明さをもち合わせていれば、その自分自身に道を開いてくれるということを知っているのだ。(p263-264)
バイヤールさんはなぜ「本を読まずに堂々と語る方法」を思索したのか、その答えがこのパラグラフに垣間見える。本を読んで自分自身の創造性に還元するためには、本を「通過」しなければならないからだ。
もしも一冊の本に拘泥すれば、その本を位置づけることはできない。すると「共有図書館」は空疎になる。あるいは、その本を完璧に受容しようとすれば、「内なる書物」とコンフリクトする。すると結局は「内なる図書館」は貧困になる。
書物を経由しなければ自分自身には至らないが、書物を通過点にできなければ自分自身は豊かにならない。このバランスを取りながら道を歩くことが、読書家の道ということなんだろう。「共有図書館」と「内なる図書館」に一冊ずつ本を差し入れていく。そういうイメージでこれからも活字の海を泳げたらいい。(大浦康介さん訳。ちくま学芸文庫、2016年10月10日初版)
次におすすめする本は
内沼晋太郎さん「これからの本屋読本」(NHK出版)です。大小関わらず、本屋になるにはどうすればいいかを考える本。そもそも本屋とはなんだ?という思索は、読書の本質を探るバイヤールさんの姿に重なります。
千葉さんの「勉強の哲学」の読書感想はこちらです。こちらは学ぶとはどういうことか、絶望せずに学び続けるための方法が学べます。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
