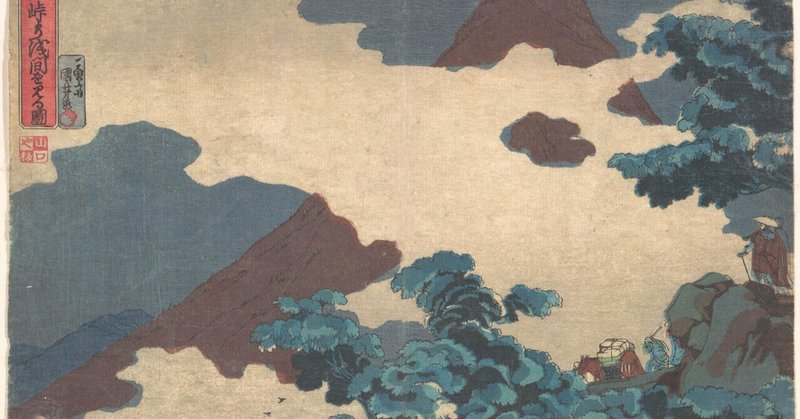
百姓は多彩な起業家だった?ーミニ読書感想「日本の歴史をよみなおす」(網野善彦さん)
歴史学者・網野善彦さんの「日本の歴史をよみなおす」(ちくま学芸文庫)が面白かったです。タイトル通り「読み直す」。つまり、私たちが日本の歴史になんとなく抱くステレオタイプを問い直し、歴史史料からその実際を検討する。これが、意外な日本の歴史像に触れられて大いに楽しかった。
その一つが、本エントリーのタイトルに挙げた、「百姓は必ずしも農民ではなく、マルチな活躍をする起業家だった」という仮説です。
本書で扱うのは、南北朝時代や室町時代など中世の日本で、主には江戸時代以前の日本の在り方。日本史に対するステレオタイプは、江戸時代や明治時代以降の日本の姿を元に、それと対比する形で中世を認識していることが原因なのかと思われます。
百姓と聞くとまずは農民の姿が浮かぶ。しかし歴史文書の中には、たとえば百姓が製塩などほかの生産活動に従事し、さらに東北や北海道の方へ向けて輸送船を操っていた姿が描かれている。すごくマルチな活躍をしていて、現代で言えば個人事業主や起業家に近い印象です。
ではなぜ百姓=農民のイメージが浮かぶかと言えば、歴史史料の多くは国家制度の必要上残しているもので、古代から日本は「農業を律令制の基板に置いた国家」だったから。つまり、年貢の取り立ては基本的に農作物とし、管理のための書類も田畑にフォーカスしたものだったのです。
こう考えると、所有する土地の少ない、あるいは取れ高の少ない痩せた土地しか持たない「貧しい百姓」の歴史像も揺らいでくる。その百姓は農業はそこそこに、他の事業に取り組んでいただけかもしれない。人々の豊かさを問い直すことになる。
これがとっても刺激的。本書では他にも、「江戸時代以前は、女性は男性と肩を並べる力を持つこともあり、決して抑圧されているばかりではなかった」ことなども取り上げられます。家父長制が日本の歴史というわけではないんだと驚かされます。
こうした発見は、歴史史料を丹念に、かつ虚心坦懐に見つめるからこそ見えてくる。見ること学ぶことがいかに難しく、でも楽しいかを実感します。
つながる本
先日このnoteで取り上げた内山節さんの「日本人はなぜキツネにだまされなくなったか」(講談社現代新書)は間違いなく繋がります。日本人は1965年を境にキツネに騙されなくなった、というユニークな歴史仮説を検討する本です。比較的薄くて読みやすい。
感想はこちらに書きました。
丹念に向き合うこと、といえば橋本倫史さんの「ドライブイン探訪」(ちくま文庫)を。かつて日本の車社会の象徴だった飲食宿泊施設ドライブインを巡って、経営者らの声を聞き取ります。
これも感想をアップしていて、こちらです。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
