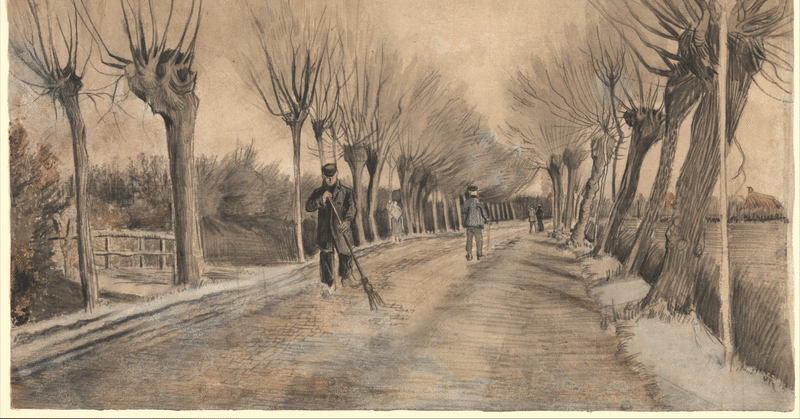
「良く迷う」ための手引書ーミニ読書感想「哲学の門前」(吉川浩満さん)
文筆家で編集者でユーチューバーの吉川浩満さんの「哲学の門前」(紀伊國屋書店、2022年9月5日初版)が面白かったです。哲学を専門的に学んでいるわけではないという吉川さんは、自身を「門前の小僧」ととらえる。本書は哲学書の入門書ならぬ「門前の小僧による門前の小僧のための哲学門前書」(p12)と銘打ちます。私は「良く迷うための手引書」と読みました。
著者の文章は自由闊達なところが魅力です。思考ものびのびとしている。あえて「門前の小僧」を自称する著者は硬軟問わず、東西幅広くさまざまな話題を取り込み、自由な議論を展開してくれる。
そして、その言葉には心地よい迷いがあるのがいいのです。
本書後半で、著者とユニットを組む山本貴光さんに関するエッセーがあります。その中で、「山本さんに嫉妬を抱くか」という問いを検討する。著者はこう回答します。
私が山本くんに対して嫉妬の感情を抱くことはあるか。あるなしで言えば、ある。おおいにある。だが問題は、嫉妬のあるなしよりも(なかったら不思議な部類の事柄である)、それがどのような嫉妬なのかだ。
嫉妬はあるなしで言えばあるどころか、おおいにある。一方でカッコ書きで「なかったら不思議でしょ」とささやかな言い訳をはさむ。その上で、問題はある・なしではなく、嫉妬のありようなんだと問いを再設定する。これが吉川節です。
問題に対して明快に答えつつ、ちゃっかり一言添える。あっちにいったりこっちにいったりしながら、問いを再設定する。
著者は考える手掛かりに、作家大西巨人氏の「三位一体の神話」という小説を持ち出す。この作品は売れっ子作家が、売れない作家の才能を羨み、殺人に及ぶという作品だそうだ。普通は売れない作家が売れっ子作家を攻撃しそうなものなのに、逆転している。まさに嫉妬の恐ろしさを物語る作品です。
著者は「いけない。ついつい「三位一体の神話」の話が長くなった」と恒例の脱線を挟みながら、こう述べる。
(中略)私には真の作家であるための資質が欠けているのか、大西巨人の描く井上光晴(と読める登場人物)の嫉妬殺害に至る心理がよく理解できない。そういうわけで、幸運にも山本くんを殺さずに済んでいる。
では、どのような嫉妬なのか。晴れてメジャーデビューを果たしたバンドをインディーズ時代から見守ってきた古参ファンの心理を想像してもらうのがわかりやすいと思う。
幸運にも殺さずにすんでいる。なんて軽妙なのか。クスリと微笑んでしまった。
実際は、後段の「メジャーデビューを果たしたバンドに対する古参ファンの心理」を持ち出せば、それがすなわち答えなわけです。しかし、著者は、あえて「違う方向」にいくし、その寄り道の際に古典作品や文学作品を補助線に、思考を深める。これが「哲学の門前」の思考法の要諦だと思うのです。
門をくぐらずに、あっちへこっちへ行ってみる。しかしその際に、門の向こうにありそうな骨太な作品を手掛かりにしてみる。こうやって迷う時の迷い方は、なんと豊潤なものかを感じさせてくれます。
本書では、民族性(エスニシティ)やジェンダー、政治、仕事などなど、さまざまな話題でこうした迷い方を実践してくれている。どれも大変に面白いです。
つながる本
吉川浩満さんの存在を知ったのは、山本貴光さんとのユニットで発表された「その悩み、エピクテトスならこう言うね」(筑摩書房)でした。ストア派哲学者エピクテトスを現代に「召喚」するという方法で、その思考法を味わう。門前の小僧たちがどうやって哲学に向き合っているかが分かります。
さまざまな人文書を二人が語り合う「人文的、あまりに人文的」(本の雑誌社)もおすすめです。まるでラジオのように、人文の名作楽しめます。
「哲学の門前」では、批評家の故加藤典洋さんへの敬愛が語られていますが、私は吉川さんと加藤さんはどことなく似ているように感じます。なので、加藤さんの文章に触れるとつながるものがある。最初に手に取るのであれば、「村上春樹は、むずかしい」(岩波新書)なんかはどうでしょうか。
それぞれ感想は下記エントリーにまとめました。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
