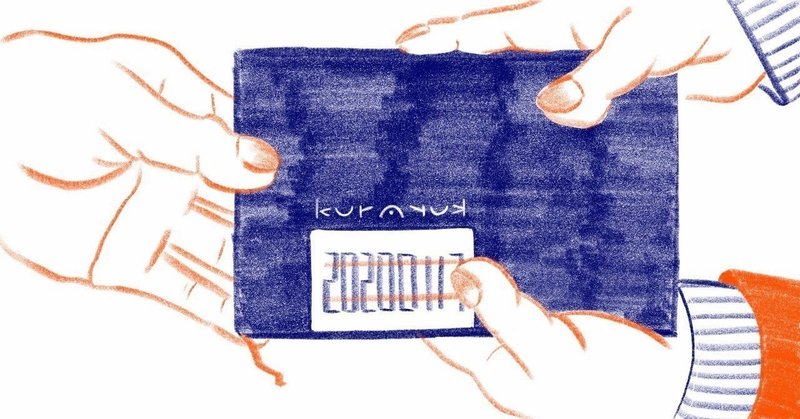
この本に出会えてよかった2019
2019年に読んだ本のうち「出会えてよかった」と思った10冊をまとめました。「ためになった」でも「役に立った」でもなく、出会えてよかった。この物語を思い返すことで、また明日も生きていこうと思える。この学びを羅針盤に、今日も考え、行動していける。そんな本たちです。
「なめらかな世界と、その敵」
この世界にずっと浸っていたい。伴名練さんのSF作品集「なめらかな世界と、その敵」はそんな物語でした。「なめらかさ」がその特徴。SFというと設定の複雑さに気構えしがちですが、本作は、どれもすっと物語に入っていける。気付けば着地している。そして文章が美しい。すーっと読者を綺麗な風景に連れ出してくれる。
最後に収められた「ひかりより速く、ゆるやかに」が最も胸に残りました。ある日、走行中の東海道新幹線が急に止まってしまうトラブルが起きた。しかしよく見ると、その車両は止まっているのではなく極めて動きが遅くなっている。「低速化」という原因不明の災害だった。新幹線の中の時はゆっくり進む。目的地にもたどり着く。このペースなら、2700年後に。
旅行に参加しなかった主人公の語りで物語は進みます。友達や、思う人を置き去りにしたまま迎えた卒業式。死ではなく時の隔たりによって断絶し、目の前にいるのに言葉すら交わせない日々。痛みと不条理を繊細に描いてくれます。そして、もちろんSF。主人公はなんとかして低速化災害を解明し、新幹線を救い出そうとする。この物語を思い出すと、自分の日常を抱きしめたくなります。
「暴力と不平等の人類史」
本書のメッセージはあまりに強烈で、あまりに残酷です。それは「歴史上、人間社会に平等化をもたらしたのは平和ではない。むしろ、戦争や革命、政権崩壊、疫病の発生が要因である」というものです。
筆者は歴史学・人類学が専門のウォルター・シャイデルさん。戦争がもたらした平等化の実例に挙げられるのは第二次大戦後の日本で、だからこそ納得感が大きい。大量の戦死と、既得権の解体によって、富裕層の資産が9割近く下落したことを証明しています。それによって、戦後の一億総中流社会を構築できた。
暴力が平等をもたらし、平和はそうではなかったことを頭に入れておくと、なぜ現在の日本で格差が拡大するかを理解がしやすい。そして裏を返すと、格差が我慢ならないレベルまで高まった時、平等を求める層が暴力に訴えることは「合理的」だと言える。平和を享受するためには貧困対策が重要だと認識しました。
「『ついやってしまう』体験のつくりかた」
打って変わってライトでポップなノンフィクションですが、学びは同じくらい深い。ズバリ「人がついやってしまうことには、仕掛けがある」です。筆者が玉樹真一郎さんというのが説得力がある。玉樹さんは任天堂でプランナーをされていて、「Wii」の担当でもあった。まさに「ついやってしまう」のプロです。
たとえばスーパーマリオを思い浮かべてください。画面の左端にマリオがいる。右側に土管があったり、ブロックがあったり。この構図によって、何の説明を受けてなくても、「つい」右側へマリオを動かしてしまう。そして右へ動かすと、風景が推移する。やっぱり合っていた!この一連の「仕組み」は「直感のデザイン」と言い、「右に動けそうだ」という「仮説」、実際に動かす「試行」、風景が動いたりストーリーが進展する「歓喜」がセットで設計されている。
玉樹さんはさらに「驚きのデザイン」「物語のデザイン」という仕組みも解説してくれます。面白いのが、実はこの本「そのもの」が、全てのデザインを体現した作りになっていること。つまり、本書の読書体験そのものが「つい読んでしまう」ように仕組まれているのです。
「平場の月」
こんな恋愛小説が読みたかった、と思いました。恋愛小説であっても、青春小説ではない。主人公となる男女は50歳に差し掛かる壮年期。しかも、お互いに事情を抱えて故郷に出戻ってきました。明るい未来とはじける若さがある二人ではない。でも寄り添っていく姿に、深い深い愛を見出せます。
「平場」というのがキーワードです。そこには上昇も、成長も、生産性も、自己実現もあったもんではない。なんとか日常を生きていく。そこで見上げる月の光。この物語が描いている希望は、そんな淡さがあります。朝倉かすみさん著。
「アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した」
一方でこのノンフィクションがあぶり出すのは、ジリジリとした苦しみです。原題の「HIRED」を大きく変えていますが、邦題が実にしっくりくる。ジャーナリストの著者ジェームズ・ブラッドワースさんが、イギリスのアマゾン倉庫やウーバーで実際に働いてみた内部告発ルポです。
テクノロジーを駆使して圧倒的な便利さを実現するこうした企業が、実は働く人の「尊厳」を犠牲にしていることが分かります。たとえばアマゾンの倉庫では、トイレ休憩さえ「アイドル・タイム(怠けている時間)」とみなされる。トイレに行く時間さえ削って生産性を上げろ。本当に生産性を考えるのならば、トイレを数多く設置すればいいのにそれはしない。だから倉庫には、黄色い液体の入ったペットボトルが転がるような始末だということです。
重要なのは、こうした「非人間性」を生み出す共犯者は、自分たち消費者でもあるということ。これには参ります。このブログにも、やっぱり便利だからアマゾンの書籍ページをリンクしてしまう。つい、やってしまう。
「21Lessons」
「労働から尊厳が奪われる」ことを、もっと大局から論じて、整理してくれるのが本書です。著者は説明不要のユヴァル・ノア・ハラリさん。2019年は「今更で恥ずかしいけど」と思いつつ「サピエンス全史」「ホモ・デウス」と本書を読みましたが、もし同じように尻込みしている方には本書をお勧めします。今更だと思っても、絶対にハラリさん作品は読破した方が良い。それほど透徹した論考です。
「21Lessons」を最初のハラリ作品として推したい理由は、3作品の中でも「現在」にスポットを当てているからです。「サピエンス全史」は過去(といっても人類が農耕を始めた頃レベルの過去)、「ホモ・デウス」は未来がテーマで、「21Lessons」はまさにその中間。たとえばトランプ政権や、フェイクニュースをどう考えれば良いのか。そういう身近な大難問にヒントをくれます。
それでいて、ハラリ人類学のキーポイントである「言語の役割」「想像力の重要性」「無用者階級の誕生」もきっちり収まっている。本書の一番の学びは「現代社会に起きる変化は、あらゆるSFが的外れになるレベルの変化である」ということ。本書を読めば、脱社畜をしてAI社会に乗り遅れるな!とかいった煽りが、きちんと馬鹿馬鹿しく思えるようになります。
「説教したがる男たち」
現代社会の必須科目として「フェミニズム」は外せない気がしています。でも、一体何から読んで学べば良いのか?その答えは、レベッカ・ソルニットさんの「説教したがる男たち」ではないかと思います。
メッセージの根幹は「性犯罪の根元には、性犯罪を許容するカルチャーがある」。ソルニットさんは端的に「レイプカルチャー」と呼びます。レイプカルチャーを追跡していくと見えるもの。それが「説教する男」です。由来はソルニットさんの実体験。ある男性と話していると「あなたの探求分野では、この本が重要だよ」と説教を始めた。なんとその本の著者がソルニットさんだったのです。つまり男性は、目の前の女性が自分に学びを与える存在のはずがないと決めつけていた。
フェミニズムとは、レイプカルチャーを打破すること。それは男女同権という紋切りではない。ある属性の人間が「上から抑圧されて当然の存在」とみなす風潮を一切解消しようと努力することだと、本書は教えてくれます。
「死にがいを求めて生きているの」
朝井リョウさんの傑作小説なんですが、ある意味でノンフィクション的。それはこの物語のテーマが「承認欲求」だからです。朝井さんは平成という時代を「相対評価から絶対評価へ」という切り口で捉えている。つまり「自分で自分を承認しないといけない」。これは実は難問ですよ、というのを教えてくれるのが本作です。
承認欲求に苦しむその人物は、こんな風に語ります。その苦しみが少しでもピンとくる方は、本作を開いて損はないと思います。
「俺、自分のためにやりたいことも、誰かのためにやりたいことも、何もないんだよ」(中略)
「昔みたいに決められたルールがないと、自分からは何も出てこないんだ。小学校で俺の言いなりだった奴も、中学で俺より頭悪かった奴も、俺より偏差値低い大学行った奴もみんな、ルールが変わった次の世界で俺を抜いていった。●●(※実際は人物名)のバイト先で集まって飲んでた社会貢献人間たちも、次の生きがい見つけて楽しそうに活動してる。もうこうなったら、あいつらとは違うやり方で戦うしかない。同じところに居続けたら、どんどん進んでいくあいつらに笑われ続けるだけだ」(p397)
「言い訳」
新書から1冊を選ぶとしたどれだろうと思った時、本書が頭に浮かびました。しかもよく考えると、この本は面白いだけじゃなく、他人の物差しで幸せを測れなくなった現代にどう生きるかを教えてくれる気がします。タイトル通り、関東芸人のナイツ塙さんが、「どうしてM-1は関西芸人が強いのか」を「言い訳」する内容。
とにかく刺さったのが「笑い脳」という一言。塙さんは「笑いが自分の才能だとは思わない」と言うのです。脳に酸素が不可欠なように、笑い脳の人は笑いのことを考え続けてしまうそうです。つまり塙さんは、好きなこと、得意なことを仕事にしたんではなく、「やらないと生きてけない」ことを仕事にしたわけです。裏返すと「やり続けることが苦にならない」というか。このスタンスって、とても参考になると思いました。好きを仕事にしなくたって、才能を探さなくったっていいんだなって。
そんな笑い脳の塙さんが語る言い訳は、どれも生き生きしていて「血の通った言葉ってこういうことか」と思わされます。しかも、昨年のM-1でなぜミルクボーイさんやぺこぱさんが躍進したかを説明できてるからすごいです。
「羊飼いの暮らし」
このノンフィクションは2019年最初に読みました。そして1年が終わっても感動は色褪せない。タイトル通り、イギリスで伝統的な羊飼いの暮らしを引き継いでいるジェイムズ・リーバンクスさんの手記です。ただ一味違うのは、リーバンクスさんはオックスフォード大で学び、自分の生き方を相対化した上で、「あえて」羊飼いの伝統に飛び込んでいる点です。
今も胸に残るのは、「長い長い鎖の小さな輪」という言葉です。引用します。
(中略)山は人を謙虚にさせ、人間の尊大さや勘違いを一瞬のうちに根こそぎにする。私は共有のフェルを利用する牧畜業者のひとりであり、歴史の浅い小規模な農場の運営者にすぎず、長い長い鎖の小さな輪でしかない。おそらく一〇〇年後には、私が羊を山で放牧していたことなど、なんの意味もない事実になる。きっと、私の名前を知る者は誰もいなくなる。しかし、そんなことはどうでもいい。一〇〇年後もファーマーたちが同じフェルに立って同じ仕事をしているとすれば、そのほんの一部を作り上げたのは私なのだ。いまの私の仕事が、過去のすべての人々の働きの上に成り立っているように。(p396−397)
羊飼いの暮らしの真髄は、歴史に名を残すことではありません。目の前の伝統は、これまでの無名の大勢の暮らしによって編み上がったものである。その長い長い鎖の小さな輪に、自分も連なることが本望なんだ。リーバンクスさんはそう語る。たしかに本当の幸福は、自分より遥かに大きな何かへ貢献することなんじゃないか。他人より秀でよ、市場価値を高めよ、という声が聞こえない日のない今の日本で、この思いは暖炉の火のように心を温めてくれました。
以上になります。2020年もたくさんの本を読んでいきたい。もう2月になっちゃって今更かとも思いましたが、noteさんになら、書いてみてもいいかも。そんな気がして筆をとりました。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
