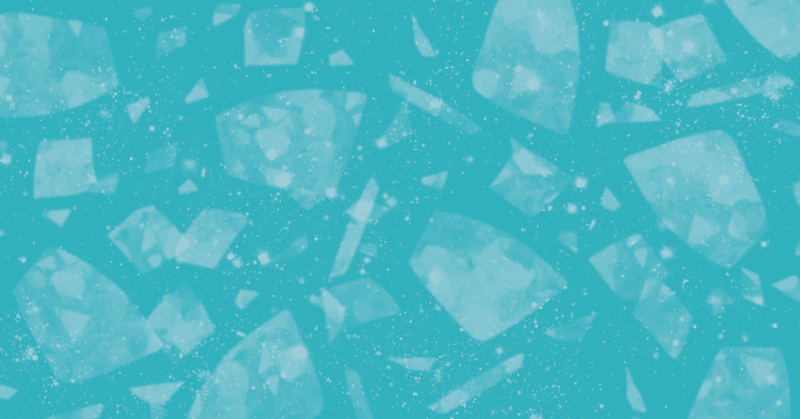
サイダーみたいな旅行記ーミニ読書感想『イスタンブールで青に溺れる』(横道誠さん)
40歳で発達障害が判明した(診断された)文学研究者、横道誠さんの『イスタンブールで青に溺れる』(文藝春秋、2022年4月28日初版)が面白かったです。発達障害が関連して生じる独特の感覚を言語化し、その感覚を持って世界中を旅した経験をまとめた旅行記。読むことで、独特さを少し追体験できるような気がしました。
その不思議な読み心地は、サイダーを連想しました。喉の渇きを癒し、甘みが嬉しいと同時に、シュワシュワとした泡が刺激を起こし、何とも言えない浮遊感を呼び起こす。サイダーみたいな旅行記だ、と思いました。
たとえば、『アルプスの少女ハイジ』のモデルになったとされるスイス・マイエンフェルトを訪れた時の話。著者は発達障害ゆえに、山道で「ゾーン」に入ったと語ります。
(中略)発達障害があると過集中という意識状態に入りやすい傾向がある。定型発達者が問題なくできる作業が、発達障害者には難度の高いものになるため、集中力が爆発的に跳ねあがるのだ。この結果、心理学で「フロー体験」と呼ばれるものが生まれる。大きなうねりに流されているような神秘的な感覚。スポーツ選手はこれをよく「ゾーン」と表現し、自分の身体能力が飛躍的に上昇していると感じる。
僕の歴史は、そうした歩行の歴史だ。マイエンフェルトで「ハイジの道」を歩いていたときも、もちろん同じように歩いた。長大な山道で、僕にとってはかなりの運動量になったから、ふだんよりも負担は大きかった。だからゾーンに入りっぱなしだった。
発達障害ゆえにゾーンを体験しやすいという事実が、まず「へえ」と思わされる。著者は非常に明快に、冷静に自身の障害や感覚を捉えていて、それを淡々と読者に伝えている。だから、著者の特有の感覚とそれによる経験がどんなものか、読んでいてクリアにわかる。
その一方で、本書には独特のリズムがある。引用した二つ目のパラグラフの「僕の歴史は、そうした歩行の歴史だ」がそう。突然「僕の歴史」という時空をすっ飛ばすワードが飛び出し、時間感覚を揺さぶられる。それでいて歯切れがいい。
著者の障害には、こだわりや、関係ないものの突然の連想が含まれる。たぶんそれが、リズムの独特さにつながっている。
旅行記といえば、美しい風景や珍しい体験がつまったもの。でも本書はそれだけでなくて、著者の感覚や連想といった「内面世界」としばしば接続する。それが読みどころになっています。
たとえば後半のロサンゼルスの章では、ある瞬間からほとんどマイケル・ジャクソン氏の話になる。著者の深い思い入れが爆発し、「マイケル氏と著者」の過去の思い出に飛躍する。いきなりそんな展開になったら「何のこっちゃ」となりそうなのに、不思議と、引き込まれてしまうのでした。
発達障害に関心がある人はもちろん、ない人も、この浮遊感(ふわふわ感)を楽しめると思います。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
