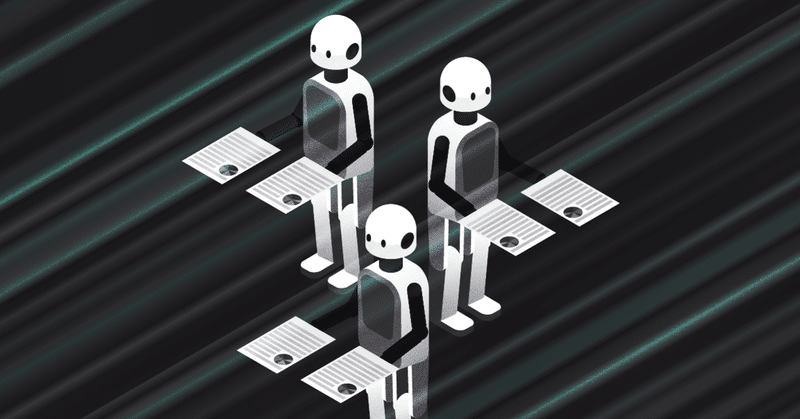
「次世代ガバメント」が視界をクリアにする(本の感想6)
若林恵さん責任編集「次世代ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方」が刺激的でした。若林さんの放つ言葉は視界をクリアにする。今回は「なぜいま行政機構が機能不全に陥っているのか」「じゃあどうしたらいいのか」という問いを、考えやすい形に言語化してくれる。
脱「生物歯車」
政府、市町村、官僚機構がなければ、現代はこんなにも豊かになってはいない。でも今となっては、多様化する問題に対処しきれているようには思えない。それはなぜなのか?それは「機械的」に構築した行政組織を動かすのが「機械ならざる人間」だから。
若林さんは「生物歯車」という言葉を使います。
いかに無表情にロボットを装ってみたところで、その「生物歯車」は時に集中力を欠けば、気も散るし、むしゃくしゃすることもあれば、ついつい悪心や出来心を起こしてしまったりもする。(中略)にもかかわらず近代の行政システムは、人に機械であることを求め続ける。なかなか酷なシステムだった。システムがシステムとして作動するために、人が無色透明な機械であることを、それは要求し続けるのだ。(p19)
本来、複雑化する課題に対応すれば機械そのものも複雑化する。スマホをイメージすればいい。でも、行政機構の生物歯車は、どこまでいっても人間だ。行政課題が複雑化し、国民のニーズが多様化しても、人間が「超人」になれるわけではない。結果として、公務員はどんどん過酷な労働環境に追い込まれる。
だから本書では、生物歯車を本当の機械=テクノロジーによって補完することを模索する。それこそ副題の「小さくて大きい政府」なんです。
「アウトプット」から「アウトカム」へ
機構改革から見れば「脱生物歯車」となる次世代ガバメントを、「ユーザー側=国民側」から見るとどうだろう?ここでのキーワードは「アウトカム」です。
「アウトカム」は「アウトプット」とは違う。本書のメインコンテンツ「仮想雑談」で、こんな問答が収められている。
アウトプットがゴールになってしまうことの別の問題を言いますと、そうなってしまうと正しく評価ができないんです。
ーーと言いますと。
アウトプットがゴールになっていると、アウトプットが完成したら、それで一〇〇%達成じゃないですか。
ーー「できた!おしまい!」ですよね。
それって評価できないですよね。つくることがゴールだとすると、つくることが終わってしまったら「よくできました」としか評価できません。(p142-143)
アウトプットは「作る側」の視点でしか語っていない。「行政の側」の発想であり、アウトプットを考える限り、「やったもん勝ち」になってしまう。では、アウトカムとはなんなのか?
ですから、プロジェクトに関わるみんなが共有しなくてはいけないのは、「アウトカム」の方なんです。「起こしたい変化」を実現するために、本当にそのサービスプログラム=アウトプットでいいのか、と考えるのがロジックモデルにおいては基本的な筋道ですので、アウトプットは、そういう意味では二義的なものでしかないんです。(p142)
アウトカムは「受け取った側」に起きる「変化」である。これは「国民の側」の話。重要なのは、政府がどんな政策を行うかではなく、その政策が国民にどういう作用を及ぼすか。
「国民の望む変化」が多様化しているのが現代である。そう考えると、従来のアウトプットでは希望あるアウトカムが出ないのも頷けます。だから、アウトプットからアウトカムに思考を変えていくのが大切。
ヒントはもう目の前にある
若林さんの話が面白いのは、行政の話に行政的な言葉を使わないからだと思います。むしろ、テクノロジー企業、スタートアップが意識している理論を応用する。脱生物歯車は、アプリの活用として既に実装されている。アウトカム思考は、「UX」とか「カスタマーサクセス」と言われていることだと思います。
そう考えると、行政改革のヒントは「目の前」にある。遠大な理想を持つことはもちろん大切なんだけど、日々やっている仕事、楽しんでいるエンターテインメントにヒントを探してみる。そういう「思考法」自体が、とても次世代ガバメント的な、大事なツールだと感じました。(2019年12月9日初版、黒鳥社発行、日本経済新聞出版社販売)
次におすすめの本は
加藤典洋さんの「村上春樹の短編を英語で読む」(ちくま学芸文庫)です。加藤さんが村上作品のうち短編に絞り、長編名作につながる問題意識の萌芽だったり、村上さんの思考の変化を分析します。英語で読むと書いてありますが、本編は全部日本語。行政は全く関係ないですが、作品の読み方をガラッと変える解釈力・言語化力は、「次世代ガバメント」と同じくらいの刺激があります。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
