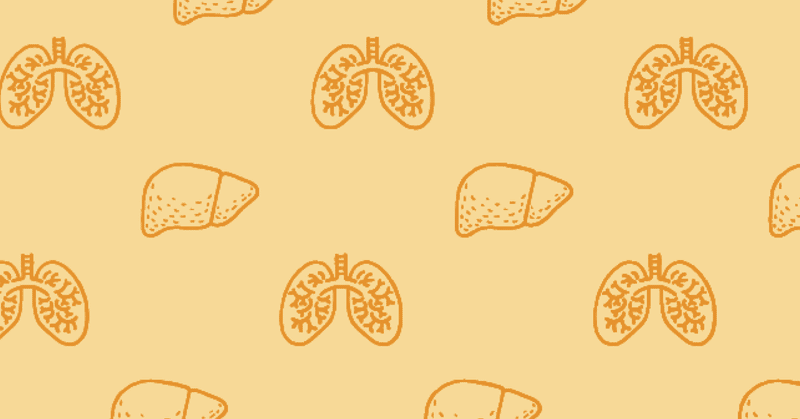
能力は臓器ではないーミニ読書感想「『能力』の生きづらさをほぐす」(勅使川原真衣さん)
組織開発の専門家、勅使川原真衣さんの「『能力』の生きづらさをほぐす」(どく社、2022年12月25日初版発行)は、メリトクラシー(能力主義)全盛の現代に必携の「お守り」になりそうです。2020年から乳がん闘病中という勅使川原さんが、いつか自分の子どもたちが会社で「無能」の烙印を押された時を想定。我が子に、能力の幻想性や、メリトクラシーとの付き合い方を指南します。
本書のパンチラインを一つ記憶するとすれば、タイトルに選んだ、「能力は臓器ではない」。まるでその人に備わっていて、あわよくば「鍛えられる」とも考えがちな能力だけど、そうではない。
では、能力とは何なのか?正確に言えば、我々が「あの人は優秀」「力がある」「使えない」などと語る時、それは何について語っているのか。
それは、「機能」だと著者は言います。
母さんがクライアントによくお伝えするのが、車の「機能」の例え。人によって、あるものごとへの選好性、つまり選びやすさや好みってのはある。「リーダーシップ」って一般的には人の先頭に立って旗を振るイメージだよね。それって、車で言えば「アクセル」や「方向指示器」の機能とも言い換えられる。でも、「アクセル」や「方向指示器」だけあれば、安全に走る車、つまりは、良い組織と呼べる? 冗談じゃないでしょ? 車は「ボディ」や「タイヤ」がなければ、走れない。走ったら走ったで「ブレーキ」がなかったらどうするよ?
だから、キャッチーで訴求しやすい「能力」のレベルを測ろうとしたり、みんなを一つの同じ「能力」獲得に向けて競争させたりって、むしろ危ない橋を渡っているように母さんには思えるの。どう安全に走る車として「機能」を担い合っていくか、っていう視点が大事だと思うんだ。
私たちが人を「使えない」と切り捨てる時、実際には「エンジンとして機能しない」「ブレーキとして弱い」と機能面での不備を言うべきであることが分かります。「使えない」と思ってる人も、実は違う役回りであれば活躍するかもしれない。能力で見るとその不足は個人の責任ですが、機能で見れば同じ事象が組織の問題に置き換わります。
臓器としての能力に着目するのは残酷です。それは時に、肝臓が強くない人に、無理やりお酒を飲ませて「強くする」ような事態を招きかねない。臓器は人間と不可分である以上、臓器の否定は「その人そのもの」の否定に繋がり、全体の毀損につながる。このように、「能力は臓器ではない」というメタファーは、パワーハラスメントの抑止に極めて効果的であると感じます。
自分があえて「能力は車の機能である」というメタファーではなく、「能力は臓器ではない」という否定系のメタファーを本書のパンチラインに挙げたのは、もう一つ理由があります。
それは「能力は○○である」という言説が、まさに能力が持つ幻想性の再生産につながり得るからです。
本書では、能力の「起源」について、「あの人はなぜ有能なのか?」という経営層の疑問に応えるために導入された科学的分析だと言及します。つまり、私たちが苦しむ「能力」もそもそも、何らかの苦悩を解決する「アンサー」として登場したわけです。
だからこそ、「あなたの悩んでいることへの答えはこれです!」という言説は、次の「能力」につながる。警戒すべきなのです。
この観点を持って本書のタイトルを見返すと、「生きづらさを解決する」ではなく「ほぐす」になっているのです。「解きほぐす」ですらなく、単に「ほぐす」。著者は、子どもたちが抱く「なぜ苦しむのか?」を、解決するのではなく、理解しやすくしているだけなのです。
本書の後半ではこのことが、著者のがん闘病体験と共に「葛藤という影とともに生きる」というキーワードで語られています。ここは必見の読みどころです。
能力は臓器ではない。だから私たちは、人の臓器を揶揄するような能力論議に気をつけなければならない。では能力とは何で、能力神話とどのように付き合っていけばよいか?その疑問には「機能」の概念を足がかりにしつつ、安易には答えに飛びつかず、迷いながら歩いていこう。
そんなメッセージを受け取りました。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
