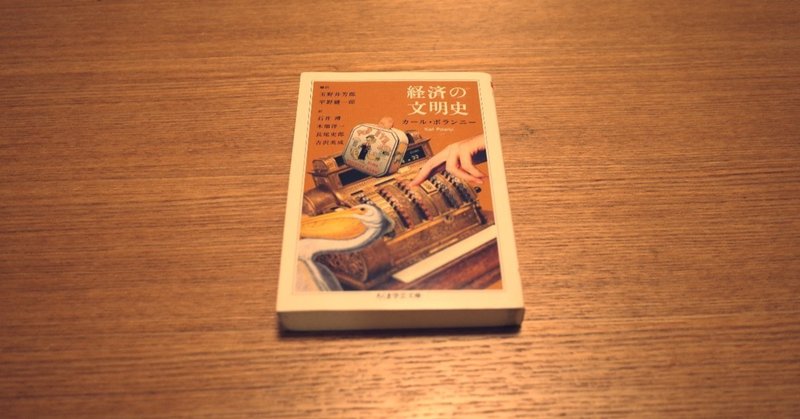
読んだ本たち③ー今はあくまで今であって
最近読んだ本たち。経済だったり資本主義だったり、今あるものはあくまで今の姿なんだなと感じました。なんとなく理解できそうな「反知性主義」の根本的な意味が実は違ったり、やっぱり歴史を学ぶのは大切。
①「経済の文明史」(カール・ポランニーさん、ちくま学芸文庫)

経済人類学者、という変わった肩書きの学者さんの本。「実は経済って、もともとは社会の『中』にあったんだよ」という話が中心になります。生産性とか、個人のブランディングとか、今は社会の「大枠」に経済があるような感覚になるから、実に新鮮な指摘でした。
たとえば、労働力。ポランニーさんは、「市場って、商品を売り買いする場所だよね。商品って、売るため、買うためのものだよね」という話から「でも人間って、働くって、そもそも売るためにも買うためにもなかったよね」という指摘をします。でも労働が「市場化」されて、いつの間にか「労働力を売って、金銭を手にする」ことが普通になった、という。
これによって「労働力を提供できないと金銭ができない」ことがスタンダードになってしまう。中世、あるいは部族社会では、あくまで社会を支えるために働いていたのに。そうして何が生まれたかというと、貧困だったり飢えだったりする。働かざるもの食うべからず、という。
これは土地と貨幣にも言える。ただそこにある自然=土地も、交換をスムーズにするための貨幣も、もともと商品じゃなかった。なのに商品にした先が今で、それは別に昔から永久不変じゃなかった。こんな警句が胸にしみました。
人類は、野蛮人時代には与えられていた弾力性、想像の豊かさや力を、もはや取り戻せないほどのところまできているのかもしれない。(p67)
②「さらば、GG資本主義 投資家が日本の未来を信じている理由」(藤野英人さん、光文社新書)

「ひふみ投信」を運営するレオス・キャピタルワークスの最高投資責任者、藤野さんによる批判&提案本です。タイトル通り、企業トップがあまりに高齢化かつ硬直化することの弊害を語りつつ、じゃあ若手や中堅はどうプレーしていくべきかを考える内容になっています。
面白いなあと思うのは、藤野さん自身、リーマンショックが直撃した2008年にレオスの業績を悪化させた責任をとって、社長を解任させられているということ。もう一度「平社員」から実績を積み上げ、再び社長をされている。辛酸を舐めているからこそ、「会社の経営者」が成長を生み出そうとせず「会社の管理者」になっていることを批判する声が、すっと胸に入ってきます。
藤野さんはキーワードに「虎」をあげる。群れをなして秩序だつライオンのような働き方から、群れを飛び出して狩りをする虎のように。それは、群にいながらも虎になることはできる、ということでもあります。藤野さんは起業家や野心的経営者に加えて、組織にいながらチャレンジをする人を「トラリーマン」と定義して、第三の道として推してくれます。
重要なのは、会社を変えることではありません。一歩を踏み出すことによって、あなた自身が変わること。(p150)
③「反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体」(森本あんりさん、新潮選書)

反知性主義の歴史をたどる本。もともとはアメリカのキリスト教史の中で登場した言葉で、単なるインテリ批判という意味ではないそうです。
森本さんが「熱病」と指摘するように、反知性主義というのは、既存の教会や牧師といったキリスト教の権威が、自らの知性を省みなくなって「権力化」することへの反発で、それは時に劇的な現象になります。その根っこには、キリスト教との平等主義があります。神の前では人はみな同じ、ということですね。
この平等主義が面白い。宗教的に正しいこと、神に報いることは、人間が「ありのまま」持ち合わせているのであって、そこに学力とか出自は関係ない。でも、あくまで平等なのは「宗教上」なんですね。だからアメリカという国は資本主義大国にもなる。平等なのは宗教上であって、金銭的な不平等は問題ではないから。
トランプさんという大富豪が、大衆のヒーローとして躍り出てきたのも、この辺りが作用している気がします。彼が金銭的に優位者であることは問題ない。ただ「なすべきことをなす」存在として、既存の権力への反発の格好の看板になったんだろうな、と感じました。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
