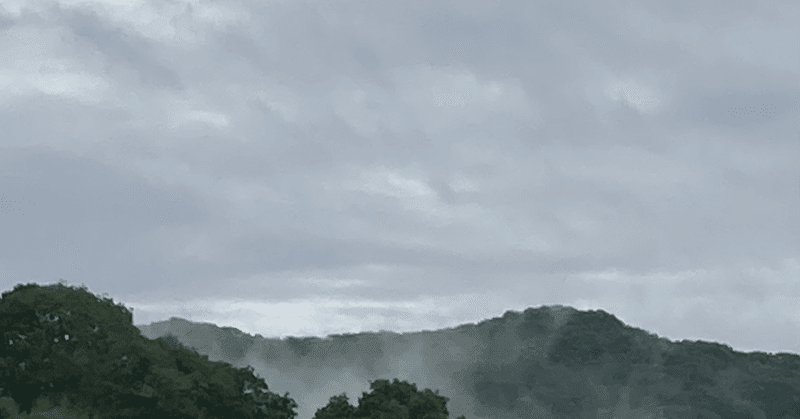
踏みにじられる側から描く戦争ーミニ読書感想「ある日 失わずにすむもの」(乙川優三郎さん)
乙川優三郎さんが2018年に刊行し、2021年に徳間文庫に収録された連作短編集「ある日 失わずにすむもの」が切なかった。近未来、勃発した世界規模の戦争に分断される各国の人々の日常を描く。踏みにじられる側、殺される側から見える戦争の景色を淡々とした筆致でつむぐ。
解説でも言及されている通り、わざわざ英語で付された副題が「twelve antiwar stories」であることは胸に留めたい。これは明確な反戦小説だ。
「戦争小説」であれば、踏みにじられる生と同様に生き残る生や、殺し合う生、そうした戦争を仕掛ける権力者など、多層的な描き方がある。あるいはある種、戦争をエンタメ化し、生きるか死ぬかのカタルシスを読者にぶつける方法もある。
しかし本書は反戦小説であって、ひたすらに戦争の理不尽さと無情さを描く。そこに救いはない。
巻頭を飾る「どこか涙のようにひんやりとして」では、米国で貧しい暮らしにあえいでいた黒人少年がなんとかジャズ演奏に救いを求めるが、軌道に乗りはじめたところで徴兵される。物語はそこで終わる。断絶だけをただただ描写する。
「偉大なホセ」では、倹約し寡黙に生きてきた男性が召集されたとき、自分のために祈る村人の姿を目にし、心が動かされる。それは救いともとれなくもないが、戦場で命が失われる運命は変わらない。あまりに心もとない救いではないか。
戦場で命を落とす人たちを語る一方、意図的に「描かれないもの」がある。なぜ大戦が起きたのか。どの国とどの国がなぜ争っているのか。それらの説明は一切ない。これがコントラストとなって、主人公たちの小さな背中がはっきりと浮かんでくる。
いま、ロシアがウクライナに仕掛けた戦争もまさにそうではないか。なぜこんな戦争をしたのか、釈然としない。出口は見えない。本書に登場するような人たちが、彼の国に実在することに思いを馳せずにはいられない。
タイトルの「ある日 失わずにすむもの」が何なのか、読後も分からない。失ってばかりの物語を、ただ抱きしめることしかできない。
つながる本
かなり昔に読んだ記憶で朧げながら、ティム・オブライエンさんの「本当の戦争の話をしよう」(文春文庫)に読み心地が似ているように思います。
本書より希望の色合いが濃いですが、須賀しのぶさん「革命前夜」(文春文庫)も思い起こされます。
近刊では、日露戦争や日中戦争の描写が生々しい小川哲さんの「地図と拳」(集英社)ともつながると感じました。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
