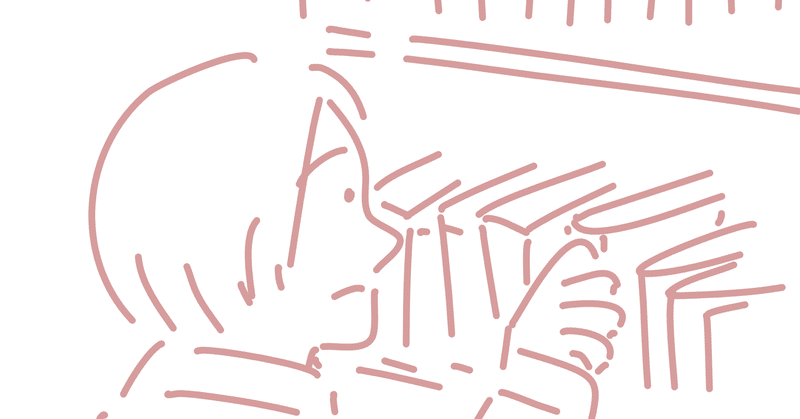
この本に出会えてよかった2020
本は、今年もそばにいてくれた。気軽に本屋に行けなくても、きままに立ち読みできなくても。当たり前がすっかり崩れた毎日の中で、本は少し先の未来を照らしてくれた。身近にある小さな喜び。遠大な歴史に存在する教訓。こことは全く異なる世界のあり方を、教えてくれた。年末に抱く思いは、去年のそれと変わらない。この本に出会えてよかった。そんな10冊を紹介します。
①「なぜ私だけが苦しむのか」
タイトルが目に入り「今の自分の気持ちだ」と手に取った。様々な場面で同じ思いを感じた方は多いのではないかと想像します。
著者H・S・クシュナーさんはユダヤ教の神父にあたる「ラビ」で、幼い自分の子どもが難病にかかり、命を落としている。「神はなぜ自分をこんな苦しい目に遭わせるのか」。この問いに自ら直面したクシュナーさんは、深く深く悩まされる。
「お子さんを神が欲したのです」「この試練には理由があるんだ」。ありきたりなどの教えにも納得がいかなかった。出来る限り善く生きようとした自分が、懸命に生きようとした子が、なぜこんな苦境に遭うのか。その答えにはなっていないと思った。そうして悩み抜いた末に、クシュナーさんは旧約聖書の「ヨブ記」にたどり着く。そして、「不条理」と「神の存在」を両立するような考え方を見出した。
その考え方は非常に納得のいくものだった。神が存在した上でも不条理が起こることを、明快に整理できるようになる。それはつまり、「なぜ私だけが苦しむのか」という泥のような問いを抜け出すヒントを得られるということ。もしもこの難問に苛まれる方がいれば、ぜひ開いてほしいし、67ページまで堪えて読んでほしい。岩波現代文庫、斎藤武さん訳、2008年3月14日初版。
②「そして、バトンは渡された」
2020年、最も祝福に溢れた小説でした。
主人公の優子は、ポジティブでも、「逆境に屈しない」という強さを持ってるわけでもない。その独特のキャラクターは最初の一行で示される。
困った。全然不幸ではないのだ。少しでも厄介なことや困難を抱えていればいいのだけど、適当なものは見当たらない。いつものことながら、この状況に申し訳なくなってしまう。(p8)
優子は幼い時に母を亡くし、継母と海外赴任する実父の板挟みにあった末に継母を選び、その後も何やかんや、いくつもの「親」の間を転々としている。なのに、それを不幸だとは全く思わない。それはポジティブさとも違う。我慢強さとも。本当に、ナチュラルに、不幸だと感じないのだ。
その優子の姿勢に勇気をもらう。いまの現実は「つらくない」と思うのが難しい。実際につらい場面がたくさんあるけれど、つらくないときもある。そんな時に表情を切り替えにくいし、「つらい」と声を上げる人が大勢の中で朗らかに過ごすのは少し気まずい。優子は、はっきり「全然不幸じゃない」と言ってくれる。その姿はちょうど良い陽だまりみたいだ。
なぜ優子はのほほんとしていられるのか。物語を読み進めると、そこにはそれぞれの親が一心に注いだ「愛情」があることがわかる。その愛情もまた、型にははまらない。見方によっては冷徹に見える愛情もある。人の、家族のありようはさまざまだ。そんな祝福が物語のひとかけら、ひとつまみに溢れている。著者は瀬尾まいこさん。文春文庫、2020年9月10日初版。
③「深夜高速バスに100回ぐらい乗ってわかったこと」
スズキナオさんは何でもないことに幸せを見出す天才だ。そんな人に出会えたことは本当にありがたかったです。
たとえば、老舗のラーメン屋の大将の話。銭湯のシャワーのところに広告を出した話。自分の父親と飲んでみる話。どれも「自分にもできる」ような気がするけど、きっとナオさんのように柔らかくは受け止められない。だからこそ、読後感は風呂上りのように、固くなった筋肉がほぐされるような思いがある。
改めてどこが好きかと思って読み返すと、まえがきが一番かもしれないと思う。
(中略)思うようにならず、息苦しさを感じることもある毎日の中で「まあ、まだまだ楽しいことはあるよな」と少しでも前向きな気持ちになってもらえたら嬉しい。(p7)
まあ、まだまだ楽しいことはあるよな。そのくらいでいいんだと思う。人生は。スタンド・ブックス、2019年11月22日初版。
この本は、SIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERSさんのオンラインストアで購入した。本屋に行けなくてもこんなにも素敵な本に出会えるという経験も、得難いものだったと思う。
詳しい読書感想はこちらです。
④「日没」
この小説は決して希望を抱かせるものではない。それでも、決して胸を離れない。読んだことを忘れたくないという気持ちがこびりつく。
主人公の小説家・マッツ夢井は突然「文化文芸倫理向上委員会」という機関から「召喚状」を受け取る。有無を言わさない呼び出しに仕方なく応じると、案内された先は断崖絶壁に立つ「療養所」だった。そこでマッツは軟禁状態に置かれ、自分の作品について「反省」を迫られる。
なぜ反省すべきかと言えば、マッツの作品には暴力的な性表現があり、「まるでそうした暴力を肯定している」と読者から「告発」があったからだ。療養所所長の多田は、そうした読者の声を根拠にマッツを激しく糾弾する。
(中略)先生方が無責任に書くから、世の中が乱れるということがわかっていない。猥褻、不倫、暴力、差別、中傷、体制批判。これらはもう、どのジャンルでも許されていないのですよ。昨日は言いませんでしたが、先生は文芸誌の対談で、政権批判もされてますよね。いえ、否定しても証拠がありますから。私たちは、ああいうことはやめて頂きたいんです。ええ、心の底から。作家先生たちには、政治なんかには口を出さずに、心洗われる物語とか、傑作をものして頂きたいんですよ。映画の原作になるような、素晴らしい物語をね。先生はどうして書けないんですか。ノーベル賞とは言いませんから、せめて映画原作くらいの本を書いてくださいよ。何であんな異常な小説ばかり書くのですかね。絶対に変ですよ。(p110)
「日没」のすごさは、この「反転」にあると思う。自分はどちらかと言えば、普段は多田に近いことを思っている。官能小説の類は読まないし、まさに「心洗われる物語」を好む。でも、もしもその考えを相手に強制したら。こんなにも醜悪なことはないと、多田の語りが浮き彫りにする。
一部の読者が批判した作家を軟禁し、思想の「更生」を強いる。この世界は、今の社会と地続きだ。それに気づいた時、身震いする。不倫や暴力がどのジャンルでも許されない。そんなものより、マーケットに評価される良作を量産せよ。そういう声を上げているのは現実では多田ではなく、私たちではないか。著者は桐野夏生さん。岩波書店、2020年9月29日初版。
⑤「日の名残り」
不要不急の外出は控えてと言われると、1時間も2時間も本屋さんにいることが憚られる。でも急いで選ぼうとするほど、うまく決められない。確実に面白いであろう、有名な作家さんの作品を手に取りがちで、本書もそうした選び方の末に対面した。だけれど、本当に、手に取ってよかった一冊でした。
英国で長年、執事の仕事に邁進していたスティーブンス。第二次世界大戦を終えて、いまや屋敷の主人は米国人になった。そんなとき、少しの暇を与えられた彼は、かつて同僚だった女性を車で尋ねることにする。物語は、道中にスティーブンスが書き綴った手紙を読者が開く形式で進む。
道中は決して長くはないし、特殊ではない。でも屋敷にこもりっきりの生活が長かったスティーブンスには新鮮に映る。そして一つ一つの情景が、積み重なった職業人生を振り返るきっかけになる。手紙は回顧を含み、やがて、「執事とは何か」という哲学的な問いにも向かっていく。
たしかに執事の大半は、いろいろやってみても、結局、自分は駄目だったと悟らざるをえないのかもしれません。が、それはそれとして、生涯かけて品格を追求することは、決して無意味だとは思われません。(p49)
スティーブンスの丁寧な文体も、出会う景色も、語られる思い出も、全てが美しい。そして、何やかんや仕事のことを考えてしまう実直なスティーブンスの姿が微笑ましい。物語は静かに進み、やがて、小さな結末を見る。そのときはすっかり、スティーブンスに感情移入している。その小さな老人の肩に、そっと手を回してあげたいと思う。ハヤカワepi文庫、土屋政雄さん訳、2001年5月31日初版。
⑥「ブルシット・ジョブ」
例年よりノンフィクションを読むのが苦しい1年だったと思う。そんな中で読みきった本書は、仕事について斬新で、深い傷口を残すような考え方を与えてくれた。
副題が端的で、本書は「クソどうでもいい仕事の理論」。著者の人類学者デヴィッド・グレーバーさんが「クソどうでもいい仕事はなぜクソどうでもいいのか?」を論理的に解き明かしてくれる。
第2章の「どんな種類のブルシット・ジョブがあるのか?」が特に参考になる。グレーバーさんは、どうでもいい仕事を5類型する。最初は「フランキー(取り巻き)」で、誰かを偉そうにするための装飾品のような仕事。続いて「グーン(脅し屋)」は同様に雇用主が外部に対して力を顕示するための存在だ。「ダクトテーパー(尻拭い)」は組織の欠陥を取り繕うために注力する人。「ボックスティッカー(書類穴埋め人)」は官僚化した結果として生じる無数の書類をさばくだけの人。最後の「タスクマスター」は、こうしたブルシット・ジョブを他人に割り振るメタ的なブルシット・ジョブになる。
本書を通読すれば、自分の仕事も漏れなくブルシット・ジョブだと気づく。正確には、現代の仕事にはブルシット・ジョブ的な性質を孕んでいると言える。完全にブルシット・ジョブから逃れるのが難しいのなら、それをどう最小化していくかを考えていかなければと思う。岩波書店、酒井隆史さん、芳賀達彦さん、森田和樹さん訳、2020年7月29日初版。
⑦「読んでいない本について堂々と語る方法」
もともと春先に読んだ千葉雅也さんの「勉強の哲学」で登場し、気になって原典を手に取った。この本を読む前と後では、読書に対する考え方が少し変わってきたように思う。
タイトル通り、読んでいない本について堂々と語ることはできるのか?を考える本。すると、ある本を通読すること、くまなく理解することが「読む」ではないという考え方に到達する。では、読むとは何か。本書の中では「共有図書館」と「内なる書物」という二つの概念に整理される。
特に慧眼だと思えたのは、後者の「内なる書物」。著者のピエール・バイヤールさんは、シェイクスピアを全く知らない部族が、その場で聞かされた戯曲にあーだこーだと意見を言う様子を引き合いにこんな風に語る。
ただ、彼らはたしかにこの戯曲の内容に関して自分たちの考えを表明するが、かといってその考えは、戯曲を知ると同時にできあがったものでも、それよりあとに生まれたものでもない。それは極端にいえば戯曲を必要とすらしていない。彼らの考えはむしろ戯曲を知る前からでき上がっていたのである。つまりそれは、ひとつの体系として組織された、ある世界観の総体を形づくっているのであって、そのなかにシェイクスピアの作品は迎え入れられ、場を得たのである。
(中略)私はこの神話的、集団的、ないしは個人的な表象の総体を〈内なる書物〉と呼びたい。(p135)
内なる書物を持った人は、外部から取り入れた物語に「場」を与えることができる。このとき主となるのは内なる書物であって、本はその世界を広げるための触媒に過ぎない。こう考える時、本はまさに会話相手と同じで、自分の心と何らかの位置関係をもち、コミュニケーションする存在だと思えるようになる。ちくま学芸文庫、大浦康介さん訳、2016年10月10日初版。
詳しい読書感想はこちらです。
⑧「自由の命運」
上下巻の物凄く「重い」はずのノンフィクションでしたが、読み終えたときは不思議とスッキリしました。歴史にはこんな見方があるのか。見晴らしの良い場所に出られた気がする。
著者のダロン・アセモグルさんとジェイムズ・A・ロビンソンさんのコンビは「国家はなぜ衰退するのか」がベストセラーになっている。今回は、「自由や民主主義がどんな条件下で存続するのか?」をローマ帝国から現代のアフリカ諸国まで世界史上のさまざまな国を題材に考える。
本書の凄みは、その解をたった一枚の図に落とし込んでいること。「ファスト&すスロー」が行動経済学の原理をシステム1/システム2というシンプルな理論に集約したのと同様で、簡潔でありながら深みのある結論。それが副題にもなっている「狭い回廊」。自由は国家の力と社会の力がバランスした狭い回廊にしか存在できない。
知の行き着く先は、こんなにも力強い。お二人には遠く及ばないのはもちろんであるけれど、小さくても自分なりの「学び」を続けたい。そう思える一冊でした。早川書房、櫻井祐子さん訳、2020年1月20日初版。
詳しい読書感想はこちらです。
⑨「路」
今年、一番遠かったのは「旅」。その経験を疑似的に味わさせてくれた物語が吉田修一さんの「路(ルウ)」でした。
台湾新幹線の実現に尽力した日本の商社マン(商社ウーマン)や、現地の作業員、技術者のお話。その横糸に縦糸をなすように、ある日本女性と台湾男性の淡い恋が描かれている。何よりの魅力は、台湾の匂いが感じられる景色。
夜風を感じながら仁愛路を歩いていた春香は、大通りから食堂が並ぶ路地へ入った。狭い路地にはずらりと海鮮食堂が並び、海老でも炒めているのか香ばしい大蒜と香辛料の匂いが漂ってくる。(p64)
(中略)夜市はこれからが賑わいのピークらしく、あちこちの店から大音量で流れる音楽の中、どの屋台の前にも人だかりができている。人豪は人並みを掻き分けて、肉圓の屋台のテーブルについた。店主のおばさんに大声で注文すると、こちらを見もせずに手だけで応える。人豪は待ちきれずに割り箸を先に割った。(p242)
行けないけれど、目の前にある。そう感じさせてくれるのが、文章の、物語の力だと思う。吉田さん作品らしい暗さが、本作では隠し味のようになっているのも面白い。文春文庫、2015年5月10日初版。
詳しい読書感想はこちらです。
⑩「三体Ⅱ 黒暗森林」
とりあえず「三体Ⅱ」が読める夏まで踏ん張ろう。そう思っていた春がすっかり懐かしい。社会に垂れ込めた暗雲はまだまだ晴れないけれど、今度は「三体Ⅲ」が読める日までなんとか粘っていけたらいいと思う。
今読み返すと、書き出しの味が深い。
大頭蟻は、かつてここが故郷だったことをすっかり忘れてしまっていた。夕陽に染まる大地と空に瞬きはじめた星々にとって、そのあいだに経過した時間などゼロに等しかったが、しかし、蟻にとっては永遠にも等しかった。忘れ去られた日々に、蟻の世界はひっくり返った。土が吹っ飛んで、深く大きな地溝が出現し、そのあとふたたび土がどさどさ降ってきて、その地溝を埋めた。埋め戻された大地の端には、黒い峰がひとつ、そそり立っていた。(p7)
この蟻は人類の比喩に感じられる。星々からすればないに等しい時間の経過は、蟻にとっては永遠のように長い。それは、三体Ⅱを読み終えた今も混迷の中にいる読者の姿に重なる。
三部作の最初にあたる「三体」は、強大な異星文明との出会いだった。彼らに対抗するために人類は4人の「面壁者」を選定し、彼らに膨大な資源を投入する。しかし、ひとり、またひとり。面壁者が追い込まれるたびに、人類はどうなってしまうのかと手に汗を握る。ここに希望はないのか。いや、ここにも希望はないのか。
しかし「三体」が驚きの連続だったように、著者の劉慈欣さんは決して読者に先を予想させない。下巻の最後まで読み切った時、人の想像力の広大さに爽快な気分になる。何より、この物語に先があることが嬉しい。三体Ⅲは2021年夏には刊行されるそうだ。これは間違いなく希望だ。早川書房、大森望さん、立原透耶さん、上原かおりさん、泊功さん訳、2020年6月25日初版。
三体の感想はこちらです。
2019年の「この本に出会えてよかった」はこちらです。
来年もきっと、出会えてよかったと思える本に出会えると信じて。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
