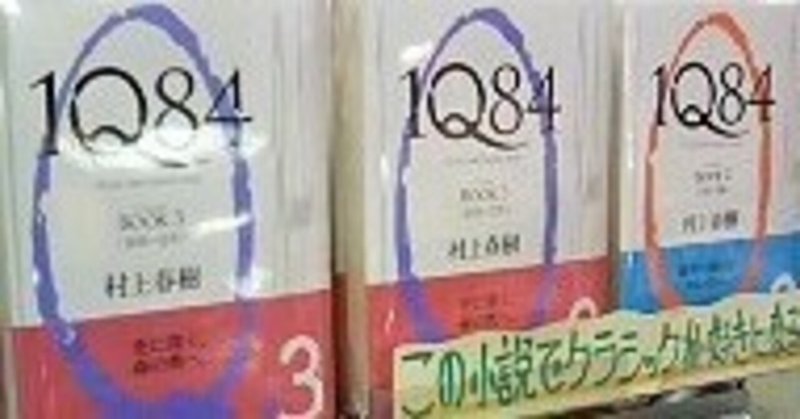
連載更新 「コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼」 第1部 ⒏ 『1Q84』を7回通読した人もいた
土居豊のエッセイ「コロナ以後の読書〜村上春樹読書会と聖地巡礼」
第1部
【コロナ前、村上春樹読書会で口角唾を飛ばしで議論し、大笑いしながら打ち上げの飲み会を楽しんだ】

⒏ 『1Q84』を7回通読した人もいた
(1)久しぶりに村上春樹『1Q84』を読んだ
久しぶりに村上春樹『1Q84』を読んだのは2018年秋、台風21号による暴風被害の傷跡も生々しい大阪・北浜のレトロビルでの読書会だった。レトロビル周辺の道筋も、台風でなぎ倒された街路樹の根っこが歩道にごろごろしていた。
本作は、一世を風靡したミリオンセラー小説だ。09年に発売されると、たちまち社会現象になった。9年後改めて読み返すと、当時よくわからなかった細部がクリアに読み取れる。参加者も、丁々発止の意見交換を楽しんでいた。災害が多発し世情不安だからこそ、参加者からも思い入れの深い意見が次々飛び出し、時間が足りなかった。時を経て、本作が多くの人に読まれた必然性を感じさせられた。
筆者が注目するのは、全編通してさりげなく書かれている神の存在だ。まず最初、ヒロインの「青豆」が小説中の架空の世界へ迷い込むきっかけをつくるのは、ベンツに乗った奇妙な中年女性だった。このご婦人は、2巻の終わりで青豆が自殺しようとするときも、3巻の終わりで青豆が異世界である1Q84ワールドから脱出するときにもその場に立ち会っている。青豆は後半、突然神を信じてしまうが、その神のイメージはこのベンツのご婦人なのだ。
このような不思議な「神」の描きかたの意味を掘り下げることで、本作を現在の世界情勢にからめて読み解くことも可能となる。現実の社会現象を読み解く手掛かりとして本作を読む方法は、小説の読解としては邪道かもしれない。だがそうしたくなるほどに、本作は現代社会の写し鏡となっている。
ところで、偶然ながら読書会の会場のオーナーが、古い蔵書の中から旧満州国の写真集をみせてくれた。満州国は、村上春樹が『羊をめぐる冒険』『ねじまき鳥クロニクル』など多くの小説でこだわって描き続けているモチーフだから、これは実に興味深かった。ちなみに、このオーナーは『1Q84』をなんと7回も通読したという。実はそれまで村上春樹を読んだことがなく、話題の本だから手に取ったそうだ。最初は内容に納得できず投げ出しかけたが、世間であれほど評価の高い村上春樹だから何かあるに違いない、と信じて読み通したら、なぜか気になって何度も読み直すことになったという。初めての読者をこれほどに引き込む魅力が、本作には確かにあるのだとわかって非常に感銘を受けた。

(2)土居豊による『1Q84』の読みの視点
1)『1Q84』のワクチン効果
【12年目のワクチン】
リトルピープルが象徴する「小悪」、馬鹿げた戯画化された悪のあり方、コロナ危機の中での安倍晋三の「歌ってみた」動画が代表する、脱力感しかない悪の存在
それらに対するワクチンとしての1Q84の物語、その構造が示す善悪の対決、家系図における決戦というドストエフスキー的・ロシア文学的な宿命の構造
空気さなぎという寓話に描かれたワクチンは、そういう系図的・構造主義的な物語の宿命に対し、もっとふわふわした、緩くもしなやかな結びつきを示唆?
1Q84が広く読まれたことによって、サブカル的物語の力が多くの人に埋め込まれた。そこには、二次創作の可能性が鉱脈のように眠っている。
みんながそれぞれの1Q84を物語っていいのだ、というサブカル的・カウンターカルチャー的な生き方の示唆。
春樹が無意識に物語としてワクチンをばらまいた結果、12年してから我々の中に、サブカル的な緩やかなカウンターが育っている?
物語をそれぞれが内心、秘めているはず。それは「叶わなかった初恋・学校の廊下のすれ違い」のような原体験、原風景であろうか。春樹の物語る学校の廊下的モチーフが、1Q84から12年後の今、リトルピープルのような馬鹿げた戯画化された小悪の跳梁を封じるための武器として、それぞれの心に蘇るのだろうか。
組織の機械、暴力装置として動くことを否定する動機付けが、まるでラノベ・アニメチックな「学校の廊下」エピソードであったとして、それが多くの心に眠っているとして、それらの総和が小悪の跳梁跋扈を封じることができるかもしれない。中二病的な発想そのものだが、それこそが1Q84のワクチン効果かも。
2)作中の注目ポイント
※ページ数は、単行本による

『1Q84 BOOK1』
天吾について
p44
星占いの文章を書いていて、占いが意外と当たったこと。
p224
戎野が、深田は「ちょうど君ぐらいの体格だ」と、天吾が深田の子であることを示唆。
p169
天吾の父に、満州引き上げのアドバイスくれた役人の正体は?
ふかえりについて
p423
戎野がいう「渦の中心にいるのはエリだ」という言葉で、ふかえりが物語の鍵を握っていることを明示。
青豆について
p189
米ソの月面基地、という記述は、この世界では「月」が一つであることを示唆する。なぜなら、月が複数ある場合は必ず「名前」で呼ぶから。
p195〜196
「狂いを生じているのは私ではなく世界なのだ」
「単に私の頭がおかしくなっているというだけかもしれない」
青豆の狂気を示唆。
p295
青豆の徹底的な破壊ぶりは、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』のシステムの二人組を思い起こさせる。
p435
青豆が「さきがけ」の名を聞いたことがないのは、記憶の改竄。
小松について
p42 東大60年安保の幹部(戎野との関係?)
p309
小松が、天吾に月の2つの描写をうながした。小松は明らかにこの世界の秘密を知っている。
老婦人について
p402
10歳の時、パリに転勤し、第1次世界大戦の血塗れの記憶を持つ。
p441
老婦人がいう「よその世界に移ってもらう必要がある」という言葉の使い方は、世界改変(平行宇宙)を前提にしている。
『1Q84 BOOK2』
p31
タマルとサハリンの関係と、天吾がふかえりに読んでやるチェーホフ『サハリン島』。
p91
「学校の廊下で、声をかけていたら」というのは、近作の『一人称単数』にも出てくるモチーフ。恐らくは春樹の原体験。
p140
病原菌と、ワクチンの比喩。
そのメインキャリアが、天吾とふかえりである。
p181
猫の町は、伝染病で人間が死に絶えた後にできた。
p242
リトルピープルの名は、ふかえりがつけた「小さな人たち」を、深田が「リトル・ピープル」と変えた。
p255
ふかえりの耳=羊をめぐる冒険のキキ
p340
「これが新しい世界なのか」という天吾の感慨、だがそれは同時に、青豆が深田を殺した後の世界である。この時点で、1Q84世界から、book3の世界に入り込んだ。
『1Q84 BOOK3』
新たに加わった、牛河の視点が重要
p200
牛河は、「ソーニャに出会えなかったラスコーリニコフ」
p228
タマルの子、17歳。これが、ふかえりか?
p250
牛河と似た親類は、唯一、祖父の従兄のみ。江東区の金属会社の工場勤務。1945年、東京大空襲で死ぬ。
p259
牛河の別れた妻と二人の娘は名古屋在住。妻は再婚。
p263
花柄のカーテンは、春樹氏の旧居のカーテンを連想させる。
p310
深田保が、牛河を見出した。
p378
牛河は『スプートニクの恋人』のように、たった一度、ふかえりと交差した。「魂の交流」
p505
「冷たくても、冷たくなくても、神はここにいる」(ユング)
タマルは牛河を殺す前に、この言葉を言わせ、まるで祈りのように余韻を味わう。これは儀式。
p568
牛河は空気さなぎになる。この先の物語を生み出す苗床。
土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/

