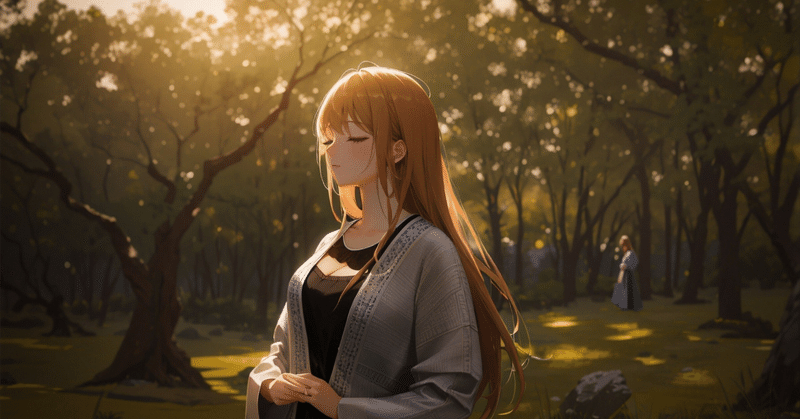
キャリアに関する自分語り①-自分の人生が動いた日
1. はじめに
私が過去投稿させていただいた記事の反応から判断するに、一番読者の方からウケがいいテーマはキャリアに関するお話である。
また、私がnoteで他の方の記事を読む際、一番ワクワクするのは「その人自身の実体験」である。
この実体験の面白さというのは、ハーバード大学に飛び級で合格しましたとか、長澤まさみさんにプロポーズしましたとかいう経験である必要はなく(もちろん、そうした経験があるのであれば是非読んでみたいが)、その人でしか語れない、他では読めないストーリーがあるからだと思っている。
というわけで、私のキャリアに関する個人的なお話を、これから数回にわたってしてみたい。
面白いな、と思ったら続けて読んでもらえると嬉しい。
2. キャリア形成について
キャリアと聞くと、多くの方々にとっては仕事が連想されると思うが、私にとってキャリアとはより広義の意味で「自分の人生をどう生きたいか」であり、その一つとして職業選択があると捉えている。
そして、「自分の人生をどう生きたいか」という究極の問いに対する答えは、一朝一夕で出来上がるものではなく、その人自身が無数の試行錯誤の末に、何年もかけてじっくり構成されていくものだと思う。
私にとって、明確に「こういう人生を歩みたい」という意思を持ったのは高校生の時であり、そこから真の意味で自分の人生はスタートした。
昔懐かしき高校時代から振り返り、自分のキャリア形成の道のりを語りたい。
3. 事の始まり
私が当時置かれていた状況から説明しよう。
私は学区2番手の進学校に通っていた。
と書くと、なんだか誇らしげな感じもするが、入学当初の私にとってその学校に通うことは不本意なことだった。
中二病真っ盛りだった私にとって、自分は頑張れば何でもできる人間であり、そういう人間が行く学校は学区1番手に決まっているという想い(というか妄想)があった。
そして悲しいことに、みっともないことに、想いの立派さに反比例して行動がまるで伴っておらず、塾に行く以外の自主学習は限定的であった。
この頃の私にとって勉強とは強制されてやるものであって、自ら積極的に取り組むものではなかった。
中学校での成績は1番手の学校に及ぶものではなく、2番手の学校にしぶしぶ進学した。
そんな想いを抱いて入学したので、入学当初私は周りを完全になめ腐っており、「自分はここにいるべき人間ではない。周りに馴染んではいけない」と思っていたし、そうした態度も取っていた。
当然、クラスで友達は全くできなかった。
ところが、入学して最初の統一模試でわかるのだが、私の順位は320番中310番であった。
つまり、馬鹿なのは周りのクラスメイトではなく、私だったというわけである。
その状況に気が付くころには、クラスではすっかり人間関係は出来上がっており、私は「根暗で友達のいない、頭のあまりよくない人」という地獄のようなカテゴリーで暮らすことになった。
完全に自業自得であり、同情の余地は欠片もないが、それでも当時はしんどかった。
あれから15年以上の年月を経た今ですら、当時の日々を思い返すと辛い気持ちになる。
私は常に早弁であり、昼休み前には食事を終えていた。
お腹がすいたからではなく、昼休みに一人教室で弁当を食べることに耐えられなかったからだ。
昼休みが始まると真っ先に図書室に行った。
当時愛読していたのは、夜回り先生で有名な水谷修さんの本であり、自分にも夜回りしてくれないかなぁと夢想した。
もっとも、仮に当時の自分に会いに来てくれたとしても、本に出てくるような自分ではどうしようも出来ない理由から辛い日々を送っている生徒たちと違って、私は自分の努力不足以外何も悪いところはない(家族も健全だし、いじめられたりとかもなかった)ので、「勉強頑張れ」としか言われなかった気もするが。
4. 転機
高校1年生の秋、とても寒い日だった。遅刻しそうになっていた私は、自宅近くの坂をひーひー言いながら自転車を漕いでいた。
カーブを曲がろうとしたその時、自転車がずるっと滑った。寒さで路面が凍結していたのだ。
私は、右ほおを下敷きにする形で、コンクリートの道路を横滑りしていった。
幸いなことに、傷そのものは深くなかったものの、右ほお全体が傷だらけになった。
家に戻る時間すら惜しく、私はそのまま学校へ向かった。
保健室で治療を受け、ガーゼだらけになった顔で、私は急ぎ教室へと入っていった。
さて、ここで皆さんにお伺いしたい。
あなたのクラスメイトが、ある日突然、顔の半分ガーゼまみれになって教室に現れたら、あなたはどういう反応をするだろうか。
心配するだろうか?
面白がるだろうか?
触って困らせてやろうと思うだろうか?
この時の私の正直な気持ちとしては、99%はツイていないな、というものだったが、1%くらいは「話のネタになる。これは美味しいかも」という気持ちが混じっていた。
なんて説明しようか、くらいのシミュレーションも頭の中でしていた。
結論から申し上げよう。
何もなかった。クラスの誰からも、先生からもまっったく何の反応もなく、その日一日はつつがなく終わっていった。
この日ほど苦しかったことはない。
何が苦しかったかと言えば、自分の存在はあの空間において何の価値も持たないのだ、ということを思い知らされたことだった。
断言するが、仮にあの日私が傷と言わず、交通事故で死んだとしても、状況は変わらなかっただろう。
自分を変えなければだめだ、自分の人生を変えなければ駄目だ、と布団の中で泣きながら誓ったのがこの日だった。
(続きます)
サポートもとても嬉しいのですが、「この記事、まぁまぁ良かったよ」と思ってくださった方は「スキ」を、「とっても良かった!また新しいのを書いたら読ませてね」という天使のような方は、フォローしていただけるともっと嬉しいです!
