
【男の友情】 おすすめのバディ・ムーヴィー4選 【ネタバレあり】
はじめに
友情というのはひどく曖昧な感情な気がする。目に見えるわけではないし、言葉にすると薄っぺらい気がする。親子愛や兄弟の絆などであれば、血がつながっているわけだし、国の制度として書面上は同じ苗字を用いており、同じ屋根の下に暮らしているわけなので、何らかの特別な感情や固有の念が湧くのも理解できる。恋愛という感情も、種の保存のために本能的に抱くようにインプットされた機能ということで納得できる(人間のご先祖となる微生物たちは個体の情報を保存するため、ウイルスや細菌などの外敵に対して免疫を発達させたり、自身を高等生物化することで情報を複雑化して対抗していたが、ウイルスなどの方が進化のスピードが速く対処し難いため、遺伝情報の半分が詰まった細胞同士を掛け合わせて、自らを飛躍的にアップグレードする行為が生殖だという、めちゃ面白い記事を何かで読んだことがある)。
では友情とは一体何であるのか?『戦争における「人殺し」の心理学』という本の中で、戦場における兵士と兵士の友情というのは、親子愛に匹敵するものだという記述があった。兄弟愛や夫婦愛では比較にならないくらいの目に見えない情愛が、同じ部隊の親しい兵士同士には流れているらしい。要は兵士と兵士が背中合わせで互いを援護し合うとき、自分の体のうち半分はその戦友に預けているわけで、そこから否応にも生じる相手への信頼感というのは絶大だということだ。これは母親に体を預ける赤ん坊、親子の関係くらいしか比べる対象がないということらしい(従って兵士の数がちょうど半分になった辺りから、その部隊の士気は急激に下がる。生き残った兵士は「俺のせいであいつらが死んだ」と慚愧の念を抱くようだ)。
では互いに自分の体や命、何か自分にとって大切なものを預けられれば、それは友情といえるだろうか?確かにそうかもしれない…。ただし先ほどの兵士の話じゃないが、相手に預けた結果、それを失う可能性もある。生き残る兵士がいれば、死ぬ兵士もいる。生き残った兵士にとって友情とは戦友に命を預けることだろうが、死んでいった兵士にとっては何だろうか…死人に口なしなのでその答えは分からないが、少なくとも死んでいった兵士は、自分の取った行動に関しては後悔していないだろうと思う。兵士と兵士の間に真の友情が流れているのであれば、自分の犠牲で戦友が助かれば本望だろうと思うからだ(もちろん自己犠牲によって救った戦友以外のことに関しては悔いが残るかもしれないが…)。つまり、真の友情とは相手のために自分のことを犠牲にできるかどうか、で決まるのではないかと思う。
筆者は昔からバディ・ムーヴィー…男と男の泥臭い友情を扱ったもの、が好きだった。しかし、男同士の友情を描いた映画は意外と少ないと思う。物語の基本はやはり“ボーイ・ミーツ・ガール”であり、従ってバディ・ムーヴィーの組み合わせも男と女である方が名作の割合が高いような気がする(ボニー&クライドとか)。今回はそんな希少な男同士の友情を扱った映画を4つほど紹介したいと思う。
はぐれ者同士の友情 『スケアクロウ』
この映画はロード・ムービーで、アメリカン・ニューシネマに分類される映画群の一つだ。刑務所を出たばかりで喧嘩っ早いマックス・ミラン(以下マックス)と、船乗り生活から足を洗ったばかりでお調子者のフランシス・ライオネル・デオプッケ(愛称ライオン)が出会うところから物語は始まる。

この映画のオープニング・シークエンスは完成度が非常に高く、二人に友情が芽生える様を鮮明に捉えている。
荒野、丘を下って来たマックスが有刺鉄線を潜ろうとするが、図体がデカいため上手くいかない。その様子を道端にたむろするライオンが眺めている。やっとのことで金網を越えたマックスは、ライオンを見つけ、ヒッチハイクのライバルがいることを知る(二人とも金がないから基本的に移動はヒッチハイクか無賃乗車)。
車が通り過ぎるたびにお互い大声をあげて呼び止めようとするが、なかなか止まってくれない。気のいいライオンは仲良くなろうとしてマックスとコミュニケーションを取ろうとするが、その度にマックスは突っぱねて、「お前は座ってろ!」と自分勝手な要求を下す。
お互い一本道を挟んだ反対側にたむろして、カットバックで待ちの間の各々を映し出す演出は見ていて非常に心地よい。そしてついに、お互いが歩み寄る時が来る。マックスのライターがオイル切れを起こしたのだ。咥えタバコに火が付かず、イライラするマックス。振ったり叩いたりするがオンボロライターはうんともすんともいわない。その様子を見ていたライオンがふと自分のポケットを探り、どこかのホテルの萎びた紙マッチを取り出す。マッチは残り1本だ。ライオンは使っていいよ、とジェスチャーで示す。ついにマックスは根負けする。そして観念したとばかりに頷くのだ。
こうしてヒッチハイクで相手より先んじようとする争いは終わり、対立構造以外で初めて二人は同じ画面に納まる。道の真ん中でクロースアップ、風が強いためにほぼ密着に近い形でお互い身を寄せ合い、防波堤の要領でお互いの手をマッチ棒の周りにかざす。そして、ジュッという音とともにマッチ棒に火がつく。
『スケアクロウ』はこの極めて映像的な友情の灯火を画面に収めつつシーン変わりし、二人が農夫のトラクターに二人で乗っけてもらい移動を果たした様子が描かれる。
このオープニング・シークエンスにおけるマッチ棒の火とは、間違いなく友情が点火されたことを視覚的に表現したものであり、お互いの過去やらキャラクターやらを十分に描く前に、お互いの距離を縮めるための演出の離れ業、「火が灯ったのを見たね?じゃあもう友情成立だ」という“省略”の技術の粋だと思う。

そこにマッチの仄かな火が加わって友情の灯火が成立する。
人間関係の移り変わりを、人物の動きとマッチの火という小道具で映像的に表現している。
素晴らしいシーンなのだ。
友情が成立した二人は徐々に仲を深めていく。マックスは刑務所内で洗車業を始める段取りを組んでおり、ライオンに自分のビジネスパートナーにならないかと誘う。開業の金はピッツバーグに預けており、そのためマックスの行き先はピッツバーグだということが明かされる。一方、ライオンは船乗り業を辞めたばかりで、特にやりたいこともないので二つ返事でマックスの申し出を受けるが、デトロイトを経由するという条件を設ける。実はライオンは家出同然に故郷を飛び出しており、残してきた妻と、産まれているはずの子供に一目会いたいというのだ。ライオンは稼ぎのほぼ全てを贖罪のため妻に送金しており、まだ見ぬ子供のためのプレゼントも持っている(男の子でも女の子でもいいように、子供用の電気スタンド)。マックスはしぶしぶ了承する。
その後、様々な出来事が彼らの旅路に降りかかる。アルバイトをしようとして追い出されたり(マックスの短気が原因)、喧嘩をして刑務所にぶち込まれたり、マックスの妹の元で束の間の休息を味わったり。
そしてついに、ライオンの目的地・デトロイトに到着する。しかし、土壇場になってもライオンは直接会う勇気がない。身重の妻を残して逃げるという、酷いことをした自覚があるからだ。直接会う勇気が出ず、彼は公衆電話で妻に連絡を取るが、妻は泣きながら彼を糾弾する。そして一匙の嘘を会話に盛る。「子どもは死んだわよ。洗礼も受けずに死んだから天国にも行けないわ。あんたのせいよ」と。実は子供は普通に生きているが、妻は元夫を傷つけようとしてこんなことを言ったのだった。ライオンは恐ろしくなって電話を切る。
この時の演出が白眉で、電話ボックス(という個人的な空間)から出たライオンは、「どうだった?」と聞くマックスにガッツポーズしてみせるのだ。「男の子だった!」と。二人は抱き合って喜び、一杯ひっかけるために歩き去ってフレームアウトする。ただしカメラは二人を追わない。カメラはライオンが映画冒頭から欠かさずに持っていた、子どもへのプレゼントを入れた箱へと静かにズームインしていく。旅中に色々あってボロボロになっているが、ライオンはどんな目に遭ってもこの箱だけは放さなかった。あまりに無策だが、彼はこの箱の中のプレゼントに賭けていたはずだ。しかし彼には実際に元妻のところへ出向く勇気もなく(行っていれば子どもの声くらい聞けたはずだ)、電話では人生を否定されてしまった。この箱を置いていくということは、彼が自分の人生を見限ったも同然で、その恐ろしい事実がこのプレゼントへのズームインに集約されている。

マックスとライオンは画面外に消えるが、カメラは頑なにプレゼントを捉え続け、
ズームインしていく。恐ろしいショットなのだ。
この後、ライオンは錯乱状態に陥る。電話の後、二人は公園に行き、マックスはスコッチかなんかをあおり、ライオンは噴水近くで子どもたちと戯れている。おとぎ話に出てくる巨人の真似をして子どもたちを喜ばせているライオンだが、時折ふと視線が遠くへ向く。何となく不穏な空気だ。そんな挙動を繰り返すうちに、彼は子供を抱え上げ、噴水の中へと入って中心部へと進んでいく。子供がずり落ちそうになるのも構わず、彼はずんずん進んでいき、恐怖に駆られた母親が慌てて彼を止めようとする。ボケっと酒を飲んでいたマックスも異変に気付き、大慌てでライオンを止めに入る。子どもは無事だったが、ライオンは精神錯乱で何やら訳の分からないことを喚き散らした挙句、ぶっ倒れてしまう。
医者から意識が戻る見込みはない、と言われたマックスは途方に暮れる。「女房に何を言われたんだ!?元気を出せ!」と昏睡状態のライオンを励ますが、返事はない。彼は医者に詰め寄り、何とか治してやってくれ、と言う。「金ならあるんだ」と。
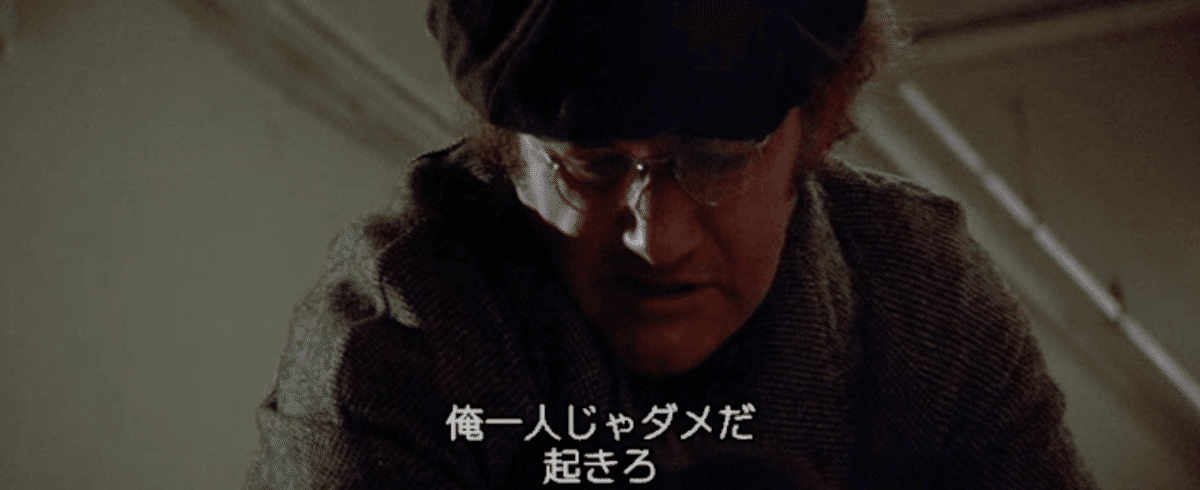
こうしてマックスは自分の夢(洗車業で一発当てる)と、友情(ライオンの治療費)を天秤にかけ、友情を選ぶ。彼は今や夢を諦め、友人を救うためにピッツバーグへと洗車業をするために貯めていた金を下ろしに行くところでこの映画は終わる(ちなみにこのラストシーンはマックスが終始大事にしていたオンボロ靴の伏線が回収される見事なシーンになっている)。

一人では火はつかないのだ。
恋か友情か、という問いは結構巷にあふれているが、自分の夢か友情か、という問いは中々ないのではないか。友達のために自分の夢を諦められるか?と聞かれたら大体の人間の答えはNOだと思うが、この映画でマックスはYESと答える。アメリカン・ニューシネマらしい非常に悲しくも潔いラストを迎えるこの『スケアクロウ』は、ジーン・ハックマンとアル・パチーノの演技がバチバチに冴え渡っている映画でもあるので(特にアル・パチーノ)、そういった意味でもお勧めの一本なのだ。
制服警官の激しい日常 『エンド・オブ・ウォッチ』
世にも珍しい刑事映画、の中の制服警官を描いた映画だ。制服警官ということで、主人公らは刑事ではない。彼らは巡査であり、ロサンゼルスで最も治安の悪い地域配属のパトロール警官なのだ。
主人公のブライアン・テイラー(白人系)と、マイク・サヴァラ(メキシコ系)のコンビが、様々な事件に接触し、現場を封鎖するまでの攻防が描かれている(封鎖した後は刑事の仕事)。
お互いを“相棒(パートナー)”と呼び合う二人は、正反対な性格だ。ブライアンの方は頭は良いが多少自堕落なところがあり、特に女にだらしない。刑事志望の野心家であり、大学の講義にパスするために色々と頑張っている。サヴァラの方は学生結婚して以来、妻一筋であり、猪突猛進でブライアンの女癖の悪さをいじったりしている。

普段は馬鹿話ばっかりしているロス市警の問題児コンビな二人。
彼らはパトカーに乗ってロスの郊外を巡回するわけだが、常に馬鹿話をしていて(奥さんの弟がムカつくとか、最近気になる女の子ができた、とか)、仲がいい感じがリアルに伝わってくる。脚本・監督のデヴィッド・エアーは実際に治安の悪い地域の出身らしく、出てくるギャングと警官の描写が圧倒的にリアルなのだ(ちなみにその地域での子供の憧れの職業は、ギャングか警官か、という両極端なものらしい)。妙にズレたところで怒ったり、意味の分からない隠語(「カーブサイドだ!ボケ!」とか。台詞を書いたエアー自身にもよく分からないが、そう言っているのを聞いたことがあるらしい)を喋ったりと、実際そうなのかも、と思わせる描写が多々ある。

基本的に現場には彼らが一番に到着するため、瞬間瞬間の判断で行動していかなければならない。
パトロール警官とはタフな仕事のなのだ。
舞台のロサンゼルス某所は、元々黒人系のギャング団が幅を利かせていたらしいが、現在メキシコ系麻薬カルテルの浸食を受けており、2派の小競り合いが続いている。二人は黒人のギャングと喧嘩したり、メキシコ系麻薬カルテルの構成員を取り締まったり、火事現場に飛び込んで幼児を救い、州から表彰されたりしながら日々の業務をこなしていくが、偶然にも麻薬カルテルの隠れアジトを数回摘発したことで目を付けられ、極秘裏に組織から抹殺命令が出てしまう。
あくる日、アパートの吹き抜け部分で襲撃を受けた二人はたまらず一室に逃げ込み、状況を整理しつつ応援を要請する。この部屋にいてもジリ貧だと判断した二人は、威嚇射撃を行い、アパートを飛び出す。刺客を何人か射殺しつつ細道を行く二人。しかしもうすぐ大通りだというところで、ブライアンが被弾してしまう。崩れ落ちるブライアン。サヴァラは必死に介抱するが、ブライアンは意識を失う。近所の住人に警察を呼べ!、と呼びかけるが、返事はない。そして、ブライアンの応急処置や応援要請に気を取られすぎて、カルテルのチンピラがすぐ後ろに佇んでいる。サヴァラの背後でガチャリ、と撃鉄を操作する音が聞こえる。しかし、ここで怯む彼ではない。彼は真の警察官なのだ。観念するでもなく、逃げるでもなく、すぐさまホルスターに手を添え、拳銃を引き抜こうとする。しかし到底間に合うはずもない。チンピラたちに滅多撃ちにされたサヴァラは、そのままブライアンをかばうようにして倒れる。

二人の命運やいかに?
その後、チンピラたちは応援に駆け付けた警官たちによって射殺される。パトロール隊のメンバーたちは、ブライアンとサヴァラが気絶しているのを発見する。結果としてブライアンとサヴァラ、どちらが生き残ったのか、それともどちらも殉職したのか、は見ていただきたいので公言は避ける。
ナチスの強制収容所での経験を記した『夜と霧』という本の中で、良い人ほど先に死ぬ、という旨の記述がある。咄嗟の判断で自分よりも他人を優先してしまう人ほど、危険な目に遭いやすく、割を食いやすいということだろう。そういう人は救われた人にとっては英雄なんだろうが、残された家族や友人は非常に悲しい思いをするだろう。
『エンド・オブ・ウォッチ』は危険区域のパトロール警官という死と隣り合わせの職業を描いた物語で、残された側の悲哀も少し描かれている。(アメリカの)警察官がどんな業務をこなしているかや、真の警察官とは何か、結婚するときの判断方法はどうすればいいのか、など、色々な含蓄が描かれた物語で、何より単純に見ていて面白い映画でもあるので、見ていただきたい作品である。
友情に遺伝子の垣根なし 『ガタカ』
このSF映画におけるメインテーマは、“徹底的に努力すれば、夢は叶う”というもので、友情の要素というものはおまけ程度でしかない。しかし確かに友情と、そして奇妙な依存関係が描かれており、また映画としても非常に面白いため書いていく。

上はガタカ入社前、下はユージーンの協力を得てガタカ入社後。
ライザップもびっくりなイメチェンだ。
近未来の片田舎で物語は始まる。この時代では遺伝子操作による出産が一般的になっており、あらかじめ遺伝的な欠陥や病気を排除し、精子と卵子の無数の組み合わせの中からIQが高い種を選び、受精させるということがごくごく普通に行われている。こうして生まれたデザイナーベビーたちは「適性者」、反対に自然分娩で生まれた赤ん坊は「不適正者」と呼ばれる世の中なのだ。
主人公のヴィンセント・アントンは「不適正者」として生まれ、心臓に遺伝的劣性を抱え(推定寿命30歳)、注意力散漫、一般的な「不適正者」の特徴である近視持ちだった。彼には宇宙飛行士になるという夢があるが、それは「適性者」の仕事で、「不適正者」である彼には万に一つも可能性はなかった。宇宙関連の職に就こうにも、面接で遺伝子サンプルを求められるのだ。今や肌の色や人種で差別する時代は終わりを告げたが、代わりにあらゆる場所で遺伝子情報を求められ、「不適正者」はまともな仕事には就けない、という遺伝子差別がまかり通っている。
しかし、ヴィンセントは宇宙局「ガタカ」に潜り込むことに成功する。闇ブローカーの仲介で「適性者」のDNAを入手し、その人物と同居し、日々DNAサンプル(尿や血液、フケや垢、髪の毛や、運動時の心拍パターンなど)の提供を受ける代わりに、その人物の生活を支えるという奇妙な共同生活が始まるのだ。

天才ゆえの繊細さと傲慢さ、そしてプライドを持ち合わせたキャラクター。
DNA提供者はジェローム・ユージーン・モローといい、水泳のスター選手だったが、海外で交通事故に遭い、下半身不随になったのだった。遺伝子操作でも性格は変えられない、どころか、作中に出てくる「適性者」たちは自分の能力が高いが故に、高慢であることが多い。ユージーンもその例に漏れず、初めはヴィンセントを見下している傲慢な人物だった。根性のない奴が嫌いで、必ずやり遂げるように口を酸っぱくして命令するが、自分は酒を飲んで尿サンプルを採取するほど間が抜けている。そんなユージーンだが、ヴィンセントと共同生活を営み、彼のひたむきさに触れるにつれて徐々に変わっていく。根本的な傲慢さは変わらないが、サンプル集めに熱心になったり、ヴィンセントのピンチには脂汗を流しながら這いずり回るようになる。
最終的にヴィンセントは夢を叶え、宇宙に旅立つ。では、残されるユージーンはどうするのか?彼はヴィンセントを見送る際、「旅に出る」と言い、宇宙で読むようにと封筒を渡して見送った後、一生分の細胞サンプルを残し、水泳選手時代に獲った銀メダルを首にかけて焼身自殺する。
彼が自殺をしたのはヴィンセントが地球に帰って来た時に自分がいては困るだろうという配慮か、それとも目標を達成した相棒を目の当たりにし、自らも人生の幕を下ろそうと考えたのか、定かではない(どちらにせよヴィンセントはAIが算出した寿命を越えているため、生きて地球に戻ることはないと思う)。
おそらくどっちの要因もあったのだと思う。ユージーンは天才であったが、一番になることの出来なかった人間だ。水泳選手時代はどういうわけか二番手止まりだったらしい。才能では上回る彼が二番手止まりなのはどういうわけか。それはこの映画のテーマとも密接に関わっていて、冒頭でも述べた“徹底的に努力すれば、夢は叶う”というものが表のテーマだとすれば、裏の主張は“どんなに努力して才能があっても、一人では決して夢は叶わない”ということだからだ。
主人公のヴィンセントは幼いころから差別を受け続け、地球から逃げ出したいと切に願っていた。しかし、いざ宇宙に旅立つとなると、たまらない郷愁が胸に広がるのを感じる。彼は人生の悲願である宇宙飛行を達成できたのは、様々な人の助けがあって初めて成しえたことであることを自覚している。尿の遺伝子検査をごまかしてくれた担当医師、自分が「不適正者」であることを受け入れてくれた恋人、自分の存在を消しながら協力してくれた友人、もちろん本人の努力が一番であることに変わりはないが、要所要所で崩れそうになる自分を支えてくれたのは、これらの人々であることを知っているのだ。
対してユージーンはどうか?多分、ヴィンセントと出会う前の彼はそうではなかったと思う。一等賞を取ること、自分が優勢であると示すこと、自分の名声、自分の功績、そんな風に考えて、自分を支える人たちのことなんて眼中になかったのではないか。だからこそ彼は下半身不随になったときに誰からも助けてもらえず、闇ブローカーなんかに頼るほかなかったのだろうと思う。
しかし彼はヴィンセントと暮らすうちに変わり、我の強い自分がどんどん薄れていき(実際にヴィンセントが活躍すればするほど、世間的な認知もそちらに移っていくため、彼の存在はどんどん小さいものになっていく)、最終的にヴィンセントの目標こそが彼の生きがいになる。自分の事しか考えなかった奴が、遂に人を支える立場になって、支えることに人生を捧げるよう成長するのだ。

しかしユージーンもまたヴィンセントに感謝している。
これを友情と言わずして何と言うか。
物語の最後、ユージーンが旅立つヴィンセントに渡した封筒には、自身の遺髪が入っている。私の心は常にあなたの元にあるという意味なのか、自分を変えてくれた友に対する感謝のしるしなのかは不明だが、『ガタカ』におけるユージーンの変化を見ていくと、真の友情とは犠牲を払った方にこそある、と思えるのだ。
ドタバタ・コンビ 『ヴェノム』
このアメコミ映画にもある種の友情が描かれているが、それは人間同士のものではなく、人間と地球外生命体との間で結ばれる。
ジャーナリストのエディ・ブロックは、歯に衣着せぬ突撃取材が売りだったが、ライフ財団のリーダーであるカールトン・ドレイクに、取材厳禁だと釘を刺されていた人体実験について問い詰めたことがきっかけで仕事を干され、恋人にもフラれてしまう。
失意の中、新たな就職先を探すエディだが、ひょんなことから自分を陥れたライフ財団に潜入することに成功する。そこでは浮浪者たちを使ったゴリゴリの人体実験が行われており、エディは被験者に襲われ、地球外の寄生生命体・シンビオートに寄生されてしまう。
その日以降、凶暴性や食欲が異様に増し、頭の中で声が聞こえることに困惑するエディだが、シンビオートを取り返しに来たライフ財団が自宅に突撃してきたことによって、彼の内に巣食う寄生生命体・ヴェノムが顕在化する。ライフ財団が差し向けた傭兵軍団と渡り合いつつ、自らをシンビオートに寄生させたドレイクの野望(一旦シンビオートのいる惑星に行き、大量のシンビオートを持ち帰って人間に寄生させ、人類全体のレベルを底上げする、というもの)を打ち砕くべく協力してライフ財団に乗り込む…。というのがざっくりしたあらすじだ。
あなたの周りにいる人間5人の平均があなた、という法則がある。交友関係は同じレベルの者としか成立しないということを現したジンクスだが、エディとヴェノムも同じような境遇を共有している。彼らは互いに“社会の落ちこぼれ”なのだ。“負け犬”と言っても差し支えないかもしれない。地球ではほぼ敵なしのヴェノムだが、確認されているシンビオート全21種の中では最弱なのだ。エディもエディで歯に衣着せぬ性分のせいで、ようやく就いた定職をフイにしてしまい、挙句は恋人にも愛想を尽かされる始末である。要するにお互いそれぞれの惑星で不適応者だったのだが、落ちこぼれ同士波長が合ったのか、エディとヴェノムの同調率は非常に高い(変形能力で勝る敵のドレイク&ライオットのペアに白兵戦で渡り合い、「強いホスト(宿主)を見つけたな」、と言われている)。

人こそ人の鏡、とはよく言ったもので、
この後ヴェノムも負け犬であったことが判明する。
よっぽど故郷で辛辣な目に遭わされたのか、地球を乗っ取る目的で来たはずのヴェノムは逆に地球を気に入り、自分の種族(シンビオート)のリーダーであるライオットに刃向かうようになる。最初はヴェノムを拒絶していたエディだが(リアルに肉体的に拒絶反応が出ていた)、ドレイク&ライオットコンビの計画を止めるために現実的にヴェノムの力が必要であったことや、傭兵集団から身を挺して守ってくれたり、喋ってみると意外と話の分かる奴であったこと、ライフ財団に捕らえられたときに危険を冒して助けに来てくれたことなどが重なり、実利の関係を越えて次第に打ち解けていくようになる。
実際エディとヴェノムのやり取りはドタバタ劇のようで見ていて楽しいが、時おり核心を突くような会話もなされる。元恋人に迷惑をかけるばかりのエディに対し、ヴェノムは「お前まだ一回も謝ってないぞ」と指摘する。エディもまさか地球に来て日の浅いエイリアンに、対人関係についてやんわり諭されるとは思ってもみなかったろうが、結果的にヴェノムのアドバイス通りに元恋人に謝っている。ここら辺はお互いの足りないところを補い合う感じがして、見ていてほっこりするシーンだ。
最終的にエディ&ヴェノムは宇宙船で飛び立とうとするドレイク&ライオットと対決する。「勝算はあるのか?」と聞くエディに対し、「…限りなくゼロに近い」とヴェノムが弱気になるような負け戦に挑む両者だが、実際同調率では勝っていても、そもそもの基本スペック(ヴェノムがスパイダーマンの能力しか使えないのに対し、ライオットはスパイダーマンの能力と身体を刃のように硬質化させる能力が使える)が違うため、タイマン勝負では歯が立たない。結果的にほぼ自爆特攻のような形でヴェノムが宇宙船の燃料タンクに亀裂を入れる。そのまま漏れ出るジェット燃料が噴出口からの炎に引火して大爆発を起こし、ドレイク&ライオット組は焼死、ヴェノムはエディをかばって燃え尽きた…と思ったら、実は生き残っていた。

自分の上位互換に対して中々いい勝負をするが、
あと一歩及ばない(この後あっさり逆転される)。
落ちこぼれ同士が手を組んで、優秀な奴らに一杯食わせる構図は見ていて面白い。強引だが、力なき者でも結束すれば権力者に対抗できる、というテーマも見出すことができる。
ヴェノムは死を覚悟してエディを爆炎から守り、エディもヴェノムを認めて体に寄生することを許し、二人は身も心も共有する真のバディになった。物語の最後、「あんたは誰だ?」と強盗から聞かれて二人で「俺たちはヴェノムだ」と答えるシーンは小気味良い。上記3作品と比べると幾分ライトな作りの『ヴェノム』だが、色々なアメコミ映画の中でも筆者が特に好きな作品でもあるので、ここに紹介させていただいた。

予告編と本編では言い方が少しだけ違う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
