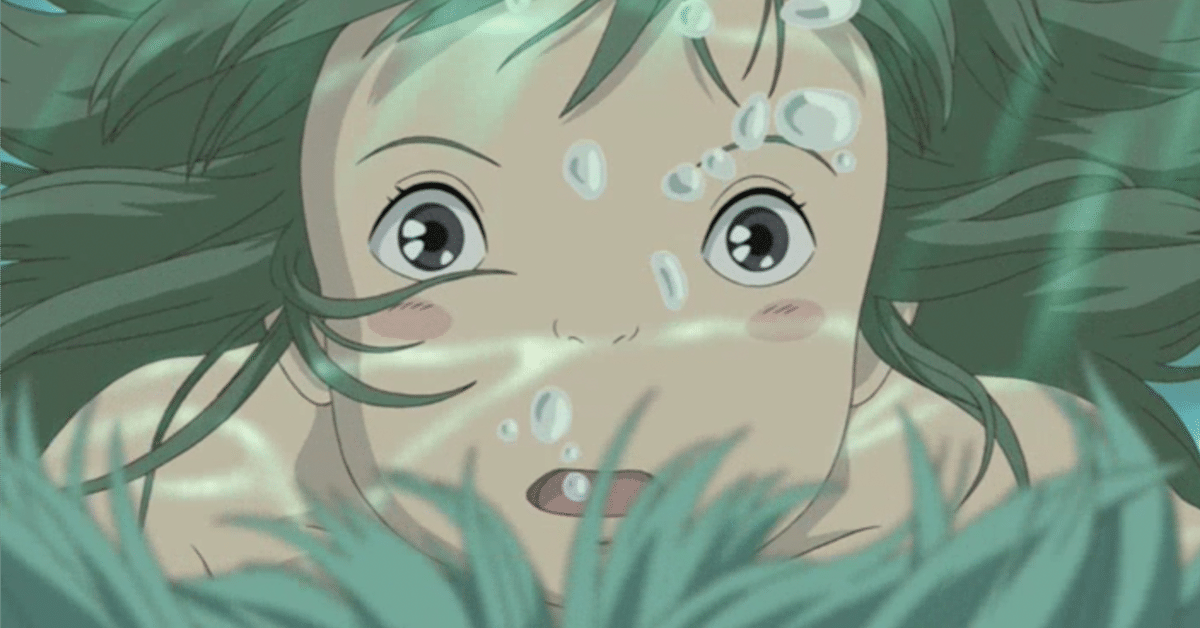
【映画紹介】『千と千尋の神隠し』はなぜアカデミー賞を獲れたのか考えてみる【ネタバレあり】
はじめに
ジブリ作品が嫌いな人はあんまりいないように思える。映画とか物語に全く興味のない人は置いておいて、日常的に映像作品を観る人からジブリの悪口を聞くことはあまりない。それはジブリ作品の(特に宮崎駿監督作品の)完成度が非常に高いからであり、大人から子どもまで楽しめる、を地でいっているからだ。かくいう筆者も幼い頃からジブリ作品を観ていて、トトロあたりから始まり、ナウシカ、ラピュタ、もののけ姫、と成長と共にジブリ作品を楽しませていただいていた(ちなみに個人的なベスト・ジブリは『もののけ姫』です)。
ここからは勝手な妄想だが、ジブリの屋台骨である宮崎駿監督のフィルモグラフィーを辿っていって、中期宮崎作品の集大成ともいえる作品が『千と千尋の神隠し』ではないかと思う。ベルリン金熊賞をはじめ、なんとアカデミー賞まで受賞しているのだ。宮崎駿なんだから別にアカデミー賞くらい獲るだろ、と思わないでもないが、それにしても日本映画衰退期にあって、ど真ん中のアカデミー賞を受賞しちゃうのは凄いことだと思うのだ。権威に弱い筆者はなおの事そう思う。
今回は、この『千と千尋の神隠し』がなぜアカデミー賞を受賞できたのかを(勝手に)考察していきたい。

引っ越しが嫌で憂鬱な表情。
これからドエライことに巻き込まれるなんて思ってもいないのだ。
通過儀礼の物語
改めて『千と千尋の神隠し』のあらすじを少しだけ。
ある田舎町を千尋一家は引っ越しのため車で移動しており、主人公の千尋は憂鬱そうな表情だ。彼女は引っ越しなどしたくない。クラスメイトから貰った別れの花束を握りしめる千尋。
そのうち父親が道を外れ、獣道を進んでいくとトンネルに鉢合わせする。千尋一家が興味本位でくぐってみると河があり、向こう岸には何やら多国籍な街並みが広がっている。千尋の両親は千尋が止めるのも聞かずにずんずん進んでいき、食事処に入り、あろうことか勝手に店内のものにがっついて豚に変化してしまう。仰天する千尋。
その後すったもんだあった挙句、千尋はハクという少年と出会う。両親を豚から人間に戻すために、ハクの助言を受け、この街を支配している強欲な魔女・湯婆婆の元へ行き、八百万の神々が湯治に赴く油屋という高級銭湯で働くのだった…というのがこの映画の大まかな流れだ。
この映画は神々の世界、あるいは現世に住む人間が足を踏み入れてはいけない場所である常世、に迷い込んだ千尋が、豚にされた両親を救い出す物語で、大いに通過儀礼の様相を呈している。
通過儀礼とは子どもが大人になるための儀式で、その土地や国ごとに多種多様な方式がある。日本だと髷を結んだり、どこか遠い国ではバンジージャンプをしていたらしい。通過儀礼とは要するに、それまでの自分の価値観や考え方、生きている世界や環境を否定する行為だと思う。それまでの自分を一度疑似的に殺すことで、全く新しい自分へと生まれ変わりをはかろうとする行為ともいえる。
通過儀礼と言うと何か仰々しい感じがするが、下準備のいる大掛かりな儀式を経なくても、個人で勝手に行う通過儀礼がある。それはどこか知らない場所に行き、ある程度の期間一人で生活をすることだ。
筆者は学生時代にある先生がこう言ったのを覚えている。「兵役がある分、外国の人の方が、日本人より大人っぽく見えるなぁ」と。
かわいい子には旅をさせろ、ということわざがあるが、兵役は一人で訓練所へ行き、赤の他人と話したり、良い奴も悪い奴もいる中で一緒に仕事をしたり、上官にこれでもかと怒られたり、新しい友人らと共同生活を行ったりする。要は見知らぬ土地に行き、その土地の見知らぬ誰かと話したり何らかの接触をもつことが絶対に必要な環境に身を置くこと。これが通過儀礼になりうると思う。郷に行っては郷に従え、じゃないが場所によっては現在の自分が全く通用せず、新しい自分を形成して適応進化していく必要があるからだ。兵役でなくとも、例えば一人旅とか留学、一人暮らしなどもその範疇に含まれると思う。
要は見知らぬ環境に身を置くことで、“自分”というものが一度否定される。その上で全く異なる一段ブラッシュアップされた価値観や考え方を手に入れる。かわいい子に旅をさせてある程度の地獄を見せれば、不思議とその子は一人前になって帰ってくる、ということを昔の人は理解していたのだと思う。昔の剣術遣いは廻国修行を経て一人前とみなされたし、現代でも実家暮らしの奴は独り暮らしの奴に何となく馬鹿にされる風潮がある。
見知った人ではなく、赤の他人というフィルターを通して自己を認識し、そして必要に応じて変化することではじめて一人前と認められるのだ。
なぜ通過儀礼が必要なのだろうか?それはその者が未熟だからだろう。従って通過儀礼の過程において、誰かしらの理解者・協力者が必要になってくる場合もあると思う。メンターじゃないが、その者の至らない点をサポートしたり助言してやったりする者がいて初めて通過儀礼を完遂できる場合もあるのではないか。さらに、その協力者なり理解者は現地で探す方が良いだろうと感じる。家族や元からいる友人ではなく、自力で開拓した人間関係の中で、社会生活を営んでいくことが大切なのだ。
『千と千尋の神隠し』では、ハクという少年が協力者にあたる。捨てる神あれば拾う神あり、というが常世に迷い込み両親が畜生になって、そのままくびれ死んでもおかしくなかった千尋に、ハクは救いの手を差し伸べる。
ハクはなぜ千尋を助けたのか?その理由はよく分からない。ご都合主義と言ってしまうと元も子もないが、こういった唐突な救済、偶然はしかし現実世界でも度々起こりうることだと感じる。現実世界でも自分が困っている時に、意外と誰かが助けに入ってくれた経験がある人は多いと思う。また誰かに相談したら、意外とあっさり抱えていた問題が解決した経験があると思う。おそらく神と言えど人と言えど、基本的にはそれぞれの関係性とその営み中で暮らしていくしかないため、その営みをすべからく循環させる試みとして、誰かが困っていたら助ける、という構造が成立するのだと思う。誰かを助ければ、自分が助けてもらえる可能性が生まれる。家族だったら理解できるが、何で赤の他人である自分にこんなことをしてくれるんだろう、仕事じゃあるまいし、と最初は思うかもしれない。ひねくれた人間なら、時間と手間を投資して自分に何かしてくれるなんて、この人下心があるんじゃないかしら、と思うのかもしれない。そうでなくとも、もしかしたらハクにも油屋に来た当初、助けてくれる人物がいて、自分がしてもらったことと同じことを千にしただけかもしれない。しかし、結果的にハクが窮地に陥ったとき、千は身を挺して恩返しをしたわけで、長い目で見れば両者の関係はウィンウィンである。
結局はこういう不確実な関係の中に身を委ねることでしか自立した自我というものは成立しないのではないか、と思う。家族というあらかじめ用意された関係の中を抜け、外の世界に行き、自分で自分の居場所を確立する。一人前になるというのはそういうことなのだ。

放っておいたらどうなっていたんだろうか…?
千尋は名前を奪われ、千となる
この映画が通過儀礼の物語だと考えると、湯婆婆が千尋の名前を半分奪うことも納得できる。名前を奪われるまでもなく、千尋は未熟な人間だからだ。要するに物語序盤の千尋は半人前だということで、湯婆婆の言葉を借りるなら「見るからに愚図で甘ったれで泣き虫で頭の悪い小娘」なのだ。
ただし、問題があるのは千となった千尋だけではない。「油屋」にいる従業員のほとんどが何かしらの欠陥を抱えているのだと思う。彼らのうち、男はカエル、女はナメクジだし、リン(白狐)にしろハク(竜)にしろ何かやむにやまれない事情があって「油屋」にいるのだと推察できる(ハクは魔法を覚えるため、リンの目的は不明だが「いつか町へ行く」と言っている)。湯婆婆にしたって、双子の姉である銭婆と二人で一人前なのだ。要は「油屋」とは満月を夢見る半月の集まりで、それを的確に表現する方法として“名前の一部を奪う”という秀逸な設定を用いたのだと思う。
名前を奪われた翌日、千が自分の名前をハクに教えられて困惑する場面があるが、これは現実世界でも通用するような反応だと思う。例えば、学校や職場で馬鹿だとか愚図だとか言われ続けると、本当にそうだと思い込んでしまう現象があるのではないか?筆者も昔職場であまりに使えなさ過ぎたため、上司から「お前、勉強以外なんもできねぇか?」と吐き捨てられたことがある(筆者は大学中退で専門学校卒。その上司は中卒で映像業界に入ってドラマの制作担当までいった人だった。今から考えると、その人は学歴コンプレックスというやつだったのかな?と思う)。言われた直後はうるせぇばか、くらいにしか思っていなかったが、ミスする度に馬鹿だとか愚図だとか言われているうちに徐々に心が削られていって、自信がなくなっていき、自分は本当に駄目なんだなぁ、となっていったのをよく覚えている。自信と自身は一字違いだが、個人差はあれど人は呼ばれる名前や、名前の上に冠される肩書や学歴といったものに想像以上に影響されるものではないか?と思う。

社会人1年目は人生で一番辛い年だという。
誰しも辛い境遇の時に誰かが自分を慰めてくれて、そのおかげで今の自分がいる…
という経験が何かしらあるのではないか?
半月・カオナシ
油屋の従業員たちは働かなければ豚になってしまう哀しい存在で、一人前になろうと日々あくせくしているわけだ。しかし、彼らのような半月ではあるが、彼らとはまた異質な存在がこの映画には出てきて、それが“カオナシ”だったりする。この妖怪(?)は自分の言葉を持たず、表情にも乏しく、そしてお札や砂金などの贋作を出現させる不思議な力を持っている。ハクの魔法にかかって気配が消えているはずの千尋を感知していたことから、それなりの手練れなのかもしれない。しかし、このカオナシもやはり半月なのだ。誰かと喋る時は人の声を借りねばならず、砂金を出す妖術にしても自分で考えてそれを出すというよりも、むしろ相手がその時欲しいと思っているものを出す、という相手依存の術なのだ。
このカオナシと油屋の従業員たちとの最大の違いは、結局のところ主体性だったりする。自分の現状についてどう思っているかは定かでないが、少なくとも油屋の従業員たちは自分の意志で「ここで働かせてください」と湯婆婆に申し出た上で働いているわけだし、ハクやリンのように明確な目的を持っている者も少なくないだろうと思う(当初の目的も忘れてその日暮らししている者もいるだろうが)。しかしカオナシに関してはよく分らない。千のことが好きで、他の従業員みたく取り込みたいようにも思えるが、それなら腐れ神が来訪した際、薬湯の札をあげるときに、本物ではなく自身の出した偽物を渡せば取り込めただろう(咄嗟のことだったので術を使う余裕がなかっただけかもしれないが)。砂金をばらまいて“お大尽様”ともてはやされる様になった後も、食ったり飲んだりで大騒ぎし、自身の長所である隠密性を消してしまっている。何ともチグハグな奴なのだ。
人の声を拝借し、自分で稼いだわけではない模造品の金品で人を惑わし、人の足元を見て横暴になる。油屋の従業員たちは自分の意志で身を粉にして働いているが、カオナシは努力することなく欲望を達成しようとする。見ている最中は「これは宮崎駿監督から見た現代の若者像なのかな?」と思ったりもした(宮崎監督はアニメ好きの人をあまり快く思っていないようだし)。自身を顧みても、ニート時代の自分は確かにカオナシのような気質があったかもしれないと思う。親の家で働きもせずゴロゴロし、友達と飲んでは虚勢を張り、親に何か聞かれれば嘘をついてごまかす。心のうちにいつも失意を抱えていて、それでも自分から行動しようという気にはならない。自暴自棄になることはなかったが、親からすれば我が子と言えども何を考えているのか分からない、薄気味悪い存在だったろうなと思う。

覚悟を決めて千尋に話しかけるでもなく、客として訪れる度胸もなく、
さりとて潔く引き返す気もさらさらない。
中途半端で何がしたいのか分からない。何とも煮え切らない奴なのだ。
完全に余談だが、アメリカン・ニューシネマに『ファイブ・イージー・ピーセス』という映画があって、親子の断絶が描かれている。音楽一家に育った息子が、自分の才能の無さに絶望し、厳しい親の期待に応えられない自分を不甲斐なく思い、締め付けてくる家を飛び出して工事現場などの作業員をやりながら日銭を稼いで暮らしている。数年ぶりに帰省すると、父親は脳梗塞かなんかをやらかして喋れなくなっており、車椅子での生活を余儀なくされている。散歩に出る二人。主人公は父親の車椅子を押すが、ふと手を止め、向き直って心情を吐露する。「姉さんは2人で話せと言う。俺と父さんが分かり合えると思ってるんだ。初めから、お互いに心が通じないのを知らないのさ」と。父親からの返事はない。ほとんど植物人間のようになった父親からは表情が消えており、喋ることもできないため、父親の意志というのを推し量ることはできない。主人公はしかし、告白によって胸のつっかえが取れたのか、ある程度納得した様子だ。彼はこう言ってシーンを締めくくる。「俺にできるのは謝ることだけだ。すまないと思ってる」と。
上記のシーンを見たとき、筆者はハッとした。これは要するに、修復不可能な親子関係を描いているように見せかけて、実は世代間の断絶を描いていると思ったのだ。例えば、パソコンでも携帯電話でもユーチューブでも、何か新しいものが出た時に拒否反応を示すのは若者ではなく、若者の親世代だと思う。大部分の親たちはユーチューバーになりたいという子どもの気持ちが分からないし、何でもかんでもスマホだクラウドだと言って、人間と人間のつながりを軽んじる下の世代たちのことを理解不能なものだと思っているかもしれない。しかし、実は逆もまた然りで、下の世代も上の世代のことをよく分らないと思っていることが結構あるのではないか?仕事が終わったらさっさと帰って休めばいいのに、何でやたらと飲みに行きたがるのか?意味もない残業を何故毎日のようにするのか?ワードやエクセルを使えばいいのになんで手書きにこだわるのか?卑近な例を挙げたが、要するに『ファイブ・イージー・ピーセス』という映画は、世代が一つ違えば、お互いのことは理解不能で、永遠に分かり合えることはない、ということを観客に突きつけた映画なのだ。綺麗ごと抜かす奴等もいるけど、結局親父の気持ちは分からないし、ガキの気持ちもまた分からない、という非常にドライなことを主張しているのだ。

彼は当時のアメリカの厭世感、若者の自堕落さを体現したキャラクターなのだ。
カオナシもまたよく分からない存在である。自身に当てはめてみるのも面白いかもしれない。筆者はニート、映像制作、会社員、アルバイト等を経験しているが、その全てにカオナシのような要素が潜んでいると思う。ニート時代は先に述べた通りだし、会社員である今もやはりカオナシ的なものは持っている。言いたいことを言わず、参加したくもない飲み会に参加しておべんちゃらを使っている。相手の求めるリアクションを無意識に探り、表情を作り、相手に向かって差し出す。AD時代なんてその最たるものだった。こうして映画の記事を書いている今でさえも、『千と千尋の神隠し』という宮崎駿監督とジブリ関係者が血の小便出しながら作った映画をネタに好き勝手なことをほざいているのだ。全く救いようがない。
もしかしたら、カオナシとは現代病なのかもしれない。
過去を振り返る者は死ぬ…「決して振り向いちゃいけないよ」
映画の主人公の宿命として、物語を前に進めていかなければいけない、というものがある。映画は大体90分~180分の間の出来事なので、とにかくせっせとプロットを展開していかないといけないのだ。そのため、主人公は行動し、アクションを起こし、困難を突破し続けないといけない。逆に言えば、物語の世界で立ち止まり、過去を振り返る人物は軒並みロクな目に遭わないということでもある。
「決して振り向いちゃいけないよ」とは、千尋が現世に帰る際にハクに言われた台詞だが、これはそのまま映画の法則にも当てはまると思う。もしあそこで振り返っていたら、千尋はきっと二度と現世には戻れていなかったのだと思う。日本神話でイザナギが蛆まみれのイザナミから逃れる羽目になったのも、やはり振り向いてはいけないと言われた状況で振り向いてしまったからだ。物語を進めるために存在するはずの登場人物が、立ち止まって過去を顧みることは御法度だ。こうしたことは物語の中で繰り返し言及されていて、従ってハクのあの台詞は物語の法則に準拠したものだったと言える。『千と千尋の神隠し』は、こうした物語の法則に則って作られているのだ。
映画記号について
結論から述べると、『千と千尋の神隠し』がアカデミー賞をはじめとして各賞を獲れたのは、作品のクオリティが非常に高く、カオナシなどのキャラクター造詣が優れていたこともさることながら、作中に映画的な記号がふんだんにちりばめられていたからだと思う。
例えば、この映画はトンネルをくぐって物語が始まる。そして、映画の中のトンネルとは単なるトンネルではない。端的に言うと、物語の世界では日常の世界と、非日常の世界があって、それをつなぐのが“トンネル”などの映画的記号だということだ。我々が平穏に暮らす日常の世界と、我々の常識が通用しない非日常の世界があって、そこをつなぐ境界としての“トンネル”が物語の世界には存在する。そこを一度通り抜けてしまったら理不尽な非日常が襲いかかってくる。
こうした映画記号の良いところは、無駄な説明を省略できるという点だ。なぜトンネルを潜った先には神々がいて、それらをもてなす“油屋”があるのか、その近辺に住んでいる人たちはなぜ気が付かないのか、観客が思わず「?」となってしまうようなことに説明を加えることなく、即座にシフトすることができるのだ。なぜなら、“トンネルという境界線をくぐる”という視覚的動的なイメージを観客に見せているからだ。そこに映画的な記号を配置して、それを的確に捉えて観客に提示できれば、本来必要なはずの手順を省略してはい次、という風に物語を進めることができるのだ。こうした映画記号のテクニックは、脚本家というよりも監督の力量がものを言う。要はどちらかというと演出の範疇なのだ。別にトンネルなんてなきゃないで成立はすると思うのだが、それだと説明をしなければならない。しかしトンネルを潜るという視覚的な表現を噛ませておけば、余計な説明を省くことができる。
そして、こういう映画記号的表現は映画好きを感動させる。あくまでも個人的な見解だが、こうした映画的記号を上手に用いた映画というのは、賞レースに強いと思う。映画賞に出品するのは基本的には映画が大好きな人だろうし、それを観て審査するのもまた映画好きだからで、こうした映画的記号というのは映画好き(特にシネフィルと呼ばれる人たち)にとっては垂涎もので、たまらないものだからだ。

これは川端康成の小説『雪国』の冒頭部分だ。
雪国の鮮やかな銀世界を連想させると同時に、未知の世界が広がっていたことを示唆している。
『千と千尋の神隠し』も、やはりトンネルを抜けてから物語が動き出す。
繰り返される境界線のイメージ
トンネル以外にも『千と千尋の神隠し』には境界線のイメージが頻出する。最もよく出てくるのは、橋のイメージだと思う。映画の中で千尋は何度か橋を往復する。ハクの導きで湯婆婆に会いに行く時、豚になった両親の元へ行く時、銭婆のところへ行くために電車に乗る時、ハクを救って油屋に帰って来た時、などがそれだ。この橋が日常と非日常を分かつ境界線とするならば、それは千尋と千を分かつ橋だといえるかもしれない。つまり、橋を渡って油屋に行けば労働者としての“千”、橋を渡って元来た方向に行けば一人の人間としての“千尋”、ということを表しているのかな、という憶測も成り立つと思う。
また、別パターンの境界線イメージでは線路がある。線路も昔から映画で繰り返し使われてきた映画記号の一つで、駅と駅とを分かちつつも同時につなげている装置だ。映画の後半、千は瀕死のハクの呪いを解くために銭婆のところへと赴く。その際に電車に乗るのだが、車内には半透明の人々が出てきて何となく不気味である。多分だが彼らは死者で、未練があるのかやり残したことがあるのか、それとも消滅の前にやり遂げるべきことがあるのか、電車に乗って目的の場所へと行こうとしているのだ。それが他者にとって不吉をもたらすのか、はたまた彼らの魂に安寧をもたらすのか、いかなる結末をもたらすのかは推し量るしかないが、一つ言えることは、映画の中に出てくる電車には、確かに不吉なイメージが付きまとうということだ。例えば映画の中で主人公が電車に乗ったら、やっぱりどこかで強盗が乗り込んできたり、何かしら事件が起きることを期待してしまいがちだと思う。これは移動に関することで、駅から駅に向かうという行為が、こちら側からあちら側に向かうというイメージを有しているので、様々なことに置き換えが利くためだ。此岸と彼岸でもいいし、常世と現世でも良い。日常と非日常。オープニングとエンディングでもいいだろう。AからBに向かうとして、AからBに至るまでの間にはもしかしたら魔物が潜んでいるかもしれないし、テロリストが待ち構えているかもしれない。少なくともAとBの間に何があるかは我々観客は知らされていないため、いくらでも想像力を働かす余地があるのだ。要するに、映画の世界である地点からある地点まで移動するという行為には常に困難が付いて回る、ということだ。主人公は物語をすすめようと前へ前へと目的地に向かうが、目的を達成するには葛藤がつきもので、Bに向かっていると思っても、邪魔が入ってそのまま死んであの世に行ってしまうかもしれない。我々が普段乗っている電車は、滅多に事故を起こさないが、映画の世界の電車は何かとトラブルが起きやすい演出装置だと思う。
実際、『千と千尋の神隠し』に出てくる電車もかなりイレギュラーな列車だ。何せ死者が乗っていて、千は片道分の切符しか持っていない。ハクを救うという目的を胸に抱いているが、銭婆の機嫌次第では命を落とすことだってあり得るのだ(大人しくしているが、さっきまで激怒して大立ち回りを演じたカオナシも同乗しているし)。
そして、こうした不穏なイメージを含んだ電車(と線路)というモチーフもまた、映画好きにはたまらないものなのだ。もしかしたらこうしたイメージは台本上では非常にあっさりした書かれ方をするのかもしれない。それともふんだんに情景描写がなされ、キャラクターの心情から動きの一つ一つまで細かく書いているのかもしれない(そういう台本はあんまりないと思うが)。そうした台本の空白なり行間なりを感情表現や心理描写、人間の動きなど埋めることが演出の最たる仕事だとするなら、こうした電車という装置を使って、本来なら映像には映らないはずの主人公の覚悟や思いを表現するというのは、物凄い技術なのだ。だってこの演出が失敗したらスクリーンに映るのはただ電車に乗っている人、になってしまう。筆者もドラマの撮影現場に従事した経験があるから少しは分かるのだが、監督とは本来非常に孤独な存在で、常に不安と闘っているはずなのだ。このシーンはこのカット数で大丈夫なのか、何かやり忘れた、言い忘れたことはないか、俳優や助監督、カメラマンにこんなこと聞かれたらどうしようとか、編集でうまくつなげるように撮れているのか、そもそもこのシーンはこの撮り方で面白くなっているのか、演技はこれで大丈夫なのか(ちなみに何十年も助監督をやっている方曰く、監督が不安なほどカット数が増える傾向にあるようです)、などなど。監督は撮影現場のヒエラルヒー最上位だが、同時に抱えている責任や不安も凄いのだ。並の監督だったら電車に乗る千の覚悟を、表情や台詞で表現してしまいそうだが、宮崎監督は電車という装置、あるいは片道切符という小道具を使って、分かりやすい方向に走らずテクニカルに千の覚悟を表現することに成功していると思う。

主人公にも、物語で成し遂げたい目的がある。
電車とはそのことを強く視覚的抽象的に示すことのできる装置だと思う。
また、線路のイメージとはそれだけで非常に映画的なものだ。線路を誰かが歩いているだけで、もうそれは何かしらの意味を持つと思う。自分の道を往く、という決意を見て取れるかもしれないし、結局お前は人が敷いたレールの上しか歩けないんだよ、という突き放した見方もできる。また、線路の先には駅があるはずだから、駅を何かの光明に置き換えて、その人生の希望に向かって歩いているのかもしれないし、もしかしたらその駅は希望ではなく実は絶望の暗夜行路なのかもしれない。そこらへんは物語の文脈によるだろうが、希望にしろ絶望にしろ、台詞で何か言うよりもよっぽど視覚に訴えることの出来る演出方法だと思うのだ。ちなみにこの映画に中の線路を描いた最もメジャーな作品として、『スタンド・バイ・ミー』があると思うのだが、どうだろうか?
物語に漂う不穏な水のイメージ
この映画には水のイメージがたくさん登場する。例えば川であったり、海であったり、雨であったり、そもそも銭湯という舞台がすでに水まみれだったりする。そして個人的に思うことなのだが、映画に出てくる水というのは不吉な印象があるのだ。
川でも海でもいいのだが、画面にぱっと水が出てきて想起するものは死というものであると思う。海には人食いザメがいるものだし、河はたびたび氾濫を起こす。また八岐大蛇などという化け物がいるし、何でもない川でも三途の川を連想することができる。また、水場には霊が多いという俗説もある。何が言いたいかというと、創作において水というのは多分に不吉なものだということだ。
そして、水というイメージもまた、映画賞では強いのだ。例えば雨。西洋圏では特にそうだが、雨が降ると連想することは洗礼であり、生まれ変わりというものも思わせる。要するに、水のイメージは死を連想させがちだが、同時に生まれ変わりの可能性も秘めているのだ。
主人公が河の前に立っている、効果的なアングルで撮られていればそれだけで印象的な画だが、主人公が足を進めて河を渡り出したらどうだろうか?彼または彼女は“河を渡る”という行為を完遂できるだろうか、急流に流されて藻屑となりはしないか、或いは河の奥底に潜む得体のしれない魚や幽霊に足をすくわれやしないか、凍え死ぬんではないか。逆に主人公が無事に河を渡り切ったら?それはもう過去の主人公とは別の人間であり、一つの葛藤を乗り越え、死を潜り抜けて生まれ変わりを果たした人物だと思うのだ。人間は暗い羊水の中で育ち、そこを脱することで産声を上げる。もしかしたら、海は生き物にとっての胎盤なのかもしれない。ただしそこは弱肉強食の法則が作用する恐ろしい場所でもある。人間の先祖は立ち止まることなく前へ前へと進み続け、海の境界を越えて陸地に上がることによって、結果的に地上の覇者となった。映画における水とは、筆者にそういうものを連想させるのだが、皆さんいかがだろうか?おそらくだが、こうしたことを意図的にやっていて、しかも画面上に効果的に反映させている映画が世界の色々な賞を獲っているだと思う。そして、この水に関する演出の伝統は『千と千尋の神隠し』にも継承されていると思う。
総括
これまでグダグダと述べてきたが、要するにトンネル、橋、線路、水、振り返りという行為が効果的に描かれているから『千と千尋の神隠し』はアカデミー賞を獲れたのではないか、ということだ。宮崎駿監督の凄まじいところは、こうしたモチーフを複数個描いていることで、普通こういったモチーフは多くて3つか4つなのだが、何個も何個も作品にぶっこんで、それでいて全体の輪郭がぼやけないというところだと思う(今回は省いたが、ハクと千が落ちる“穴”というモチーフもまだあるのだ)。さらに言えば、こうした映画記号と物語のダイナミズムを両立させているところが凄まじい。「芸術はアマチュアでもプロでも作れるが、エンターテイメントはプロにしか作れない」と昔筆者に教えてくれた人がいたが、どちらかに極端に振れるでもなく、抽象的な表現をいくつも挟みつつ、きちんとエンタメとして成立させる剛腕演出は、並の監督では無理だと思う。
この『千と千尋の神隠し』を筆者はDVDで観賞させていただいたのだが、「そらアカデミー賞獲るわ」と、素直に感じたので、今回はこんな記事を書かせていただいた次第である。
以上。長文駄文失礼いたしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
