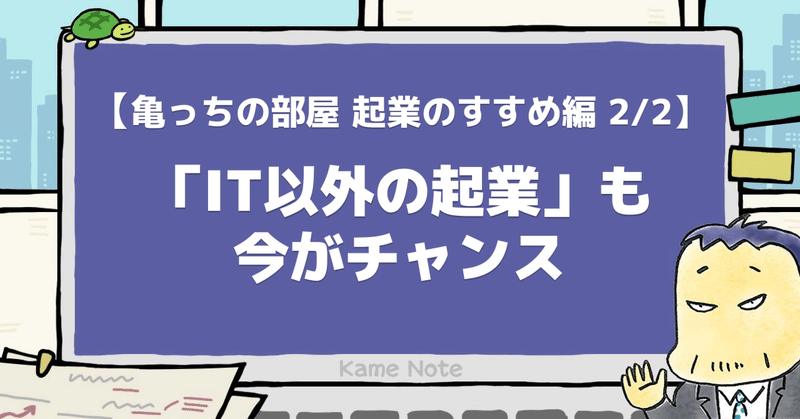
「IT以外の起業」も今がチャンス【亀っちの部屋 起業のすすめ編 2/2】
「NewsPicks」2023年07月28日掲載
※音声版は「亀っちの部屋ラジオ」でお聞きいただけます。配信先は Spotify、Apple Podcast、Voicyです。
今は格段にお金が借りやすい
野村 前編に続いて、今度はITではない業種の商売の始め方を伺います。
亀山 飲食店を開くとかIT以外の業種だと、投資家たちに投資してもらうのはやっぱり難しい。でもそこは、融資という手があるわけ。いわゆるデットだよね。
誰かに株を渡すんじゃなくて、お金を借りて商売を始めるってこと。株主は自分だけなので、借金さえ返せば稼いだ利益は総取りだし、上場するもしないも自分で決められる。うまくいけば、ストックに比べてもお得で自由な最強の起業だね。
国が起業支援と言ってるのは何もベンチャー投資だけじゃなくて、融資にも力を入れているんだよ。たとえば日本政策金融公庫なら、今はかなり緩い条件でお金を貸してくれる。
どれくらい緩いのかと思って知人に聞いたら、1〜3%の低い利率で、最大で自分の持ってる金額の10倍(上限3000万円)まで借りられるらしいね。
野村 そんなに借りられるんですか。
亀山 しかも最近は、個人保証なしのケースも多いらしい。昔なら個人保証か担保が絶対に必要だったし、俺がバーをするために初めて信用金庫から2000万円借金したときは、親だけじゃだめで親戚の保証もつけてくださいと言われた。
そこまでしてようやく借りられるとしても、金利は7~8%だったからね。
野村 いま考えると、信じられないぐらいの高金利ですね。
亀山 まあ当時は物価も上がっていたからね。とはいえ、もし事業で失敗したら、借金を背負って自己破産するか、一生かかって返すかのどちらかになる。少し前まではみんな、そういうリスクを背負って店を開いていたわけよ。
そんな時代を知ってる俺たちからしたら、これだけ低リスクでお金を借りられるんだったら、やったもん勝ちだよね。やらない手はない。
ITがさっぱりわからなくても、うまいラーメンを作れるというんだったら、それで起業すればいい。円も安いし、外国人観光客向けのバーやホテルを作るのもチャンスだよね。8割がたは数年以内につぶれちゃうけど、それでもITよりは成功率が高いと思うし。
野村 100人に1人、1000人に1人、というITよりは確率が高いと。
亀山 2店舗目、3店舗目となると別の難しさがあるけど、自分が現場に立って店をやりたいというのであれば、店を開くところまでできたら2割くらい残るんじゃないかな。
うまくいったら自分の夢が叶うわけだし、収入も上限がない。失敗しても「失敗した」という履歴が残るだけで、融資の条件が緩い今は失うものがあまりないんだ。だから投資だろうと融資だろうと、商売を始めたいなら「やらなきゃ損よ」と言いたいね。
もちろん融資の条件は金融機関によって違うから、そこは自分でちゃんと確認してね。
時代は「スタートアップ島耕作」?
亀山 さっき言った「失敗したという履歴」だけど、昔はたしかに「あいつは倒産した会社の元社長だ」とか白い目で見られることもあった。でも今は起業して失敗した経験というのは、ある意味プラスに働くと思うんだよね。
野村 そうなんですか。
亀山 少なくともIT業界ではその考えは多いと思うし、うちなんか、めちゃくちゃポジティブに見るけどね。
DMMは新規事業をどんどん立ち上げる会社じゃない。だから、起業家マインドは一番ほしいところなのよ。実際に会社を立ち上げて、資金調達に苦労して経営者の孤独を味わった経験は強みになる。教科書で勉強しただけの頭でっかちとは、全然違うよね。
起業家というのは、要するに社長だよね。社長って、バランスよくいろんな能力を理解できないといけないんだ。オーケストラでいうと指揮者みたいな存在だね。
野村 すべての楽器のことがわかっている存在ですね。
亀山 そうそう。技術も営業も、経理も……と複合的に理解しなきゃいけない。
とはいっても人間は完璧じゃないから、ピアノとバイオリンはわかるけど、太鼓がわからないというふうに、どれかが欠けている場合がある。そんな理由で失敗した経営者には、太鼓のわかる人間を補えばいいだけなんだよ。
つまり、総合力で欠けている部分があっても、DMMでそれを補うことができれば、マネージャーとしてやっていけるんだ。俺なんて、どの楽器も一切弾けないのに指揮者をやってる(笑)。起業して失敗したら、骨はDMMが拾うよ。
野村 なるほど。
亀山 それにこれからは、ITだけじゃなくて非ITのレガシーな大企業でも、起業家マインドが必要とされるようになると思うんだ。
野村 それはどうしてですか?
亀山 最近は「残業しないで帰りなさい」と言われるから、昔と違って猛烈サラリーマンがいなくなったじゃない。そんなマインドを刷り込まれてきたのに、管理職になっていきなり業績アップを求められたりするのは、チェンジできないと思うんだよね。
それだったら会社の大事なポジションには、外で経営を経験してきた人を抜擢しようとなるんじゃないかな。スタートアップでは失敗したけど、大企業に入って役員になれました、みたいなケースだってあるかもしれない。
野村 これまでのような「新卒よーいドン」だけではなくて、外で失敗も含めた経験を積んで、横スライドするようなキャリアパスが今後は増えていきそうですね。
亀山 経営をまじめに考えたら、そっちの方向に行くのが自然だと思う。「課長島耕作」じゃなくて、「スタートアップ島耕作」から大企業の役員になる、みたいな感じだね。
AI時代に求められる経営者的スキル
亀山 これから、AIの時代になるじゃない。人間の何をAIが代替して、何が人間に残されるのかと考えると、人間はますます、マネジメント力やプロデュース力が問われるようになると思うんだよね。
簡単なことはAIにやらせて、それを検証するような仕事の仕方になるだろうから、1から10まで自分で作るんじゃなくて、どういう指示を与えたらどういうものができるのか、どういう選択をすれば良いものを選べるのかということが大事になってくる。
編集者とAIが組んで、おもしろい漫画を生み出すこともあるわけよ。
野村 あり得ると思います。
亀山 こういうのって、マネージャーやプロデューサーの仕事だよね。つまりAIの時代では、起業家に限らずどんな職種であっても、マネジメント力が必要なスキルになってくる。
このスキルが一番身につくのが、経営者なんだよね。誰かの指示を待つんじゃなくて、このポジションに何人雇うのか、どこと取引するのか、別の方向にビジネスを切り替えるべきかとか、全部自分で決めないといけないから。
つまり、別に経営者になりたいわけじゃなくても、「一度起業してみるのはいい経験になると思うよ」ってのが、俺の言いたいことかな。
野村 組織で生きていくにしても、これからの時代に求められる汎用的な能力が、起業で身につくわけですね。
亀山 起業って大変じゃない。体力もいるし、トレンドをつかむ必要もある。だから、せっかくなら若いうちに起業してみて、そのスキルを元に今後のキャリアを切り開いていけばいいんじゃないかなと。
野村 会社員のまま、ある程度の年齢になってしまったら、やっぱり厳しいですか。
亀山 経営者のほうが100%の力で仕事に向き合えるから、若いほうが早いぶん有利だね。けど、AIの登場で求められるスキルがより総合的なものに変わってきたから、経験を積んだ強みを生かせば、何歳でもやった方がいいと思う。
いったん起業してまたサラリーマンに戻ったとしても、その経験で、より良いパフォーマンスを発揮できるようになるんじゃないかな。
野村くんはどうなのよ? 去年独立して、言ってみれば起業したみたいな感じじゃない? 会社員時代と比べて変わったことはある?
野村 会社員だと自分の職掌範囲がある程度決まっていて、その中で「いかにうまくやるか」で評価されていました。
けれど自分の会社となると、何をやるのか、それをやるためにどういう人に集まってもらうのか、どんなツールを導入するのかなど、すべて自分で決めなければいけない。自由な半面、その結果も引き受けないといけないのが最も違う点ですね。
ビジネスの勉強ばかりではだめ
亀山 そんなふうに総合的な力が求められるから、経営者は経営・経済の勉強だけをしていてもよくないんだよね。文学や歴史、哲学や科学とか、ビジネス以外のことにも目を向ける必要がある。
何だかんだいっても、AIは過去をまとめるツールなんだ。しかもそのデータは、ITでデジタル世界の中からしか引っ張ってこられない。だから人間は、山登りしたり、きれいな景色を見たり、人と出会ったことも含めて仕事に反映させれば、AIに勝てるってことだよね。
野村 デジタル世界だけのもので判断しないということですね。
亀山 うん。ちなみにこれからの日本は、AIやWeb3の分野でけっこう有利だと思う。アメリカのWeb3は冬の時代になっちゃったし、生成AIだって後ろ向きな国もある中で、日本は「どんどん活用しましょう」という姿勢になってるんだから。
こんなふうにグローバルで見ても有利だから、そこに投資が集まって、日本から本当のグローバル企業が出てくれないかという期待はあるんだ。
そしてこんなふうに今、俺が話していることは想像だよね。しかもその内容は、Web3やAI界隈の情報だけでなく、他のいろんな知識や経験から総合的に作られている。これが人間の強みなんだ。AIは未来を想像することはできないからね。
この想像力・妄想力を生かせるかどうかが、AIを使う人とAIに使われる人の分かれ道になると思う。これからは、AIを上回る人はやたらと給料が良くて、下回る人はかなり安くなってしまう、みたいな感じになるんじゃないかな。
野村 たしかに、人材の二極化、価値の二極化は起こりそうですね。
与えられたお題をうまくやることの価値が、AIの登場でどんどん低減していくと感じています。他のものと組み合わせたり、流れを変えたりして新しい価値を出せる人が、評価される世の中になるんでしょうね。
亀山 だから俺も仕事だけじゃなくて、一人旅をするとか、ものごとを広く見ようと思ってるけどね。みんな、勉強ばかりしてちゃだめだよ。空を見てボーッとするのも大事だよってこと。
せっかくなら社会の大変化を楽しむ
亀山 まあ俺もこう言いながら、実のところChatGPTは一週間くらいしか触ってないんだけどね。
野村 そうなんですか(笑)。かなり使い込んでると思っていました。
亀山 社員には全員やれと言ってるよ。使うたびに費用がかかるんだけど、金のことは気にしなくていいからしばらく使えって。そう言いながら、俺がやってないという(笑)。
野村 さすが、楽器の弾けない指揮者(笑)。そういえば仮想通貨のときも、亀山さん自身はビットコインを買ったことがないと言っていましたよね。
亀山 まあ楽器が弾けないままでも、「ピアノはこんな音がするんじゃないかな」って想像力だけで、ここまでやってきたから。
野村 それで成立してるのがすごいと思いますけど(笑)。
経営者は経営の勉強だけでなく、いろんなコンテンツに触れることが重要という話があったじゃないですか。人によって分かれるところでしょうが、私はそういう価値観、けっこう好きですね。
いろんな人に会って、いろんなジャンルや体験に触れて、それを自分の頭の中で組み合わせて妄想していく。それが価値につながる時代って、楽しいだろうなと。
亀山 天変地異とか政治体制とか、社会が大きく変わるときに、それを不幸に感じるかおもしろいと感じるかは、人によって違う。けど、温暖化になったり人口が減ったりと、どうやっても社会は変わっていくんだから、それを楽しめたほうが幸せだよね。
だから、自分がすべての最終決裁者になる起業のような経験をしてみることは、失敗したからといって、何かしらの価値はある気がするのよ。
野村 そういう経験を、意識して取りに行こうということですね。
亀山 そうそう。俺もリスクを取って商売をしてきたことで、いろいろ学んでいる気がするし。しかも今は、起業するリスクが昔よりもずいぶん低くなってる。
だから、やらなきゃ本当に損だよ。
起業する阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら起業せにゃソンソン、で締まったね。
前の記事(1/2)
起業するなら「今」と語るワケ【亀っちの部屋 起業のすすめ編 1/2】
