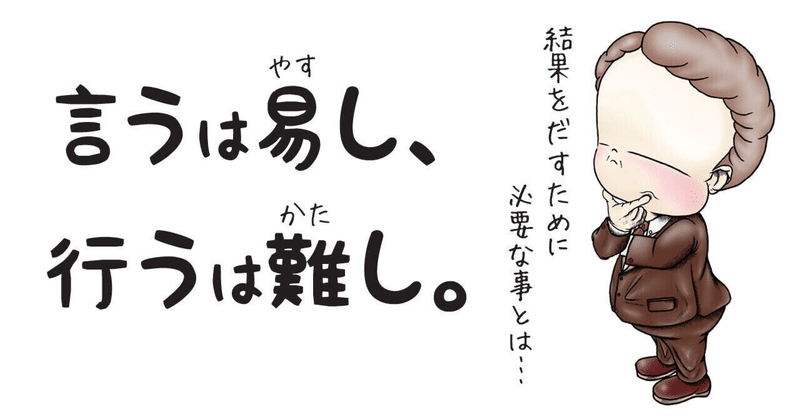
EC通販の利益創出について考える
EC通販の利益創出について考える
コロナ当初のEC通販バブルも1年か1.5年ぐらいで落ち着いて、昨年あたりからは当初の売上に戻りつつあるという話を良く聞く。また同じ時期に沢山の異業種(サービス業やB2Bの製造業など)がECサイトをオープンしてチャレンジしたが、それもコロナ明けで一段落。良い企業は本業回帰で回復したり、別サービスが伸びて業績が回復したり、別のメイン商品が出来て回復基調などの喜ばしい話も聞く。
本来、EC通販ビジネスは高利益を目指すビジネス
これは自論でもあり、利益を公表している上場企業などの利益率で分かるように、概ね営業利益で5%~10%。もしくはそれ以上の20%などの利益率を見ることがある。DTCなどのビジネスで分かるように自社で生産(OEMを含む)して直販する。かつIT化などで間接費を抑えるモデルからも分かりやすい。
例えば、下記のような事業構造。
・商品原価 10~50%(商品ジャンルや生産・仕入方法によって大きく変わる)
・広告等プロモーション経費 5~30%(事業参入時期で拡大基調の時は50~100%という数字も良く見る)
・主な間接経費 20~30%
物流費用、システム費用、人件費や設備費用。※店舗販売などに比べてスタッフ数が少なく済み、BPOなどのアウトソーシングも多いことから他業種に比べて低くなる傾向あり。
・その他費用 商品開発費用など。
結果、事業モデルとしては弊社が提唱してきた「商品原価・プロモーション費用・間接経費+営業利益」が「1・5・4」~「3・3・4」などのDTCモデルか、「5・2・3」などの仕入れモデルやネットモール型などに収まり、詳しくは過去のブログをご参照ください。
EC通販の事業構造
もしくはAmazonに詳しく記述した自書を出しておりますので、リアル本が良い方は下記もご参考にされてください。
「単品ECハンドブック/A4版」
例えば、飲食業の一般的な事業モデルは、
食材原価/30%+人件費/30%+家賃/10%+その他の経費/20%で、営業利益は5%~10%。なお販促費は5%程度とも聞く。EC通販の事業モデルと似ているように思えるがプロモーション費用が違うのと、物流・システム関連費用が違う。事業モデルが違うので当たり前であるが・・・ここを理解されず、別業種からEC通販に参入される方々が広告費用を準備されていなかったり、システムも安ければ良いとシンプルなカートだけ用意して、広告もしなければ売れる訳が無いのだが、この話は今回の本論ではない。もしくは自販機ビジネスを検討された方が賢明かもしれない。
生産・仕入コストを圧縮する
これは弊社の本業ではないので、いわゆる生産管理のプロに任せるとして現場で良く聞く話。
・効率化
生産効率を上げるためにスタッフの勤務時間や配置を考えたり、シフトや残業圧縮や機械化を計るなど。
・原料費の圧縮
単純な仕入れ交渉は通じないので、仕入れ先のロットや輸送方法、また新素材へのチャレンジなど。
・ロット拡大
利益創出で一番効くのが明後日(2023年10月1日)からも多い上代の値上げや商品重量や入り数を少なくする。この秋はこれが一番良いと考えているが手を付けていない方々は直ぐに検討された方が良い。ロット拡大については数倍ぐらいの拡大ではそれほどの貢献は無い。生産現場の詳細が分かっているなら、例えばOEM企業でも抽出釜を大きくしたり、先方のコストダウンにつながる事柄とそのロットで話をしないと始まらない。もちろん販売数アップと共に取り組むことなのでマルチチャネル販売の検討なども重要。
生産管理については多くを触れられないので、発想転換の時によく使う方法としては「社会問題の解決」でどんな事が推進されているか?
・例えば、2024年問題として良く取り上げられる物流問題。ドライバーの方々などの働き方改革や、教育や医療の現場での先生たちの残業圧縮など。これを発想転換で考えるとモーダルシフトなど。トラック輸送を列車輸送や船便など活用できないか?~原料仕入れ時に考えられるし、中間輸送費の圧縮など検討に値するかもしれない。残業圧縮については業務の一部を外注化。また一人だけに負担のかかる=一人だけに現場のノウハウが集中することを避けるための複数によるチーム業務にして、時短の社員さんを増やしたり、副業可能なプロの応援をいただいたり、弊社のような販売代行会社にサイト運用は預けてもらったり等。
商品の再考
上述したように、今は「値上げ時期」である。原料や光熱費の高騰や人件費アップなどの事を考えて適正な上代になっているか?弊社でも昨年からお得意先の複数とご一緒にテストを繰り返しながら、10~20%などの値上げチャレンジを多くして、概ね上手く行っている。販売数量が当初少し下がるのは否めないが、それを金額でカバーしている。金額でカバーすると商品販売額に占める下記の物流費やシステム関連経費が下がるので、利益率は上がる。それと同時に一部の送料有料化も効く。
そして10年以上も前から合言葉として、商品は「薄くて、軽くて、配りやすいモノ」を考えましょうと主に単品通販や食品・雑貨メーカーさんと取り組んできた。3センチ厚のA4サイズで1kg以内や60cm→40cmへの検討など。
一番わかりやすいのはコレも物流費のダウンであるが、資材費のダウンや友人紹介が増えたりするメリットがある。「薄くて・軽い商品」は物流費や資材費のコストダウンとなり、「配りやすい」が友人紹介につながり、実は定期コースの維持率にも貢献する。
また商品のラインナップ強化として、プレミアム商品や低コスト商品などの品ぞろえ強化を行うと一時的に仕入れコストや生産コストはアップするが、クロスセルやアップセルを仕掛けやすくなるので、普及品の上代を変えずに客単価アップやリピート率の向上(休眠客の復活も)というサブメリットも出てくる。
物流・システムコストのダウン
さあ、コストダウンで本丸とも言えるこの項目。物流費については6~7年前に配送会社の各種値上げはこの後も続く。2024年問題はEC通販企業にとっては物流スピードのダウンと共に物流費のアップと捉えておく必要がある。従ってコストダウン交渉はほぼ難しいと考えて、商品の小型化による物流費コストのダウンが分かりやすい。また倉庫内の作業効率化も聞くし、東西の物流拠点で複数からの配送も効く。もちろん複数の配送会社による相見積もりは続くであろうし、詳細な条件詰めも必要ではあるのだが。
システム費用については、これは新しいシステムに変えることによる人件費の圧縮と共に考えた方が良いので、複数年で考えるべき。本丸と書いたが、個別のケースが多いので、自社の経営戦略として、また中期計画の中で位置づけて推進していきたい。当たり前であるが目的のはき違えで、新しいシステム導入ありきで臨むと、考えても見なかった「しっぺ返し」があったりするので、例えば新システムが動かない等の悲惨なケース。なので、コストダウン=業務効率化につながるという事と、顧客の定着化やファン化に役立つ機能重視で臨みたい。システムと言う意味ではRPAなどの導入で業務効率化や機械化(自動化)などから始めるのも良いと思う。
その他の経費圧縮
一番大きいコストは広告費なのだが、今後もCPA高騰のままであると前提していた方が良い。なのでアナログ媒体にチャレンジしたり、新規獲得はコストであるので最低限度の件数をキープしつつ、CRM活動強化の方が利益創出につながる。長期借入金などの資金調達と共に、各種の補助金や助成金も検討したい。例えば、IT導入補助金や販路開拓助成金や事業再構築補助金や小規模持続化の補助金などは私は税金の取り戻しだとも考えている。
ご興味ある方々は、一度ご意見交換もしてみたいので、気軽にHPからお問い合わせください。最後までお読みいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
