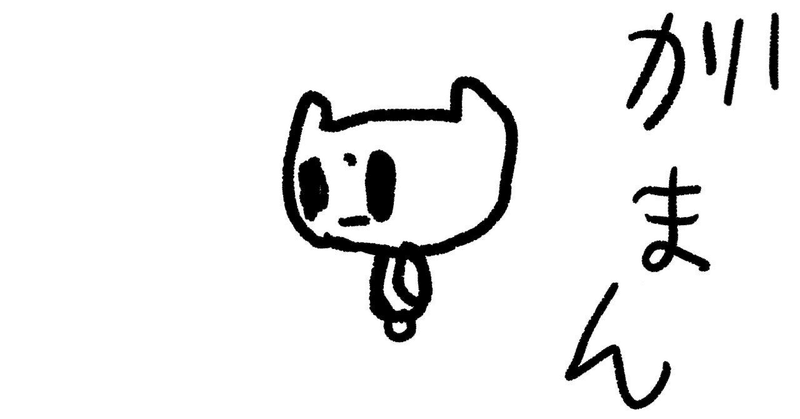
日銀が耐え忍ぶ円安、そして実質賃金低迷
円相場で注目される毎勤統計
8月9日、厚生労働省が発表した6月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所、以下毎勤統計)は1人実質賃金が前年同月比▲1.6%と15か月連続で下落しました(減少幅も5月から拡大):
同日の東京時間ではこれが円売り材料として受け止められたとの解説も見られ、非常に興味深く感じました。黒田体制時代から日銀は「+2%の物価目標を念頭に置いた上で名目賃金上昇率が+3%、つまり実質賃金が+1%上昇の姿が理想的」という情報発信をしてきた経緯があります。周知の通り、そうした賃金上昇の必要性・重要性は植田体制発足以降、声明文に明記されているところでもあり、為替市場で材料視されること自体に根拠はあります。実質賃金の仕上がりが悪いほど、日銀に対する引き締め期待は萎むことになり、円売り安心感が醸成されるわけです。いくら春闘が30年ぶりの上昇率を確保しても、実体経済の消費・投資動向に大きな影響を持つ実質賃金の仕上がりが悪ければ話は進みません。今後、毎勤統計が円相場の取引材料となる展開は念頭に置くべきものかもしれません。
円安の「負の側面」を表す実質賃金
こうした実質賃金の情勢は長引く円安相場と無関係ではありません。今年に入ってから「昨年の『悪い円安』論はどこへ行ったのか」という論調をしばしば目にします。筆者から言わせれば「どこにも行っていないし、問題の所在は昨年と変わっていない」というのが実情に思います。日本でも株高が進み、GDPもプラス成長が続いてることもあって、円安の「負の側面」は昨年対比で確かに議論されにくくなっていますが、慢性化する実質賃金の低迷はどう考えても円安はやはり絡めて考えるべきものです。
実質賃金の変化率は、定義上、①労働生産性、②交易条件、③労働分配率の3つの変化率に分解できます。図に示すように、昨年来、実質賃金の押し下げに寄与しているのは交易条件です:

輸入物価の相対的な上昇で悪化する交易条件は円安と共に悪化する計数です。昨年は資源高と重なったことで過去に類例のない悪化に直面したことは周知の通りです。スポット市場で起きた円安が即座に国内物価上昇に効くわけではなく、為替予約のリーズやラグズも影響する中で、時間を置いてから実際の値上げとして現れます。1ドル152円をつけたのは昨年10月下旬でも、市井の人々が感じる物価上昇、ひいては実質賃金下落は今年に入ってから本格化しており、円安に伴う「負の側面」が消えてなくなったわけでは全くないでしょう。「昨年の『悪い円安』論はどこへいったのか」という疑問に敢えて答えるとすれば、それは単に報道する側や多くの市場参加者が「見ようとしなくなった」だけに思います。毎勤統計は定期的に、その「負の側面」を思い起こさせる契機になります。
円相場で注目される毎勤統計
日銀自身がそう述べているように、実質賃金が上昇しない以上、緩和路線は持続される筋合いにあります。しかし、緩和路線を持続することが円安の背景になり、実質賃金を押し下げているという事情もあります。一方、円安や資源高による物価上昇の機運があるからこそ春闘で30年ぶりの上昇率が確保されたのも事実です。総合すれば、当面は「金融緩和やそれに伴う円安、結果としての実質賃金下落に目を瞑りながら、名目賃金がキャッチアップを座して待つ」という局面が想定されます。今年の春闘の仕上がりはそうした理想シナリオの兆しというのが日銀の基本認識です。
しかし、今年の春闘は+4%台のCPIを参考に展開されたという経緯がある。これが半分の+2%台になる2024年の春闘は必然的に熱量が下がってくることが予見される。みずほリサーチ&テクノロジーズ(RT)の予測によれば、2024年の春闘賃上げ率は+3.2%(ベースアップ分1.4%)、2025年を+2.8%(ベースアップ分1.0%)と近年の日本としては高い伸びを維持できそうであるものの、鈍化傾向が示されています。もちろん、CPIも下がってくるので実質賃金が一方的に下がるわけではありませんが、実質賃金に関しても「2023年後半に概ね前年比ゼロ%近傍となるが、2024年に入ると政府による物価高対策の縮小・終了に伴う反動により物価上昇率が再び高まることを受けて小幅なマイナスに転じる」とみずほRTは予測しています。
程度の差こそあれ、「いつも通りの日本」に戻っていくというのは多くの市場参加者が想像するシナリオと一致するのではないでしょうか。
先般のイールドカーブ・コントロール(YCC)修正を受けて、「次の一手」としてのマイナス金利解除に大きな注目が集まるものの、これを可能にする実質賃金上昇は見通せる将来において期待できそうにありません。それとも今年がそうであったように、来年以降も大方の予想を覆すような春闘の仕上がりが出てくるのでしょうか。2024年中のマイナス金利解除を合理的に予想するとすればそのようなシナリオに賭けるしかないように感じます。人手不足が極まる中、絶対に無いとは言えないシナリオですが、あくまでリスクシナリオの範疇に入る展開にとどまりそうです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

