
『無法松の一生』と広島カープとヨドバシカメラ
これ以上ないくらいに意味わからんタイトルとサムネイルですね、自分で言うのもなんですが。ともあれ、ちょっとした発見をしました。この3つには音楽の面で関連性があったのです。
『無法松の一生』鑑賞での気付きを調べてみると、いろんなことが分かり面白かったので、時代考証というと少し大げさですが史実とも合わせてまとめてみたいと思います。

まず『無法松の一生』をものすごく簡単に紹介すると、気性が荒い無法者の人力車夫の松五郎が、早くに夫を亡くしてしまった良子夫人とその息子の敏雄との出会いによって、天涯孤独の身から生き甲斐を感じるようになるというお話。
場所は九州の小倉。時代で言うと明治30年~大正3年、西暦で1897年~1914年という設定です。
「無法松の一生」という作品は、過去4度に渡って映画が作成されており、1943年版(主演:阪東妻三郎)、1958年版(主演:三船敏郎)、1963年版(主演:三國連太郎)、1965年版(主演:勝新太郎)とがあります。主演が凄いメンツ…

最初の2つは、伊丹万作が脚本で稲垣浩が監督という部分が共通しています。というのも、1943年版は戦前の内務省によって、そして戦後のGHQによって2回に及ぶ検閲の結果、多数のシーンがカットされてしまい、そのリベンジで作られたのが1958年版だからです。そしてこの1958年版はヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞しています。リベンジ成功です。
今回私が鑑賞したのも、その三船敏郎主演の1958年版。なんと映画館で初鑑賞でした。ありがとう、「午前10時の映画祭」。
話を戻します。全く関係が無さそうな『無法松の一生』と広島カープとヨドバシカメラ。
この映画の後半で、1914年(大正3年)に第一次世界大戦での「青島の戦い」で日本が勝利したことを町を挙げてお祝いするシーンがあるのですが、その時に管楽器で演奏されている軍歌が、広島カープの応援歌とヨドバシカメラのテーマソングだったという話です。
広島カープの応援歌「宮島さん」
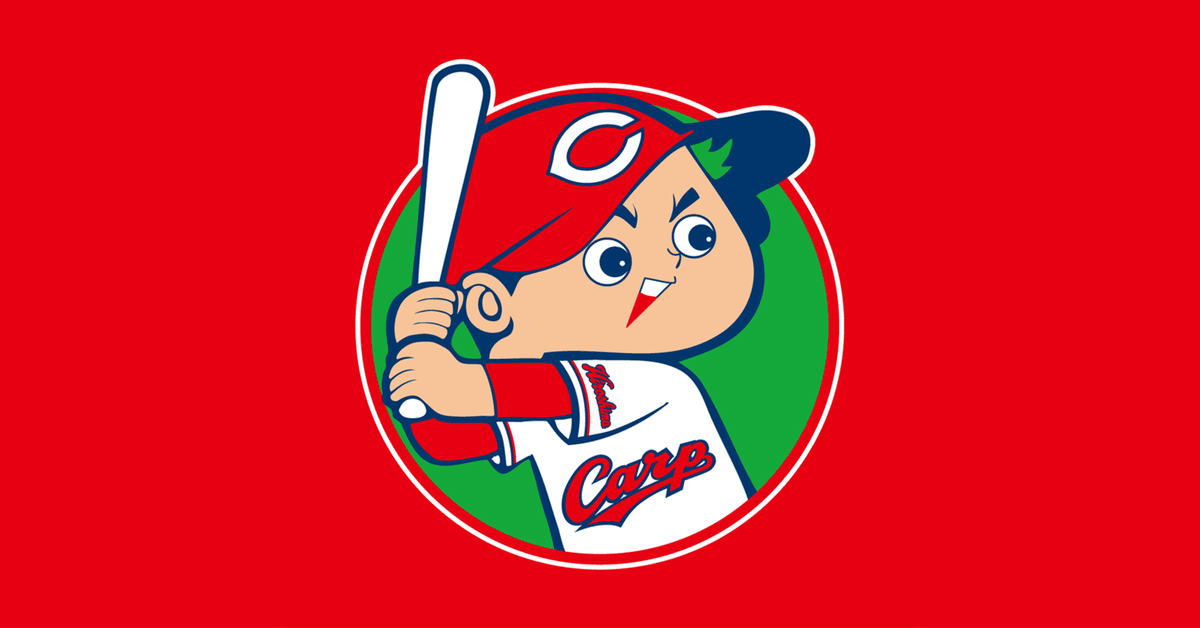
プロ野球好きの方は聞き覚えがあるかもしれませんが、広島カープが点を入れた時に歌われる「宮島さん」という曲が劇中で流れます。
野球の応援歌ですから、メロディーラインを聴いた感じは、金管楽器の音色が勝利を鼓舞する雰囲気が、軍隊の士気を上げるのに相性の良い曲だったのではないかという印象を持ちました。
宮島さんの神主が おみくじ引いて申すには
今日もカープは 勝ち 勝ち 勝ち 勝ち
これの原曲は1901年(明治34年)の唱歌「花咲爺」で、本来は軍歌とは関係ないようです。映画の中では、青島の戦いに勝利した1914年にこの曲が流れているので、実際に曲が世に出て13年後ですから、世間に定着して軍歌隊が演奏していても不自然ではありません。
そもそも日本の軍歌隊・吹奏楽の文化は、1869年(明治2年)に薩摩藩でイギリス人の指導により薩摩バンド(薩摩藩軍楽隊)を結成したのがその発祥なので、九州が始まりなのです。『無法松の一生』の舞台も同じ九州内の小倉なので、発祥の地からそれなりに近いエリアです。
近いと言っても300km以上離れていますが、軍歌隊の発祥から劇中での「花咲爺」の演奏に至るまでは45年経っている設定ですので、この頃には割と広範囲に軍歌隊の文化が広まっていることが窺えます。
そうして広島にも広まり、野球の応援歌として定着したのだと思うと感慨深いですね。詳細は調べても分かりませんでしたが。そう願いたい。
ヨドバシカメラの曲

そして、もう1曲。こちらも劇中のほぼ同じタイミング。「青島陥落」で小倉の町が湧いている中、主演の三船敏郎が将棋を指しているシーンの後ろでうっすらと流れているんです、ヨドバシカメラが。
まあるい 緑の 山手線 まんなか 通るは 中央線
新宿 西口 駅前と Akibaの ヨドバシカメラ
すっかり電化製品ミュージックとして耳に馴染みがありますが、こちらも元々は「リパブリック讃歌」というアメリカ南北戦争(1861年~1865年)で北軍が行軍曲にしていたものです。
当時のアメリカの軍歌を日本で使っていたのも不思議な感じがしますが、「青島の戦い」があったのは1914年で、同年のサラエボ事件から半年後、第一次世界大戦が始まってすぐだったので、まだ日本とアメリカは敵対関係にはありませんでした。
リパブリック讃歌は、1890年(明治23年)にクリスマスの子供讃美歌集に初めて収録され、1902年(明治35年)には軍歌集として日本に入ってきています。なので広島カープの「花咲爺」と同じくらいの時期に庶民へと広がり、軍歌としても使われだした可能性があります。
そしてこの曲の替え歌として広まったのが「権兵衛さんの赤ちゃん」。これで小さい頃に踊ったりしませんでしたか?
権兵衛さんの赤ちゃんが 風邪引いた
権兵衛さんの赤ちゃんが 風邪引いた
権兵衛さんの赤ちゃんが 風邪引いた
そこであわてて 湿布した
ってやつです。私も完全に忘れてましたけど「湿布した」のフレーズで思い出しました。懐かしい…
全然関係ないですけど、クレヨンしんちゃんの『カンフーボーイズ ~拉麺大乱~』でも、ももクロが歌うブラックパンダラーメンのCMソングはヨドバシメロディなんですよ。
ちなみに、この『無法松の一生』の中に出てくる「青島の戦い」というのは、日本の戦争で初めて航空機が使用された戦いでもあります。航空機同士の空中戦はこの頃から始まったのです。

『紅の豚』のポルコ・ロッソは、オーストリア=ハンガリー帝国軍とのイタリア戦線(1915年~1918年)において活躍したと言われている(という設定)ので、空中戦における黎明期のキャラクターということになります。
こうして同じ時代をテーマに作られた全く違う映画を並べてみると興味深いし勉強になりますね。
おわりに

映画の内容にはほとんど関係なかったのですが、聴いたことある曲が「え、こんなシーンでかかるの?なんで?」から始まり、背景を調べて時代考証していくのが面白かったので、少しマニアックですが紹介してみました。
映画『無法松の一生』とても良い映画ですので、観たことない方は是非とも。クソ泣いたんで。ではまた次回!
2023年4月7日追記
1960年代に札幌市で幼少期を過ごした私の母が、ヨドバシカメラの歌の替え歌をよく唄っていたらしく、その歌詞を教えてくれました。これも消えてしまうかもしれない歴史の一部なので書き残しておこうと思います。
錦糸輝く日本の
あいこでアメリカヨーロッパ
パリフランスドイツ
スイス軍隊負けちゃった
子どもの唄っていた歌詞なので、単なる語呂合わせなのか、史実が盛り込まれているのかは分かりません。原曲のリパブリック讃歌は1860年代の南北戦争の時の曲なので、この時すでにスイスは永世中立国です。
そのため「スイス軍隊負けちゃった」の部分は、戦争での敗北というより自国防衛の戦いの中で負けたという意味なのか…3行目の「パリフランスドイツ」からはナチス・ドイツのフランス侵攻を想起しますね。
結論は出ないですが。興味深いです。
この記事が参加している募集
最後までお読みいただき本当にありがとうございます。面白い記事が書けるよう精進します。 最後まで読んだついでに「スキ」お願いします!
